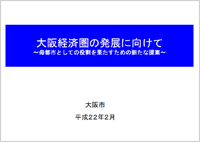平成22年2月17日 大阪市長会見全文
【大阪経済圏の発展に向けて】
(それでは私のほうから、『大阪経済圏の発展に向けて』という新たな提案をさせていただきます。)
現在、国におきましては、6月の策定に向けて成長戦略が議論されております。東京に偏った議論がされているというふうにも聞こえてきておりまして、先日、上京した際にも大阪圏の発展が日本の成長にとって重要であるという認識も申し上げ、東京一極集中という形をこのあとも続けるのかなあという疑問も含めて、地域主権をおっしゃってる民主党政権というものが、今後、成長戦略をどう考えられるのかという中で、この基礎自治体であり、そして政令市、母都市である大阪市からの1つの提案、現状分析と提案というふうに考えていただければと思います。地域主権の実現が現実化しているという、一方では、そういう動きと同時に、大阪市は、言っておりますように、都市州をめざすというふうに言っておりますが、この大阪圏の経済の発展に対しまして、大阪市が持っている責任というのは何なのか、これが、今、明らかにする必要があると思って、ここでお話をさせていくものです。ただし、これは大阪市だけで、もちろん、解決できるもんでも何でもありません。この大阪市が果たす役割、さらには、広く連携をとることによって、関係機関と議論を深めることによって、環境、それから広域インフラ、これが変わっていくのではないかという思いで、提案するものでございます。
まず、環境先進都市大阪の実現に向けた取組みでございます。大都市が持続的に発展していくために、都市活力の向上と環境負荷の低減を両立させるという戦略が必要でございます。これまでに都市再生緊急整備地域制度、これの延長でありますとか、あるいは金融税制面での要件緩和などを国に要望してまいりましたが、それに加えて民間都市開発を推進しながら、都市全体の環境配慮につなげていくための施策として、環境基金の創設を提案いたします。これは土地の高度利用が可能となっている都市再生緊急整備地域等において、例えば更なる規制緩和により、排出枠を上回る分を環境基金として負担してもらうものです。そして、この基金を市内の密集市街地での建替え促進等に活用し、都市全体でのCO2 排出量の削減を図るというものです。ここで増えた分をここでマイナスになるような形に、そして、このマイナスの効果が大きいような形に誘導するという方向性を持っております。
次に、アジア環境技術国際標準化支援センターの提案でございます。仮称です。
国際標準化というものが国際競争力の強化と結びついた具体例としましては、1994 年に日本の民間企業が開発して、2000 年に国際標準化となりましたQR コードというものがあげられます。国際競争が激化する中で、国際標準の獲得が国際市場を制するうえで必須であるという考え方のもとで、これから、今まではそういったその標準というものが欧米中心に進んでいる標準化に対抗する意味でも、急激な発展で市場の重要性が増すアジアが中心となるべきではないか。そして、そのアジアが中心となって標準化を進める必要性の中で、大阪というまちが持っている環境技術での高いポテンシャル、さらにこれから大阪駅北地区で新たな拠点として、オープンイノベーションによって知的創造からビジネス創造、それを展開していこうという戦略拠点が何を生み出していくのか。こうしたものをまとめて考えていきますと、こういった優位性は、環境分野でアジア重視の国際標準化支援センターというものを大阪へ持って来ることができるんではないかということに取り組んでいきたいと。それが、これから新しいものづくり産業の基礎体力の向上、これにつなげられるんではないかと思っています。
次に、広域インフラについてなんですが、この間、関係機関で様々な提案や議論がされています。で、この間の議論を受けたという形で、大阪圏の活性化に向けて、さらにこの提案でつなげていきたいというふうに考えている次第です。まず、阪神港のストックを日本全体の成長に向け活用するという観点から、産業集積に向けた広域物流インフラの一体運営の提案でございます。これは、西日本の貨物を集約する、物流に絞った広域ネットワークの充実と、産業を集積させ創荷、「荷を創る」と書きますが、創荷を図る施策として連携を進めるためのものです。そのため、港湾と高速道路、双方の経営を効率化する必要があるであろうということです。港湾では、内航航路の競争力を強化し、ターミナルを効率的に運営するために、管理、運営の一体化を図ります。そして高速道路につきましても、複数ある管理、運営主体を一体化するというものです。そして、この港湾と高速道路を全体としてシームレスな物流ネットワークにすることにより、料金割引などを可能にすることもできるでしょうし、産業の立地誘導策とも連携させ、相乗効果をねらってはどうかという提案でございます。そして、中を見てみますと、港湾ですが阪神港における基幹埠頭の経営の効率化や一体化に向けた取組みに加えまして、広域から荷を集める集荷や経済特区等による創荷、荷を創るということですが、創荷を図ってまいります。これによって当然、貨物量が拡大する訳ですが、基幹航路を維持拡充し、阪神港の国際物流機能をさらに強化する国際コンテナ戦略港湾をめざすというものです。そのためには、まず大阪港埠頭公社を平成23年に株式会社化するという方向性と、さらに神戸港と連携をとるというのを進めていこうということです。その後、神戸港の埠頭公社が株式会社化されたあとは、将来の経営統合も視野に入れた検討を進めて、連携から一歩進んで早期に阪神港として一体的な運営をめざすものであります。
もう1つ、その道路なんですが、高速道路につきましては、ミッシングリンクの解消というものが、この近畿、関西にとりまして、大きな課題でございます。そしてそのミッシングリンクだけではなくて、料金体系自体がばらばらになっているということから、利用者にとっては使いづらく、料金面での不公平感があるというのも事実です。先日の関西財界セミナーにおきまして、大阪府から提案があったようですが、私としましては、これらの課題を解消するために、都市圏高速道路等の一体的な運営形態を構築し、完全対距離料金制の導入、また建設債務の償還期間の延長等の施策を講じることによって、投資余力が現状と比較して大幅に生み出される仕組みをつくるということを関係者とともに考えたいと思っております。それによって、公平な料金設定や利用料金の引下げなど弾力的な対応ができるとともに、多額の事業費が必要となる淀川左岸線延伸部などの新規路線整備の実現可能性が高まると思っております。さらに大阪府の提案に加えまして、高速道路ネットワークを、この黄色いところなんですが、高速道路ネットワークを健全に維持していくために、債務の償還期間終了後も料金による維持管理を継続することにより、持続可能な高速道路ネットワークのあり方を新たに提案するということで、書かせていただいています。
最後に、関西国際空港に関する提案です。関空は日本の二大ハブ空港の1つとして、日本の成長戦略にとって大変重要でありますが、多額の有利子負債を抱えております。国の成長戦略会議でも、関空の債務圧縮に成田の株式上場益を活用することが議論されていますが、この議論だけでまだ具体化の方策というものが出ておりません。この議論を具体化するためには、株式会社である関空、成田ともに、土地と負債のみ保有する機構、ここでは仮に土地・負債保有機構と名付けておりますが、そういった機構と、空港施設を管理する会社とに分離するということを提案いたします。将来的には、中部空港や、さらには伊丹、羽田を民営化したうえで、首都圏、中部圏、関西圏にある5つの基幹空港の上下分離も考えてはと思っております。伊丹の存廃に関わらず、このように上下分離することによって、関空の経営安定化が図られると考えております。成田空港だけ売却、株、上場して売却益が出たとしても、空港特会(空港整備特別会計)に入ってしまって、これを関空に使うことは無理であるという現在のスキームをなんとかこれで1つにできないかという提案でございます。
今回の提案ですけれども、ご覧いただきましたように、大阪市という都市が基礎自治体でありながら、非常に力を持っていた時代、さらには、あらゆるものを1都市でこなしていくという、基礎自治体でありながら、母都市という機能を持っております。それなるがゆえに、この真ん中から色々な情報をしっかりと外へ向かって発信していく、大きな流れにしていくためにも、例えば、港湾で環境先進都市と言っている大阪が未来エネルギーというものをしっかりと見つめると。そしてそれを、ものづくり企業を誘致していく中でつくりあげていく。一方では、北ヤードでそういったものを考える頭脳を、世界中から集まってくる、そういった磁場を形成することによって、ここがより一層、その物流の拠点ともなりうるエリアであるし、あるいは周辺との都市との水平連携を図ることも可能であろうと思います。北ヤード、臨海部を中心とした産業施策の推進とあわせ、大阪市版経済成長戦略につなげていきたいというふうに思います。今回提案させていただいたことは、これ色々なところにすでに言われていること、さらにそれを大阪市なりに、こういう方向性のほうがいいんではないですかという形で、提案をさせていただこうというものでございます。以上でございます。
質疑応答現在、国におきましては、6月の策定に向けて成長戦略が議論されております。東京に偏った議論がされているというふうにも聞こえてきておりまして、先日、上京した際にも大阪圏の発展が日本の成長にとって重要であるという認識も申し上げ、東京一極集中という形をこのあとも続けるのかなあという疑問も含めて、地域主権をおっしゃってる民主党政権というものが、今後、成長戦略をどう考えられるのかという中で、この基礎自治体であり、そして政令市、母都市である大阪市からの1つの提案、現状分析と提案というふうに考えていただければと思います。地域主権の実現が現実化しているという、一方では、そういう動きと同時に、大阪市は、言っておりますように、都市州をめざすというふうに言っておりますが、この大阪圏の経済の発展に対しまして、大阪市が持っている責任というのは何なのか、これが、今、明らかにする必要があると思って、ここでお話をさせていくものです。ただし、これは大阪市だけで、もちろん、解決できるもんでも何でもありません。この大阪市が果たす役割、さらには、広く連携をとることによって、関係機関と議論を深めることによって、環境、それから広域インフラ、これが変わっていくのではないかという思いで、提案するものでございます。
まず、環境先進都市大阪の実現に向けた取組みでございます。大都市が持続的に発展していくために、都市活力の向上と環境負荷の低減を両立させるという戦略が必要でございます。これまでに都市再生緊急整備地域制度、これの延長でありますとか、あるいは金融税制面での要件緩和などを国に要望してまいりましたが、それに加えて民間都市開発を推進しながら、都市全体の環境配慮につなげていくための施策として、環境基金の創設を提案いたします。これは土地の高度利用が可能となっている都市再生緊急整備地域等において、例えば更なる規制緩和により、排出枠を上回る分を環境基金として負担してもらうものです。そして、この基金を市内の密集市街地での建替え促進等に活用し、都市全体でのCO2 排出量の削減を図るというものです。ここで増えた分をここでマイナスになるような形に、そして、このマイナスの効果が大きいような形に誘導するという方向性を持っております。
次に、アジア環境技術国際標準化支援センターの提案でございます。仮称です。
国際標準化というものが国際競争力の強化と結びついた具体例としましては、1994 年に日本の民間企業が開発して、2000 年に国際標準化となりましたQR コードというものがあげられます。国際競争が激化する中で、国際標準の獲得が国際市場を制するうえで必須であるという考え方のもとで、これから、今まではそういったその標準というものが欧米中心に進んでいる標準化に対抗する意味でも、急激な発展で市場の重要性が増すアジアが中心となるべきではないか。そして、そのアジアが中心となって標準化を進める必要性の中で、大阪というまちが持っている環境技術での高いポテンシャル、さらにこれから大阪駅北地区で新たな拠点として、オープンイノベーションによって知的創造からビジネス創造、それを展開していこうという戦略拠点が何を生み出していくのか。こうしたものをまとめて考えていきますと、こういった優位性は、環境分野でアジア重視の国際標準化支援センターというものを大阪へ持って来ることができるんではないかということに取り組んでいきたいと。それが、これから新しいものづくり産業の基礎体力の向上、これにつなげられるんではないかと思っています。
次に、広域インフラについてなんですが、この間、関係機関で様々な提案や議論がされています。で、この間の議論を受けたという形で、大阪圏の活性化に向けて、さらにこの提案でつなげていきたいというふうに考えている次第です。まず、阪神港のストックを日本全体の成長に向け活用するという観点から、産業集積に向けた広域物流インフラの一体運営の提案でございます。これは、西日本の貨物を集約する、物流に絞った広域ネットワークの充実と、産業を集積させ創荷、「荷を創る」と書きますが、創荷を図る施策として連携を進めるためのものです。そのため、港湾と高速道路、双方の経営を効率化する必要があるであろうということです。港湾では、内航航路の競争力を強化し、ターミナルを効率的に運営するために、管理、運営の一体化を図ります。そして高速道路につきましても、複数ある管理、運営主体を一体化するというものです。そして、この港湾と高速道路を全体としてシームレスな物流ネットワークにすることにより、料金割引などを可能にすることもできるでしょうし、産業の立地誘導策とも連携させ、相乗効果をねらってはどうかという提案でございます。そして、中を見てみますと、港湾ですが阪神港における基幹埠頭の経営の効率化や一体化に向けた取組みに加えまして、広域から荷を集める集荷や経済特区等による創荷、荷を創るということですが、創荷を図ってまいります。これによって当然、貨物量が拡大する訳ですが、基幹航路を維持拡充し、阪神港の国際物流機能をさらに強化する国際コンテナ戦略港湾をめざすというものです。そのためには、まず大阪港埠頭公社を平成23年に株式会社化するという方向性と、さらに神戸港と連携をとるというのを進めていこうということです。その後、神戸港の埠頭公社が株式会社化されたあとは、将来の経営統合も視野に入れた検討を進めて、連携から一歩進んで早期に阪神港として一体的な運営をめざすものであります。
もう1つ、その道路なんですが、高速道路につきましては、ミッシングリンクの解消というものが、この近畿、関西にとりまして、大きな課題でございます。そしてそのミッシングリンクだけではなくて、料金体系自体がばらばらになっているということから、利用者にとっては使いづらく、料金面での不公平感があるというのも事実です。先日の関西財界セミナーにおきまして、大阪府から提案があったようですが、私としましては、これらの課題を解消するために、都市圏高速道路等の一体的な運営形態を構築し、完全対距離料金制の導入、また建設債務の償還期間の延長等の施策を講じることによって、投資余力が現状と比較して大幅に生み出される仕組みをつくるということを関係者とともに考えたいと思っております。それによって、公平な料金設定や利用料金の引下げなど弾力的な対応ができるとともに、多額の事業費が必要となる淀川左岸線延伸部などの新規路線整備の実現可能性が高まると思っております。さらに大阪府の提案に加えまして、高速道路ネットワークを、この黄色いところなんですが、高速道路ネットワークを健全に維持していくために、債務の償還期間終了後も料金による維持管理を継続することにより、持続可能な高速道路ネットワークのあり方を新たに提案するということで、書かせていただいています。
最後に、関西国際空港に関する提案です。関空は日本の二大ハブ空港の1つとして、日本の成長戦略にとって大変重要でありますが、多額の有利子負債を抱えております。国の成長戦略会議でも、関空の債務圧縮に成田の株式上場益を活用することが議論されていますが、この議論だけでまだ具体化の方策というものが出ておりません。この議論を具体化するためには、株式会社である関空、成田ともに、土地と負債のみ保有する機構、ここでは仮に土地・負債保有機構と名付けておりますが、そういった機構と、空港施設を管理する会社とに分離するということを提案いたします。将来的には、中部空港や、さらには伊丹、羽田を民営化したうえで、首都圏、中部圏、関西圏にある5つの基幹空港の上下分離も考えてはと思っております。伊丹の存廃に関わらず、このように上下分離することによって、関空の経営安定化が図られると考えております。成田空港だけ売却、株、上場して売却益が出たとしても、空港特会(空港整備特別会計)に入ってしまって、これを関空に使うことは無理であるという現在のスキームをなんとかこれで1つにできないかという提案でございます。
今回の提案ですけれども、ご覧いただきましたように、大阪市という都市が基礎自治体でありながら、非常に力を持っていた時代、さらには、あらゆるものを1都市でこなしていくという、基礎自治体でありながら、母都市という機能を持っております。それなるがゆえに、この真ん中から色々な情報をしっかりと外へ向かって発信していく、大きな流れにしていくためにも、例えば、港湾で環境先進都市と言っている大阪が未来エネルギーというものをしっかりと見つめると。そしてそれを、ものづくり企業を誘致していく中でつくりあげていく。一方では、北ヤードでそういったものを考える頭脳を、世界中から集まってくる、そういった磁場を形成することによって、ここがより一層、その物流の拠点ともなりうるエリアであるし、あるいは周辺との都市との水平連携を図ることも可能であろうと思います。北ヤード、臨海部を中心とした産業施策の推進とあわせ、大阪市版経済成長戦略につなげていきたいというふうに思います。今回提案させていただいたことは、これ色々なところにすでに言われていること、さらにそれを大阪市なりに、こういう方向性のほうがいいんではないですかという形で、提案をさせていただこうというものでございます。以上でございます。
記者
僕からは1つ、高速道路のところの将来にわたってネットワーク維持のための料金を取り続けるということについてです。市長が選挙で支援を受けられました民主党さんは、阪高と首都高以外のところは、社会実験をしながらということですが、無料化ということを言われています。で、大阪圏というか、大阪市が言われている経済圏で有料化ということになれば、場合によっては、考え方、これが競合するというかですね、昨日の幹部の説明だと、今の無料化の議論と逆行するかもしれないという説明でした。この点についてどうお考えなのか、お願いします。
市長
高速道路の有料化が、民主党の高速道路無料化と一致しないんではないかというご指摘かと思いますけれども、今日、申しております、これといいますのも、つまり、ミッシングリンクと言われる部分が、関西では大きく3つ言われますよね。なにわ筋線、あっごめんなさい、なにわ筋線は鉄道ですけれども、淀川左岸線の延伸部、それから阪神高速道路湾岸の西進、西に向かう、そして名神と湾岸との接続という、このミッシングリンクっていうのは、これから言っております成長戦略、港湾の成長戦略、空港の成長戦略、あるいは道路としての集荷作業での成長戦略にとって欠かせないという認識は、もうみんないっしょだと思うんです。私は、道路の時に、ブレーキも、ハンドブレーキもフットブレーキも踏んでいると言ったがために、なんか大阪市がそれに向かって一生懸命邪魔してるというようなニュアンスを持っておられるんですが、それは違うんですよということを分かっていただくためにも、本来必要なものです。ただ、その主体がどこかはっきりしないのに、今までは、「いいもんやから旗振れー」で旗振ってたような行政ではだめでしょうという、私の姿勢でもありますから、ああいう言い方をしました。ただ、この方式であれば、それが解決されるのではないかということから、全体の、日本全体の高速道路無料化とかいう部分とは違う形でのアプローチであることは確かです。でも、これをやれば、その方向性、つまり関西の全体の経済圏の発展というものに大きく寄与する方向であろうというふうに思っておりますから、言わせていただきました。