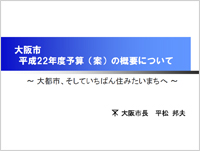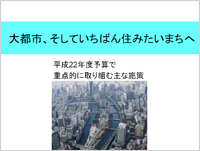平成22年2月17日 大阪市長会見全文
【平成22年度予算案について】
(おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは、私から平成22年度予算案の概要につきまして説明いたします。)
お手元にスクリーンと同じものをお配りしておりますので、よろしくお願いします。始めに予算編成方針についてですが、本格的な人口減少、少子高齢社会が到来しまして、飛躍的な経済成長が望めない時代を迎える中で、リーマンショックに端を発した金融危機は世界的な景気後退をもたらし、本市でも雇用や中小企業経営をはじめ市民生活に深刻な影響を及ぼしております。このような社会構造の変容と景気循環の激変のもとで、本市では市税収入の大幅な減少や生活保護費の大幅な増加が見込まれる中で、「負の遺産」と言われる財務リスクの処理に着実に取り組む必要があるなど、極めて厳しい財政状況にございます。こうした中、予算編成にあたりましては、持続可能な都市づくりに向け、財政の健全化を進めるとともに、政策推進ビジョンをいっそう深化させるという観点に立ちまして、将来にわたって活力あふれる「元気な大阪」をめざすということにいたしました。
こうした編成方針のもとに計上いたしました22年度予算は、引き続き緊縮基調ではあるものの、扶助費の増加などにより、前年度と比べて627億円、3.9%増の1兆6,905億円となっております。また、全会計の歳出規模は、前年度と比べまして151億円、0.4%増の3兆8,550億円となっております。22年度予算の特徴についてですが、歳入の根幹となる市税収入につきましては、厳しい経済状況を反映して、個人市民税や法人市民税の落ち込みが見込まれることから、前年度と比較いたしますと319億円、5.0%の大幅減となっております。中でも法人市民税に関しましては、金融不安による急激な景気の悪化による落ち込みが激しく、昭和55年度決算以来の1,000億円割れとなっております。一方、生活保護費につきましては、景気、雇用情勢の悪化による被保護世帯の急増により、420億円、17.2%の大幅増となっております。なお、扶助費全体では、生活保護費の大幅増に加え、子ども手当の創設等により742億円増の4,844億円となっております。
こうした中、財政の健全化についてですが、市政改革の取組みとして22年度予算におきましては、「経費削減の取組み」に加え、「事務事業の総点検」の前倒し分も含め、489億円の削減に取り組んでおり、5年間の歳出削減目標2,250億円に対しまして、これまでの4年間と合わせ、目標を上回る2,719億円の削減を見込んでおります。しかしながら、現在の財政状況等を勘案いたしますと、今後とも引き続き歳出の内容を精査し、さらに経費の削減に取り組む必要があると考えております。特に人件費につきましては、これまでより職員数の削減に努めてまいりましたけれども、22年度にも約800人の削減を行うことから、5年間では全会計で約8,400人の削減となっております。また、市債残高につきましても、全会計において5年連続で減少することとなりましたが、依然として高水準にあることから、引き続き市債発行の抑制に努める必要があると考えております。このように市政改革の取組みを進めているものの、市税収入が大幅に落ち込むなど、厳しい財政状況の中、真に必要な市民サービスを守るため、不用地の売却代、それから蓄積基金、公債償還基金の繰入金により446億円の補てん財源を確保するとともに、地方交付税等につきましても、1,222億円を計上することにより、ようやく収支不足を解消しているという状況でございます。予算編成におきましては、施策の選択と集中に取り組み、職員数の削減などによる人件費の見直しや、物件費、投資的経費の削減などにより生み出された限りある財源を地域力の復興と未来への投資、この2つの大きな柱としまして、施策の重点化に取り組んでおります。なお、これらの具体的な事業につきましては、「重点的に取り組む主な施策」として、後ほどご説明させていただきます。
それから、大阪府と関連する課題といたしまして、「差等補助」という、これも意味の解らない言葉で使い続けておりますので、お許しをいただきたいと思います。これまでから、その解消について府に申し入れを行なってまいりましたけれども、22年度予算においても引き続き、4億4,400万円の差等補助が見込まれております。この内容をご覧いただきましたらお分かりのように、教育、子育て等に関連いたしました事業の補助金が大阪市民であるということを理由に措置されないということでございます。大阪市民は、もう皆さんご存知のようにすべからく大阪府民でございます。大阪市民も府内の他の住民と同じように府民税を負担しているにもかかわらず、政令指定都市であることを理由に補助金等を措置しないということは、私、何度も申し上げておりますけれども、道理に合わないことでございます。差等補助の存在自体が是正されて、大阪市民にも補助金が配分されるよう、これからも大阪府に対して強く求めていこうと思っております。以上、平成22年度予算案の概要でございました。 次に、平成22年度予算で重点的に取り組む、主な施策のご説明に移らせていただきます。表題のキーワードといたしまして『大都市、そしていちばん住みたいまちへ』、この言葉を深化させたい、そういう思いで重点的に取り組む施策を組み立てた次第でございます。就任以来、市民の方、企業の方、そして様々な方々にお会いしまして、あらためて大阪のまちを見つめ直してまいりました。そこで感じたことは、この大阪っていうまちは本当にすごいまちであるということを実感させられたと思っていることでございます。このまちで、住み、学び、働くという、このことができる喜びと誇りを持ち続けられる、そんな持続可能なまちにしていくべきであると考えております。去年3月につくり上げました政策推進ビジョンから少しずつではありますけれども、種が芽を出し始め、大阪が動き出しているという手ごたえを感じております。厳しい財政状況ではありますけれども、施策の選択と集中により、政策推進ビジョンを深めて、地に足のついた実効性のある成長戦略としていくことが、今ほど大事な時期はない、そう思っております。その観点から、平成22年度予算では地域力の復興と未来への投資、これを柱として重点的に取り組んでおります。
まず、1つ目の柱、地域力の復興についてでございます。都市の本当の豊かさを考える時に、地域の中のコミュニケーションでありますとか、共に助ける、「共助」ですね、と言われる助け合いを通じて、地域社会が力をつけていくということは非常に大切なことだと思っております。都市の基本である安全・安心ということにつきましても、地域に根ざした市民の皆さんと行政が力をあわせなければ効果は上がりません。 大阪市には地域の結束であるとか、自治の能力が高いという、これは伝統でございますが、町会の加入率も下がってきたとはいえ7割を超えておりまして、担い手の高齢化などの課題があるとはいえ、大阪をいいまちにしたいという熱い思いを持たれ、色んな活動をされているという方をたくさんお見受けしましたし、色んなお話もしてまいりました。そういった地域の力を大阪再生の原動力にさせていただきたいという思いが日々強くなっております。そして、それを大都市大阪がやるからこそ、大きな意味があると私は考えております。地域の活動をされている方からは、役所は予算はつけるんやけれども、組織の中で連携がないであるとか、そして今一番必要なのは人的支援であり、地域課題にいっしょになって取り組む姿勢であるというお話もよく聞きます。これまでの仕組みを見つめ直して、行政も地域の皆さんといっしょになって向き合うことから始めなければならないと思っています。そのために、新たに港区の3つの小学校区で、まず地域の皆さんが地域の課題を発見、整理することからスタートします。そしてタウンミーティングで地域の課題を共有したうえで、協働プロジェクトを立ち上げ、課題の解決を図るという取組みを実施してまいります。もちろん、とりわけ区役所の役割というものが今以上に大きくなってまいります。地域が「こうしたい」というのを支える区役所になっていく、そんな区役所づくりの第一歩にチャレンジしたいと思っております。
続きまして、地域を元気にする取組みでございますが、地域防犯対策、これはもう市長になりましてから何度も言わせていただいております。街頭犯罪発生件数、この2カ年で約1万件減少いたしました。発生率ではワースト1を脱却しました。こんな大きな成果が市民の皆さんとの協働によって果たすことができました。また、大阪府警にも大きなお力添え、そして主体となって動いていただいております。まさに、それらの成果が見える形として、実感できるものになってきたと思っております。22年度には、これまでの取組みのほかに、青色防犯パトロールをさらに地域に広げていくとともに、新たに公共施設でも道路などを撮影する防犯カメラを設置するなど、地域全体で防犯対策を進めていきたいと思います。それから放置自転車対策なんですが、こちらも大きな成果があがっております。台数が5万台から4万2千台へと減っておりまして、千日前通りでは、なんと80%の減となりました。今回新たに、一部、路面に貼る放置禁止シールを、子どもたちの思いが込められた、こういった絵画でつくろうと思っております。これは夏休みぐらいに募集をして、秋ぐらいから貼り出せればなあという、テストケースを色々やってみようと思ってるんですが、この子どもたちが描いた絵の上、禁止シールと、上に、大阪、もともとやさしい人たちが多いと私は思っておりますんで、そういった人たちが乱雑に自転車置くことがないようにという思いを込めた訴えでございます。放置自転車につきましては撤去ではなく、盗まれたという誤解のもとに引き取りに来ないというケースが数多くございます。そこで今回、放置自転車の府警への照会、これをオンライン化することで引き取りを迅速に進め、今、放置自転車を撤去したものを一時保管所に置いてる訳ですが、そこがもう一杯になりがちでございます。そこを早く空けて撤去台数を増やしていく、こんな仕組みで放置自転車を減らそうと思っております。
次は、地域の商店街、地域企業の育成支援とありますけれども、商店街や中小製造業者の皆さんは、地域活動の重要な担い手であると思っております。まず、商店街を元気にということなんですが、去年、夏の消費拡大キャンペーンで、250もの商店街が結集し元気な商店街を大いにアピールすることができたと思っています。市内の商店街それぞれ特色がございます。それに応じた支援をきめ細かく行いたい、それが大切やと思っています。そこで市の職員が各地域の商店街の皆さんと同じ目線で考えて悩んで、その中からいっしょになって企画をし、商店街の魅力を発掘、発信してまいりたいと思っています。22年度は、中央卸売市場も一部参加しまして、各地の商店街で、まちなかイベントを3カ月間行うという、これはまだ仮称でございますけれども、『大阪あきない祭り』を実施し、新たな振興施策へ展開したいと考えています。また、中小製造業への支援でございますけれども、すでに西淀川区の工業活性化の取組みでありますとか、東成区と生野区で、『ものづくりフェスタ』という2区が協働してやっているフェスタがあります。それに加えて、大阪商工会議所支部など支援機関との連携ですとか、産業創造館、工業研究所のノウハウを活用することにより、経営力強化の支援を図ってまいります。また、新たな試みとしまして、これですけれども、広範囲に工場が集積している西淀川区の一部地域、この地域で住宅等の立地規制を行います。工場の操業環境を守るということでございます。それと、今週から取扱いを開始しました景気対応緊急融資ですが、22年度も継続することにしております。原則として全業種が利用でき、小規模事業者を優遇した内容となっていますので、是非、活用していただきたいと思っています。
次に、2つ目の柱でございます未来への投資であります。将来の大阪、ひいては関西の発展のために、また、都市が都市であり続けるために、大きく3つの分野で投資していきます。成長産業と都市魅力、そして人でございます。また戦略拠点としては北ヤードと臨海部に重点を置いております。世界は、地球温暖化、エネルギー、金融の3つの危機に見舞われると言われますが、関西には二次電池や太陽電池などの環境関連産業の集積という強みがあります。大阪市では、この強みを活かしながら、低炭素社会に向け、産業構造、社会システムをいち早く変革して、危機をチャンスに変えていきたいと考えています。まずは、再生可能エネルギーの徹底した活用です。臨海部では、再生可能エネルギーをつくる側として、大規模な太陽光発電を展開させるとともに、消費する側として化石燃料から転換し電気自動車の普及拡大を進めます。将来的には、蓄える側としてEV(電気自動車)に搭載した二次電池等を活用し、多様なクリーンエネルギーを最適に活用できるシステムを構築することをめざしたいと考えております。来年度は、夢洲の西の端にございます、ここですが、これが15haあるんですけれども、これを提供しまして電力会社以外では民間事業として日本最大級、およそ10メガワット以上になると思われますが、そのメガソーラー発電の導入を検討してまいります。これは、住宅での太陽光パネルのおよそ3000戸分に相当する電力でございます。
それから、森之宮地区でございます。ご存知の森之宮焼却工場と、それから、その隣に中浜の下水処理場、これが並んでいる訳ですが、この並んでいるという立地を利点としまして、エネルギー循環のまちづくりを大阪市が中心となって描きたいと思っています。おととしの森之宮ごみ焼却工場の建替え計画凍結宣言から、私は焼却工場について、迷惑施設というマイナスのイメージから、これからのエネルギーをつくり出す環境にも住民にもプラスになる施設に転換すべきだと主張してまいりました。その思いがようやく形になってきたと言えると思っております。周辺の都市再生機構の住宅等とも連携しまして、エリア全体でのエネルギーの有効活用を検討し、その中で焼却工場のあり方も検討いたします。特に、焼却工場で放熱されていた低温排熱を下水処理場に有効活用することや、食品廃棄物を活用して下水処理場でバイオガスを高度に発生させるなどの新たな取組みも検討いたします。検討のあと基本計画がまとまれば、環境影響調査などの手続きを経て、概ね10年ぐらいで新たな工場が完成できる見込みでございます。これは、こういう住宅密集地の中にあるという大都市ならではの、私は挑戦、チャレンジだと思っています。
電気自動車でございますが、大阪府と連携して普及拡大を図りたいと思っています。交通システムを低炭素に変え、関西の強みである二次電池の市場拡大を図り、環境・エネルギー産業をさらに成長、強化させることがねらいです。市民に利用機会を拡大してもらうために、民間事業者と提携して咲洲地区で5台、都心部で5台の電気自動車を活用したカーシェアリングを行ないます。咲洲では、企業、マンション住民、ATCなどの集客施設を対象に利用拡大を図りまして、今後は、市内の他の開発地区へと展開させていきたいと考えています。本市自らは、公害パトロールカーにEV2台を導入し、休日には市民や企業にも利用してもらいます。また、区役所で使用している青色防犯パトロールカーにも5台導入してまいります。安心して走行できる環境の整備として、EVの倍速充電スタンドを公的駐車場等に10基設置いたします。
次に、環境やエネルギー産業以外にも成長が見込める産業につきましては、将来を見据えて重点的に投資していくことが重要です。例えば少子高齢社会におきまして、介護や健康、医療などの分野は有望ですが、ロボットラボラトリーを開設いたしまして5年、大阪市が実績を誇るロボット関連技術にとりまして実用化が期待できる絶好のターゲットと言えると思います。具体的には、『コンソーシアム関西』のような専門機関と提携し、介護ロボットなど『医工連携プロジェクト』を進めていきます。また、世界トップクラスといえる大阪のロボット技術に対しまして、フランスやデンマークなど海外からの連携の話も増えてきています。こうした機会を捉えることで、海外の企業や人材を大阪に呼び込むことができるのではないか、あるいは北ヤードを拠点にしたロボットのビジネス化につなげることができるのではないか。国内での実用化には、医療行為に関する法規制などの課題があります。そういったことから海外の事例を参考に国へも働きかけを行っていきたいと思っています。また、デザインや広告といったクリエイティブ産業も、力を注ぐべき都市型のサービス産業であると思っています。『メビック扇町』が廃止となりますけれども、100社を超える企業が、この『メビック扇町』から育っております。そしてコミュニティがつくられたという成果を踏まえまして、これに代わる拠点を整備することで、扇町モデルを他地域に広げられればと期待しております。さらに成長するアジア市場を強く意識しまして、中小企業の製品や技術を海外市場へ確実に売るための支援を進めます。
そして大阪市最大の戦略拠点、北ヤードでございますが、来年度さらなるステージへステップアップいたします。ナレッジ・キャピタルを中核としまして、企業、大学だけではなくて、様々な研究者、クリエーター、市民をはじめ、アジアそして世界から様々な人、もの、情報が集積する磁場となる拠点として動き出します。先行開発区域では、建築工事は、いよいよこの3月に着工の運びとなります。ナレッジ・キャピタルの実現に向けては、産学の最先端の技術やアイデアを結び、新しい価値を創造する拠点として、『大阪オープンイノベーションセンター』の準備を開始いたしまして、平成24年度下期のまちびらきにあわせて本格稼動するようにパイロットプロジェクトの創出などに取り組みたいと思っています。2期開発区域でございますけれども、ここにおきましても環境をテーマとしたビジョンの具体化でありますとか、JR東海道線の支線地下化に取り組むなど、先行、2期を含めた全体構想の実現に向けた節目の年になります。なお、先日報道されました梅田貨物駅の移転が平成25年の春になるということですが、この期間を十分活用し、2期開発の実現に向けた仕組みづくりや手続きを進めたいと思っています。また、大規模、複合型の環境技術を取り入れた球技専用スタジアムにつきましては、府、市、経済界、そしてサッカー協会等による協議会を19日にも立ち上げまして、国立施設としての誘致に取り組んでまいります。
臨海部です。関西の強みであると思っていますし、成長が期待される環境・エネルギー産業分野の実践エリアとしての取組みを進めます。夢洲先行開発地区では、産業振興に不可欠な国際物流機能の強化を図るため、国が進める国際コンテナ戦略港湾に阪神港が指定されるよう取り組みます。また、コンテナ埠頭の一元管理を視野に入れて、23年度には埠頭公社を株式会社化できるように取り組みます。またインセンティブ方策に加えまして、経済特区制度の創設に向けた検討や、私自らが先頭に立って誘致プロモーションに取り組みたいと思っています。咲洲では、府庁舎の移転を見据えて、ビジネス環境と住環境の改善に前倒しで取り組みます。WTCとコスモスクエア駅を結ぶペデストリアンデッキの設置や、防災機能の整備に着手してまいります。
また、国連世界観光機関の唯一の地域事務所でございますアジア太平洋センターをATCに誘致し、外国領事館などの機関と連携しながら、ソフト面を中心にコンベンション機能の充実に努めます。なお、臨海部については、『夢洲・咲洲地区まちづくり推進協議会』の第3回会合を、橋下知事、経済界のトップ3人とともに、竹山堺市長にも参加していただいて、今週19日金曜日に開催する予定でございます。
次は都市魅力の創造です。去年開催いたしました『水都大阪2009』では、企画や運営段階におきまして、主体的に市民、企業、NPOの皆さんに関わっていただき、190万人もの来場者を数えました。このような市民参加の実現に加え、国や府、市、経済界が一体となって開催できたことは大きな成果でございました。こうした『水都大阪2009』で得たものを次へしっかり引き継いでいきたいと思っています。22年度は中之島公園など水辺ににぎわいをもたらすイベントの開催をはじめ、市民、NPO等への支援をするなど、大阪府と連携して水辺のにぎわいのつくり出し、にぎわい魅力の創出に取り組んでいきたいと思っています。さらに、まちのにぎわい、文化、歴史、ホスピタリティを活かした、観光まちづくりに取り組みます。『OSAKA光のルネサンス』の開催では、およそ304万人の来場者でにぎわいましたが、引き続いて中之島の魅力を市民の方はもちろん観光客にも広くアピールしていきたいと思います。近代美術館についてでございますが、平成22年度は、先日の「あり方検討委員会」からの提言を踏まえ、市民が愛着と誇りを持てる美術館として、姿の見える新たな基本計画案をお示ししたいと考えています。市民の皆様や議会のご意見を踏まえて、ご理解の得られる基本計画が策定できましたら、早ければ平成28年度にも完成できるように取り組んでいきたいと思います。次に、重要文化財の泉布観でございますが、23年度中のオープンをめざし、民間事業者を公募する旧桜宮公会堂とあわせて、一体的に「泉布観地区」として再生を進めてまいります。22年度に3700万円を計上しておりますが、『ふるさと納税制度』による寄付金等を活用させていただきたいと思います。市民ボランティアなどが来訪者とふれあいながら「大阪のええとこ」を案内して歩くことで人気のコミュニティ・ツーリズム推進事業では、22年度は、コースの数を増やしまして、海外ビジター向けにも多言語音声観光ガイドも用意いたします。ますます多くの方に楽しんでいただけると思います。
続きまして、次代を担う人材育成でございます。未来の産業や都市を支えていくのは人であり、人材の育成は大阪市にとって大変重要な課題です。まず子育て支援です。私の公約であります保育所待機児童の解消につきましては、必要な入所枠を確保し、21年度末に待機児童を解消するための基盤がようやく整いました。そのうえで、22年度以降は新たな保育施策のステージへと展開してまいります。具体的には例えば、年度途中での低年齢児の入所希望が増えております。それに応える対策を新たに始めます。確かな学力の向上につきましては、学力向上強化戦略に掲げております習熟度別少人数授業の拡充などに継続して力を注いでまいります。高等学校につきましては、大学や産業界と連携して高校、大学のトータル7年間を見据えた、新しいタイプの商業高校を平成24年4月に開校する予定で校舎の建設を行いました。また、工業教育では産業界と連携し、エキスパートエンジニアの育成をめざした具体的な方策の検討を行います。
続きまして、雇用や年金など生活保障制度の再構築を視野に入れた、雇用と福祉の連携によるセーフティネットの構築についてご説明いたします。まず、市民から信頼される生活保護の実施ですが、『生活保護行政特別調査プロジェクトチーム』での議論を踏まえまして、22年度は市民生活を支えるセーフティネットとしての制度の適正実施と、不正を許さない厳正な対応の徹底に取り組んでまいります。特に、喫緊のテーマとして、社会参加によって地域との絆を回復していただき、自立を支援するという生活保障の原点に立ちまして、「働ける人には働いてもらう」という基本の確立と、大阪の実情を踏まえました貧困ビジネス事業者への対応、これにつきまして国に早急に具体的な提案を行ってまいります。そのうえで、雇用、年金など社会保障制度のあり方を含めた制度の抜本改革や、国民の最低限度の生活保障というナショナルミニマムとしての生活保護費の全額国庫負担、これにつきまして国に対して、制度改善に向けた具体的な提言を行っていきたいと思っています。市民生活と景気に直結する問題として、特に大変厳しい情勢にある雇用でございますけれども、これは最も重要で喫緊の課題であるとも考えております。先日、大阪府内の10月から12月にかけての完全失業率の速報が出ましたが、7.2%と依然として高く、生活保護受給者の増加にもつながっているほか、失業者の半数近くを若年層が占め、新卒の未就職者対策も急がれる状況にあります。この状況の解決に向けて、働く場を提供する就業支援事業を一層進めていく必要があります。22年度は、緊急雇用創出事業と先頃、国の2次補正で創設された重点分野雇用創造事業に、合計24億円を計上しております。この内、重点分野雇用創造事業は、今後、成長が見込まれる分野で新しい雇用を創り出すこと、そのニーズに応じた人材育成を同時に図るものです。例えば、働きながら資格をとる、介護雇用プログラムは、介護の現場で働きながら費用負担せずにホームヘルパー2級などの資格が取れるというものです。また、太陽光発電設備の施工の仕事に就き、実践的な技術を習得するというプログラムも用意しております。雇用側のインセンティブも確保しながら、将来の正規社員への就職につながるものになればと期待しております。あわせて、初めての試みになりますけれども、とりわけ急増しております生活保護受給者や新卒の未就職者に優先枠を設けました。最も困っている人に確実に雇用機会を提供することができたらと思っております。
さらに、早急に取組む必要がある課題として、次の5つに重点的に取り組んでいきます。その中で、あいりん地域の環境改善事業についてご説明いたします。おととしの屋台火災を契機といたしまして、また地元からの強い要望も受けて、今年度、萩之茶屋小学校周辺の道路上にある47件の屋台等不法占拠物件について全件撤去を行いました。30年来手が付けられなかった課題ではありましたが、『萩之茶屋地域環境改善特別チーム』を立ち上げて、庁内横断的な取組みを進めたことにより、また地域の方々や警察署等の協力もあり解決することができました。しかしながら、いまだ解決すべき多くの課題があり、この機を逃さず今後も重点的に取組みを進める予定でございます。先日、一部報道により、特に公園に関して、現場での誤解、混乱が生じているという報告を受けておりますが、22年度は、すでに地元と道路改良に向けて協議を始めております。そして道路の再不法占拠対策として、巡回パトロール、および立寄所の設置、そして30年近く閉鎖されている萩之茶屋北公園において時間帯開放に向けたフェンスの交換や老朽化した遊具の撤去などの機能回復を図ります。あわせて地域で意見を出し合える協議の場の形成支援などにも取り組みます。
救急医療対策ですが、去年10月に『救急安心センター』を立ち上げて以来、1日平均460件もの問い合わせがあり、常に医師に相談できることから、ご好評をいただいております。相談の結果、救急車が駆けつけて緊急手術を行い、事なきを得たなどの事例が14件もございます。21年度では国のモデル事業として始めましたが、これが21年度で終わってしまいます。しかし、今後も続けます。市民に安心いただける、いい事業だから「いっしょにやりませんか」という私の呼びかけに応じていただきまして、来年度は早速、堺市と吹田市など、およそ10市で参画していただけることになりました。私がいつも言っております、都市どうしの水平連携のいい例だと思っております。是非、取組みが広がっていくことを期待したいと思います。
それから、総合医療センター内に周産期の救急ともいえる『総合周産期母子医療センター』を、22年度中に開設いたします。これによりまして、重症の妊産婦さんや、ハイリスクの新生児にも対応できるようになります。地域の医療をしっかり支え、市民の皆さんの健康と安心を、これからも守っていきたいと思っています。
最後にまとめです。以上、ご説明した内容を都市のイメージとして申し上げますと、私の目標といたします『大都市、そしていちばん住みたいまちへ』とは、文化が薫る都市格を備えたまちと言えると思います。工業社会から知識社会へ、そして、経済成長のみを重視する社会から、心の豊かさや生活の質を重視する社会への変化を踏まえ、都市のインフラは人であり、その人間的な力が都市を成長させるという認識に基づいております。固有の歴史と文化を有するこの大阪で、新しい社会をつくるという知恵を備え、創意に富み、熱意にあふれた人々が集まることで、まち全体が活気づき、関西全体の繁栄にも貢献していく。そんな大阪市にしたいという想いを込めたものが今回の予算でございます。平成22年度予算としての説明は以上でございます。
質疑応答お手元にスクリーンと同じものをお配りしておりますので、よろしくお願いします。始めに予算編成方針についてですが、本格的な人口減少、少子高齢社会が到来しまして、飛躍的な経済成長が望めない時代を迎える中で、リーマンショックに端を発した金融危機は世界的な景気後退をもたらし、本市でも雇用や中小企業経営をはじめ市民生活に深刻な影響を及ぼしております。このような社会構造の変容と景気循環の激変のもとで、本市では市税収入の大幅な減少や生活保護費の大幅な増加が見込まれる中で、「負の遺産」と言われる財務リスクの処理に着実に取り組む必要があるなど、極めて厳しい財政状況にございます。こうした中、予算編成にあたりましては、持続可能な都市づくりに向け、財政の健全化を進めるとともに、政策推進ビジョンをいっそう深化させるという観点に立ちまして、将来にわたって活力あふれる「元気な大阪」をめざすということにいたしました。
こうした編成方針のもとに計上いたしました22年度予算は、引き続き緊縮基調ではあるものの、扶助費の増加などにより、前年度と比べて627億円、3.9%増の1兆6,905億円となっております。また、全会計の歳出規模は、前年度と比べまして151億円、0.4%増の3兆8,550億円となっております。22年度予算の特徴についてですが、歳入の根幹となる市税収入につきましては、厳しい経済状況を反映して、個人市民税や法人市民税の落ち込みが見込まれることから、前年度と比較いたしますと319億円、5.0%の大幅減となっております。中でも法人市民税に関しましては、金融不安による急激な景気の悪化による落ち込みが激しく、昭和55年度決算以来の1,000億円割れとなっております。一方、生活保護費につきましては、景気、雇用情勢の悪化による被保護世帯の急増により、420億円、17.2%の大幅増となっております。なお、扶助費全体では、生活保護費の大幅増に加え、子ども手当の創設等により742億円増の4,844億円となっております。
こうした中、財政の健全化についてですが、市政改革の取組みとして22年度予算におきましては、「経費削減の取組み」に加え、「事務事業の総点検」の前倒し分も含め、489億円の削減に取り組んでおり、5年間の歳出削減目標2,250億円に対しまして、これまでの4年間と合わせ、目標を上回る2,719億円の削減を見込んでおります。しかしながら、現在の財政状況等を勘案いたしますと、今後とも引き続き歳出の内容を精査し、さらに経費の削減に取り組む必要があると考えております。特に人件費につきましては、これまでより職員数の削減に努めてまいりましたけれども、22年度にも約800人の削減を行うことから、5年間では全会計で約8,400人の削減となっております。また、市債残高につきましても、全会計において5年連続で減少することとなりましたが、依然として高水準にあることから、引き続き市債発行の抑制に努める必要があると考えております。このように市政改革の取組みを進めているものの、市税収入が大幅に落ち込むなど、厳しい財政状況の中、真に必要な市民サービスを守るため、不用地の売却代、それから蓄積基金、公債償還基金の繰入金により446億円の補てん財源を確保するとともに、地方交付税等につきましても、1,222億円を計上することにより、ようやく収支不足を解消しているという状況でございます。予算編成におきましては、施策の選択と集中に取り組み、職員数の削減などによる人件費の見直しや、物件費、投資的経費の削減などにより生み出された限りある財源を地域力の復興と未来への投資、この2つの大きな柱としまして、施策の重点化に取り組んでおります。なお、これらの具体的な事業につきましては、「重点的に取り組む主な施策」として、後ほどご説明させていただきます。
それから、大阪府と関連する課題といたしまして、「差等補助」という、これも意味の解らない言葉で使い続けておりますので、お許しをいただきたいと思います。これまでから、その解消について府に申し入れを行なってまいりましたけれども、22年度予算においても引き続き、4億4,400万円の差等補助が見込まれております。この内容をご覧いただきましたらお分かりのように、教育、子育て等に関連いたしました事業の補助金が大阪市民であるということを理由に措置されないということでございます。大阪市民は、もう皆さんご存知のようにすべからく大阪府民でございます。大阪市民も府内の他の住民と同じように府民税を負担しているにもかかわらず、政令指定都市であることを理由に補助金等を措置しないということは、私、何度も申し上げておりますけれども、道理に合わないことでございます。差等補助の存在自体が是正されて、大阪市民にも補助金が配分されるよう、これからも大阪府に対して強く求めていこうと思っております。以上、平成22年度予算案の概要でございました。 次に、平成22年度予算で重点的に取り組む、主な施策のご説明に移らせていただきます。表題のキーワードといたしまして『大都市、そしていちばん住みたいまちへ』、この言葉を深化させたい、そういう思いで重点的に取り組む施策を組み立てた次第でございます。就任以来、市民の方、企業の方、そして様々な方々にお会いしまして、あらためて大阪のまちを見つめ直してまいりました。そこで感じたことは、この大阪っていうまちは本当にすごいまちであるということを実感させられたと思っていることでございます。このまちで、住み、学び、働くという、このことができる喜びと誇りを持ち続けられる、そんな持続可能なまちにしていくべきであると考えております。去年3月につくり上げました政策推進ビジョンから少しずつではありますけれども、種が芽を出し始め、大阪が動き出しているという手ごたえを感じております。厳しい財政状況ではありますけれども、施策の選択と集中により、政策推進ビジョンを深めて、地に足のついた実効性のある成長戦略としていくことが、今ほど大事な時期はない、そう思っております。その観点から、平成22年度予算では地域力の復興と未来への投資、これを柱として重点的に取り組んでおります。
まず、1つ目の柱、地域力の復興についてでございます。都市の本当の豊かさを考える時に、地域の中のコミュニケーションでありますとか、共に助ける、「共助」ですね、と言われる助け合いを通じて、地域社会が力をつけていくということは非常に大切なことだと思っております。都市の基本である安全・安心ということにつきましても、地域に根ざした市民の皆さんと行政が力をあわせなければ効果は上がりません。 大阪市には地域の結束であるとか、自治の能力が高いという、これは伝統でございますが、町会の加入率も下がってきたとはいえ7割を超えておりまして、担い手の高齢化などの課題があるとはいえ、大阪をいいまちにしたいという熱い思いを持たれ、色んな活動をされているという方をたくさんお見受けしましたし、色んなお話もしてまいりました。そういった地域の力を大阪再生の原動力にさせていただきたいという思いが日々強くなっております。そして、それを大都市大阪がやるからこそ、大きな意味があると私は考えております。地域の活動をされている方からは、役所は予算はつけるんやけれども、組織の中で連携がないであるとか、そして今一番必要なのは人的支援であり、地域課題にいっしょになって取り組む姿勢であるというお話もよく聞きます。これまでの仕組みを見つめ直して、行政も地域の皆さんといっしょになって向き合うことから始めなければならないと思っています。そのために、新たに港区の3つの小学校区で、まず地域の皆さんが地域の課題を発見、整理することからスタートします。そしてタウンミーティングで地域の課題を共有したうえで、協働プロジェクトを立ち上げ、課題の解決を図るという取組みを実施してまいります。もちろん、とりわけ区役所の役割というものが今以上に大きくなってまいります。地域が「こうしたい」というのを支える区役所になっていく、そんな区役所づくりの第一歩にチャレンジしたいと思っております。
続きまして、地域を元気にする取組みでございますが、地域防犯対策、これはもう市長になりましてから何度も言わせていただいております。街頭犯罪発生件数、この2カ年で約1万件減少いたしました。発生率ではワースト1を脱却しました。こんな大きな成果が市民の皆さんとの協働によって果たすことができました。また、大阪府警にも大きなお力添え、そして主体となって動いていただいております。まさに、それらの成果が見える形として、実感できるものになってきたと思っております。22年度には、これまでの取組みのほかに、青色防犯パトロールをさらに地域に広げていくとともに、新たに公共施設でも道路などを撮影する防犯カメラを設置するなど、地域全体で防犯対策を進めていきたいと思います。それから放置自転車対策なんですが、こちらも大きな成果があがっております。台数が5万台から4万2千台へと減っておりまして、千日前通りでは、なんと80%の減となりました。今回新たに、一部、路面に貼る放置禁止シールを、子どもたちの思いが込められた、こういった絵画でつくろうと思っております。これは夏休みぐらいに募集をして、秋ぐらいから貼り出せればなあという、テストケースを色々やってみようと思ってるんですが、この子どもたちが描いた絵の上、禁止シールと、上に、大阪、もともとやさしい人たちが多いと私は思っておりますんで、そういった人たちが乱雑に自転車置くことがないようにという思いを込めた訴えでございます。放置自転車につきましては撤去ではなく、盗まれたという誤解のもとに引き取りに来ないというケースが数多くございます。そこで今回、放置自転車の府警への照会、これをオンライン化することで引き取りを迅速に進め、今、放置自転車を撤去したものを一時保管所に置いてる訳ですが、そこがもう一杯になりがちでございます。そこを早く空けて撤去台数を増やしていく、こんな仕組みで放置自転車を減らそうと思っております。
次は、地域の商店街、地域企業の育成支援とありますけれども、商店街や中小製造業者の皆さんは、地域活動の重要な担い手であると思っております。まず、商店街を元気にということなんですが、去年、夏の消費拡大キャンペーンで、250もの商店街が結集し元気な商店街を大いにアピールすることができたと思っています。市内の商店街それぞれ特色がございます。それに応じた支援をきめ細かく行いたい、それが大切やと思っています。そこで市の職員が各地域の商店街の皆さんと同じ目線で考えて悩んで、その中からいっしょになって企画をし、商店街の魅力を発掘、発信してまいりたいと思っています。22年度は、中央卸売市場も一部参加しまして、各地の商店街で、まちなかイベントを3カ月間行うという、これはまだ仮称でございますけれども、『大阪あきない祭り』を実施し、新たな振興施策へ展開したいと考えています。また、中小製造業への支援でございますけれども、すでに西淀川区の工業活性化の取組みでありますとか、東成区と生野区で、『ものづくりフェスタ』という2区が協働してやっているフェスタがあります。それに加えて、大阪商工会議所支部など支援機関との連携ですとか、産業創造館、工業研究所のノウハウを活用することにより、経営力強化の支援を図ってまいります。また、新たな試みとしまして、これですけれども、広範囲に工場が集積している西淀川区の一部地域、この地域で住宅等の立地規制を行います。工場の操業環境を守るということでございます。それと、今週から取扱いを開始しました景気対応緊急融資ですが、22年度も継続することにしております。原則として全業種が利用でき、小規模事業者を優遇した内容となっていますので、是非、活用していただきたいと思っています。
次に、2つ目の柱でございます未来への投資であります。将来の大阪、ひいては関西の発展のために、また、都市が都市であり続けるために、大きく3つの分野で投資していきます。成長産業と都市魅力、そして人でございます。また戦略拠点としては北ヤードと臨海部に重点を置いております。世界は、地球温暖化、エネルギー、金融の3つの危機に見舞われると言われますが、関西には二次電池や太陽電池などの環境関連産業の集積という強みがあります。大阪市では、この強みを活かしながら、低炭素社会に向け、産業構造、社会システムをいち早く変革して、危機をチャンスに変えていきたいと考えています。まずは、再生可能エネルギーの徹底した活用です。臨海部では、再生可能エネルギーをつくる側として、大規模な太陽光発電を展開させるとともに、消費する側として化石燃料から転換し電気自動車の普及拡大を進めます。将来的には、蓄える側としてEV(電気自動車)に搭載した二次電池等を活用し、多様なクリーンエネルギーを最適に活用できるシステムを構築することをめざしたいと考えております。来年度は、夢洲の西の端にございます、ここですが、これが15haあるんですけれども、これを提供しまして電力会社以外では民間事業として日本最大級、およそ10メガワット以上になると思われますが、そのメガソーラー発電の導入を検討してまいります。これは、住宅での太陽光パネルのおよそ3000戸分に相当する電力でございます。
それから、森之宮地区でございます。ご存知の森之宮焼却工場と、それから、その隣に中浜の下水処理場、これが並んでいる訳ですが、この並んでいるという立地を利点としまして、エネルギー循環のまちづくりを大阪市が中心となって描きたいと思っています。おととしの森之宮ごみ焼却工場の建替え計画凍結宣言から、私は焼却工場について、迷惑施設というマイナスのイメージから、これからのエネルギーをつくり出す環境にも住民にもプラスになる施設に転換すべきだと主張してまいりました。その思いがようやく形になってきたと言えると思っております。周辺の都市再生機構の住宅等とも連携しまして、エリア全体でのエネルギーの有効活用を検討し、その中で焼却工場のあり方も検討いたします。特に、焼却工場で放熱されていた低温排熱を下水処理場に有効活用することや、食品廃棄物を活用して下水処理場でバイオガスを高度に発生させるなどの新たな取組みも検討いたします。検討のあと基本計画がまとまれば、環境影響調査などの手続きを経て、概ね10年ぐらいで新たな工場が完成できる見込みでございます。これは、こういう住宅密集地の中にあるという大都市ならではの、私は挑戦、チャレンジだと思っています。
電気自動車でございますが、大阪府と連携して普及拡大を図りたいと思っています。交通システムを低炭素に変え、関西の強みである二次電池の市場拡大を図り、環境・エネルギー産業をさらに成長、強化させることがねらいです。市民に利用機会を拡大してもらうために、民間事業者と提携して咲洲地区で5台、都心部で5台の電気自動車を活用したカーシェアリングを行ないます。咲洲では、企業、マンション住民、ATCなどの集客施設を対象に利用拡大を図りまして、今後は、市内の他の開発地区へと展開させていきたいと考えています。本市自らは、公害パトロールカーにEV2台を導入し、休日には市民や企業にも利用してもらいます。また、区役所で使用している青色防犯パトロールカーにも5台導入してまいります。安心して走行できる環境の整備として、EVの倍速充電スタンドを公的駐車場等に10基設置いたします。
次に、環境やエネルギー産業以外にも成長が見込める産業につきましては、将来を見据えて重点的に投資していくことが重要です。例えば少子高齢社会におきまして、介護や健康、医療などの分野は有望ですが、ロボットラボラトリーを開設いたしまして5年、大阪市が実績を誇るロボット関連技術にとりまして実用化が期待できる絶好のターゲットと言えると思います。具体的には、『コンソーシアム関西』のような専門機関と提携し、介護ロボットなど『医工連携プロジェクト』を進めていきます。また、世界トップクラスといえる大阪のロボット技術に対しまして、フランスやデンマークなど海外からの連携の話も増えてきています。こうした機会を捉えることで、海外の企業や人材を大阪に呼び込むことができるのではないか、あるいは北ヤードを拠点にしたロボットのビジネス化につなげることができるのではないか。国内での実用化には、医療行為に関する法規制などの課題があります。そういったことから海外の事例を参考に国へも働きかけを行っていきたいと思っています。また、デザインや広告といったクリエイティブ産業も、力を注ぐべき都市型のサービス産業であると思っています。『メビック扇町』が廃止となりますけれども、100社を超える企業が、この『メビック扇町』から育っております。そしてコミュニティがつくられたという成果を踏まえまして、これに代わる拠点を整備することで、扇町モデルを他地域に広げられればと期待しております。さらに成長するアジア市場を強く意識しまして、中小企業の製品や技術を海外市場へ確実に売るための支援を進めます。
そして大阪市最大の戦略拠点、北ヤードでございますが、来年度さらなるステージへステップアップいたします。ナレッジ・キャピタルを中核としまして、企業、大学だけではなくて、様々な研究者、クリエーター、市民をはじめ、アジアそして世界から様々な人、もの、情報が集積する磁場となる拠点として動き出します。先行開発区域では、建築工事は、いよいよこの3月に着工の運びとなります。ナレッジ・キャピタルの実現に向けては、産学の最先端の技術やアイデアを結び、新しい価値を創造する拠点として、『大阪オープンイノベーションセンター』の準備を開始いたしまして、平成24年度下期のまちびらきにあわせて本格稼動するようにパイロットプロジェクトの創出などに取り組みたいと思っています。2期開発区域でございますけれども、ここにおきましても環境をテーマとしたビジョンの具体化でありますとか、JR東海道線の支線地下化に取り組むなど、先行、2期を含めた全体構想の実現に向けた節目の年になります。なお、先日報道されました梅田貨物駅の移転が平成25年の春になるということですが、この期間を十分活用し、2期開発の実現に向けた仕組みづくりや手続きを進めたいと思っています。また、大規模、複合型の環境技術を取り入れた球技専用スタジアムにつきましては、府、市、経済界、そしてサッカー協会等による協議会を19日にも立ち上げまして、国立施設としての誘致に取り組んでまいります。
臨海部です。関西の強みであると思っていますし、成長が期待される環境・エネルギー産業分野の実践エリアとしての取組みを進めます。夢洲先行開発地区では、産業振興に不可欠な国際物流機能の強化を図るため、国が進める国際コンテナ戦略港湾に阪神港が指定されるよう取り組みます。また、コンテナ埠頭の一元管理を視野に入れて、23年度には埠頭公社を株式会社化できるように取り組みます。またインセンティブ方策に加えまして、経済特区制度の創設に向けた検討や、私自らが先頭に立って誘致プロモーションに取り組みたいと思っています。咲洲では、府庁舎の移転を見据えて、ビジネス環境と住環境の改善に前倒しで取り組みます。WTCとコスモスクエア駅を結ぶペデストリアンデッキの設置や、防災機能の整備に着手してまいります。
また、国連世界観光機関の唯一の地域事務所でございますアジア太平洋センターをATCに誘致し、外国領事館などの機関と連携しながら、ソフト面を中心にコンベンション機能の充実に努めます。なお、臨海部については、『夢洲・咲洲地区まちづくり推進協議会』の第3回会合を、橋下知事、経済界のトップ3人とともに、竹山堺市長にも参加していただいて、今週19日金曜日に開催する予定でございます。
次は都市魅力の創造です。去年開催いたしました『水都大阪2009』では、企画や運営段階におきまして、主体的に市民、企業、NPOの皆さんに関わっていただき、190万人もの来場者を数えました。このような市民参加の実現に加え、国や府、市、経済界が一体となって開催できたことは大きな成果でございました。こうした『水都大阪2009』で得たものを次へしっかり引き継いでいきたいと思っています。22年度は中之島公園など水辺ににぎわいをもたらすイベントの開催をはじめ、市民、NPO等への支援をするなど、大阪府と連携して水辺のにぎわいのつくり出し、にぎわい魅力の創出に取り組んでいきたいと思っています。さらに、まちのにぎわい、文化、歴史、ホスピタリティを活かした、観光まちづくりに取り組みます。『OSAKA光のルネサンス』の開催では、およそ304万人の来場者でにぎわいましたが、引き続いて中之島の魅力を市民の方はもちろん観光客にも広くアピールしていきたいと思います。近代美術館についてでございますが、平成22年度は、先日の「あり方検討委員会」からの提言を踏まえ、市民が愛着と誇りを持てる美術館として、姿の見える新たな基本計画案をお示ししたいと考えています。市民の皆様や議会のご意見を踏まえて、ご理解の得られる基本計画が策定できましたら、早ければ平成28年度にも完成できるように取り組んでいきたいと思います。次に、重要文化財の泉布観でございますが、23年度中のオープンをめざし、民間事業者を公募する旧桜宮公会堂とあわせて、一体的に「泉布観地区」として再生を進めてまいります。22年度に3700万円を計上しておりますが、『ふるさと納税制度』による寄付金等を活用させていただきたいと思います。市民ボランティアなどが来訪者とふれあいながら「大阪のええとこ」を案内して歩くことで人気のコミュニティ・ツーリズム推進事業では、22年度は、コースの数を増やしまして、海外ビジター向けにも多言語音声観光ガイドも用意いたします。ますます多くの方に楽しんでいただけると思います。
続きまして、次代を担う人材育成でございます。未来の産業や都市を支えていくのは人であり、人材の育成は大阪市にとって大変重要な課題です。まず子育て支援です。私の公約であります保育所待機児童の解消につきましては、必要な入所枠を確保し、21年度末に待機児童を解消するための基盤がようやく整いました。そのうえで、22年度以降は新たな保育施策のステージへと展開してまいります。具体的には例えば、年度途中での低年齢児の入所希望が増えております。それに応える対策を新たに始めます。確かな学力の向上につきましては、学力向上強化戦略に掲げております習熟度別少人数授業の拡充などに継続して力を注いでまいります。高等学校につきましては、大学や産業界と連携して高校、大学のトータル7年間を見据えた、新しいタイプの商業高校を平成24年4月に開校する予定で校舎の建設を行いました。また、工業教育では産業界と連携し、エキスパートエンジニアの育成をめざした具体的な方策の検討を行います。
続きまして、雇用や年金など生活保障制度の再構築を視野に入れた、雇用と福祉の連携によるセーフティネットの構築についてご説明いたします。まず、市民から信頼される生活保護の実施ですが、『生活保護行政特別調査プロジェクトチーム』での議論を踏まえまして、22年度は市民生活を支えるセーフティネットとしての制度の適正実施と、不正を許さない厳正な対応の徹底に取り組んでまいります。特に、喫緊のテーマとして、社会参加によって地域との絆を回復していただき、自立を支援するという生活保障の原点に立ちまして、「働ける人には働いてもらう」という基本の確立と、大阪の実情を踏まえました貧困ビジネス事業者への対応、これにつきまして国に早急に具体的な提案を行ってまいります。そのうえで、雇用、年金など社会保障制度のあり方を含めた制度の抜本改革や、国民の最低限度の生活保障というナショナルミニマムとしての生活保護費の全額国庫負担、これにつきまして国に対して、制度改善に向けた具体的な提言を行っていきたいと思っています。市民生活と景気に直結する問題として、特に大変厳しい情勢にある雇用でございますけれども、これは最も重要で喫緊の課題であるとも考えております。先日、大阪府内の10月から12月にかけての完全失業率の速報が出ましたが、7.2%と依然として高く、生活保護受給者の増加にもつながっているほか、失業者の半数近くを若年層が占め、新卒の未就職者対策も急がれる状況にあります。この状況の解決に向けて、働く場を提供する就業支援事業を一層進めていく必要があります。22年度は、緊急雇用創出事業と先頃、国の2次補正で創設された重点分野雇用創造事業に、合計24億円を計上しております。この内、重点分野雇用創造事業は、今後、成長が見込まれる分野で新しい雇用を創り出すこと、そのニーズに応じた人材育成を同時に図るものです。例えば、働きながら資格をとる、介護雇用プログラムは、介護の現場で働きながら費用負担せずにホームヘルパー2級などの資格が取れるというものです。また、太陽光発電設備の施工の仕事に就き、実践的な技術を習得するというプログラムも用意しております。雇用側のインセンティブも確保しながら、将来の正規社員への就職につながるものになればと期待しております。あわせて、初めての試みになりますけれども、とりわけ急増しております生活保護受給者や新卒の未就職者に優先枠を設けました。最も困っている人に確実に雇用機会を提供することができたらと思っております。
さらに、早急に取組む必要がある課題として、次の5つに重点的に取り組んでいきます。その中で、あいりん地域の環境改善事業についてご説明いたします。おととしの屋台火災を契機といたしまして、また地元からの強い要望も受けて、今年度、萩之茶屋小学校周辺の道路上にある47件の屋台等不法占拠物件について全件撤去を行いました。30年来手が付けられなかった課題ではありましたが、『萩之茶屋地域環境改善特別チーム』を立ち上げて、庁内横断的な取組みを進めたことにより、また地域の方々や警察署等の協力もあり解決することができました。しかしながら、いまだ解決すべき多くの課題があり、この機を逃さず今後も重点的に取組みを進める予定でございます。先日、一部報道により、特に公園に関して、現場での誤解、混乱が生じているという報告を受けておりますが、22年度は、すでに地元と道路改良に向けて協議を始めております。そして道路の再不法占拠対策として、巡回パトロール、および立寄所の設置、そして30年近く閉鎖されている萩之茶屋北公園において時間帯開放に向けたフェンスの交換や老朽化した遊具の撤去などの機能回復を図ります。あわせて地域で意見を出し合える協議の場の形成支援などにも取り組みます。
救急医療対策ですが、去年10月に『救急安心センター』を立ち上げて以来、1日平均460件もの問い合わせがあり、常に医師に相談できることから、ご好評をいただいております。相談の結果、救急車が駆けつけて緊急手術を行い、事なきを得たなどの事例が14件もございます。21年度では国のモデル事業として始めましたが、これが21年度で終わってしまいます。しかし、今後も続けます。市民に安心いただける、いい事業だから「いっしょにやりませんか」という私の呼びかけに応じていただきまして、来年度は早速、堺市と吹田市など、およそ10市で参画していただけることになりました。私がいつも言っております、都市どうしの水平連携のいい例だと思っております。是非、取組みが広がっていくことを期待したいと思います。
それから、総合医療センター内に周産期の救急ともいえる『総合周産期母子医療センター』を、22年度中に開設いたします。これによりまして、重症の妊産婦さんや、ハイリスクの新生児にも対応できるようになります。地域の医療をしっかり支え、市民の皆さんの健康と安心を、これからも守っていきたいと思っています。
最後にまとめです。以上、ご説明した内容を都市のイメージとして申し上げますと、私の目標といたします『大都市、そしていちばん住みたいまちへ』とは、文化が薫る都市格を備えたまちと言えると思います。工業社会から知識社会へ、そして、経済成長のみを重視する社会から、心の豊かさや生活の質を重視する社会への変化を踏まえ、都市のインフラは人であり、その人間的な力が都市を成長させるという認識に基づいております。固有の歴史と文化を有するこの大阪で、新しい社会をつくるという知恵を備え、創意に富み、熱意にあふれた人々が集まることで、まち全体が活気づき、関西全体の繁栄にも貢献していく。そんな大阪市にしたいという想いを込めたものが今回の予算でございます。平成22年度予算としての説明は以上でございます。
記者
まず、市長に、全体を通してですね、今年の予算の、最後のまとめのところでおっしゃっていただきましたけれども、あらためて今回の予算、どういったところに重点を置いたのか、市長ご自身の思いの入れ方といいますか、そのあたりを教えていただきたいのが1つと、あと個別で申し訳ありませんが、今回、低炭素社会の構築というところに対して30億円入ってますけれども、大阪府ですとか国も同様の施策をやってるところもありまして、この中で大阪市ならではのカラーといいますか、大阪市のグリーンニューディールというか、そういった部分はどのようにお考えかというところ。で、さらに3点目ですけれども、市長がずっとおっしゃっている府市、または他都市との連携ですね、特に大阪府との連携というものを、今回の、今年度の予算の中ではどのように意識をされていたかという点、3点お願いします。
市長
はい。ありがとうございます。全体の予算としては、予算編成作業自体も今までとはずいぶん変えまして、1局ずつ聞いていたものを、関連する施策、事業に関しては、横の連携をとろうということから、複数の局に入ってもらった予算ヒアリングを行って、それぞれの局がやっている事業の関わり方みたいなものを見つめることができたかなあというふうに思います。そしてそれを、どう皆さんに見ていただくのか、市民に分かりやすく出せるのかということにも苦労いたしました。トータルとして考えた時に、やっぱり地固めの2年間をさせていただいて、そっから新たな方向性を導いていかないといけないということと同時に、それが大阪というまちの値打ちを上げるといいますか、都市格を再構築する、そういう意味では「都市のルネサンス予算」という名前をつけていただければありがたいかなあというふうに思っております。それから、低炭素社会の構築ということで30億円つけておりますけれども、その大阪市版グリーンニューディールといいますと、非常に大袈裟な感じもしなくもありません。しかし、やっぱり大阪市という基礎自治体であり、母都市というあらゆる機能を備えているまちだからこそできる多様な連携を模索するということが、一番大事なのではないかと思います。見える形としては、夢洲の奥にメガソーラを設置することへ、その誘致をかけていくことであるとか、あるいは、環境関連事業というものをおやりになっているところに、私を含め、政策企画室と連携をとりながら、どんどん企業誘致の動きをかけていく。さらには、海外都市との連携、これが低炭素社会という部分でいうと、日本、しかもその非常に大きなエネルギーに関する産業集積を持っている地域の優位性をどこまで表に出していけるかということを非常に小回りよくやるべきであると。それがなんで30億やねんと言われると、細かいところを全部、皆さんにお見せしないといけないことになるかと思いますけれども、今見ていただいたら、お分かりいただけるように、今まで、なかなか堂々とここを言ってこなかったみたいなところを、「はっきりと言っていこうよ」っていう形に、私なったと思うんです。さっきの森之宮の焼却工場にしても、「これは、もういらんやろ」というような話とか、ここには、もうれっきとした下水処理場の施設があって、こんなに近いところにあるものを、連携させへん訳はないやろうということを、今でいうと環境局と建設局っていう形になる訳ですから、知恵を使った、非常に財政が厳しい中で知恵を使いながら、環境であるとか低炭素社会をつくっていくうえで、この母都市であり力があると言われる、今やもう本当にぎりぎりの財政状況でありながら、知恵を使おうとする大阪市の形を、是非、皆さんに分かっていただきたい。で、こういったものを、やっぱり、地域、市民の皆さんといっしょに色んなことを連動させながら盛り上げていく機運というのをつくりたいというふうに思った次第でございます。
それから府市連携。ちょっとこの府市連携、言うた瞬間に、ぴぴっと、やや緊張するような最近の風潮はあるんですけれども、ただ、橋下知事との間でいいますと、連携に関しては、もうやれるもんはやっていくという基調は変わりませんので、ありとあらゆる連携に関して取組みを進めるということでいいかと思います。咲洲を見ていただきましたら、当然、来年度中には経済局がATCに移りますし、その経済局が移るっていうことはどういうことかっていうと、その『夢洲・咲洲地区まちづくり推進協議会』、これをより一層、具体的な動きにしていくためのあらゆることを考えてくれよという1つのサインでございます。それと同時に、府市連携部局というものも消えた訳ではございませんし、具体的にどういう名前になるのか、どういった陣容になるのかというのは、まだお互いに詰めをしているという状況でございます。それが見えてくることによって、さらに、まず私どもは、この夢洲・咲洲地区のまちづくりというものから、やれることを具体的に見せていく、府と市で見せていくという形になればいいのではないかと思ってやっていきたいと思います。よろしいでしょうか。
記者
生活保護に関して2点お伺いしたいんですけれども、まず来年度、生活保護費がですね、2800億円ですか、歳出の大きな部分を占めてるということについてのご感想と、あと、適正な実施に向けて13億円あまり計上なさってますけれども、そのポイントと、来年度具体的にめざされているところがなんなのかを、改めて教えていただきたいんですけれども。
市長
まず財政の硬直化っていうふうに言われますが、もう使い道が決まってしまっているというところに、これだけ巨額、多額を通り越した巨額の費用を計上しなければならないという部分について、大きな、やっぱり矛盾を感じております。で、これ自身が、例えば大阪市民で今20人に1人と言われる訳ですけれども、20人に1人の実態が果たして生活保護という本来めざすべき方向性と合っているのかどうかを、昭和25年以来、何度も申し上げますけれども、一切抜本的改革がなされていないということによる濁り、よどみといったものであるというのをはっきりと国に申し上げていきながら、具体例を挙げて改革を臨んでいきたいというふうに思っております。それと予算的にということでいいますと、13億のその中味。適正な実施に向けてっていうのは、これは、その中にはおそらく、細かく私見ておりませんけれども、新たにケースワーカーを配置する費用であるとか、ちょっと今資料を。(資料を探す)新規として入っているのが、2109万円を適正化推進チームの事業に使うであるとか、あるいは任期付職員で、これで3874万円であるとか、そういったものを積み重ねていくことと、それと、そのほか自立支援、これは全額国ということになるんやけど、国と市の、ごめんなさいね、ちょっと。細かい数字の内容というものを全部覚えておりませんので申し訳ないなあと思うんですが、要するに適正実施を求めるために何が必要なのか。それによって逆に、本来2880(億)って言ってた数字が、今回その最終予算では下げることになりましたが、これが適正化でもたらされる効果であるというふうにみております。で、その適正化というものは、今うち(大阪市)がやっておりますプロジェクトチームによる、適正化推進プロジェクトチームの中の、適正化推進チームによる動きで流れ出してしまっていたもののコックを適正に閉めるという動きにつなげていきたい。なおかつ、不正に受給している人たちに対して毅然たる態度で徹底した対応をしていきたいという形にお金を使わせていただく。ケースワーカーは今までも不足しておりました。で、それを今回、この間に一気に増えている生活保護受給者に、今やっている施策をきちんと対応させるためにも、必要な人員確保という形で使わせていただきたいということでございます。ごめんなさい。
記者
まず財政状況についてなんですけれども、まだ莫大な借金があるということと、税収の落ち込みということで、改めてなんですが、これをどう思われるのかということが1点と、それから先程、予算のヒアリングの時に複数の局でされたというお話もありましたけれども、コストカットについて何か今回の予算、工夫されたことがあるのか、2点お願いします。
市長
はい。財政状況、これは2600億というその長期の見通しを立てて、それよりもまだ、いったん悪い状況になりつつあった時期も当然ある訳ですから、どう盛り返すための施策を打つかということが必要ですけど、一母都市、大きい都市、基礎自治体、政令市、色んな言い方ありますけれども、一政令市でやれることは限られているっていうのが正直なところです。今回でも、その交付税として1222億円ですか、これがなければもうにっちもさっちも、もちろんいかない訳で。公会計っていうか、財政制度っていうものは、足らずを国からいただくと。その足らずと言える部分をきちんと支出しているかどうかという証明があるかどうかという部分ですから、これは国が1222億をおそらく交付税措置してくれるであろうという現在の見込みの上に立っております。で、それと同時に、414億やったっけ、400足らずの部分、これですね、446億円、これが足らんのです、はっきり。で、それを今、我々が持っている財産で補填するということですから、非常に苦労して練り上げてくれた予算だというふうに思っています。これでもまだ減債償還基金には手をつけていないということですから、「公債償還基金繰入金」というのは、これ剰余分と書いている、剰余分ですから、上積みしている部分を取り崩すということです。それから、部局がいっしょになって予算、これ細かく、ここを切ったとかですね、ということを今、ちょっと例示はできないんですけれども、やはり、ヒアリングを受けている、予算ヒアリングを受けている中で、この予算って、ほんとは、じゃあこっちの、例えばA局とB局が並んでヒアリングを受けている時に、同じような事業の場合は、この予算はこっちの局でやれるんちがうんかという形で、随分とならす作業はやりました。ですから、それが具体的な施策を打っていく際に、主体となるのはこの局、応援部隊としてこの局あるよっていう認識にも、職員の相互認識にもつながったという意味で、それが長い目でみるっていうか、具体的な数字のコストとして挙げられはしませんけれども、確実にコスト削減効果につながってるというふうには思っています。
記者
「都市のルネサンス予算」とお名前をつけられて、これまでの地固めの2年間から新たな2年へというぎりぎりの中で、未来に向けて力を使ったというようなことをおっしゃってたんですけども、すみません、また非常に月並みな質問で恐縮ですけど、例年出てるんで、採点すると何点ですか。
市長
100点です。
記者
去年と同じ。
市長
はい。ほんとにこれだけ厳しい財政状況の中ですから、点数つけるとしたら100点でしょう。で、その100点を、この22年度の予算を執行していく、その執行段階もきちんとチェックすることによって、120点にも130点にもできるという形につなげていきたいと思ってます。
記者
あと、すみません。今年の平松カラーという意味でいくと、その、都市のルネサンスという。
市長
あのね、やっぱり『人間力』というのを1月に書かせていただいた、これは自分自身が底に流れているものをしっかりと入れた言葉だと思います。で、あらゆる人と、今キャッチフレーズで『いっしょにやりまひょ』って言わせていただいているこの言葉も非常に気に入っていまして、どこへ出ても「いっしょにやりまひょ」って言える軽い感じと、「いっしょにやりまひょ」っていう促す感じと、あらゆるトーンを使い分けることができますんで、市民協働の輪をより一層強めていきたいというのと同時に、主体となられる市民と地域、その地域から市政改革、市政を変えるということを主眼に置いて活動していきたいなと、22年度は区役所の役割強化、それも、今までですと、区役所の役割強化と言うた途端に24区の区役所が対象になったんです、全部がね。そうじゃないよっていうことをはっきりと言わせていただいてます。これは行政改革検討委員会でも、そういう方向性っていうのがしっかり出始めておりますから、まさにその大阪市が変わりつつあるというところを認識していただける、感じていただけるような予算の執行体制になればと、今気を引き締めているところです。
記者
法人市民税がピーク時の3分の1近くまで減っているということなんですけれども、これ景気低迷ということも当然あるかと思うんですが、企業流出とかですね、そういう構造的な問題もあるんじゃないかという気もするんですけども、その辺りの認識というのが1点とですね。先程、質問出ましたけれども、生活保護のことで、これだけ職員も、だいたい関係職員の方400人ぐらい増やすってことになると思うんですけれども、これだけ人と金の、金というこのエネルギーですね、生活保護行政に注ぎ込まざるを得ないというこの状況についてどう思っていらっしゃるかという。
市長
企業誘致は積極的に仕掛けてまいります。それは経済特区であるとか、特に規模的に言いますと、やっぱりベイエリアというのが一番可能性が高いと思います。で、それと連携する形で北ヤードへの研究機関の呼び込みであるとか、アジア太平洋センターの構想であるとか、そういったものがリンクしてくるものだと思います。やっぱり、先日もこの市役所の1階ホールで、介護ロボットであるとか、関西が持っている今まで開発してきた二足歩行型ロボットではない、また新たな視点でのロボット、それが具体的に海外では実用化される動きがある。そういったものを連携をとるということで、今日はフランス、デンマークという2つの国をご紹介しましたが、そのほかにも色々な場所とのリンクを図っていきたい。そういう意味でも、先日東京では大使館公使を相手に来ていただいて、都市プロモーションをやらせていただきましたが、大阪が持っている可能性っていうものは、我々、ここに住んでいる者が感じる以上に、東京におられる、日本にある在日外交官の方たちにとっては新鮮に映ったように私は感じております。それを進めるということで頑張りたいと思います。それから、生活保護でございます。確かにおっしゃるように、これ、生産を生まない出費と言っていいんだと思います。で、それを本来あるべし形にするためには通らなければならない出費であると、支出であるという観点で取り組みます。ですから、それを取り組むことによって、逆に今まで気づかずに漏れていた、漏水していた部分にしっかりとパテをあてる。さらには、間違った配管をしていたところは完全に閉ざすという形で、しっかりと国に対しても、このやり方では、こういった事例がどんどん出てしまいますよというのを、プロジェクトチームでの会合でまとめた形で国に持っていくという、その現場とそれから国に対してとを、しっかり連動させながら動いていきたいと思います。はい。
記者
今言われた企業集積とちょっと関係するかもしれませんが、国内最多のですね、中小企業対策の関係なんですが、中小企業の関係で、現状の認識を教えてほしいんですが、今回、例えば緊急保証制度のようなですね、融資施策をやってる一方で、預託金が非常に増え、預託金が増えたりとかしている現状がありますよね。企業、かなり資金繰りに困っていると。で、その結果ですね、税収減につながってくるというこの悪循環に陥っています。この現状についてどう思われるかというのが1点です。2点目は、先程、言われたその環境基金のような、儲けると言ったらあれですけれども、そういう施策も打っていかれるというふうな姿勢は分かるのですが、それだけではおそらく、財政かなり立ち行かない状況で、今回の切り込まれなかったいわゆる市民サービスの、一定我慢していただくという、諦めていないとおっしゃっられてましたけれど、例えば敬老パスの有料化であるとか、上下水道の福祉減免であるとかですね、もうここは立ち行かない、財政が立ち行かない中で基金を取り崩して、今回はなんとかされましたけど、ここに、今回切り込まれなかったというかですね、まだされるということをおっしゃっているのかもしれませんけれども、これはどうしてなのか、または、いつ頃やろうと思っているのか、そこらへんを教えてほしいというのが2点目。
市長
はい。中小企業の現状については、非常に厳しい状況を脱していないというふうにも聞いております。ただ、あらゆる施策を打ちながら、うち(大阪市)が持っている産創館の機能を、より一層拡充するという方向で、支援できるところは徹底して支援していこうと。それと、『大阪あきない祭り』に象徴されるように消費拡大のキャンペーンを、適宜、タイミングを見計らって打っていくということで、しのぎたいと思っています。ただ、売りづくりという点で、本当にビジネスマッチングと従来言われてたマッチング機能だけではなくて、海外の事例、あるいは海外のニーズといったものを具体的に探る動きもようやく出始めていますので、個別に見ますとね。そういったものをどんどん広げていくことで、かといって、全体の中小企業が、それで、うち(大阪市)は20万あると言われているんですかねぇ、事業所が、それを一気に底上げできるとは思っていません。ただ、景気っていうものは、何かそのパイロットになるようなものが、1つ灯りがともると、そこにこう、集積してくる傾向はあると思いますんで、是非それを早く活性化させながら導いていきたいと思っています。これだけ厳しい中で、市民サービスにどこまで切り込むのかということでございますけれども、前回のパスの、敬老優待乗車証の件、あるいは、福祉、水道、上下水道の減免ということにつきましても、反対の一番大きな理由として議会がおっしゃったのは、「雑巾絞りきったんか」という議論だったと思います。今回、この間、ずっと三千数百という事務事業の総点検をやり、なおかつ、来年度も事業仕分けを、大阪市、徹底してやろうと思ってますんで、そういったものの中から、今後の景気動向にもよりますけれども、本来我々が見直そうとしているのは、やっぱり、受益と負担の原則というものをしっかりと市民の方に分かっていただくという努力を続けたいと思っていますから、完全にあれはなくなりましたということではございません。今回は、出していません。
記者
先程、市長、人間力が都市を成長させるという、地域の人の力を活かしてですねっていう、今後の市政の大きな骨格みたいなところを打ち出されたと思うんですけども、それをですね、実際に本当に、その理念をですね、本当に実現するということは非常に難しいものだと思うんですね。で、例えば職員がいっしょになってやるとかですね、本当に若い人がそういうとこに加わっていくということがほんまにできるんかなというところで、もしかしたら、それ言うだけで終わってしまう可能性もあるということなんですが。じゃあ、どういうふうに具体的にね、そういう難しい所にアプローチしていくのか。今打ち出してますけども、そのへん市長、どういうふうに考えていらっしゃるのかっていうこと、お願いします。
市長
おっしゃるように、この非常にでかい、非常に大きな大阪市の組織で、たくさんの職員がいますから、私が言ったことがすぐ隅々まで浸透するというような楽観視はしておりません。かといって、方向性が正しいという、私は自信を持っておりますんで、これをどこまで深化できるかっていうのは、折に触れ、機会のあるごとに発信し続ける以外にないであろうと。で、予算的にはですね、やはりかなり特徴のある、区役所対策っていいますか、新しい区役所への、区役所の自主性というものを尊重する形をとらせてもらいました。そうはいっても、その区役所全員が、じゃあそこに向いて走り出すかっていうのは、それも楽観視しておりません。でも、言わないことには始まらない、で、言うことで始めようというものを、この2年間経験させていただいています。この2年間走り続けたことによって、確実に変わりつつある現場というものも、市民の方からも「変わってきたよ、最近」というふうに伺うことも多々ありますし、私が町の中歩いてても、これはやっぱり見える形でやらせていただいている違法駐輪の問題とか、街頭犯罪の発生件数であるとか、変わりつつある大阪というものを感じていただいて、それに乗り遅れない形で動いてもらうというしかありません。でも、それをやりきりたいという、そういう思いで自分はおりますので。これが全く、暖簾に腕押しみたいな感覚の市民ばっかりがいらっしゃるようだと、たぶんここまで強い思いを持たなかったと思いますが、行く先々で非常にリアクションのいい、手ごたえのある市民の方たちとの協働という形が、今、動き始めてます。それに気づかない人も、市役所の職員でようけいると思います。でも、気づかない人が、「あっ、俺は遅れてしまった」、「私は遅れてしまった」と感じるような動きにしていきたい。で、それを言い続けることによって、きっと変わる人たちがいると信じてます。