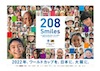平成22年7月8日 大阪市長会見全文
【FIFA視察時に大阪をアピールします】
皆さんこんにちは、よろしくお願いします。今日は、ワールドカップの話題でございます。今朝方、2010FIFAワールドカップ日本代表チームを率いられました、大阪市出身の岡田武史監督に、『大阪元気アップ大賞』という市長特別表彰でございますが、贈らせていただきました。その際、セレモニーに参加してくれた子どもたちに対して、本会議場で岡田監督から、本当に素晴らしいメッセージを子どもたちに贈っていただいたことも、私、印象に残りました。お昼のニュース等ですでに放送していただいた皆さん、どうもありがとうございました。残念ながらベスト8までに残れませんでしたけれども、日本代表チームの奮闘というものは、日本中にさわやかなブルーの風を吹かしてくれたんではないかなというふうに思いますし、それと同時に、あの際にも申しましたように、チームプレイ、連携プレイ、それぞれの個性という、これは岡田監督がおっしゃってましたが、それぞれの個性をどう伸ばすかという、そういう方向性も素敵なお話でございました。こういった感動を是非、12年後の2022年、再び、ここ大阪で味わいたいという思いが、より一層強くなっております。そのためにも、国に国立球技場としての建設、あるいは、まだ土地のほうの問題もございますし、是非、前向きに動くように、そして今年の12月2日に開催地の決定ということになります2022年に、日本は立候補している訳ですから、本当にいい結果が出るようにと思っております。この夢の実現のために、重要な鍵を握るのが、FIFA関係者の視察でございます。視察は7月19日から22日にかけて行われますが、視察予定の詳細につきましては明日、招致委員会から発表される予定になっております。しかし、視察団が来られる際には、私も公務日程を視察日程という形にシフトをさせていただいて、招致委員会の皆さんとともに、大阪・日本のプレゼンテーションを行ない、アピールしたいなと思っております。そして、招致委員会との共催という形になると思います、大阪市公館にFIFA関係者の皆さんをお招きして、レセプションをさせていただくことになっております。このレセプションでも、大阪が誇る、おもてなしの心というものをアピールできればなと思っておりますし、そういったことの積み重ねから、招致実現につなげていきたいと思っています。2022年ワールドカップ開催が決まるのが12月2日ということですから、もう150日を切っております。大阪・日本での開催実現に向けまして、招致委員会に全面的に協力し、多くの市民が大阪市で開催されることを待ち望んでいるという、そういう熱を視察団の方々にお送りできればと、こういうふうにも思っております。
その1つといたしまして、こちらに出ましたが、市役所の御堂筋側壁面に、7月の17日から7月31日まで、これは横断幕と言っていいんでしょうか、これを掲げます。デザイン的にはピッチをイメージしております。ピッチをイメージしたデザインに、「大阪に、緑を。そして大阪に、夢の舞台を。」というコピーをのせまして、FIFAをはじめとするサッカー関係者や世界にアピールしようというものでございます。この大きさなんですけれども、縦が13m、横が19mになっております。それから、小学生たちにワールドカップ大阪開催への思いをカードに書いてもらうように募集しましたところ、およそ4万5千枚もの熱い思いが寄せられております。一部を市役所1階正面玄関ホールや各区役所に7月1日から展示しておりまして、子どもたちのメッセージをFIFAの視察の時に、紹介することにしております。
さらに、7月13日から20日まで、梅田、淀屋橋、心斎橋、天王寺などの主要駅では、これでございますが、「ワールドカップを日本に、大阪に」というポスターを大々的に貼らせていただきまして、機運を盛り上げ、FIFA関係者に訴えたいと、このように思っております。本日は以上でございます。
その1つといたしまして、こちらに出ましたが、市役所の御堂筋側壁面に、7月の17日から7月31日まで、これは横断幕と言っていいんでしょうか、これを掲げます。デザイン的にはピッチをイメージしております。ピッチをイメージしたデザインに、「大阪に、緑を。そして大阪に、夢の舞台を。」というコピーをのせまして、FIFAをはじめとするサッカー関係者や世界にアピールしようというものでございます。この大きさなんですけれども、縦が13m、横が19mになっております。それから、小学生たちにワールドカップ大阪開催への思いをカードに書いてもらうように募集しましたところ、およそ4万5千枚もの熱い思いが寄せられております。一部を市役所1階正面玄関ホールや各区役所に7月1日から展示しておりまして、子どもたちのメッセージをFIFAの視察の時に、紹介することにしております。
さらに、7月13日から20日まで、梅田、淀屋橋、心斎橋、天王寺などの主要駅では、これでございますが、「ワールドカップを日本に、大阪に」というポスターを大々的に貼らせていただきまして、機運を盛り上げ、FIFA関係者に訴えたいと、このように思っております。本日は以上でございます。
質疑応答
記者
すみません、ちょっとサッカーとは関係ないんですが、ごめんなさい。生野補選のことについて、まずお願いします。生野補選、結局、武(なおき候補)さんのマイク握られることにしたんでしょうか、どうでしょうか。
市長
えっと、今のところと言いましても、もうあまり日にちございませんので、おそらく握ることはないと思います。はい。
記者
当初ですね、握る可能性もあるということでおっしゃってたと思うんですが、その握ることないとお決めになったのは、どういう理由からですか。
市長
いえ、当初から決めていないということで、私申していたはずでございます。ただ、今までの等距離と少し違う踏み込み方ということで、皆さんからは代理戦争というような見出しを頂戴したりしてる訳ですけれども、これは選挙公報、それからビラですね、候補のビラに私の名前を、そして写真を使っていただいたということで、一歩踏み込んだということにはなると思いますが、はい。
記者
6月の25日の会見で、民主の候補を応援するとはっきり明言されてたのは市長ご自身ですから、それに関しては割とそんなに、そういった割には踏み込まなかったな、という印象なんですけど。
市長
「応援します」というメッセージをビラに載せているということで、今までとは全然違うスタンスだと自分では思っておりますし、で、こういった動きも何度も申しておりますように、1人という、民主党からお1人だったと、自民党、公明党さんの候補がいなかったということから、そういう決断をしたものでございますんで、自分の中では、これで適当な判断かなと思っておりますけれども。
記者
はい、分かりました。ありがとうございます。
記者
関西広域連合について、大阪市のほうが入っていくというようなことなんですけれども、これ、いつそれに参加されるということなのかというのと、2点目は、今まではですね、オブザーバーという形で、積極的ではなかったと思うんですけど、このスタンスを変えられたのはどうしてか。で、3つ目はですね、4日のタウンミーティングの時に、市長は市民からの質問にですね、「関西州をつくる主体に大阪市はなりません」ということをおっしゃってたと思うんですが、この発言と今回の行動というのは整合性が取れてるように私は思えないのですが、それはどういうふうにご説明されるのか。
市長
はい。まず、いつ参加するかということなんですが、参加しようにも、現在まだ存在しないものでございます。で、関西広域連合というものが、おそらく、この滋賀県の知事選挙を終えて、具体的な動きになっていくんだと思いますが、その段階では、我々政令市の参加について、正式参加ですね、想定されていないような手続きの状況が進みつつあるということですから、いきなりのっけから「入ります」って手をあげると、逆に事務的な混乱に陥る恐れは感じますんで、入る時期は問題にしていません。で、向こうの広域連合が立ち上がって、そこにいつでも政令市入れますよという形になれば、神戸・京都等とも堺とも相談しながら、その関西の中にある力のある都市が、広域の中でどういう役割を果たすべきかみたいな形で入っていきたいと思っています。で、なぜっていうのが、今の中に含まれている訳でございますが、私たちがめざす、その広域というものの、例えば関西州という呼び方にしても、これは何のためにつくるのかっていうと、やっぱり地方分権、地域主権という大きな流れの中で、いかに広いところを効率よく、そして経費を少なくしながら、一番核になる、住民と一番近いところがしっかりと自治をやっていくという形になるはずですから、より一層小さく我々の方向性を固めるのではなく、広い提携という都市間連携、あるいは都市連合という言葉を使ってらっしゃる方もあるようですが、それを具体化することによって、より一層、府県の境を越えやすくする働きは我々ができるのではないか。ですから、関西州の主体は我々ではないというのは、まさしくそこにありまして、我々というのは、例えば大阪市ではないという意味で。単に大阪市が関西の主体になるのではなく、それぞれの地域主権の担い手である、あるいは、その小さなコミュニティの担い手である市民の思いというものを、どれだけ効率よく国の施策、地域の行政に生かせるかという形を追求すべきであろうというふうに思っております。で、4日のタウンミーティングの際に、関西州の主役では大阪市はないというふうに申しましたのも、そういう理由から申し上げました。
記者
すみません、間違ってたら。多分、市民の方はそういうふうに受け、多分そういう今みたいな説明がなかったんで、そういうふうに受け止められなかったかもしれませんが、市長はあの時の説明でも、関西州は大阪都ではなくて、とおっしゃってたかどうか分かりませんが、関西州をめざすんだとおっしゃっておられたのであれば、積極的にそれを進めるという意味で、今回、広域連合のほうにも参加したいというふうに思われたのかなと思ったんですが、そういうことではないのですね、今の説明では。
市長
いや、つまり府県同士の話し合いの進み方のテンポ等を見てまして、やっぱり枠組みだけの話になりそうであるということを感じました。ですから、これから我々っていうものが地域主権の担い手である市民を一番近いところで、その効率であるとか、進めていかなければならない立場でありますから、その立場でもって、広い広域、関西州というものの中でどうあるべきかっていうものを、都市間連携、あるいは都市連合という形で、核になるのは現在のところ、割と狭い地域の関西州になります、コンパクトな。今、大きく話がされているような範囲までは、多分含んでおりません。私どもが考えられるのは、やはり、ずっとこの間やってきた4都市連携、京阪神・堺という、この政令市4市の非常に密接なつながりって言いますか、地理的な近さみたいなものから連携をする。さらには、私どもでも隣接都市協議会っていうものがございまして、大阪市と市域を接している市との連携というものも模索してます。そうした細かい単位でのつながりと、それを、府県を越えるつながりとを融合させる動きをとっていきたい。これが具体的にですね、例えば、今、おっしゃってるような、例えば大阪都みたいな形に、すっと言えないのは、逆にそういう細かい単位が色々と、色んな思いでもって、その地域を支えるであろうという気持ちから、ワンフレーズで言いにくい部分ではあるんです。それを、区というもので、今さらに我々はその内容を深めようということを大阪市域の中でやってる訳ですから。それぞれのコミュニティっていうものが何を欲するのか、どう自分たちで動くのかということで考えればいいのではないかなと思って、整合性とかいう部分で、そこまで疑問を自分では持ってないですけどもね。はい。
記者
今の関西広域連合の話なんですけれども、なぜ今なんでしょうか。まず、そもそもですね、今、市長は関西広域連合に参加したいという気持ちをお持ちで、それを今、表明しようということでよろしいんでしょうか。
市長
関西広域連合自体がまだ存在しておりませんから、そこがどういう形になるのか、ただ方向性としてはもう聞いております。それは関西広域機構というものが長年積み上げてきた中から、まず、やれるところから提携していこうということを、私は市長になってすぐの広域機構の会議で聞いた覚えがあります。ただ、その時にも、屋上屋を重ねるのではないかとか、色んな議論があったことも承知しています。一方で、やはりこの間、政権交代があり、それぞれの市民が地域主権、あるいは地方分権という言葉になじんできた現状を考えると、自分たちがめざす社会というものは、やっぱり自分たちのこの立っているところから、きちんと自分たちの思いをつなげなければならないのではないか。じゃあ、今まであった広域の自治体のありようっていうのは、これでいいのだろうかということを考えた時に、やはり進むべきはそういった広い単位での、薄く広いというものであろうと。で、その中で、ただ地域が壊れてしまうとか、都市が壊れてしまうとかいう問題ではなくて、それをしっかり支えながら、そういう広いものをつくりたいという思いがあるから、今、申し上げました。はい。
記者
今、先ほど市長がおっしゃったように、政令市自身が参加できるかどうかも分からないような、で、また、枠組みだけかもしれないような中で、なぜ今なんでしょうか。
市長
はい。ですから広域機構の動きの中で、この秋にも広域連合というものがつくられるであろう。ところが、我々はオブザーバーとしてしか参加していないという現状がございます。で、本当にその広域の、関西広域、ごめんなさい、関西州というものをめざされる関西広域連合という動きになるんであれば、ちょっと井戸さん(兵庫県知事)とはまた違う考え方になるのかもしれませんけれども、そういう動きになるんであれば、その下準備の段階、あるいは助走の段階から、我々、京阪神・堺という都市間の連携、提携、具体的な動きを色々お示しする中から、「あっ、そういう提携なら、うちでもできるわ」というような形で全国に広がってってほしいなという思いがあるから、できたものに入る、確かに段取りとしてはそうなるんでしょうけれども、今からそういうアピールをすることは決して無駄ではないと判断したから言わせていただきました。
記者
橋下知事の、橋下代表の大阪都構想への対抗であるとか、もしくは生野補選に向けての何かのアクションであるとか、そういったこととは全く関係ないということでよろしいんでしょうか。
市長
えっと、今、選挙中ですので、やや微妙な発言になりますから、そうですね、全くないとは言えません。ただ、この間、広域連合というものであれ、関西州というものであれ、当初、地方分権が言われた時と比べますと、全体の興味、あるいは流れといったものが、ややそうではない方向にいっている危惧は感じております。ですから、本来この国をどう立て直すんかということを考えた時には、やっぱり地方分権、地域主権という流れであることは間違いない訳ですから。それは二重行政とかいう言葉自身が、昭和30年代より前から言われている言葉がいまだに解消していないっていうのは、制度の問題に帰結する部分と、それとそれぞれの土地が持っている特性っていうのがあると思いますけれども、多くの方々がそういった言葉に敏感に反応されるという現状を見た時に、より一層広い広域行政というものを、しっかりと国民が意識しないといけないし、もう一方では、地域、コミュニティっていうものが、今こそしっかりとこの国を支えないといけないんだという思いを言えるのは、やはり直接行政をやってきている大阪市みたいなまちであるとか、あるいはそれぞれの基礎自治体からであろうと思うから言わせてもらいました。
記者
すみません。その組織の中に入って大阪市は何をめざすんですか。
市長
はい。やはり、これからの地域主権のあり方というものに対する単位としてのコミュニティがどうつくられるのか、それを我々は今つくろうとしています。で、そのつくっていくモデルとなるような地域の本当に積極的な人々っていうものを、私は目の当たりに、全員ではございませんけれども、させていただいております。そういった方たちと、この大阪市役所がいっしょに動くことで何が起きるのかということを、是非、多くの人に見ていただきたいし、その結集こそが、この日本をしっかりした土台からもう一度築き上げる1つの単位になるであろう。もちろん一方では、もっと、もっと開発しなきゃだめだとか、あるいは工業投資をどんどんぶち込んで景気をよくするんだという方たちがいらっしゃることも承知の上で、今、我々がめざさねばならないのは、いや、そういう方向性ではなくて、むしろ、もう一度我々の地域、成り立ち、コミュニティといったものをしっかりと見つめていく動きのほうが必要であろうと、そう思うから、そういう役目を大阪市として、基礎自治体、地域主権の世界っていうのは広くあっても、1つのコミュニティというのはしっかりしてないとだめな訳です。でないと、中央集権というものが今まで築いてきたものが、薄皮のままに見えてより一層、二層性の中央集権という形になる恐れだってある訳ですから、そうはなってほしくないという気持ちから、今、言わせていただいている部分もございます。はい。
記者
生野補選の件と、あと生活保護の件でちょっと2点お伺いしたいんですけれども、まず生野補選のほうなんですが、先日のタウンミーティングに関してですね、橋下知事と市長の代理戦争云々というのは置いといて、公職選挙法上で、政令指定都市の中では、告示日から選挙の行なわれる当日まで演説会などを、政党その他の政治活動を行なう団体は行なうことができないという条文があるんですけれども、先日、市長は政治活動にあたらない、市長としてやってるというふうにおっしゃってましたが、そのタウンミーティングそのものっていうのは、公職選挙法に抵触するものではないというふうにお考えなのかっていうのを、あらためてお伺いしたいんですが。
市長
あのタウンミーティングが、どういう形であったのかというのは、ご覧いただいた方にはお分かりいただけると思いますが、政治活動と取られないように、随分、気も遣いましたし、単に私どもが大阪市政が進んでいない、改革が進んでいないと言われる中で、きちっと市民の皆さんに聞いていただこうということでやりましたので、触れないと思ってやっております。はい。
記者
ありがとうございます。あともう1つ、中国人の生活保護の集団申請についてなんですが、先週の市長の会見の中で、確証は無いと前置きされたうえでなんですが、貧困ビジネスの可能性も否定できないというふうに。
市長
先週ですか?先週?
記者
先週。
市長
先週の定例?
記者
はい。会見で、確証は無いと前置きされたうえでなんですが、貧困ビジネスの可能性も否定できないとおっしゃってたんですけれども、その認識は今お変わりないですか。
市長
この認識については、当時も条件付けで申し上げました。で、実態がまだ分かりません。ですから、それについては何も言えない現状であるというのと同時に、今、入国管理局で、その審査内容の見直しでありますとか、見直しじゃないな、再検討かな?どういう言葉を使えばいいのかな、一番いいのが。
健康福祉局生活保護制度担当部長
はい。入国管理局のほうでは精査をしております。はい。
市長
精査。精査ということの結果を待っておりますんで、それと同時に私どもが、やはり身元引受人の方が、どういう方なのか、どういうおつもりで、あれだけ多くの方の身元引受人になられたのかということが分からないと、何とも言いようがないというのが現状だと思います。はい。
記者
ということは、今の段階では少なくとも、ご発言を撤回されるお心づもりはないということでしょうか。
健康福祉局生活保護制度担当部長
すみません、健康福祉局のほうから。今、中国国籍の方々の、申請中の方、あるいはすでにもう決定されてる方につきまして、やはり我々はケースワーカーのほうもどういう生活実情にあるかということを、今、調べておるところでございます。で、貧困ビジネスというものが、例えば犯罪ということに結びつくのであれば、大阪府警さんのほうにも状況はご説明を申し上げておりますので、今、現在は色んな角度からですね、検討していると、このようにご理解いただいたらいいのかなと思います。
市長
発言を撤回っていうのは?
記者
私どもで取材しておりますと、貧困ビジネスと言うには、ビジネスで儲ける人がいないのではないかという、あくまでも私たちの取材の過程での認識なんですけれども、そうなってきますと、貧困ビジネスというふうに確証無い中おっしゃったということがありますので、それについては、ある程度の名誉回復とか必要ではないかと思うんですけれども。
市長
前提条件をつけたうえでの発言でございますので、で、なおかつ、我々がやっているプロジェクトチームでの動きがあったからこそ上がってきた情報であり、で、そういった情報をほとんどの方がご存じないまま、日常生活の中でコミュニティを支えていかないといけない、その市の当局者もいる訳で、で、そこへいきなりその日本語を話せない方たちが大量に入ってこられた。じゃあ、それをどうすればいいのかっていうことも対応しないといけない訳ですから、我々は。対応して当たり前な訳ですから。そういった意味で言うと、なぜそうなったのかと、で、もともとそのプロジェクトチームっていうものは、この生活保護行政が持っている矛盾であるとか、長年の、完全に時代遅れになってしまっている部分、あるいは現金給付の問題性、そして医療費の問題とか、あらゆる部分にもう一度大阪市が先頭に立ってメスを入れていく、あるいは今もっている我々の矛盾している情報を総合することによって、この制度の持っている問題点というのが浮かび上がってくるということでやってまいりましたんで、その時々の反応の発言を1つ1つ、前提条件無しに私が決めつけたんであれば、もちろん名誉回復の為に謝罪もいたしますし、そうでないというつもりでお話をしておりますんで、是非その辺は分かっていただきたいというのが正直なところです。
記者
ありがとうございました。
記者
今日の発表、サッカーワールドカップ、19、20日にFIFAの視察が来られるということで、市長、公務を視察にシフトなさるっていう、具体的にはどういうことを今、指示されていらっしゃるのか、ちょっと教えていただきたいんですけど。
市長
やはり、そうですね、いらしたら多分いっしょに行動しながら、で、今は何も建っておりませんけれども、ここが我々が予定している国立球技場を誘致しようとしている現場ですというような形でご説明すると同時に、今、先ほどもポスター出ましたけども、208スマイルですか、その全ての世界の地球上の国々で、サッカーに親しんでいる国々の大きな総意として、2022年、子どもたちの夢を乗せたFIFAワールドカップが、この一日に250万人の乗降客があるというターミナルで、これはつまり、環境問題とかを考えましてもね、郊外に大きなものをつくって、そこへどんどん車で行って下さい、あるいはそれに新たに線路をつくるというのもありかもしれませんけど、色んな手段で来られる真ん中に、それが一日に250万通常で動いてるんですよというだけで、やっぱりものすごいインパクトが私あると思いますから、是非そういうことで、将来の、未来のエネルギーも含めたモーダルシフト、さらには、そこには太陽光発電等も含めた環境、エコっていうものを二期の中心に、全体ですね、あのエリア全体に据えていますんで、そういった訴え方を、これだけ大都会の真ん中で堂々と、大々的にエコを言っていけるまちは他にはないんじゃないですか、みたいなことは訴えたいですね。
記者
すみません、大阪市の公館でレセプションをなさるというのは、これは日取り決まってらっしゃるんですか。
市長
この日程も明日、20日?はい、20日の夜?
ゆとりとみどり振興局スポーツ部長
20日の夜です。
市長
はい。
記者
先月なんですけれども、大型客船のクイーン・メリー2、QM2の関係で、キュナード(・ライン)のほうから、横浜から大阪市への寄港が来年3月、発表されてたんですけれども、これについて、15万トンクラスっていうのが、初の関西入港ということになりますんで、大阪市、受け入れる側の、それを受けた時のご感想と期待、それと課題みたいなものを、取組みですよね、大阪市として、どのような形で今、港湾局さんも含めてお話進められているかなというのを教えていただければと思います。
市長
今日は港湾局は来てないよね。はい。
情報公開室長
来てないです。
市長
クイーン・メリー2、本当に世界最大級の豪華客船と言われているものの入港、確か来年春だったと思いますけれども、について準備を進めるという方向と、それと同時に、やはり多くの観光客に大阪の素晴らしいところを見ていただきたいという思いがございます。で、また夏にはこれも上海から来ると思うんですが、イタリア船籍のクルーズ客船が入ってくる予定もあるように聞いてます。そんな中で、これはまだ結論は出ておりませんが、国際コンテナ戦略港湾という、港湾でありながら大都会に近い、しかも歴史も文化もあるという奈良・京都を後ろに控えて、そこへ海から多くのお客様を迎えるというのは、やはり古代から海を通してつながっていた大阪ならではの雰囲気が醸し出せればというようなことを今、考えておりますけれども、まだ具体的にはこれをこうしたいとか、ああしたいとかっていうのはこれから練り上げていく形になると思います。港と言いましても、あそこは今、天保山の岸壁になると思うんですけれども、水深の問題、航路の問題等をきちっと大丈夫ですという形でお迎えしてこそ、大阪の港はいいなっていうふうに言っていただけると思うんで、港湾局にその辺は頑張ってもらおうと思ってます。現時点では大丈夫なんですけども、大丈夫な中で、より安全に、快適に入っていただこうと。で、より多くのそういった海外からのクルーズ船、今クルーズブームにもなっているというふうに聞いてますんで、空は関空から、海は天保山へというような形になればいいなと思っています。はい。
記者
ありがとうございます。