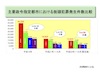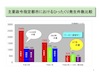平成22年7月23日 大阪市長会見全文
【喜多俊之氏を市長特別顧問に委嘱します】
皆さんこんにちは。先週、ひょんなことから立ってやろうかって話になりまして、今週からスタンドでやらせていただきます。
はじめに、本日は市長特別顧問に就任していただきます喜多俊之(きた としゆき)さんにご同席していただいております。ありがとうございます。先程、市長特別顧問の委嘱状をお渡ししたところでございます。改めまして、喜多さんのご紹介をさせていただきますが、液晶テレビなどの家電、家具、ロボット、家庭日用品に至るまで、幅広い分野で多くのヒット商品を生み出され、その作品はニューヨーク近代美術館やパリ・ポンピドゥセンターなどにコレクションされており、まさに世界的な工業デザイナーとして活躍されておられます。また、現在、シンガポール、タイ、中国政府のデザイン顧問や、大阪芸術大学のデザイン学科長を務められるとともに、日本の伝統工芸や地場産業の活性化にも関わっておられます。現在、本市では経済成長戦略の策定に取り組んでおりますけれども、その中で、大阪を活性化させるためのアプローチを検討しております。喜多さんには、これまでのご経験を活かしていただき、創造的なまちづくりの観点から、プロデューサー、デザイナーの立場で、アドバイスを頂戴してまいりたいと考えております。
また、こちらをご覧いただきますと、上海万博「日本産業館」の壁面を梯子で上り下りするロボット『夢ROBO(ロボ)』が話題を呼んでおりますけれども、その総合的なデザインをされたのが、こちらにいらっしゃる喜多さんでございます。私も来週28日、「なにわの日」に合わせて上海万博にまいりますんで、実物を見せていただくのを楽しみにしております。それでは、喜多さんから、特別顧問就任にあたっての抱負と申しますか、お考えをお話しいただきたいと思います。喜多さん、どうぞよろしくお願いいたします。
それから、これはですね、大阪は3、40年前までは日本で一番の国際見本市のまちでしたね、皆さんご承知のように。で、それをひとつ、リビング&デザインという国際見本市を去年立ち上げていただきまして、インテック(ス)大阪ですね。住まいのリノベーション、いわゆる今、大変日本の住まいが戦後ですね、たくさん建ったんですが、小さくなってしまって、間取りも小さい。その結果、どういうことが起こってきたかというと、納戸化が進んでしまって、この納戸化が進んでしまった状態では、次のクリエイティブなことはもうできないだろうというようなことで、住まいを1回リノベーションしようと。ちょっと貯金下ろせば、もう夢のような暮らしができるんじゃないかと。で、そういった事例とですね、それから多くの企業が参加して、約250ぐらいの企業が参加して、去年立ち上げまして、結構、人気がありまして、今年第2回やります。これは、国際的にも随分アピールができました。はい。
それから今、市長が言っていただいた日本産業館なんですが、これは再利用というね、昔の上海にある工場を元にして、これも工場の、ビルをつくるときの足場をですね、再利用できる、リサイクルして使えるんですが、それを使って総合的なパビリオンにしまして、ここは今、3、4時間並んでるっていうぐらい人気館になりました。こういったことも大阪発で色々、案が出ましたので、いわゆるクリエイティブなこと、それからアイディア、それからそういったクリエイティブな、そういう世界への発信、それにはおそらく暮らしのこと、それから教育の、子どものころからの教育の問題、色々に波及すると思います。そんなことで、少しでもお役に立てればというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに、本日は市長特別顧問に就任していただきます喜多俊之(きた としゆき)さんにご同席していただいております。ありがとうございます。先程、市長特別顧問の委嘱状をお渡ししたところでございます。改めまして、喜多さんのご紹介をさせていただきますが、液晶テレビなどの家電、家具、ロボット、家庭日用品に至るまで、幅広い分野で多くのヒット商品を生み出され、その作品はニューヨーク近代美術館やパリ・ポンピドゥセンターなどにコレクションされており、まさに世界的な工業デザイナーとして活躍されておられます。また、現在、シンガポール、タイ、中国政府のデザイン顧問や、大阪芸術大学のデザイン学科長を務められるとともに、日本の伝統工芸や地場産業の活性化にも関わっておられます。現在、本市では経済成長戦略の策定に取り組んでおりますけれども、その中で、大阪を活性化させるためのアプローチを検討しております。喜多さんには、これまでのご経験を活かしていただき、創造的なまちづくりの観点から、プロデューサー、デザイナーの立場で、アドバイスを頂戴してまいりたいと考えております。
また、こちらをご覧いただきますと、上海万博「日本産業館」の壁面を梯子で上り下りするロボット『夢ROBO(ロボ)』が話題を呼んでおりますけれども、その総合的なデザインをされたのが、こちらにいらっしゃる喜多さんでございます。私も来週28日、「なにわの日」に合わせて上海万博にまいりますんで、実物を見せていただくのを楽しみにしております。それでは、喜多さんから、特別顧問就任にあたっての抱負と申しますか、お考えをお話しいただきたいと思います。喜多さん、どうぞよろしくお願いいたします。
喜多氏
皆さんこんにちは。今回、大阪市長特別顧問に就任します、喜多俊之でございます。工業デザイナーって、大変堅苦しい感じがするんですが、もともとは人々の暮らしのためのものづくりっていいますか、そういうことを仕事にしております。歴史ある、このなにわのまちの活力がですね、ずっと人々のコミュニケーションで支えられたように、これからの大阪も、人々がコミュニケーションしやすいまち、それから、暮らしと経済産業の活性化にクリエイティブ、そしてデザインの力が大変欠かせない時代になってきました。今、アジアの国々が大変な勢いで、「デザインは新しい資源です」ということで走ってきております。大変な勢いで、それを伸ばしつつある中で、大阪市がこれからどういうまちをめざすかということを、市長が考えられてるんじゃないかと思いますので、私できることを色々やっていきたいと思います。人々が心豊かに暮らせる、活力のある国際都市・大阪をめざして、頑張っていきたいと思います。活力のあるまちをつくる土壌は人々の暮らしです。それから、経済産業がそこにですね、根付いて、そして活気のあるまち、日本のまち、世界の都市へ発展すると思います。大阪には素晴らしいインフラがたくさん整ってますが、これをどう活用するか、そういったことも大きなテーマじゃないかと思います。そして、アジアの中の大阪、世界の中の大阪、そして関西、日本ということで、これから日本が海外から大変注目されている今、大阪市の役割は大変、大きなものがあるんじゃないかと思っております。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
それで、ここにですね、ちょっと今日、どうしましょう、これは華やかな、なにわの大阪、なにわの時代ですね、ちょっと前の大阪ですね。100年ぐらい前の大阪の姿です。そして、それが、これが、つい斜め向かいですけれども、この橋がですね、当時の大変アジアの中では群を抜いていたまちの大阪の名残を残してる風景ですね。この建物もそうです。それから、私がちょうどこの近くに住所がありまして、25年ぐらい中之島のほとりに事務所を構えてます。この北浜の高麗橋とですね、毎年この10年ぐらい、こういうお花見を、実は「花会」ってしてるんですよね。4月の第一土曜日にしてますが、年々こうして大きくなりまして、最初30人ぐらいが今、150人ぐらいになりまして、これは良き時代の暮らしの再現、晴れの日の再現っていうか、「そういったことをめざしてやれば楽しいやない」っていう、「楽しく暮らせるやん」っていうようなね、そういうことをやってみようということでやっております。会費制でですね、たった3時間なんですが、もう1年中、皆さん、次を待ってくれてるという人気のあるものになりました。それから、これはですね、大阪は3、40年前までは日本で一番の国際見本市のまちでしたね、皆さんご承知のように。で、それをひとつ、リビング&デザインという国際見本市を去年立ち上げていただきまして、インテック(ス)大阪ですね。住まいのリノベーション、いわゆる今、大変日本の住まいが戦後ですね、たくさん建ったんですが、小さくなってしまって、間取りも小さい。その結果、どういうことが起こってきたかというと、納戸化が進んでしまって、この納戸化が進んでしまった状態では、次のクリエイティブなことはもうできないだろうというようなことで、住まいを1回リノベーションしようと。ちょっと貯金下ろせば、もう夢のような暮らしができるんじゃないかと。で、そういった事例とですね、それから多くの企業が参加して、約250ぐらいの企業が参加して、去年立ち上げまして、結構、人気がありまして、今年第2回やります。これは、国際的にも随分アピールができました。はい。
それから今、市長が言っていただいた日本産業館なんですが、これは再利用というね、昔の上海にある工場を元にして、これも工場の、ビルをつくるときの足場をですね、再利用できる、リサイクルして使えるんですが、それを使って総合的なパビリオンにしまして、ここは今、3、4時間並んでるっていうぐらい人気館になりました。こういったことも大阪発で色々、案が出ましたので、いわゆるクリエイティブなこと、それからアイディア、それからそういったクリエイティブな、そういう世界への発信、それにはおそらく暮らしのこと、それから教育の、子どものころからの教育の問題、色々に波及すると思います。そんなことで、少しでもお役に立てればというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
質疑応答
記者
今回の特別顧問の就任にあたってですね、具体的に何かこういうことを大阪市のためにやってやろうみたいなことですね、アイデア段階で結構なんですけれども、何か、もしお考えがあったら聞かせてください。
喜多氏
まだ市長とは下打ち合わせはできてないんですけれど、でも私思うのは、大阪はやはり、今ちょっとご覧になったように、日本でもピカイチの歴史のあるまちですから、そういう中で、元気な頃の大阪へ戻っていくということはいいんじゃないかと。今アジアが大変な勢いで大きく進展している中でですね、大阪がどう再生するか、そしてアジアのため、日本、アジア、そして世界のためにどういう役割ができるのか、そして何よりも、この大阪から世界へ何が発信できるのかということを探っていきたいというふうに思っております。そして、世界から知的な職業っていいますか、そういう人たちがたくさん関西、大阪にやって来ていただく、そういう仕組みをね、つくって、そして市民、そして子どもからお年寄りまでみんなですね、とにかく心豊かな暮らしになれる、そういうまちになれば素晴らしいなというふうに思っております。
市長
どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
喜多氏
ありがとうございました。
市長
喜多先生にリビング&デザイン展、去年もごいっしょに行かせていただきまして、本当に心豊かな暮らしというものを、納戸化している日本の住宅事情とか、リビング&デザインというジャンルでしたので、そういう形で各国からの色んな楽しい作品、さらには日本の学生の作品等も展示されておりました。
【市長が中国を訪問し、トッププロモーション等を行います】
それでは発表項目にまいります。まず中国と大阪の交流促進の話題でございます。来週7月26日の月曜日から31日土曜日までの6日間、私、中国を訪問いたします。中国では、上海万博で、なにわの日、7月28日にちなんだイベントに参加しますほか、経済界の方々といっしょに、観光や経済交流のプロモーションを行います。市民、企業、そして行政が力を合わせて、オール大阪で、中国と大阪の協力関係を築いていきたい、そう思っておりますけれども、そのための大きなステップになると思っております。
スケジュールの概要でございますけれども、今、大阪の高校生を乗せた帆船、これ「あこがれ」の出航時の風景なんですけれども、今日の正午頃の場所でございますが、大阪港からは935キロぐらい離れているところの東シナ海の洋上にあって、もうすでにこの上海市までの距離の半分以上を来ていると、順調に航海を続けているということでございますが、26日に上海に着く予定になっております。その入港歓迎式に間に合うように、私、中国に飛んでいきたいと思います。次の日、27日と28日は、上海万博の「なにわの日スペシャルデーイベント」に出席することになっています。27日は前夜祭としまして、「大阪―上海友好交流の夕べ」がございます。韓正(かんせい)上海市長をはじめとしまして、中国側、大阪市合わせて700人が参加するという盛大なものでございます。大阪府にも主催に入ってもらっておりますし、市民を含めたオール大阪で友好を深めたいと思っています。28日のなにわの日の当日なんですが、盆踊りで万博会場を大いに盛り上げようと思っております。29日からは、大阪商工会議所の佐藤会頭はじめ、経済界の方々といっしょに、中国との経済交流を深めるプログラムに取り組みます。29日は「大阪プロモーション」ということで、上海市政府の方や中国の業界関係者に向けて、2つのセミナーを行います。1つ目の「大阪港セミナー」では、国際コンテナ戦略港湾に取り組んでいる大阪港や都市の魅力をアピールいたします。
続いて、「大阪 環境・水技術セミナー」と題しまして、大阪市が持っております、環境や水についての官民の優れた技術をアピールします。これには、上海万博大阪館に出展してもらっております企業にも参加していただく予定です。さらに、30日には、深圳(しんせん)市に移動いたしまして、大阪商工会議所佐藤会頭一行にも入ってもらい、市書記や市長など、政府要人と会談いたします。会談では、大阪市の魅力を官民一体でアピールするとともに、観光や環境をはじめとする各種分野での、今後の交流促進に向けた覚書に調印する予定でございます。これは、中国初の経済開発特区として、目覚しい発展を遂げている深圳市と大阪市の間の協力関係を強める、大きな節目になると期待しております。このように今回は府にもご協力いただき、大阪から多くの市民・企業の皆さんにも参加していただいて、いっしょに大阪の魅力を発信できる訳でございます。まさにオール大阪体制で、上海から中国、そして世界に、大阪の力と魅力をアピールしてまいりたいと、こう思っております。
スケジュールの概要でございますけれども、今、大阪の高校生を乗せた帆船、これ「あこがれ」の出航時の風景なんですけれども、今日の正午頃の場所でございますが、大阪港からは935キロぐらい離れているところの東シナ海の洋上にあって、もうすでにこの上海市までの距離の半分以上を来ていると、順調に航海を続けているということでございますが、26日に上海に着く予定になっております。その入港歓迎式に間に合うように、私、中国に飛んでいきたいと思います。次の日、27日と28日は、上海万博の「なにわの日スペシャルデーイベント」に出席することになっています。27日は前夜祭としまして、「大阪―上海友好交流の夕べ」がございます。韓正(かんせい)上海市長をはじめとしまして、中国側、大阪市合わせて700人が参加するという盛大なものでございます。大阪府にも主催に入ってもらっておりますし、市民を含めたオール大阪で友好を深めたいと思っています。28日のなにわの日の当日なんですが、盆踊りで万博会場を大いに盛り上げようと思っております。29日からは、大阪商工会議所の佐藤会頭はじめ、経済界の方々といっしょに、中国との経済交流を深めるプログラムに取り組みます。29日は「大阪プロモーション」ということで、上海市政府の方や中国の業界関係者に向けて、2つのセミナーを行います。1つ目の「大阪港セミナー」では、国際コンテナ戦略港湾に取り組んでいる大阪港や都市の魅力をアピールいたします。
続いて、「大阪 環境・水技術セミナー」と題しまして、大阪市が持っております、環境や水についての官民の優れた技術をアピールします。これには、上海万博大阪館に出展してもらっております企業にも参加していただく予定です。さらに、30日には、深圳(しんせん)市に移動いたしまして、大阪商工会議所佐藤会頭一行にも入ってもらい、市書記や市長など、政府要人と会談いたします。会談では、大阪市の魅力を官民一体でアピールするとともに、観光や環境をはじめとする各種分野での、今後の交流促進に向けた覚書に調印する予定でございます。これは、中国初の経済開発特区として、目覚しい発展を遂げている深圳市と大阪市の間の協力関係を強める、大きな節目になると期待しております。このように今回は府にもご協力いただき、大阪から多くの市民・企業の皆さんにも参加していただいて、いっしょに大阪の魅力を発信できる訳でございます。まさにオール大阪体制で、上海から中国、そして世界に、大阪の力と魅力をアピールしてまいりたいと、こう思っております。
【中国国籍の方の生活保護申請に関して】
続きまして、中国国籍の方の生活保護申請に関しての報告です。この問題は、入管法では、国又は地方公共団体に負担をかけるものは入国を拒否することになっているにも関わらず、日本に入国して、すぐに生活保護を申請しており、在留資格の審査について、法の趣旨を大きく逸脱しているとしか思えない運用がなされているのではないかという問題提起を、まずさせていただきました。また、生活保護法、これは昭和29年の通達になりますが、単に形式的に適法に在留資格を得ていることのみをもって、生活保護制度を準用するということになっていることも問題であるというふうに申し上げてまいりました。結果的に大阪市として、何の裁量権もなく生活保護法を適用しなければならないということでは、市民の多くの方の理解も得られません。また、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できかねるということでございます。今回、プロジェクトチームでこの問題をあえて公表し、警鐘を鳴らし、繰り返し厚生労働省や法務省に対して、問題を提起し続けてきた訳でございますが、その結果、おととい、厚生労働省から見解が示されました。見解の趣旨に従いますと、今回のケースでは入国直後に生活保護を申請しており、身元保証人による保証の実態がないことは明白で、結果的に生活保護の受給を目的として入国したと見なさざるを得ません。基本的に生活保護法を準用することはできないものと判断いたしました。従いまして、生活保護申請中の方につきましては決定を保留し、現在受給中の方につきましても、8月分の支給を保留することになります。今後、改めて大阪入管局の精査の結果や、入国審査関係書類を照会し、大阪市として最終的に決定いたします。
なお、本日正午頃に、長妻大臣が記者会見で、この厚生労働省からいただきました回答の文書でございますけれども、この文書に至る経緯として基本的な考え方を厚生労働省として示したものであると。で、具体的な判断については大阪市に任せるということ、さらに今回のこの回答については、大阪市からの具体的な問い合わせに対して考え方を示したものであるという記者会見をされたという情報が入ってきております。なお、人道上の観点からの取り扱い、あるいは中国残留孤児の子孫全般の方たちの処遇をどう捉えるのか、こういう問題は、国の責任において、別の制度、施策を設け、きっちりと対応すべきものでございます。そのことを、国に対して改めて申し入れてまいりたいと思っております。この間、市民の方から、「大阪市は一体何しとんねん」とかですね、非常に厳しい批判をいただいております。議会からも、心配する声が上がっておりました。しかし、私が投じた一石は、間違っていなかったと思っております。
一部報道によりますと、大阪府の橋下知事から、この件で「素晴らしい、見事」「シロアリではなく、働きアリだ」というお褒めの言葉をいただいているという情報もありましたが、プロジェクトチームの働きを正当に評価していただいたというのはありがたいですが、依然として、市の職員はアリか、という部分もございます。
今回、厚生労働省から、このような反応があったのは、我々の声に真摯に耳を傾けてくれた結果だというふうに受け止めております。こういう意味で言いますと、平成18年の10月に、全国知事会・市長会から新たなセーフティネットの提言という具体的な方向性をお示ししたにもかかわらず、全くその抜本的な改革というものについての歩みが見られなかったこの問題について、我々がプロジェクトチームをつくり、あるいは全国の市町村に呼びかけながら取り組んでいく具体的な提案も、これからさせていただくということで、実質的な抜本的改革につながる動きをとり続けてまいりたいと、このように思っております。改めて申しますけれども、生活保護制度、昭和25年から実施されました、この制度自体が、何度も国に対して抜本的な改革を求めてまいりました。で、大阪市は今後、他都市との水平連携を生かしまして、秋までに提言を取りまとめて、制度の抜本的な改革を国に求め続けてまいりたいと、このように思っております。
なお、本日正午頃に、長妻大臣が記者会見で、この厚生労働省からいただきました回答の文書でございますけれども、この文書に至る経緯として基本的な考え方を厚生労働省として示したものであると。で、具体的な判断については大阪市に任せるということ、さらに今回のこの回答については、大阪市からの具体的な問い合わせに対して考え方を示したものであるという記者会見をされたという情報が入ってきております。なお、人道上の観点からの取り扱い、あるいは中国残留孤児の子孫全般の方たちの処遇をどう捉えるのか、こういう問題は、国の責任において、別の制度、施策を設け、きっちりと対応すべきものでございます。そのことを、国に対して改めて申し入れてまいりたいと思っております。この間、市民の方から、「大阪市は一体何しとんねん」とかですね、非常に厳しい批判をいただいております。議会からも、心配する声が上がっておりました。しかし、私が投じた一石は、間違っていなかったと思っております。
一部報道によりますと、大阪府の橋下知事から、この件で「素晴らしい、見事」「シロアリではなく、働きアリだ」というお褒めの言葉をいただいているという情報もありましたが、プロジェクトチームの働きを正当に評価していただいたというのはありがたいですが、依然として、市の職員はアリか、という部分もございます。
今回、厚生労働省から、このような反応があったのは、我々の声に真摯に耳を傾けてくれた結果だというふうに受け止めております。こういう意味で言いますと、平成18年の10月に、全国知事会・市長会から新たなセーフティネットの提言という具体的な方向性をお示ししたにもかかわらず、全くその抜本的な改革というものについての歩みが見られなかったこの問題について、我々がプロジェクトチームをつくり、あるいは全国の市町村に呼びかけながら取り組んでいく具体的な提案も、これからさせていただくということで、実質的な抜本的改革につながる動きをとり続けてまいりたいと、このように思っております。改めて申しますけれども、生活保護制度、昭和25年から実施されました、この制度自体が、何度も国に対して抜本的な改革を求めてまいりました。で、大阪市は今後、他都市との水平連携を生かしまして、秋までに提言を取りまとめて、制度の抜本的な改革を国に求め続けてまいりたいと、このように思っております。
【平成22年上半期の街頭犯罪発生件数について(暫定値)】
次にまいります。すでに大阪府警から、おととい、平成22年1月から6月末現在の、大阪府下全域の街頭犯罪発生件数について報道発表されております。私から、大阪市の街頭犯罪発生件数についてお知らせいたします。
平成22年6月末現在、上半期の集計で、13,623件、前年比19.5%の減少となっておりまして、現在ワースト2位の名古屋市との差が540件になっております。これが平成19年の段階の、1年間大阪市内、44,205件ありました。これが今年の1月、これは、去年です、ごめんなさい、去年の1月から6月までの数字でございます。去年と比べまして、今年こういう数字になってるということ、さらにこの差が去年の半期では2,937件であったものが、現在504件に縮まってきているということでございます。大阪府警の全面的な協力、あるいは市民の皆さんの幅広い協力、青色防犯パトロールカー、あるいは防犯カメラの設置、そして様々なひったくり防止活動の啓蒙活動、啓発活動といったものが、少しずつ実を結んでいるというふうに私思っておりますが、大阪の街頭犯罪の代名詞と言われた、ひったくりでございます。
ひったくりについてご覧いただきますと、このように平成21年、去年の段階では2位と383件の差があったんですが、今年1月から6月まででは、すでに逆転しております。前年比368件減っておりまして、最も多い名古屋市との差は現在97件、半年間で97件です。平成22年上半期の結果としては、ひったくりをはじめとする8項目ある街頭犯罪のうち、5項目でワースト1を脱却中でございます。8項目とも全てワースト1であった平成19年末の状況から、20年、21年、20年の秋からこの運動を提唱し、そして21年から予算執行しておりますが、市民の皆さんの幅広い協力があらばこそ、そして大阪府警の、本当に全力を挙げてくださってる協力のおかげだと思っております。
しかし一方でですね、部品ねらいという項目につきまして、これが2,149件と今年1月から6ヵ月連続して増加傾向にあります。この内、ナンバープレートの盗難被害が35%を占めているということで、本市といたしましても、8月9日から市税事務所で、ここにございます、皆さんのお手元にも、は、いってないのかな、ごめんなさい、すみません。ここにございますが、これが従来型のナンバープレートを留めてあるねじです。で、一方この、防犯ねじっていいますか、盗難防止ねじ、これはいったん締めまして、その真ん中に開いているところに金具をさらに入れて、それを埋め込んでしまうという形で、いったんこれでつけますと、外せなくなるということから、盗難防止ねじなんです。8月9日から各市税事務所や区役所でオートバイ用ナンバープレートの盗難防止ねじ、4万個を配布いたします。8月9日から4万個の配布を開始いたします。ナンバープレートが盗まれるということは、次の犯罪に使用される恐れもあるということで、この取組みをしてまいりたいと思います。また、圧倒的にカーナビの盗難というのも増えておりまして、これは後付け型が一番狙われるらしいんですけれども、すぐに外せるようなカーナビ、後からつけられた方がたは、面倒でも車の中に、外から見えないような形に直していただくか、あるいは駐車中は外して、ご自宅の中に保管されるかっていうのが予防策としてはいいのではないかと思っています。引き続き、安全なまち大阪をアピールするためにも、街頭犯罪発生件数ワースト1の返上に向けまして取り組んでいきたいなと思っております。本日は以上でございます。
平成22年6月末現在、上半期の集計で、13,623件、前年比19.5%の減少となっておりまして、現在ワースト2位の名古屋市との差が540件になっております。これが平成19年の段階の、1年間大阪市内、44,205件ありました。これが今年の1月、これは、去年です、ごめんなさい、去年の1月から6月までの数字でございます。去年と比べまして、今年こういう数字になってるということ、さらにこの差が去年の半期では2,937件であったものが、現在504件に縮まってきているということでございます。大阪府警の全面的な協力、あるいは市民の皆さんの幅広い協力、青色防犯パトロールカー、あるいは防犯カメラの設置、そして様々なひったくり防止活動の啓蒙活動、啓発活動といったものが、少しずつ実を結んでいるというふうに私思っておりますが、大阪の街頭犯罪の代名詞と言われた、ひったくりでございます。
ひったくりについてご覧いただきますと、このように平成21年、去年の段階では2位と383件の差があったんですが、今年1月から6月まででは、すでに逆転しております。前年比368件減っておりまして、最も多い名古屋市との差は現在97件、半年間で97件です。平成22年上半期の結果としては、ひったくりをはじめとする8項目ある街頭犯罪のうち、5項目でワースト1を脱却中でございます。8項目とも全てワースト1であった平成19年末の状況から、20年、21年、20年の秋からこの運動を提唱し、そして21年から予算執行しておりますが、市民の皆さんの幅広い協力があらばこそ、そして大阪府警の、本当に全力を挙げてくださってる協力のおかげだと思っております。
しかし一方でですね、部品ねらいという項目につきまして、これが2,149件と今年1月から6ヵ月連続して増加傾向にあります。この内、ナンバープレートの盗難被害が35%を占めているということで、本市といたしましても、8月9日から市税事務所で、ここにございます、皆さんのお手元にも、は、いってないのかな、ごめんなさい、すみません。ここにございますが、これが従来型のナンバープレートを留めてあるねじです。で、一方この、防犯ねじっていいますか、盗難防止ねじ、これはいったん締めまして、その真ん中に開いているところに金具をさらに入れて、それを埋め込んでしまうという形で、いったんこれでつけますと、外せなくなるということから、盗難防止ねじなんです。8月9日から各市税事務所や区役所でオートバイ用ナンバープレートの盗難防止ねじ、4万個を配布いたします。8月9日から4万個の配布を開始いたします。ナンバープレートが盗まれるということは、次の犯罪に使用される恐れもあるということで、この取組みをしてまいりたいと思います。また、圧倒的にカーナビの盗難というのも増えておりまして、これは後付け型が一番狙われるらしいんですけれども、すぐに外せるようなカーナビ、後からつけられた方がたは、面倒でも車の中に、外から見えないような形に直していただくか、あるいは駐車中は外して、ご自宅の中に保管されるかっていうのが予防策としてはいいのではないかと思っています。引き続き、安全なまち大阪をアピールするためにも、街頭犯罪発生件数ワースト1の返上に向けまして取り組んでいきたいなと思っております。本日は以上でございます。
質疑応答
記者
すみません。まず生活保護の件ですけれども、打ち切りの方向で検討してるっていうこと、昨日から公表されてるんですけど、これについて、今のところ中国の、例えば総領事館とかからですね、何か反応があったのかどうかっていうのが1点と、あと、すみません、ちょっと全く話し変わるんですけれども、府の咲洲庁舎に経済三団体、事務所移転してほしいという要請を知事と連名で出されてたと思うんですけど、これが一応、断られたということに対する市長のお考えをお伺いしたいと。で、あと最後3点目、すみません、橋下知事がですね、市長が先日発表した「地域主権宣言」について、ひどい内容であると、自治体間の連携で解決できたらそれは簡単だけれども、合意できないものについてはどうするんだというような主旨の発言をされてまして、この3点についてお願いします。
市長
分かりました。まず1点目、中国総領事館の反応について、私のところにはまだ何も入っておりません。何か?
健康福祉局生活保護制度担当部長
まだ何も来ておりません。
市長
まだ何も来ておりません。で、我々も保留ということでございますが、この保留というのも入管がどういった審査結果を出されるかの、その期間を待っている保留ということでございます。大きな方向性としては、昨日、おととい、いただきました厚生労働省の回答に則って、我々はきっちりと判断をしたと思っておりますので、大きな方向性はそうです。ですから、あとは入管の審査待ちで、それが出たあとで何らかの形でご報告に行かないといけないことが生じるかもしれないとは思っております。はい。それから、経済団体に対する咲洲庁舎への移転要請について、来ていただけないということでございますが、私自身は極めて冷静に受け止めております。これからあのエリアを府市協調して経済界のご協力をいただきながら、活性化を図っていく訳でございます。その際には、色々な、国に対しては経済特区の申請であるとか、あらゆる特区の申請ということでやってまいりますし、一方、経済界に対しては、あらゆる経済界のネットワークを使わせていただきながら、その企業誘致活動の実効ある形、それを協力、情報提供いただいたりということでございますから、それがある程度軌道に乗って姿が見えてきたときには、逆に改めて経済団体に来ていただけますか、あるいは経済団体自体、ご自身の判断でここに来ると、より一層、仕事がはかどるというような環境になれば、自然にそういう流れが来るんであろうというふうに思っておりますので、お願いはしました。そして、来ていただければいいなあという思いではありましたけれども、今のところ来られないという判断だというふうに理解をして、かといって、しょっちゅう連絡はできますので、色んな情報交換が頻繁にさせていただくルートはもうできたというふうに思っております。
最後のご質問なんですが、私、先週、先週ですよね、「地域主権確立宣言」という形で申しました、あの内容は本来、その地域主権というものを自治体がどう考え、どう取り組むべきなのかという本来のあるべき姿というものをお示しいたしたつもりです。で、これが「ひどい」という一言でお片付けになる根拠というものが分かりません。で、むしろ、それを「ひどい」とおっしゃることは、地域主権ってじゃあ何なのかということ自体を全て否定されるような形になると。私は大阪市だけがこれをやるんだという宣言ではなく、今、ややぼやけかかっている地方分権とか地域主権とかいうものは本来こうあるべきなんじゃないですか、っていうことでお示しした宣言のつもりでございます。ですから、大阪市だけではなくて、色んな市が連携をしながらこれから府や県という旧来からある枠組みを超えた動きをすることが、関西経済圏全体の発展につながるということは絶えず申しております。じゃあ、都市間連携がでけへんやろうと、それで何ができるんだという枠組み論でもしお話をされるんであれば、例えば、じゃあ、大阪府下の市町村の連携というものをおまとめになるのは、今の府の役目ではないかなと、一方で。で、府は府で他の県と、どれぐらい連携をやろうとされているのか。それがうまくいけば関西広域連合だけではなくて、その先にある道州制というものへのステップをしっかりと築けるのではないか。ただ、こっちのほうがおそらく時間はかかるでしょうと思います。それは、長年にわたる府と県、都道府県というこの制度がしっかりとした根を下ろしていることや、あるいは都道府県出身の方が各市町村で首長さんになっておられたり、依然として副市長に何人もなっておられる、そういったその上下関係、はっきりした上下関係かどうか私どもは分かりませんけれども、やはり、国、都道府県、市町村という、その上下関係の縦の流れの中の支配構造といいますか、権限の移譲にしても何かこう、ひもがついてた時代もおそらくあったでしょう。今は、ほとんどないと思いますけれども。そういったことを考えると、都市間連携のほうが、きっと圏域を超えた色々な具体的な動きにつながると。それが次は、圏域いうのは経済圏なんかの「圏」という字です、それがその圏域の繁栄、具体的な盛り上がり、特に京阪神はそういう意味で言うと、すごい力を持っているところですから、それ全体の底上げにつながる動きを柔軟にやれるのは大阪、京都、神戸、そして堺という、この政令市が固まっているエリアが一番早いという信念は変わりません。
記者
知事が市長のそういった水平連携っていう考え方に対して、以前からずっと言っているのは、合意できるところはいいけども、合意できないところはじゃあ、どうやっていくんだっていうところ、ずっと言われてると思うんです。それに対する反論というか、それはどうするのかというところを。
市長
私は合意できるものは当然合意しますが、合意できないものはしっかりと話し合いをしながら、その話し合っている内容を多くのそれぞれの当該市民に公開して、その情報を公開する中から、どっちのほうがいいのかっていう選択を求めたいと。つまり、合意できないものは敵だとみなすというような動きは、とるつもりもございませんし、そういう姿勢でずっとこの間やってきたつもりです。それが、ある意味、そうですね、救急安心センターの拡大の動きであるとか、自治体ならではの連携というものを、しっかりとその住んでらっしゃる方の、市民の利益に移していく動きにつながってると思っておりますし、生活保護問題のプロジェクトチームの動きをとりましても、各政令市、そして周辺の市の皆さんにも参加していただきながら、色んな連携は可能である。色んな連携をするということ自体、大阪市は今まで何もやっていなかったんではなくて、例えば地下鉄にしろ、それから水道事業にしろ、あらゆる点で我々が持っている技術であるとか、人材であるとか、それを直接行政ならではの協力体制ということをやってきております。ただ、やってきていることを、あまり大きな声では言っていなかったから、何もやっていないというふうに、多くの市民の方に見られてしまうのかも知れませんが、本当に数多くの分野で我々が持っている技術、それは大阪市が大都市であるから、逆にそういった優秀な職員も来てくれた、その職員がほかのまちへの技術協力とか、新しい技術の開発であるとか、そういったものをやってきた歴史っていうものを、やっぱり、しっかりと、もういっぺん、皆さんに分かっていただきたいというふうに思います。はい。
記者
今の関連ですみません。知事の、その発言の続きなんですけど、区長公選制の話にもつながるんですけど、要は人口が260万人と、広島県よりも大きいその自治体の中に市町村長、要は区長さんですね、知事が言うところの、置かないっていうのは、自分ひとりが独裁的に全部やるといっているに等しいというような発言がございまして、これについて反論があれば教えてくださいというのが1点です。もう1点は全く別で、市長の決まっていれば夏休みのご日程を教えてください。
市長
はい。前から区長公選制と言っておられますけれども、その大阪維新の会がおっしゃってるのか、知事がおっしゃってるのか、ということで言うと、確か選挙戦では区長公選制とおっしゃってたんで、代表としておっしゃってるのかなあと思ってたら、定例会見でおっしゃってると。非常にどう答えていいのかなあという部分は複雑です。ただ、区長公選制、あるいは260万都市の市長が、その市町村長を決めずに独裁的に全て1人でやろうとしてるというふうにおっしゃってるんですが、地方自治法とか、日本は法律に基づく国ですから、私は大阪市長として大阪市の市民から選ばれた市長をやらしていただいてます。独裁的にやっているとは思っておりません。あらゆる区に、区なりの思いというものを聞きながら、22年度予算、今年度予算ですね、今年度予算で、それぞれの区の思いを、どう地域を活性化させるために使うのかという形で、今で2年7ヶ月を過ぎておりますけれども、2年たった時点で、いよいよ、これからのコミュニティをどう守り、どうつなげていくのかという形で動いておりますので、それが独裁的な動きだというふうにおっしゃった部分につきまして、私自身、非常に見出しなり、あるいは、あの時の文言なりを見てまして、誰のことおっしゃってるのかなあと、つい思ってしまいました。はい。じゃあ260万が多い、あるいは260万を維新の会は30万と言ってらっしゃいますから、8つの区に分けるにしても、その分け方すら、おっしゃっていないし、それは特別区になれば、市町村と同じということになると、さらに多くの費用がかかってしまう。それよりも、「やれること協力してやりましょうよ」っていうのをずっと言い続けていきたいですね。こういった形で、区長公選制については、反論しだすともっと時間がいりますんで、この辺でいいですか?で、夏休みでございますが、8月13日から20日までいただく予定にしております。どこへ行くとかいうのではなく、ゆっくりと骨休めをしたいなあと。13から20日までの予定です。もし、もちろん何かあればすぐ出てこられるようにはしておきます。すぐって言いましても、ちょっと時間はかかるかもしれませんが、はい。
記者
すみません、話を中国人のことに戻して恐縮なんですが、先程の大臣の会見の反応なんですけれども、2点ございまして、大臣もですね、大阪市の判断を尊重したいと。で、本件に関しては人数が非常に多く、来日の目的が生活保護に直結する疑いが見られるというふうにおっしゃっていて、大阪市さんの判断を尊重されてるという、このことに対しての市長の反応をいただければということと、あともう1点、市長も触れられてましたが、今回の、厚生労働省として、厚生労働省さんの通知は今回のケースのみだと。今回の大量に一度に直後に来たということに対しての反応のみだというような通知文なんですが、今後、大阪市としては、同様のケースであったりであるとか、今回、入国直後で3日から1ヶ月という期間があったんですが、じゃあこの期間が、じゃあ入国直後という概念が2ヶ月だったらいいのか、3ヶ月だったらいいとか、ケースによって全て異なると思うんですが、今後どういった対応をしていかれるのかっていうことがもし決まっていれば教えてください。
市長
はい。まず、大臣のその細かい内容については今、伺いましたが、非常に、我々の主張、それからこの問題をきっちり捉えていただいたと。今までの厚生労働省っていうと、語弊があるのかもしれませんが、こういった一自治体からの悲痛な叫びというものを、なかなか文書で回答していただくってことはございませんでした。そういった意味では、この一歩というものは非常に大きい一歩だと思いますし、なおかつ、今回、去年の9月から生活保護のプロジェクトチームを立ち上げて、私あの時に国に行きまして、「こういったものを立ち上げました。今後あらゆる我々の持っているデータ、さらには矛盾点、日本一多い受給者を抱えている自治体だからこそ分かる矛盾点みたいなものを全て洗い出して、この制度の矛盾を訴えかけていきます」っていうことを、長妻(厚生労働大臣)さんにお会いした時にも申しましたし、小沢(民主党前幹事長)さんにお会いした時も申しましたが、こういった去年の9月に言わせていただいたことが、10ヶ月たって、一定の成果を出しつつあるんだなと。それを国も受け止めていただいた動きにつながったと思ってます。で、今回の件の対応であるという部分は、これは今までの対応と比べますと、はるかに進んだ対応をしていただいたので仕方がないかなあと思う部分と、それと、厚生労働省の判断はこうだった、しかし、この問題はやはり私ども、法務省入国管理局が、あるいは日本の国全体が、中国残留孤児、あるいは中国残留邦人の家族、係累の方たちにどう対応するのかというものを、多くの国民の合意を得た上でお示しいただかないと、いくら、この件限りの回答であるということであっても、我々はおそらく同じ対応でいかざるを得ないであろう。つまり、身元引受人の方の保障、来日してからの生活の保障であるとか、そういった実態が疑われる申請に対して、いくらその要件が整っているからといって、それをすぐさま受けるという訳にはまいらないという方向性は出たのかなと思っています。ただ、これは今まだ、プロジェクトチームと話し合っていない、私の今の見解でございますんで、間違いない?
健康福祉局生活保護制度担当部長
そういうことで。厚生労働省のほうにも確認をいたしました。やはり、今回の大阪市からの個別の照会に応じて見解を示したもので、一般的な適用ということは考えていない。ですから、今後はケース・バイ・ケースということに、大阪市としてはなるんだろうと思われます。
市長
ですから、今、健康福祉局の生活保護制度担当部長でしたが、という線は変わらないと思うんです。もう1点なんでしたっけ?ごめんなさい。もう1点、何でしたっけ?ご質問。
記者
あっ、もう2ついただきました。
市長
あっ、もういいですか。はい。ありがとうございます。
記者
道頓堀の大たこの裁判の件なんですが、この裁判には色々、市だとか店側、双方、これまで色んな経緯があったようでして、この問題について、総合的に市長としては、これまでどのような思いでご覧になってこられたのかというのが1点。さらにですね、向こうは、店側の方は買い取る、買い受けるために、すぐにでも市と話をしたい等々おっしゃっているようなんですが、今後の対応等も教えてください。
市長
はい。確定、最高裁で確定したということで、我々の主張が正しいということを認めていただいたということで、評価できる判決と言いますか、評価すべきだと思います。市長になるまで、私、あそこが不法占拠やとは知りませんでした。色々、今までのニュースになってたのかもしれませんけど、たまたまそれを知らなかったということでございます。道路上、あるいは市有地の上、「私」ではないほうですね、市の土地の上に不法に占拠されている物件について、これに厳しくあたるっていうのは、これ当たり前のことでございますし、なおかつ、それが大阪の超一等地と言われる繁華街、しかも道頓堀という場所であれば、当然の判決であろうというふうに思っております。今後の対応につきまして、それはまだ、これからの話ですので、今現在、それにどう対応するかっていうことはお答えかねます。はい。
契約管財局管財部管財担当課長
買い取る選択肢はないのかということでしたけれども、買い取ることは和解をして、合意の上ということになりますのでね、そういったことが成り立たなかったがゆえに訴訟に入って、3つ目の裁判所までいったということですんで、そういったことはあり得ないというふうに考えております。
市長
ありがとう。
記者
上海万博に関してなんですが、先程、市長、オール大阪体制でというような話もありまして、仲のいい知事ともいっしょにアピールする場面もあるかと思うんですけれども、改めて意気込みなんぞを教えてください。
市長
はい。上海市と大阪市、本当に長い友好都市としての歴史を持っています。その中では例えば、外事弁公室からの職員に、私どもに来ていただいて、中国との関係で色々と通訳をしていただいたり、翻訳をしていただいたり、という動きも長年にわたって続いています。そういったものを、よりいっそう深める動きと、今回の府といっしょに、そして経済界といっしょに出したコンセプトが「環境先進都市 水都大阪の挑戦」ということでございます。私どもが持っている水技術、あるいは環境を克服してきた歴史といったものは、去年の1月に上海にまいりました時にも、中国が今、恐れている環境破壊というものを、どれだけ積極的に克服しようとしているかという姿が、もうすでに、去年の1月の段階であちこちで見受けられました。それはもちろん、中国の中でも、先進都市・上海としての当然の姿なのかもしれませんけれども、民間交流と言う言葉を最近、中国のトップの方はしょっちゅう口にされます。そういった民間交流の橋渡しを行政がどういう形でできるのか、あるいは行政が持っている能力を民間の方たちに、どうアピールしながら、マッチングを図っていくのかということで、よりいっそう積極的に府市協調も含めて、今、上海は同じフロアで事務所を、府と市の事務所を持っておりますが、協力体制をしながら日本の素晴らしい、特に関西の素晴らしい技術をアピールする場に、今後ともしていきたいし、それが相互理解のさらなる前進につながればという思いでやってまいります。具体的には中村美津子さんとか、河内家菊水丸さんとか、河内音頭を盆踊りで向こうの大阪館の前の広場でやろうという動きになってたり、多くの市民の皆さんもいっしょに行って頂けるということで、その踊りの輪の中に中国要人の方を引っ張り込んだり、私も踊ってみたりというようなこともしたいと思いますが、何しろ、ちょっと暑そうなんで、体調には気をつけたいなあと思っています。知事と色んな話をする機会もあるかもしれませんが、その中では、やっぱり府市協調を具体的にどうやって進めるのかという話を建設的にやりたいというのが今の私の気持ちです。はい。