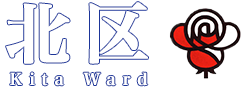寺院
2009年3月16日
ページ番号:2336

◆圓頓寺

北区太融寺町6-12
ここは落語「鷺とり」の舞台。ぐっすり寝込んだ鷺を捕まえて帯にはさんでいると夜が明けて鷺が飛び立ち、主人公が天王寺の五重塔の上に置き去りにされるという荒唐無稽なお話しです。
◆鶴満寺

北区長柄東1-3-12
上方落語「鶴満寺」は題名そのままの鶴満寺が舞台になっています。奈良時代に創建されたといわれる由緒あるお寺で、境内は落語にあるように桜の名所とされていました。
◆教恩寺

北区本庄西3-13-5
別名「さつき寺」。淀川が改修されるまでは広大な境内を持っており、樹齢300年ほどにもなる見事なさつきが明治時代までありました。花の頃は早朝から日暮まで人々が集まったといわれています。
◆源光寺

北区豊崎2-3-23
行基が天平19年(747年)に開山し、承元3年(1209年)に法然上人が復興しました。
◆光明寺

北区長柄西2-12-5
凶作の折、年貢を取り立てる領主を死をもっていさめた義人・松野登十郎の墓があります。
◆国分寺

北区国分寺1-6-18
聖武天皇の命により「長柄寺」から国分寺となりました。
◆天満別院

北区東天満1-8-26
東本願寺派の別院で、もともと本願寺の総本山です。
◆太融寺

北区太融寺町3-7
光源氏のモデルともいわれている源融(みなもとのとおる)の名をとって寺名にしたとか。かつての寺域は「北野の太融寺か、太融寺の北野か」といわれるほど広大でした。境内には淀君の墓や芭蕉の句碑など数々の史跡があります。
◆宝珠院

北区与力町1-2
弘法大師が草庵を建立したのがはじまり。