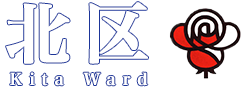名所・旧跡
2009年3月16日
ページ番号:2346

- 鶯塚(うぐいすづか)
- 緒方洪庵墓所
- 川崎東照宮跡
- 佐伯祐三生誕の地
- 泉布観(せんぷかん)
- 鶴の茶屋跡碑
- 源八渡し跡碑
- かしくの墓
- 天満の子守歌歌碑
- 淀川三十石船舟唄歌碑
- 森本薫文学碑
- 大塩平八郎墓所
- 中央公会堂
- 毛馬閘門・洗堰・淀川改修紀功碑
- 堂島薬師堂
◆鶯塚(うぐいすづか)

北区長柄東2丁目
長柄長者の姫の死後、鶯が悲しみの余り後を追うように死んだため作った墓、または、ここに埋葬した孝徳天皇の女官の鶯式部の墓、もう一説では、元旦に鶯が必ず来て春を告げたことに由来すると言われています。
◆緒方洪庵墓所

北区同心1丁目
適塾で逸材を育成したほか、大阪で初めて種痘をしたり、コレラの治療方針を示すなど近代医学の発展にも尽くしました。龍海禅寺の墓のそばには、師を慕う大村益次郎の脚を埋めた足塚があります。
◆川崎東照宮跡

北区天満1丁目
大坂夏の陣の後に大坂城主となった松平忠明が、家康の死後に建てた東照宮。大阪の人々の豊臣氏への思慕の念をぬぐい去る目的もあったといわれています。
◆佐伯祐三生誕の地

北区中津2丁目
偉大な洋画家・佐伯祐三は、大正12年(1923年)にフランスへ渡り、ゴッホ、ブラマンク、ユトリロなどの感化を受けました。わずかな活動期間に400点をこえる作品を残し、30歳で亡くなって光徳寺に眠っています。
◆泉布観(せんぷかん)

北区天満橋1丁目1
造幣寮の応接所として明治4年(1871年)に建設されました。イギリスの古典的なコロニアル式を取り入れた日本最初の本格的洋風建築です。泉布とは貨幣の古い呼び方。観は館のことであり『史記』の一節からとっています。
◆鶴の茶屋跡碑

北区茶屋町8
茶屋町という地名に昔の名残をとどめる、明治中期までの大行楽地。大坂三郷の人々の憩いの場所となっていました。豪商松並竹塘が、二羽の鶴を放し飼いにしたのがその名の由来とされています。
◆源八渡し跡碑

北区天満橋2丁目
昭和11年(1936年)に橋が架けられるまで活躍しました。梅や桜の名所もあり、大変賑わったといわれています。与謝蕪村も「源八をわたりて梅のあるじかな」と句を残しています。
◆かしくの墓

北区曽根崎1丁目2
酒乱がもとで兄を殺してしまった遊女かしくは、死罪になる前に、酒乱を直す神様になれるようにと願をかけました。法情寺にある墓には、今も酒の悩みでおまいりする人が絶えません。
◆天満の子守歌歌碑

北区天満3丁目(南天満公園内)
『ねんねころいち天満の市よだいこ揃えて~』と歌われ、なつかしいなにわの歌として今も伝えられる天満の子守歌は、天満青物市場を歌ったもの。現代でも新しくアレンジしたりして歌われています。
◆淀川三十石船舟唄歌碑

北区天満3丁目(南天満公園内)
天満青物市場の対岸、現在の土佐堀通り沿いに八軒家船着場がありました。江戸時代の人々はここと京都を結ぶ三十石船で旅をしたり物資を運んだりしたとか。その頃歌われた歌が歌碑となって残っています。
◆森本薫文学碑

北区中津2丁目(中津公園内)
戯曲『女の一生』で有名な森本薫は、明治45年(1912年)に現在の中津6丁目に誕生。京大在学中から作品を発表し、卒業後には文学座で戯曲をはじめ翻訳、ラジオドラマ、映画シナリオなど多彩に活動し、夭折しました。
◆大塩平八郎墓所

北区末広町1
天保8年(1837年)、自らの蔵書を金に換えて人々に与え、窮民救済に立ち上がりましたが、失敗して自害。人々が絶大な尊敬の念を寄せた大塩平八郎は、成正寺に眠っています。
◆中央公会堂

北区中之島1丁目1
大正7年(1918年)、故岩本栄之助氏の私財寄付により建設されました。大正時代のネオ・ルネッサンス様式の公会堂は歴史的にも大きな価値を持ち、中之島の水と緑に赤いレンガ色が映え「大阪の文化のシンボル」として親しまれています。平成11年から約4年にわたる耐震と保存・再生のための改修工事を終え、創建時の意匠に復元され、平成14年(2002年)11月リニューアルオープン。
◆毛馬閘門・洗堰・淀川改修紀功碑

北区長柄東3丁目3
明治の淀川改修工事では、橋の鉄橋化や長柄運河の開さくなど一連の工事が進められました。旧淀川(大川)に流下する水量の調節のために設けられたのが毛馬の洗堰で、船の航行の水位調節のために設けられたのが毛馬の閘門です。昭和49年の新水門完成と昭和51年の新閘門開通を機にそれぞれ引退し、現在は3門の旧洗堰と第1・第2旧閘門が保存されています。
碑には、改修工事の経緯を詳しく刻しています。
◆堂島薬師堂

堂島1丁目6
海岸がもっと内陸に近かった昔、海上の船からお堂がよく見えたことから、地名が「堂島」と名付けられたほど、由来は古い薬師堂です。当時、人びとの信仰も厚く「堂島のお大師さん」と呼ばれました。平成11年に完成した「堂島アバンザ」の庭園内に球形でモダンな建物として生まれ変わりました。