区の歴史
2025年4月22日
ページ番号:2159
古代の北区
近年、地球温暖化問題に関連して、海面上昇のおそれが指摘されていますが、縄文時代には「縄文海進」と呼ばれる海面上昇が起こり、泉北丘陵から北に伸びる上町台地が半島状に海に突き出ていた以外は、大阪平野のほとんどが水没し、台地の東側には生駒山麓まで海水が浸入して「河内湾」が形成されていました。
その後、海面が低下し、淀川や大和川による堆積作用も進み、弥生時代に入ると「河内湾」は淡水化して「河内湖」へと変りました。「河内湖」と大阪湾をつなぐ水路は神崎川付近だけに狭まったと考えられ、複雑に入り交じる潮流の速さから“なみはや~浪速”、船の難所であったため“なにわ~難波”などと呼ばれたとも言われています。
現在の区内では、天満砂州と呼ばれる砂地が天満橋付近から北に伸びていました。この砂地上には、5~6世紀頃の古墳とみられる鶯塚など、早くから人の足跡がみられます。
また、北区国分寺町一帯は摂津国の国分寺推定地、長柄橋付近は悲しい人柱伝承も伝わる長柄橋推定地ともなっています。
さらに現在の大川は、神崎川付近の難所を避けて、船が通行できるよう開削された「堀江」だとする説もあり、大和政権の外港であった「難波津」はこの「堀江」に沿った高麗橋から天満橋付近にあったとも言われています。
中世の北区
平安時代に入ると「難波津」は、大川の両岸を結ぶ渡しに由来するとされる「渡辺津」や、都から高野参りや熊野詣の船が着く「八軒家」に変わります。「渡辺津」は淀川や大和川と瀬戸内を結ぶ中継港として栄え、吾妻鏡などの史書にもしばしば出てきます。
海運の要衝としての役割は、室町時代に堺が台頭してから徐々に小さくなりますが、堺と都を結ぶ中継地としての役割が生まれました。1496年に蓮如が生玉の地の北側に、石山本願寺の礎となる施設を造営します。都から熊野詣に向かう人々や堺から都をめざす商人たちが賑やかに行き交う地であり、布教や寺院経営に適していたので造営されたという説もあります。一方、地理的重要性のため、南北朝の争いでは足利軍と北畠軍が渡辺橋で戦うなど、争乱の舞台となることもありました。
山科本願寺が1532年に焼失すると、本願寺の拠点は大阪に移り、石山本願寺として一層発展します。寺のまわりには寺内町が築かれ、日ごとに人の往来が激しくなり、日用品の売買も盛んになりました。はじめは生産者や小売人が出店販売をしていたのが、次第に定着し、問屋や仲買人のような組織が生まれたと言われています。
安土桃山から江戸時代はじめの北区

幕末1863年の大阪
改正増補国宝大阪全図
(大阪城天守閣所蔵)
石山本願寺は三方を川や低湿地に囲まれる天然の要害であり、水陸交通もこのうえなく便利な点に着目した織田信長は、石山本願寺に退去を命じたが拒絶され、1570年から本願寺攻めを開始します。天正8(1580)年にようやく本願寺は和睦に応じ、退去します。
天正10年の本能寺の変以降、羽柴秀吉が信長の遺志を継ぎ、翌年から石山本願寺跡地に大阪城の築城を始めます。秀吉は築城とともに城下町造りを進め、堀川を開き、街区を整え、武士の日用品調達と戦時に備えた物資集積を目的として堺や平野の商人を移住させました。堀川はまず東横堀川が、次いで天満堀川が現在の菅原町から扇町公園付近まで掘られました。また、天満堀川左岸から大川にかけて近在の寺を集約し、寺町を造りました。同様のまちは現在の天王寺区付近にも設けられ、有事の際の北と南の防衛陣地としての役割も持ちました。この頃から天満は大阪の一角として発展していきます。
大坂冬の陣、夏の陣により大阪城下は多大な被害を受けました。徳川幕府は、秀吉が進めていた蔵屋敷の整備など経済中心地としての役割を重視し、松平忠明を大阪城代に任じて大阪復興に努めます。忠明は秀吉の町割を踏襲しつつも、さらに城下を拡大し、堀川の開削と土地のかさ上げを進めました。戦災を逃れていた商人たちも次第に大阪に戻りはじめ、商都大阪として繁栄の道を再び歩み出しました。
大阪のまちは本町通りを境に北組と南組に位置づけられ、その後、北組から大川右岸が天満組として分離しました。これにより大坂三郷と呼ばれる町組が完成します。現在の北区は、北組ではなく天満組が基盤となっています。
江戸時代の北区
江戸時代初期の北区は、現在の寺町通りと新御堂筋に囲まれた地域がほぼ市街化され、中之島と堂島川右岸に蔵屋敷が建ち並ぶほかは、のどかな田園風景が広がっていました。
一方、堀川が張り巡らされた水都大阪では、堀川の川底の土砂を取り除いたり川幅を広げたりすることによって水運を確保し、水害対策を行うことが欠かせませんでした。北区一帯でも堂島川とその分流であった曽根崎川(蜆川)の改修が行われ、新たに整備された河岸は堂島新地、曾根崎新地となりました。新地には三郷になかった茶屋や湯屋、芝居小屋などのアミューズメント機能が生まれました。同様の経緯で開発されたのが、ミナミの道頓堀一帯です。
堀川の改修、橋の新設や架け替え、新田開発など、まちづくりは次第に幕府主体から住民主体に変わっていきます。大阪は八百八橋と言われますが、いわゆる官設の公儀橋はわずかで、多くは商人たちが出資して造ったものであり、「住民主体のまちづくり」がすでに行われていたと言っても過言ではないでしょう。
また、天満組からは2本の重要な街道が北へ伸びていました。一つは太融寺の東を抜けて北西に向かう中国街道です。中国街道は十三の渡しで中津川(現淀川)を越え、尼崎城下に通じます。この道は現在の中津(大淀警察署付近)で北に向かう能勢(池田)街道と分かれます。能勢街道は古典落語の「池田の猪買い」で詳述されています。もう一つは天満宮の西を抜けて北へ上がり、長柄から吹田へ向かう亀岡街道です。現在の天神橋筋商店街はこの街道に沿って発展しました。
亀岡街道の東側に、寺町を挟んで与力町、同心町が設けられました。この2つは東町・西町両奉行所のもと、市中取り締まりにあたる役人の居住地でした。また、1653年には京橋から現在の南天満公園付近に天満青物市場が移転し、1841年から始まった天保の改革まで大阪唯一の官許市場として栄えました。
まちの成熟とともに文化も発展しました。なかでも歌舞伎や人形浄瑠璃は都市住民の娯楽として人気がありました。これらの脚本家で最も知られるのが近松門左衛門です。作品中でも有名な「曽根崎心中」や「心中天網島(てんのあみしま)」は、北区内が主な舞台となっており、劇中では当時のまちの様子もうかがえます。
幕末の北区

大塩平八郎肖像画
(大阪歴史博物館所蔵)
19世紀に入ると幕藩体制も次第に疲弊し、さまざまな形でひずみが表れるようになりました。「天明の大飢饉」などをきっかけに打ちこわしや一揆が頻発し、天明7(1787)年には大坂三郷でも激しい打ちこわしが起き、米蔵が襲われました。
また、天保8(1837)年の「大塩平八郎の乱」では、世の荒廃を憂いた与力の大塩が、その私塾洗心洞などを通して知り合った同志とともに、体制改革を要求する強訴を計画しますが、実行前に発覚し、急遽挙兵に至ります。2月19日朝から始まった争乱は夕方にはほぼ鎮圧されますが、天満組一帯と北組の北半分は焼け野原となりました。反幕府側に武士も加わった争乱は、「島原の乱」や「由井正雪の乱」以来、市街戦は「大阪夏の陣」以来とあって、幕藩体制の崩壊の一因ともなりました。
一方、大阪には洗心洞のほか、緒方洪庵の適塾(中央区内)、篠崎三島の梅花社(中央区内)など学問の場が多数設立され、日本を近世から近代に進ませる多くの人材を輩出しました。洪庵は龍海禅寺、三島は天徳寺と、ともに北区内に墓碑があります。
幕末の動乱においては、都に近い大阪も尊王攘夷派と開国派、佐幕派と倒幕派が行き交うまちでした。大阪の薩摩藩や土佐藩の蔵屋敷は志士たちの潜伏地・中継地となったほか、豪商鴻池との縁などもある新撰組もしばしば来阪しています。さらに長州征伐の途上、大阪城に寄った14代将軍家茂が城内で病没し、15 代将軍慶喜の登場を早めます。慶喜は二条城と大阪城を行き来しながら幕藩体制の存続を図りました。しかし、慶応4(1868)年1月、鳥羽伏見の戦いに至り、兵を大阪に残したまま海路江戸に向かいます。慶喜の大阪城脱出により、幕府側の戦意は急速に衰えましたが、大坂三郷が再び戦乱に巻き込まれることは免れました。
明治の北区

初代大阪駅の駅舎
(「写真で見る大阪市100年」大阪市より)
明治維新後、大坂三郷は北、東、南、西の四大組に改組されます。これが大阪市のもととなります。明治4(1871)年には廃藩置県が実施されるなど、何度かの行政改革を経て、四大組は明治12年から区と呼ばれるようになり、北区の呼称が登場します。大阪市の設置はさらに後の明治22年になり、現在の区制はこのときからとなります。
まちづくり上での大きな出来事では、大阪-神戸間の鉄道開通に伴う明治7年の鉄道駅「梅田すてんしょ(当時の呼称)」開業があります。当時、鉄道と駅の設置は住民の反対にあうことが多く、大阪でも“町はずれ”の曽根崎の地が選ばれました。なお、開業当時、曽根崎と呼ばれる地域は、現在一般に知られるあたりよりかなり西寄りを差し、駅舎も当初は現在の大阪中央郵便局付近にありました。駅の設置が“町はずれ”であったことが、開発余地の大きさにつながり、その後の北区の発展を約束しました。
明治初期に相次いだ淀川の氾濫は、市中に多大な被害を及ぼし、近代都市への発展上、治水対策は大きな課題となりました。オランダ人技師デ・レーケの指導の下、淀川の直線化、バイパスとなる新淀川開削、毛馬洗堰の設置などを柱とする大規模な改修事業が行われ、明治42年に完工しました。中津川は新淀川(現淀川)に替わり、洗堰によって市内への水流が調整されるなど、水害対策は格段に向上します。さらに淀川改修にあわせて架橋工事を進めていた、阪神電気鉄道や箕面有馬電気軌道(現阪急電鉄)が開業し、梅田が一大ターミナル化するなど、北区の発展が進むことになりました。
大正から昭和初期の北区

昭和初期の天神橋と
堀川のまちなみ
(「写真で見る大阪市100年」大阪市より)
明治42年に「キタの大火」と呼ばれる大火事が発生しました。空心町付近で出火した火災は西へ広がり、堂島、曽根崎一帯にまで達し、当時の北区の大部分が焼失しました。この火災の復興事業として曽根崎川(蜆川)が埋め立てられたほか、四つ橋筋、天神橋筋などの拡幅、国道1・2号の新設が行われ、大火の前年に完成していた淀屋橋から大阪駅までの梅田新道(現御堂筋)とあわせて都市基盤がさらに向上しました。
明治36年に開業した市電も、道路拡幅に伴い整備が進み、北摂の郊外住宅地に住む勤め人が梅田で乗り換え、船場の商店に通勤する光景も増えました。また、大正10年には中之島に大阪市役所が移転、昭和4年には阪急百貨店が開業するなど、大正から昭和初期にかけて、中之島から梅田方面へ都市化の波が進みました。
一方、造幣局以北の大川沿いや中津運河沿いには工場が立地し、工場地帯としての様相も呈してきます。大正14年には旧中津町、豊崎町、鷺洲町が大阪市に編入され、現在の北区域はすべて大阪市に属しました。

「キタの大火」での類焼地域記録図
(「北区史」(財)大阪都市協会より)
また、大正10年から第1次都市計画が始まりました。これは梅田から難波までの御堂筋の拡幅を含む抜本的な都市再構築であり、北区内では大阪駅前での土地区画整理事業や大阪駅の現在位置への移設、都島通の新設などが行われました。さらに、昭和8 年には梅田-心斎橋間に地下鉄が開通し、近代的な都市へと成長し続けました。しかし、その間に大陸での戦局も拡大し、まちの空気も軍事色が強まってきました。
昭和16年の太平洋戦争開戦後、しばらくは大きく拡大した戦線も次第に連合軍に押され、昭和19年の秋から散発的に全国各地を見舞った空襲は、昭和20 年に入ると次第に規模と頻度を増しました。当時の大阪市内では1月3日の阿倍野区内での空襲が、北区内では1月30日未明の空襲がともに最初となりました。3月13日深夜から14日未明にかけての大阪大空襲では、旧北区内の4分の1が焼失する被害を受けました。また、6月1日と7日には旧大淀区域も含め広範囲に爆弾が落ち、特に7日には長柄橋南詰め付近で、機銃掃射により400人余の死者を出す「長柄橋惨事」が起きました。度重なる空襲によって、近代化に努めてきたまちは廃墟に変わりました。
戦後の北区

昭和25年頃の大阪駅前
(正面は3代目大阪駅舎)
(「写真で見る大阪市100年」大阪市より)
終戦翌月に大阪市は復興局を設置し、復興都市計画に着手しました。北区内でも御堂筋の北進 (新御堂筋)や天神橋筋の拡幅などの道路計画、戦災復興土地区画整理事業が進められました。終戦とその後の復興により、人口も徐々に回復していきました。一方、大阪駅前には大きな闇市も出現し、その後の北区のまちづくりに影響を及ぼすことになります。
日本全体が復興から高度経済成長に移行するなかで、郊外住宅地の発展が加速しました。その影響もあり、梅田や天神橋筋6丁目は通勤客でにぎわうターミナルとなり、商業施設も次第に増え、戦前のにぎわいを超えるほどになりました。工場やオフィスも復興し、北区は大阪における商工業の中心地としての地位を確立していきました。
経済成長が進むにつれ、新たな課題も起きてきます。自動車の普及により、交通渋滞が慢性化し、市電の廃止を求める意見が出始めるなど自動車中心の交通社会に変容していきました。
また、工場や自動車から出る排煙や排ガスによる大気汚染、生活・産業排水による水質汚濁など、都市の住環境も次第に悪化します。さらに昭和30年代後半に計画、事業化された千里ニュータウンなど、大阪市周辺の大規模住宅地整備もあいまって、人口の流出が始まりました。
万博後の北区

昭和45年頃の大阪駅前
(「写真で見る大阪市100年」大阪市より)
昭和45年の大阪万国博覧会に対応した新御堂筋の整備と地下鉄御堂筋線の北進、地下鉄堺筋線の開通と阪急線との相互乗り入れは、北区に新たな南北軸を加えるものでした。また、地下鉄網も昭和49年に谷町線の東梅田-都島間が開通するなど、一層発展していきます。
梅田一帯では阪急を基軸とした開発が進みます。まず阪急梅田駅を国鉄線(現JR線)の北側に移設し、その駅下に新たな商業ゾーン(阪急三番街)を設置します。また旧梅田駅跡には阪急グランドビル(32番街)を建設したほか、阪急ターミナルビル(17番街)などの高層ビルが次々と立ち上がります。ビルの高層化は広まり、昭和51年には大阪マルビル、昭和58年には大阪駅ターミナルビルなどが建設されます。一方、国道2号線北側に広がった密集市街地の再開発も、徐々に進みます。昭和45年の駅前第1ビルに次いで、昭和51年から55年にかけて、第2、第3、第4ビルがそれぞれ完成しました。
産業構造の転換などにより工場の移転や閉鎖も進みます。跡地には高層住宅を中心とした大規模住宅地が整備され、人口の都心回帰を促しました。昭和46年に完成した中津リバーサイドコーポはウォーターフロントでの工場跡地再開発の先駆けとなりました。
現代の北区

現代の大阪~高層化する街並~
(「わがまち北区10年のあゆみ」より)
昭和50年代後半に入ると淀川リバーサイドタウンの開発が本格化します。公共下水道の整備や産業排水規制の強化などにより、河川の水質も次第に改善され、中之島公園での水辺のプロムナードや水上バスの運行、淀川河畔での河川公園整備など、まちづくりでも水辺に回帰する動きが広がってきました。
平成に入るとさらに発展が加速していきます。独特な構造の梅田スカイビルを中心とする新梅田シティ、古い街並みを残していた茶屋町の再開発、大阪アメニティパーク(OAP)、オオサカ・ガーデン・シティ、大阪国際会議場などさまざまな都市開発が梅田の西・北方向にも進みます。また、JR東西線が開通し、北区の東西交通が強化されました。
都市環境の整備に伴い、人口流出も次第に少なくなり、近年は漸増傾向に転じています。
21世紀を迎え、阪大跡地を中心とする中之島西部地区の開発、JR梅田貨物駅の跡地利用など北区の将来を大きく左右する構想・計画が目白押しです。今後も、より良いまちづくりを進めて、明るい歴史を重ねていくことが望まれます。
「北区未来づくりブック≪都心居住の理想郷・北区≫をめざして」
(北区役所 平成13年3月発行)より
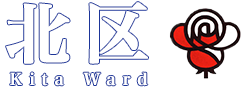






 SNSリンクは別ウィンドウで開きます
SNSリンクは別ウィンドウで開きます

