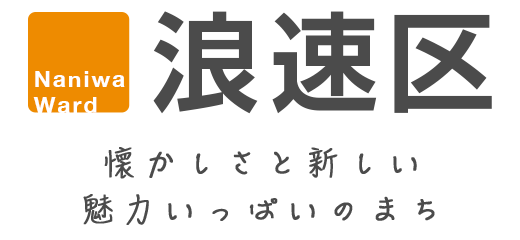浪速区制100周年プレ企画 ルックバック浪速区(第10回日本橋地域)
2025年2月1日
ページ番号:644871
座談会

地域の皆さんにお話を伺いました
宿場町として栄えた長町
区長
ではまず最初に、昔の日本橋筋について教えてください。
岩上さん
江戸時代の日本橋筋(堺筋)は公儀道でした。公儀道は長堀橋から始まって南へ日本橋、名呉橋(今の阪神高速1号線のえびす町入口)まで来て、今の恵美須の交差点のところで奈良街道と紀州街道に分かれていました。交差点から西に折れて1筋目の道を南に折れて、住吉神社の前を通って堺につながっていたのが紀州街道、交差点から四天王寺の方へ抜けていくのが奈良街道でした。交差点から西に折れて1筋目の道を北に折れて遡る街道は住吉街道と言いました。東西は住吉街道から今の日本橋公園の東側の道まで、南北は道頓堀の日本橋から今の恵美須の交差点までのエリアを「長町」と言い、旅籠(旅館)がたくさんありました。
区長
今の「オタロード」は住吉街道の一部なのですね。
宇野さん
北浜から日本橋1丁目までを堺筋といい、そこから南は紀州街道になっていました。日本橋1丁目に公儀橋がありましてね。でも島之内は夜間は立入禁止だったので、旅人は島之内から外に出なければいけなかった。それで八軒家浜にも長町にも旅館が多かったんです。
江戸時代、紀州藩のお殿さんが参勤交代で大阪に来た時は、日当で人を雇って共揃えをして、千人か二千人の行列を作って市中に入るんですが、そのアルバイトをする人間が長町にはたくさんいたんです。分銅河内屋という旅籠には弥次さん喜多さんの十返舎一九(『東海道中膝栗毛』の作者)も泊まったそうです。
区長
長町に住んでいる人がそのアルバイトをするんですか。
岩上さん
よく時代劇の映画やテレビドラマで、田畑の真ん中を大名行列が「下に、下に」と言って通る場面をみかけます。参勤交代というと国元(領地)から長い行列を作って江戸まで行ったと思う人も多いかもしれませんが、間違いです。それではお金がいくらあっても足りません。国元の城から国境まで行列で来たら、必要な人数だけ残して、あとは国元に返しました。行列の消滅です。衣装などの荷物を大急ぎで荷車に積んで、次の番所(チェックポイント)の手前まで運び、大名を待ちます。いわば「キセル」をするんです。番所の手前で供揃え(お供の人びとを揃える)をして行列を作る。その供揃えをする場所がうちの寺(大乗坊)でした。日本橋と長堀橋が番所になっていましたのでね。
うちの寺に荷物が来たら「口入れ屋(今でいう職業あっせん業者)」が人を集める。そこで集められたのが長町に住んでいる人たちでした。いわば「エキストラ」ですね。衣装をつけさせて供揃えをし、公儀道を日本橋へ長堀橋へと「下に、下に」と歩き、大阪城に登城します。その後は鴫野まで行き、エキストラはそこで衣装を脱いで、駄賃をもらって帰ってきました。
大名籠も国境で国元に返してしまい、供揃えをする場所で籠を借りていました。大きい寺は住職が乗る寺籠がありますので、その籠を借りて大名籠にしていました。
区長
面白いお話ですね。そうやって道中の経費を節約していたんですね。
岩上さん
でも、そういうことは堂々とやれないので、大名も荷車も公儀道は通らず、裏街道(住吉街道)から寺に入り、寺できちんと支度を整えて、寺の表門から公儀道(紀州街道・堺筋)に出て、日本橋、長堀橋をわたって大坂城へと入って行ったということです。
宇野さん
河原町(かわはらちょう)には芸人さんも多く住んでいたんですよ。
岩上さん
今の難波中2丁目から道具屋筋、千日前にかけて、以前は「河原町(かわはらちょう)」と呼ばれていて、芸人さんや道具方、台本書きなど舞台関係の人たちがたくさん住んでいました。最初は今の難波中2丁目あたりに住んでいて、出世すると黒門市場の方へ親方として移っていきました。京都でも「河原町」がありますが、あそこも京都の芸事に関連する人たちが多く住んでいました。
規模は天王寺村よりも河原町の方が大きかったです。道頓堀五座が近くにありましたし、移動の芝居小屋が始終やってきていましたからね。
発想豊かな大阪人~盛んだった番傘作り~
区長
長町はずいぶん市街地化していたようですが、それ以外の地域はどのような様子だったのでしょう。
岩上さん
長町の東も西も、昔は畑でした。
住吉街道と紀州街道の間に、油を搾って大阪のまちに売りに行って生計を立てていた方が多くおられました。油を搾って出た粕(カス)は畑に捨てに行っていたんですが、このあたりは砂地ですので、その砂地と油粕が合わさって良い畑ができたんです。そこで難波葱や金時にんじん、蕪(かぶら)などを作っていました。明治の時代になって難波駅ができたときは、「葱(ねぎ)畑のなかの難波駅」と言われたそうですよ。
それから江戸時代、うちの寺の西側で畑を作っていた人たちの農閑期の手間仕事として番傘作りが盛んでした。番傘は傘張りをして油を塗って作ります。「浪花百景」の中に、油を塗って干してあった傘が突然の風で飛ばされていく様子が描かれています。傘に塗る油は、長町の油屋さんの粕油です。燃やすしかないような油を手に入れて、傘に塗ってそれを乾燥させるんです。そのまとめ役をしていたのが、「御蔵跡」の辺りにあった傘屋さんたちです。油紙も和紙に油を塗って作って、大阪のまちの中に売りに行きました。江戸時代に、折りたたんで荷物の中に入れておいて雨が降ったら広げて着る、油紙で作られた携帯用の雨ガッパが流行りました。油紙は本来、書状などの大切なものが濡れてしまわないように作られたものですが、水をはじくという特性からカッパを作ったんですね。当時の大阪のまちの人の発想はすごいと思います。

「長町裏遠見難波蔵 (浪花百景)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)
履物のまち「御蔵跡」
区長
先ほど「御蔵跡」のお話が出ました。日本橋の「御蔵跡」は履物のまちとして有名ですが、「御蔵」そのものは江戸時代、今の中央区側にあったそうですね。
宇野さん
「御蔵」のあったあたりを総称して「御蔵跡」と言ったんでしょう。
昔、「御蔵」に通じていた高津入堀川が、明治時代に南の方へ延長されました。その影響で、深田橋の近くには製材所が何軒かあって、ゲタの材料を作っていたそうです。
「御蔵跡」に履き物屋さんが増えたのは、昭和の時代になって、関 一 市長が御堂筋を拡張するために、南御堂付近にたくさんあったゲタ屋さんを立ち退かせたからで、「御蔵跡」のところに集団で移転してきたと聞いています。
岩上さん
鼻緒屋さんとか、ゲタの形に木を切る人とか、草履の台を作る人とか。そういう人たちが「御蔵跡」に住んでいましたからね。
宇野さん
小学校の頃、高津入堀川の深田橋付近の空き地に、円形に高くゲタが積み上げられていました。ゲタを乾燥させていたんです。私らはそこからゲタを抜いて、遊んでいたことを思い出します。
岩上さん
そのゲタを抜いて、どこまで抜いたら倒れるか。あるいは、その中をトンネルみたいに通り抜けられるか。そういう遊びをしていましたね。
眺望閣と五階百貨店
区長
明治時代になり、日本橋筋や長町の様子も大きく変わったのでしょうね。
宇野さん
廃藩置県で地方の藩が潰れて、長町にも浪人やらが集まってきて、あまりよくない環境だったようです。
その後時代が変わって、戦前は60数軒の古本街や古着屋さんでにぎわいましたが、戦争で一掃されて、家電屋さんのお店に変わっていきました。家電屋さんも一時すごかったですけど、家具や電気の街(でんでんタウン)、履き物街も少なくなり、工具屋さんもDIYの店がたくさんできましたので、減りつつあります。
区長
少しずつ、伺っていきたいと思います。
明治時代の中頃に、「有宝地」という遊園地ができたと聞きました。そこの目玉が「眺望閣」という展望台で、それが、今の「五階百貨店」と関係があるそうですね。
岩上さん
当時の「眺望閣」は5階建てで、それが「五階百貨店」の呼び名の始まりです。
区長
「眺望閣」が5階建てだったからそう呼ぶようになったんですね。「眺望閣」は今の「五階百貨店」の場所にあったんですか。
宇野さん
「眺望閣」はもう少し北にあったようですよ。
区長
「五階百貨店」は戦前からあったそうですが、戦後、いち早く商売を再開し、日本橋の復興を支えたそうですね。
中山さん
「五階百貨店」は日本橋4丁目交差点から150メートルほど北側、ちょうど堺筋から西へ、1つ道を隔てて、さらにもう1つ西側のところまで、バラック建てでトタン屋根の建物が南北の道路を挟んで2棟建っていました。建物の中は1メートル20センチ位の通路が東西に2列あって、店舗は幅が2メートル四方ほど。土台は高さ30センチ位の木台でした。店舗は呉服屋、金物屋、電気屋さんやいろいろな店が集まってにぎやかでした。
今は月極で家賃、いわゆるテナント料ですね。それを払いますが、その頃は日払いでした。「亀山」さんという親方がいましてね、ロープ屋さんでしたが、その人が毎日、各店舗から家賃を集めていました。どの店も扉も何もなくて開けっ放しでした。皆で近くの倉庫を借りて、朝は倉庫から品物を出して、丁稚(でっち)車で店に運んで下ろす。夕方にまた品物を積んで倉庫に入れる。だから夕方になったら店の中はからっぽでした。
私は日本橋小学校の卒業生なんですが、日本橋小学校が戦災でまだ再開校していなかったので1947(昭和22)年4月、日東小学校に入学しました。再開校したのが3年生の2学期で、日東小学校で使っていた机と椅子を皆で1つずつ持って日本橋小学校に運んだことを覚えています。
その頃は堺筋にまだ市電が通っていました。軌道敷といって、市電のレールの横は30センチほどの石が敷かれていました。車道はコンクリートでした。ところが堺筋から1歩、中に入ったら地道でしたので、雨が降ったら下がドロドロになりました。それでもカッパを着て、雨の中を「五階百貨店」の品物が運ばれていくのをよく見ていました。
それから、「五階百貨店」の定休日は、廣田神社の夏祭り(22日と23日)に合わせて月に1回、23日と決まっていました。
ジェーン台風(1950(昭和25)年)の時は、風がすごかったのです。ちょうど「五階百貨店」の近くで市電の軌道敷内の工事をしていたんですが、雨が溜まりましてね。今でしたらちょっとした工事でも、ガードマンが付いて誘導してくれるでしょう。当時はガードマンはいないし危険を知らせる標識もなかったので、車が走ってきてバッシャーン!とはまり込んでしまって、その車を外に出すのに難儀していました。
五階百貨店
電気屋街と忘れられない名物巡査
区長
ではもう一度、戦前から戦後にかけてのまちの変化に話を戻していただければと思います。
岩上さん
戦前、日本橋では古本や古着、あるいは果物や野菜が売られていました。戦後、「ジャンク」といって進駐軍の払い下げの通信機を分解した、真空管などを売り出しました。それが電気屋街の始まりです。そういったものを売っていた人たちが、今でいう白物家電を作って売るようになって、小売のお店がずらっと店を構えたというのが日本橋の電気屋街です。
東京の秋葉原も同じようにして電気屋街になったんですが、向こうはお客さんに還元する「ポイント制」を考え出しました。日本橋の電気屋街ではそろばんを使って、店先で交渉して値段を決めていました。結局、東京方式のポイント制に大阪の電気屋街は負けたんですね。店先で値切るよりも、ポイントがついて後で買い物ができるというのが主流になって、日本橋の小売店では売れなくなって衰退したというのが、だいたいの歴史ですね。
区長
田原さんは戦後のお生まれですね。子どもの頃のまちの様子は覚えておられますか。
田原さん
僕は1948(昭和23)年の生まれです。物心ついた頃の堺筋には電気屋さんもすでにたくさんありましたが、革屋さん(グローブなどの革製品を扱う店)や本屋さんもあって、市電が走っていました。
私の父も家電ではなく重電関係のモーターなどを扱っていました。使えなくなったモーターを、コイルを巻き替えて売っていました。よく売れたそうです。山崎貴監督の映画「ALWAYS 三丁目の夕日」の時代描写は、私が子どもの頃の日本橋を思い出させます。
岩上さん
その当時、浪速警察署のお巡りさんで有名な人が1人いました。「宇野さん」というお名前の方でしたが、日本橋3丁目の交差点の真ん中で、ものすごいパフォーマンスで交通整理をするんです。車の往来が激しい場所ですが、車も市電も全て手信号でさばいていました。交差点のなかで車がエンストすると、すぐにそれを押して退けて、車がスムーズに通れるようにされていました。
田原さん
覚えています。とても有名な、大阪でナンバーワンの交通整理のお巡さんでしたね。交差点に立って笑顔で手招きして、優しくて子どもたちに人気がありました。
宇野さん
当時、小学校の児童が800人くらいいて、その道路を横断して通学していました。その巡査は交差点の真ん中に立って、滑らかな動きでダンスのようなパフォーマンスをしていました。
中山さん
手信号をする時は台を持ってきて、皆からよく見えるように、台の上に上って手際よくやってましたね。車の運転手は遠くの方から宇野巡査がよく見えたので、近くへ来るとスピードを落として安全運転をしていました。
宇野さん
当時は今よりも車の数は少なくて、市電や市バスが走っていました。子どもの頃に1番怖かったのは市電でした。
岩上さん
日本橋3丁目の交差点は、堺筋をまっすぐ南北に行く市電と、難波の方角に曲がる市電と、2つの市電が走っていたんです。でも子どもには、どの市電がどちらに行くのか、わからないんです。宇野巡査は市電まで止めるような働きをされていました。何度か新聞でも取り上げられていましたよ。
区長
その方が活躍されていたのは、いつ頃のことですか。
岩上さん
1950~51(昭和25~26)年頃から始められて、4年以上はされていたと思います。その後、阿倍野警察署に異動されました。
区長
その方の後を引き継がれたお巡りさんはおられたんですか。
中山さん
いえ、おられませんでした。だって普通、あの方のようなマネはできませんからね。そして児童や生徒、保護者の皆さんから、かなり慕われていました。
地域が誇る文化財~大乗坊と髙島屋別館
宇野さん
東京の神田は現在も古本の街で秋葉原へと電気屋街になり、今はオタク文化のまちになっています。日本橋も1歩遅れて同じ道をたどっています。
それから、江戸時代にはこのあたりに旅籠がいっぱいありましたが、今もホテルやワンルームマンションがたくさん建っています。130年ほどかけて1回転して、また元に戻ってきたような感じがしますね。
最近、店の形態が大きく変わってきたと感じています。以前はこんなに食べ物屋さんはありませんでしたし、コンビニも増えました。今はインバウンドの需要があるので成り立っていますが、それが収まったら果たしてどうなるのか。東京の中心街のように店がなくなって、楽しみでこのまちに来る人がいなくなってしまうのではないか。
今、日本橋筋商店街にはホテルが増えています。それまでお店をされていたところを3~4軒、集約して建てるんですが、1階はエントランスで貸さないので商店街としては歯抜けの状態になっています。これがもっとひどくなると商店街ではなくなってしまいますし、後で商店街に戻そうとしても無理だと思うんです。建物が大きいので、また小さな店舗に改造するわけにもいきませんからね。
そんな中で、毘沙門さん(大乗坊)と髙島屋の東別館があることはありがたいと思っています。それを目的に人が来てくれますからね。どちらも国の重要文化財に指定されています。
区長
大乗坊にある毘沙門天王立像は日本四大毘沙門天王像の1つで、非常に古い歴史があると伺っています。もとは今の天王寺区役所のあたりにあったそうですね。
岩上さん
織田信長の焼き討ちに遭って流浪していたのですが、江戸時代の初めに灰屋さんの別宅を譲り受けて、そこにお寺を建てて再興しました。主になる毘沙門天の首は、奈良時代の毘沙門天のものと伝わっています。仏頭だけを持って流浪してこの場所に来て、それから下の体を作って、秘仏として祀っています。
先々代が大正3年に宝蔵庫を作りました。耐火式で、当時の銀行の金庫と同じ作り方をしています。終戦直後は、うちの寺から天下茶屋の駅まで見渡せました。うちの寺もこのまちも激しく焼かれましたが、本尊が入っている宝蔵庫は残りました。これには皆、驚いていました。

木造毘沙門天王立像(写真提供:大乗坊)
区長
今の髙島屋東別館も古い建物ですね。1937(昭和12)年に完成したと聞いています。
中山さん
堺筋は今の御堂筋ができる前は大阪のメインストリートでした。髙島屋東別館は堺筋にありますが、もとは百貨店の「松坂屋」でした。その後、松坂屋は天満橋へ移転しました。

松坂屋(現在の髙島屋東別館)(浪速区・わがまちー写真でみる浪速区の今昔より)
宇野さん
建物の耐震補強をするには建物を建て替えるよりも何倍も費用がかかるそうですが、前の館長が頑張って残してくれました。昔の百貨店は大理石をふんだんに使っていて、良い建物が多いです。日本の華です。でも壊してしまったら2度とできません。
岩上さん
建物は3つに分けて建てられました。北側、南側、それから真ん中の順番です。その後、1つの建物になりました。だから、この建物の強度は南側が一番強くてその次に北側。真ん中の部分が弱いとされています。そこを補強するために東側に建物を増築して、今は1つのきれいな建物になっています。
松坂屋はもともと、堺筋から一筋入ったところの土地を買っていて、そこに建物を建てる予定だったんですが、集客がよくないということで、堺筋に面していた日本橋小学校の土地と等値交換をしたんです。等値交換をした後、小学校の体育館を建てる時には、もとの松坂屋が作った貯水槽をつぶすのに大分苦労したと聞いています。
戦時中、北側と南側の建物の屋上に1基ずつ高射砲(空を飛ぶ目標物を攻撃するための火砲)がありました。日立造船が松坂屋の建物を借り受けて海軍省の事務所のようなものが置かれていたからなのでしょう。
中山さん
建物は大阪大空襲の時に被害に遭わなかったんですね。私が小学生だった1950~1951(昭和25~26)年の頃、松坂屋の屋上はプールと遊園地でした。プールをやめた後、そこに子どもの足で漕ぐ四輪車を走らせていました。私も運転したことがありました。
岩上さん
焼失は免れています。
宇野さん
日本橋小学校は一部の校舎が被害を受け、講堂は残ったんですが、2階の体育館は焼夷弾が落ちて焼けてしまいました。ほかにも1階のガラスが割れたりして学校としては使えず、戦後しばらくは教育委員会が使っていました。
岩上さん
教育委員会が出た後は、大阪市の教職員組合の事務所として使われていましたね。
区長
さきほど、日本橋地域の重要文化財のお話がありましたが、ほかにも何か、歴史的なものはありますか。
中山さん
大阪名物「六道の辻」についてお話しします。今の日本橋小中一貫校の南東角に昔、住吉街道の「西の六道の辻」がありました。「東の六道の辻」は堺筋を隔てて東側の、今の日東公園の南西角にありました。今はどこも4つ辻ですが、昔はそこに6つの辻があったんです。悪いことをした人を追いかけて来ても、六道の辻まで来たらどこへ行ったかわからず、捜しようがなかったようです。今も学校のフェンスと道路の間にその案内石が残っています。

日本橋小中一貫校の南東角にある六道の辻案内石
区長
それから、日本橋地域出身の有名人として、著名人の似顔絵描きでも有名な、イラストレーターの成瀬國晴さんがおられると聞きました。
岩上さん
成瀬さんのご先祖さんは幕府関係の方だったと思います。明治維新の後、うちの寺の西側にある駐車場の北側で、旅籠を経営されていました。成瀬さんは自分が描いた絵に「むかでや」というサインを入れていましたが、その「むかでや」というのは実家の旅籠の名前でした。毘沙門天の使いに「むかで」がいるので、うちの寺に縁のある名前です。
これからの地域へ寄せる思い
区長
このまちの課題、あるいは今後の期待などがあればお聞かせください。
中山さん
日本橋小中一貫校の北並びに15年ほど前まで、日本橋西通り商店会がありまして、電気屋さんや呉服屋さんがありましたが、今は商店会もなくなって、オタクのまちになりました。メイド喫茶やメイド酒場が増えて、大きく様変わりしました。
昔は自分の家の1階でお好み焼き屋などの商売をしていた方が、今は店を閉めてそのままにされています。そういうところも店舗として人に貸したり活用したりして、もっと活気のあるまちになったらいいなと思います。
岩上さん
メイド喫茶は、難波中にある一芳亭の向かいの店から始まりました。もともと「メイド喫茶」というのは、お客さんに「お帰りなさい」、帰る時は「行ってらっしゃい」と言い、丁寧にお客さんに接してくれる。コーヒーを注文したら「お砂糖は入れられますか」「ミルクはどうしますか」と聞いて、お客さんの代わりにやってくれるところで、それが本来の「メイド」ですわね。今、うちの寺の近くでも、外で並んで立って客引きをしていますが、あれは違うメイドで、あの世いきの「メイド」。うちの寺の近くでやっているから「冥土」ですねん(笑)。
田原さん
一時、ボッタクリのメイド喫茶が多いとか、いろいろと問題になっていましたが、今は、そういうメイド喫茶とそうでないメイド喫茶をちゃんと区別するように動いている組織もありましてね、そういうところと我々地域も連携しています。日本橋はカルチャーのまち、趣向性の高いまちです。メイド喫茶もあるし、「日本橋ストリートフェスタ」ではコスプレイヤーのパレードもあります。オタロードは今や、いち地域のブランドじゃなくて、海外にも知られています。そういう趣向性の高いものが、時代が変わっても、このまちにはあり続けてほしいと思います。
岩上さん
最近の日本橋の変貌はものすごいです。寺の周りにもホテルが増えて、そういうものに取り囲まれているように感じます。まちが変わってくる中で、1番さみしいのは子どもが少なくなったことです。われわれのまちを残すうえで、本当の日本橋を知ってる人が残ってくれるかどうかが1番の心配です。
たくさんの外国人観光客が毎日、うちの寺にもやってきます。彼らはスタンプラリーのような感覚で来るのですが、「本尊さんをお参りしてください」とできるだけ案内するようにしています。日本の古くからあるものを大切に残していく努力をしていかなければならないと思っています。
田原さん
日本橋は住んでいる人よりも、働きに来る人や遊びに来る人たちの方が多いので、そういう意味で将来が心配になることはありますが、戦災で焼け野原になって何もなかったところから、あのように電気屋街になり、それが傾いても今やポップカルチャーのまちになっています。日本橋という地域は本当に不思議な地域で、私はまちは姿は変わろうとも、これからも発展していくだろうと楽観的にみています。
もちろん治安の問題は出てきます。たくさんのお客さんに、外国の方も含め安心してこのまちに来てもらいたいので、今、住んでいる地域の皆さま、テナントの方々と力をあわせて、そのためのよりよい環境を作っていかなければならないと思っています。
区長
皆様、本日はありがとうございました。たくさん日本橋地域の歴史のお話を伺えました。
宇野さん
私は「日本橋」をなぜ「にっぽんばし」と言うのか、ずっと不思議に思っています。東京は「にほんばし」、大阪は「にっぽんばし」。どっちが古いんですかね。
岩上さん
古さからいうと、大阪の方が古いと言われています。というのは、日本のことを「ニホン」と呼ぶのは最近のことで、古来は「ニッポン」でした。そのことから、大阪の方が古いと言われています。
区長
日本橋地域に住んでおられる方の中にも「にほんばし」とおっしゃる方が結構おられますが、私は岩上さんに叱られるので(笑)、意識して「にっぽんばし」と言うように心がけています。
それから、これは他の地域でも同じなのですが、以前はその地域の歴史がわかる町名が多かったようですね。
田原さん
私の住所も今は難波中ですが、以前は河原(かわはら)町でした。
宇野さん
今のなんばパークスは昔、幕府の米蔵があったところで、「蔵前町」だったそうですよ。
中山さん
私の町会の町名も以前は「西関谷町」でした。町名変更の時、日本橋西1丁目にするか難波南にするかでずいぶん揉めましてね。全世帯にアンケートをとって結局、日本橋西1丁目になりました。でも「日本橋1丁目」がすでに千日前通りにありますでしょう。運送屋さんやお客さんから「日本橋1丁目と書かれているんですが、店が見当たりません。どこにあるんですか」と電話がかかってきて、「日本橋ではなくて日本橋西です」と説明したことが何度かありました。
岩上さん
その、歴史がわかる名前を大阪市が改名してしまったんですよ。
田原さん
今日は私も、知らないことをたくさん教えていただきました。話は尽きないですね。
区長
その土地の歴史の話って本当に面白いですね。
日本橋地域の歴史
1.宿場町から日本橋へ
堺筋沿いに形成された宿場町
江戸時代の堺筋は、大阪から堺を経て和泉・紀伊に達する紀州街道の起点部分にあたり、参勤交代で大名行列が通った道です。この堺筋の道頓堀川にかかる「日本橋」(中央区)は公儀橋(管理・修築費用を幕府が負担した重要橋)の1つでした。この「日本橋」から今の阪神高速1号線えびす町入口までの間の筋を「日本橋筋」といい、この筋に沿って形成された市街地は「長町」と呼ばれていました。
大阪では、東西方向の道路を「町通り」、南北方向の道路は「筋」と呼びます。豊臣秀吉以来の城下町「大坂」では、大坂城の正門=大手門から直進する方向にあたる東西道路が、港とも連絡する関係で重要でした。市内の大半の屋敷はこの東西方向の道に向かって対面し、それぞれ数十軒の屋敷群で町を構成していました。つまり東西道路はどこも、家々が間口を開いてぎっしりと並ぶメインストリートでした。一方、南北の「筋」は、家々の横壁か堀が延々と続く、通過専用の横丁というわけです。例外的に堺筋に面した屋敷群が、筋に対面していたのは、この道路が紀州街道に連なる重要交通路であったことを示しています。
南大阪方面への幹線道路であった紀州街道は、住吉大社への参道として、また紀伊藩(徳川家)や岸和田藩(岡部家)の参勤交代路として、人々の往来が盛んでした。そのため、「長町」には旅籠屋や木賃宿が多く立ち並んだのです。一般的な旅館を指す旅籠屋に対して、木賃宿とは、本来、旅人自らが持参した米を炊くための薪代だけで宿泊することができる安宿のことをいいました。1802(享和2)年から1809(文化6)年に刊行された江戸から京・大坂までの旅行記「東海道中膝栗毛」の大坂編は、弥次郎兵衛・喜多八コンビが長町7丁目(現在の日本橋4・5丁目の中間)にあった「分銅河内屋」という大きな旅籠に泊るところから始まります。ほかにも「ひょうたん河内屋」など高名な旅籠屋があって、「浪花の名物」と評されました。
なお、当時の日本橋地域の「長町」を除くエリアは、畑地が広がっていました。
堀川の開削
1733(享保18)年、庶民のレクリエーション空間であった下寺と宿場町として発展していた日本橋の間に高津新地という新市街が建設されることになり、その翌年、延長約800メートル、幅約16メートルの高津入堀川が開削されました。その後、高津新地の南側に幕府が米蔵(天王寺御蔵)を設けると、道頓堀川とも連絡することとなり、舟運の利用も増えました。ただ入堀は水が滞留しやすく不衛生なため、1898(明治31)年に、現在の下寺と日本橋東の間に高津入堀川を延長させ、その後西に屈曲して現在の浪速警察署の北側を通り、さらに北折して、鼬川と接続させる工事が実施されました。
しかし、堀川の水路としての意義は、市電網の整備にともなって次第に失われていきました。戦後まもなく埋め立てられた高津入掘川の跡地上には現在、阪神高速道路環状線が通っています。
長町の改名と眺望閣
にぎやかな表通りに対して、交通の便の良い日本橋や下寺の裏通りには各地からの出稼ぎ労働者や生活困窮者が集まり、日割り家賃を支払って暮らす長屋住民や無宿者のまちとなっていきました。こうした街のイメージを一新するため、1792(寛政4)年、長町1丁目から5丁目(現在の中央区)を「日本橋」と改称し、さらに1872(明治5)年、先に改称された「日本橋」と旧6丁目以南の長町はすべて「日本橋筋」とされ、「長町」の名は消えることとなりました。
旧「長町」は、大坂三郷が四大組に改められた1869(明治2)年に、南大組に属すことになりました。その後、1875(明治8)年の第2大区を経て、1879(明治12)年の郡区町村編成法の制定により南区となりました。
明治時代になると、コレラが大流行してこともあって、大阪府によってスラム街の再開発計画が持ち上がります。当時の建野郷三知事の構想は、日本橋に大劇場を建設し、千日前に集まっている見世物小屋を移転させて、一帯を大興行街に作り替えようというものでした。この構想は実現しませんでしたが、こうした計画を見越した民間資本の手によって、1888(明治21)年、日本橋4丁目の現在の五階百貨店の西側に「有宝地」という遊園地が開業します。築山や池泉が配され、四季を通じて楽しめる花や木が植えられた和風の庭園内には茶店、売店、浴室も準備されていました。この遊園地の目玉が高さ31メートルの「眺望閣」という展望台でした。木造5階建ての楼閣からは、日本で最初の灯台である住吉の高灯籠のほか、淡路島や播磨方面まで見渡せたそうです。当時の新聞広告には、塔にのぼれば眺望が良いだけでなく、新鮮な空気を吸い込んで健康にも良いなどと謳われました。

眺望閣(大阪市立図書館アーカイブネット)
2.近代的なまちなみの形成
市電の開通
1900(明治33)年5月、第5回内国勧業博覧会を3年後の大阪で開催するという勅令がおりました。堺筋は既成の市街地から会場となる天王寺・今宮への主要な交通路にあたります。開会式当日には明治天皇の馬車も通る行幸道路でもあったため、不良住宅街は撤去されました。狭くなったところは拡張され、道にはみ出した軒の庇は屋根瓦3、4枚分の軒切りが強制されて、堺筋は幅員5メートルの道路として整備されたのです。
1903(明治36)年の内国勧業博覧会には間に合いませんでしたが、同年9月に日本初の市営市街電車が花園橋・築港間に開通し、1908(明治41)年に南北線が開通しました。梅田から四つ橋筋を南下する南北線は、難波で東に曲がった後、日本橋筋3丁目で再び南に折れて恵美須町に達します。1912(明治45)年には、第3期線として大江橋から北浜2丁目を経由して日本橋筋3丁目に至る堺筋線が開通しました。
堺筋の拡張と整備
大阪・神戸間の鉄道が開通した1874(明治7)年に梅田停車場(現在の大阪駅。レンガ仕立ての駅舎は「梅田ステンショ」と呼ばれた。)が設置されて以降、東西の「町通り」よりも交通量の増加が著しい「筋」方向の交通路の拡張・整備が必要になっていました。
道路拡張を伴う市電の敷設にあたっては、商売に差し支えるとして地元住民の猛反対にあい、堺筋線の敷設ルートも二転三転しました。将来の発展を説く声もあり、また明治末期の2度の大火災(1909(明治42)年7月の北の大火、1912(明治45)年1月の南の大火)で空き地の必要性を住民自身も痛感していたこともあって、堺筋線の敷設がようやく決定します。当時、堺筋に向かって、両側の商家の1階部分の軒は互いに半間ほど突き出しており、その軒下は荷造りや荷ほどきを行う作業空間となっていました。その軒がごっそりと削りとられた結果、堺筋は中央に市電の複線、その両側に車道が走る幅員およそ22メートルの大幹線に生まれ変わり、大阪で最初の街路樹(プラタナス)も植えられました。
大阪経済の大動脈となった堺筋に面する日本橋筋3丁目に松坂屋が1923(大正12)年から営業を開始しました。木造3階建ての仮建築の百貨店は、昭和に入って地上8階地下2階の鉄骨鉄筋コンクリート造に改築されました。
3.古書店街の形成
五階百貨店のにぎわいと古本商の開業
「ミナミの五階」と呼ばれる大阪名所となった「眺望閣」の周辺には、観光客相手に古着や古道具などを安値で売る露店ができ、これらの露店は当時流行語であった「百貨店」と組み合わせて五階百貨店と呼ばれました。「眺望閣」は1904 (明治37)年頃に取り壊されましたが露店は残り、木綿古着に加え舶来の洋服や装身具なども並びました。大正末年には古着商、古道具商、古金物商などおよそ100軒からなる中古品市場としてにぎわいました。早朝に立つ古物市には倒産品や中には盗難品もあって、警察の来ない未明に売り叩かれて大変繁昌したそうです。
交通の便が良く、古着を中心にあらゆる古物が揃う「掘り出し物のまち」日本橋には、懐具合の寂しい学生も多く出入りするようになりました。そこに目をつけたのが古本商です。
日本橋の古本屋の第1号とされる谷書店の創業者谷勘助は日本橋5丁目に住み、もともと左官業を営んでいました。夜間だけ店の前を古雑誌を売る露天商に場貸ししていたところ、その売れ行きがあまりにも良いので、1913(大正2)年になって自ら古本屋を開業することにしたといいます。
古書店の出店がその後も相次ぎますが、特に1923(大正12)年の関東大震災の後、はるばる東日本から古本を求めにやってくる顧客もあらわれるようになり、日本橋の古書店街の知名度は上がっていきました。
最盛期の昭和10年代には60軒以上の古本屋が店を構え、東京・神田と肩を並べる古書店街を形成し、日本橋筋界隈を歩いて目的の本を見つけることは、当時の人々の1つの楽しみでもありました。作家・織田作之助は私小説「木の都」のなかで、善書堂の書棚を漁って、国木田独歩や有島武郎などを読み耽ったために、危うく中学校へ入り損ねたと回顧しています。また古本を2、3冊持ち込んで映画代を稼ぎ、そのまま新世界へと下っていくという光景もみられたようで、古書店は小銭の融通機関としても便利だったそうです。
4.履物職人の町「御蔵跡(おくらと)町」
黒門市場の南側に位置する履物問屋街の街区は、かつては御蔵跡町と呼ばれました。文字通り、江戸時代に御蔵が建てられていた場所です。1740(元文5)年、高津入堀川の堀止めのところに銭座(鋳鉄座)がありました。銭座は、銅銭や鉄銭などの銭貨の鋳造場で、高津銭座と難波銭座の2つがありました。それが支配人たちの不正が発覚して廃止され、その跡地の西に1752(宝暦2)年、幕府は米蔵を設けました。幕府の天領からの年貢米などを納めたり、家臣からの俸禄米や飢饉のときの援助米を備蓄する倉庫です。「天王寺御蔵」と呼ばれたこの御蔵は、東西127メートル、南北163メートル、四周には高い堀を巡らしていました。ところが、この地は低湿地で米の貯蔵に適しなかったため、幕府は1791(寛政3)年、現在のなんばパークスの場所に難波御蔵を設け、天王寺御蔵は廃止されました。
御蔵跡一円は1869(明治2)年、大坂三郷の廃止に伴い南大組に属せられ、1873(明治6)年には東方の天王寺村入地を編入して新たに「御蔵跡町」となりましたが、その後、時を経て戦後の住居表示の実施によって「御蔵跡町」の地名はなくなりました。
大正から戦前にかけての御蔵跡町は、長屋の多い人口密集地という典型的な下町でした。戦後の区画整理がなるまでは、4メートル道路と言えば幹線であり、大部分は2メートル幅くらいの路地が縦横に巡らされて、その間を長屋が埋めていました。路地は袋小路になっていました。この路地と長屋という構成は、周辺の街区全体に当てはまる光景でした。
御蔵跡町の特徴は、履物工場の多い町であったことです。この町は高津入堀川に面しており、下駄の材料となる材木の運搬が便利だったため、大正末期ごろから下駄職人が多く住みつきました。ここでいう下駄職人とは、荒削りした下駄の材料を仕入れてそれを仕上げる職人のことで、彼らは毎月21日のお大師の市日にお大師売りを始めたところ、売れ行きが良かったので、小店で製造販売を行うようになりました。
かつて履物問屋街は本町4丁目から阿波座あたりにありましたが、昭和初期の御堂筋大拡張のため立ち退きを迫られ、折から履物職人が多かった御蔵跡町へと多くの履物卸商が移転してきたのです。生産と販売が結びついて御蔵跡町は繁栄し、全国有数の履物問屋街に発展します。日本橋筋から東へ2本目のこの通りは、当時の履物問屋街で「御蔵跡本通り」と呼ばれていました。
履物工場は典型的な家内工業でした。当時この付近の家屋は、一戸建て家屋も長屋も2階建てが多く、履物工場の家は1階が作業場で玄関先が店、2階が住居になっていました。2階には加工材の干し場があって、ゲタの素材を荒削りした鼻緒目のない下駄が円型に組まれ、高く積み上げられて干されていました。庭や店先に干している家もありました。御蔵跡町一帯には、この木材の円筒があちこちに見られ、円筒の中に入ってかくれんぼをしたり、崩したりする腕白坊主がしょっちゅう大人に叱られていました。職業柄、かんな屑が多く出るため、御蔵跡町は火災の多い町でもありました。ゲタ材を自然乾燥させたのは1950年代半ば(昭和30年頃)までで、それ以後は円筒を空高く積み上げる風物も見られなくなりました。

御蔵跡町の履物問屋街

御蔵跡履物街(浪速区制70周年記念「夢翔たく浪速のまち」より)
5.行政区域の変更と戦争の被害
日本橋地域の全域が大阪市に属することとなったのは、大阪市が1889(明治22)年4月に誕生し、第1次市域拡張が実施された1897(明治30)年4月のことで、大阪市南区の一部になりました。1900(明治33)年4月に町名の改称が行われ、それまでの字名から日本橋東、難波河原町などの新しい町名が生まれました。
1925(大正14)年4月、大阪市は13区制をとることとなり、第2次市域拡張が行われ、浪速区が南区より分区して誕生しましたが、「日本橋筋」と御蔵跡町は南区のままとされました。
1943(昭和18)年4月の大阪市行政区再編成で、区の境界は河川や運河、鉄道や軌道、都市計画道路等により決定することとなりました。これに伴い、「日本橋筋」と御蔵跡町は御蔵跡線の道路を区の境として、その南側を浪速区に、千日前などのエリアは新南区に帰属されました。
1945(昭和20)年3月の大阪大空襲では、日本橋一帯も大きな打撃を受けました。1872(明治5)年に「南区第二大区第十三番小学校」として創設された歴史ある日本橋国民学校(のちの日本橋小学校)も焼夷弾により校舎は延焼、講堂のほか一部の校舎が焼失し、わずかに松坂屋がその姿を残すのみとなり、日本橋古書店街や御蔵跡町の問屋街は壊滅的な被害を受けました。
6.戦後の復興とまちの変化
古書店街の復興
壊滅状態だった日本橋の復興を支えたのは五階百貨店の商人たちでした。彼らは中古の衣類、台所用品、大工道具に加え、鍋のふた、片方だけの靴、欠けた瀬戸物など、食料品以外のありとあらゆるものを戸板の上に並べて売りました。商人もたくましければ客もさるもので、買い物の際に値切るのは当然で、家庭での不用品はこれらの店に売りにやってきます。こうして日本橋は戦後の物資の供給地としてたちまち人の噂にのぼるところとなりました。
電気のアマチュアたちが集まるまち
五階百貨店をはじめとする日本橋筋界隈の露店のなかには、ラジオや無線機、真空管などの中古部品を扱う店もありました。戦時中に軍事用以外の電気製品の生産が完全にストップしたうえ、終戦を迎えてもメーカーは大きな被害を受けた工場設備の修復などで生産の見通しすら立たず、電気製品は世の中にはなかなか出回りませんでした。そこで中古の部品を買い集めて完成品を組み立てる「アマチュア」と呼ばれる人たちが日本橋付近に集まって活躍したのです。
日本橋にアマチュアが多かった背景には、戦中の松坂屋(現在の髙島屋東別館)店内に無線機製作部が開設されていたこととも関係があるといえるでしょう。戦時下で一般商品の販売もままならない中で無線機の組立工場となった松坂屋では、早川電気工業(現、株式会社シャープ)で技術研修を終えた大阪店の従業員が、多くのアマチュア達の指導にあたったのです。
日本橋電気街の形成
終戦直後の電気店では、電球やソケット、電線コードに加えて、ニクロム線を渦状に巻いた電熱器や、木箱の両端に銅板を張って電流を流して焼くパン焼き器もよく売れたといいます。
とりわけ政策の徹底のために情報伝達手段の整備を優先課題としていたGHQから生産指示を受けたラジオは重要な電気製品でした。ラジオを贅沢品とする戦前の物品税率が放置されていたため、完成品のラジオは当時の金額で1万5000円もしたそうですが、日本橋ではおよそ5000円で部品を買い揃えることができました。そのためアマチュアがラジオを組み立てて販売すれば1万円の儲けとなったわけです。ラジオ部品や電球の卸売りを行う「ラジオ屋」が、アマチュアが多く集まる日本橋で繁昌し、年々増えていったのは当然の成り行きでした。
終戦から2年も経つとようやくメーカーのラジオ生産も軌道にのり、生産台数も急増します。特に朝鮮戦争(1950年~53年)による特需景気で、良質で廉価な完成品が大量に出回るようになるとラジオ生産に携わるアマチュアも次第に影を潜めるようになりました。そのため日本橋で取り扱われる商品も、ラジオ部品に比してラジオ、アイロン、ミキサーなど完成品の割合が増えていきました。それにともなって卸売りが中心であった日本橋でも、一般の客の割合が増えていったのです。
まもなく真空管式からトランジスター式の小型で高性能のラジオが登場しました。こうして技術革新が進み、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など画期的な新製品が続々と誕生すると、日本橋はあらゆる家電が揃い、東京の秋葉原と肩を並べる電気街へ成長していきました。
一方、日本橋筋を行き来した市電が1966(昭和41)年に廃止され、さらに同年、庶民のデパートとして親しまれた松坂屋が天満橋に移転、1969(昭和44)年には地下鉄堺筋線が開通し、日本橋を取り巻く環境も変化を迎えることとなりました。
御蔵跡問屋街の盛衰
かつて本町4丁目から阿波座あたりに形成されていた大阪の履物問屋街は、御堂筋拡張のために立ち退きにあい、履物卸商が徐々に御蔵跡へと移転してきましたが、戦後は本格的に移転が進み、履物卸業界は御蔵跡地区が中心となって戦後の復興がなされていきました。
履物は暮らしの必需品ですので、桐下駄、雪駄などの需要によって、終戦直後から業界はスムーズに動き始め、朝鮮動乱で好景気にわいた1950(昭和25)年をピークに隆盛が続きました。1950年代半ば(昭和30年代)から、それまでの自然素材に代わってビニールが登場し、商品の主体もつっかけやサンダルへと変わりました。加えて、日本人のライフスタイルの洋風化が進み、業界は一時の勢いを失い、隆盛期には160社ほどあった御蔵跡地区の履物卸店は少しずつ減っていきました。
電気街のその後~「でんでんタウン」からオタクの聖地「日本橋」へ
戦後、電気街としてその確固たる地域を確立した日本橋は、1978(昭和53)年に「でんでんタウン」という愛称を採用し、電気の街としてさらに広く親しまれるようになりました。1990年代(平成の時代)に入ると、デジタル家電やパソコン、テレビゲームなどが次々と登場し、日本橋の市場環境も変化し始めました。特に1995(平成7)年のウィンドウズ95の登場は、パソコンブームの到来を予感させ、日本橋の客層はより専門性の高いものとなりました。一方で、電気街としての日本橋は価格競争が激しさを増し、家電量販店のさらなる大型化や郊外への出店加速、さらにネット通販の普及などで次第にその勢いを失っていきました。
専門性の高いパソコンやマルチメディア関連の店舗は急成長し、これに関連したゲームソフトやアニメ関連の店舗が数多く進出し始め、2000年代には今のオタクの街としての日本橋が形成されるようになりました。
平成の時代に電気街からオタクの街へと劇的な変化を遂げた日本橋ですが、ここ最近は、海外でも人気の高い日本のアニメやゲームなどのオタクコンテンツを求める海外からの観光客が増加、世界的にも日本橋の認知度は高くなりつつあり、オタロードと呼ばれる西側のエリアなどは新たなにぎわいを見せています。
また2005 (平成17)年から商店街活性化を目的に開催されている「日本橋ストリートフェスタ」は約13万人の来場者と300名のコスプレ参加者でスタートしましたが、その後、来場者25万人を数え、全国から1万人を超えるコスプレ参加者が訪れる国内最大規模のコスプレイベントに成長し、国内外で広く知られるようになりました。
コロナ期には中止を余儀なくされ、2024 (令和6)年に5年ぶりの開催となりましたが、総来場者数は21万人を記録し、国内最大規模のコスプレイベントの健在ぶりを示しました。
年表
- 明治 2年(1869年) 大坂三郷を廃止し、四大組に改める。「長町」と御蔵跡一円は南大組に帰属
- 明治 5年(1872年) 「長町」が「日本橋筋」に改称される。南区第二大区十三番小学校が開校(のちの日本橋小学校)
- 明治12年(1879年) 郡区町村編成法により、「日本橋筋」(旧の長町)と御蔵跡町は南区の一部となる
- 明治21年(1888年) 日本橋筋4丁目に眺望閣完成
- 明治22年(1889年) 大阪市制発足(東・西・南・北区)。「日本橋筋」と御蔵跡町は大阪市南区の一部となる
- 明治30年(1897年) 大阪市第1次市域拡張。日本橋地域全域が大阪市南区となる
- 明治31年(1898年) 高津入堀川・鼬(いたち)川連絡工事完成
- 明治41年(1908年) 市電南北線(梅田-恵美須町)開通
- 明治45年(1912年) 堺筋が拡張され、市電堺筋線(大江橋-北浜2丁目-日本橋筋3丁目) 開通
- 大正 3年(1914年) 大乗坊の毘沙門天王立像が国宝に指定(現在、国の重要文化財)
- 大正 7年(1918年) 御蔵跡公園開設
- 大正10年(1921年) 市立御蔵跡図書館開設
- 大正12年(1923年) 日本橋筋3丁目に松坂屋大阪店が開業
- 大正14年(1925年) 浪速区創設(「日本橋筋」と御蔵跡町は南区に帰属)
- 昭和 9年(1934年) 室戸台風襲来
- 昭和12年(1937年) 今の髙島屋東別館(旧松坂屋大阪店)が完成
- 昭和18年(1943年) 大阪市22区制により現浪速区となる(区域の変更により、日本橋地域全域が浪速区になる)
- 昭和20年(1945年) 爆撃により区域の約93パーセントが消失、住友金属工業が松坂屋の地下1、2階を航空機工場とする(同年8月まで)。終戦。枕崎台風襲来。東関谷町に五階百貨店再開。
- 昭和24年(1949年) 戦災復興土地区画整理事業の設計認可(東部工区)
- 昭和25年(1950年) ジェーン台風襲来
- 昭和32年(1957年) 高津入堀川埋立開始(~1964(昭和39)年に完了)。大阪市立日本橋小学校付属幼稚園を設置。
- 昭和36年(1961年) 第2室戸台風襲来
- 昭和41年(1966年) 市電南北線のうち日本橋筋3丁目-恵美須町間、市電堺筋線のうち北浜2丁目-日本橋筋3丁目間廃止
- 昭和41年(1966年) 松坂屋が天満橋に移転
- 昭和44年(1969年) 地下鉄堺筋線(天神橋筋6丁目-動物園前)開通
- 昭和53年(1978年) 電気街の愛称「でんでんタウン」が一般公募で選ばれる
- 平成 3年(1991年) 戦災復興土地区画整理事業が完了
- 平成 5年(1993年) 地下鉄堺筋線(動物園前-天下茶屋)開通
- 平成17年(2005年) 「日本橋ストリートフェスタ」を初開催
- 平成22年(2010年) 大阪市立日本橋小学校付属幼稚園が休園
- 平成29年(2017年) 日本橋小学校・恵美小学校・日東小学校を閉校し、浪速小学校開校。「日本橋小中一貫校」として小中一貫教育開始。
- 令和3年(2021年) 髙島屋東別館が国の重要文化財に指定
日本橋地域の史跡と名所
大乗坊と毘沙門天王立像(日本橋3丁目6番)
もとは、四天王寺の東北の方角にあった牛崎(筆ヶ崎)に位置し、天文(1532~1555年)・天正年間(1573~1592年)に織田信長の石山本願寺合戦の巻き添えで再三兵火に遭い、大乗坊の当時の住職秀言律師が本尊毘沙門天の仏頭を奉じて、難波村名呉街(現在の日本橋筋)に逃れて草庵を起こし、大乗坊のみ再興されました。
宝暦年間(1751~1764年)には信者の寄進による広大な寺域を持ち、以来「長町の毘沙門さん」として信仰されてきました。御前立の立像は肩に鬼の面が彫り込まれており鎌倉中期の作品と推定され、重要文化財の指定を受けています。また、本尊秘仏の「毘沙門天王立像」は、日本の四大毘沙門天王像の1つで、5月と11月の第2日曜日に御開帳されます。

大乗坊
髙島屋東別館(旧松坂屋)(日本橋3丁目5番)
髙島屋東別館は旧松坂屋大阪店として1937(昭和12)年に完成しました。地上7階建(一部8階)の建物は当時、周辺の民家や工場がせいぜい2階建ての中、ひときわ偉容を誇っていました。
外観はルネッサンス様式を基調にしたもので、1階の開口部の連続アーチにはテラコッタ (装飾焼物)を貼り付けてアーケードとし、アーケード内部は床と広いウィンドウともにアールデコ調の装飾がふんだんに使われています。また、7階には3連のアーチを連続で構え、1階のアーチとともに一層重厚な雰囲気を醸成しています。内部には大理石をふんだんに使った壁面、梁型、手すり、腰壁の見事な装飾がみられます。
設計は夏目漱石の義弟
鈴木禎次によるもので、外観・内装ともにアカンサス (キッネノマゴ科の大形多年草で古代ギリシア・ローマの建築ではこの葉を柱頭文様とした) をモチーフにしたアールデコ調の装飾が各所に見られ、鈴木禎二の傑作であるとともに全体の保存状態も良好で、日本に現存する百貨店建築の中で最も美しい建物であるといえます。
2021(令和3)年、国の重要文化財(建造物)に指定されました。
- 旧松坂屋大阪店(髙島屋東別館)
文化庁ホームページ「文化遺産オンライン」に遷移します
五階百貨店(日本橋4丁目14番)
日本橋五階百貨店は5階建てではないのに、「五階百貨店」であるという不思議な建物です。このように呼ばれるようになったのは、1888(明治21)年に「五階跳望閣」が日本橋筋4丁目に建設されたことがはじまりです。
この眺望閣は5階建てのパノラマ式高塔であり、第5回内国勧業博覧会の頃にはここを中心に見世物小屋がありました。当時は付近に建物もなく全市がよく見え、住吉の高灯籠も眺められて、人気があったということです。場内の売店には呉服・小間物・家具・書籍・文具・玩具・菓子類があり、ちょっとした百貨店でありました。
その後、眺望閣はなくなったものの、その跡地には露店が立ち並び五階百貨店と呼ばれました。
戦災を経て、呉服屋、金物屋、電気屋などいろいろな店が集まっていました。露店だったので毎朝晩、近所の倉庫から商品を荷車に積んで出し入れをしていたそうです。
現在「大阪名物 五階」と看板のある建物は、1946
(昭和21)年頃に建てられたもので、実際は3階建てです。かつて周辺の露店群を「五階百貨店」と称したように、今もこのエリアを表す「地域名」として残っています。

五階百貨店(2025年1月30日撮影)
日本橋でんでんタウン
電気街「でんでんタウン」は、なんさん通りから日本橋一帯にかけて、かつては数百店舗の電気店が軒を並べた大ショッピングエリアです。このエリアは、戦前は東京の神田と並ぶ有名な古書店街で実に60軒以上立ち並んでいました。しかし職災により甚大な被害を被り、戦後は日本の高度経済成長と共にラジオなどの電気器具店の集積する街へと変貌していきました。こうして日本橋電気街は東京の秋葉原と並ぶ電気街となり、激安価格からさらに値引きを迫る客と店員との交渉風景が見られるようになりました。
近年、日本橋電気街はサブカルチャーの発信拠点ともなり、毎年開催される日本橋ストリートフェスタではコスプレイヤーによるパレードが行われ、個性豊かなまちとして新たな発展を見せています。

でんでんタウン
御蔵跡履物問屋街(日本橋3丁目1番、5番、日本橋東1丁目1~3番)
多数の履物問屋が集まり下町情緒あふれるこの界隈は、「はきはきタウン」とよばれ、浅草の花川戸と肩を並べる履物問屋街でした。大正初期、北日東町方面には下駄の職人が多く、毎月21日のお大師の市日にお大師売りを始めたところ 割合に売れ行きがよかったので、その頃から小店で製造販売をするところが多くあり、発展したそうです。このように集中的に発展したのは御堂筋の履物問屋が道路の建設のため立ち退きとなり、今の地へ移転したことが大きな要素となっています。
日本橋東一丁目にある羽呉神社の隣には以前、履物会館がありました。今はマンションとなっていますが、その敷地は戦前、大江神社の御旅所で羽呉神社でした。戦災にあった大江神社は、社殿復興の資金づくりのためにこの地を売却することとなり、羽呉神社再興を条件に履物共同組合(はきはきタウン)が購入。組合はそこに大阪履物会館を建設し、南隣に羽呉神社を再建しました。神社は1740年(元文5)年以来、ここに鎮座しており、地域の住民や商人には親しみの深い神様でした。そこに商売繁盛を願って履物の神様を合祀することになり、全国初の履物神社が生まれたのです。境内は20坪弱と小さいですが、この神社は「羽呉神社」と「履物神社」の2つの名前を持っています。

羽呉神社(日本橋東1-1)

はきもの神社
高津入堀川
日本橋筋の隆盛に伴って長町から東、下寺町から西の土地に高津新地が建設され、その翌年の1734(享保19)年、長さ798メートル、幅16メートルの運河が開削されました。それが高津入堀川です。その後、1752(宝暦2)年、新地の南天王寺領に幕府が米蔵を設けた際、川の南端に東西29メートル、南北36メートルの船入堀を穿ち、運河とつながることとなりました。しかし、道頓堀川とつながるだけでは水運の便からも、流水の上からもしばしば停水して衛生の害もあったことから、1896(明治29)年に鼬(いたち)川と連絡することとなり、2年後の1898(明治31)年に工事が完成、最終的にその長さは2730メートルに及びました。その後、難波新川とも連絡することとなりました。
戦前、高津入堀川の川沿いの一部には、川の両側に貯木業者が並んでいました。いわゆる「木場」で、そこには多くの筏が組まれていて、半纏姿の職人が立ち働く姿を見ることができました。子どもたちにとっても筏遊びのできる絶好の場所でした。川の水も澄み、1940(昭和15)年頃までは魚釣りができ、夏の暮れなどは近所の人々が縁台を出して夕涼みをとったそうです。
戦後は戦災による焼土の捨て場となり、船出橋・南日東間が1957(昭和32)年から1958(昭和33)年にかけて、南日東・堀切橋間が1958(昭和33)年から1964(昭和39)年にかけて、堀切橋から道頓堀川合流点が1958(昭和33)年から1962(昭和37)年にかけて埋め立てられました。
参考資料
- 浪速区・まちの歴史
- 浪速区史
- 懐かしの風景画
- えいわ歴史ものしり展「日本橋往来」かわら版90(永和信用金庫)
- でんきのまち「大阪日本橋物語」(でんでんタウン協栄会)
- 創立30周年記念誌「日本橋」(大阪市立日本橋中学校)
- 閉校記念誌「日本橋」(大阪市立日本橋小学校)
- Nippombashi History(日本橋筋商店街振興組合 でんでんタウン オタロード(日本橋筋西通商店会)オフィシャルウェブサイト)
- 大阪市立図書館ホームページ、浪速区ホームページ、中央区ホームページ など
(注)この記事は地域の語り部の方々の発言をもとに作成しております。歴史考証はしておりませんので、予めご了承ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9683
ファックス:06-6633-8270