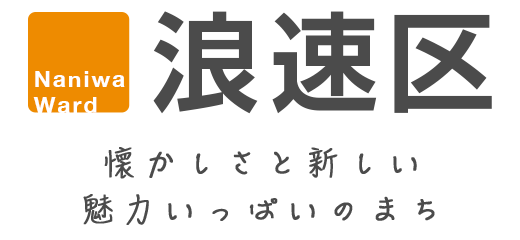浪速区制100周年プレ企画 ルックバック浪速区(第1回大国地域)
2025年3月1日
ページ番号:626208
座談会
地域の皆さんにお話を伺いました

【参加者】(左から)杉本正隆さん、大西 𠀋さん、中田 百合子さん、川口 和子さん、寺田 守さん、谷口 好子さん、川口 幸信さん、宮本 かおりさん、幡多区長、林 嘉代子さん、瀬川 節子さん、冨岡 朋治さん、寺田 日登美さん、園田 明雄さん
賑やかだった戦前の大国地域
区長
まずは戦前の大国地域について教えてください。資料によると、この地域に1903(明治36)年に私立の成器商業学校が開設され、1919(大正8)年には裁判所や共同宿泊所、簡易食堂、職業紹介所、児童相談所ができたとあります。
冨岡さん
小さい頃、成器商業高校(現 大阪学芸高等学校)があったことは覚えています。現在の今宮高校の南東にあり、相撲が強くて、全国大会にも出ていました。
また、その近くに保健所がありました。噴水がある洋風の建物でした。当時は役所ものんびりしていて、子どもの頃はよく遊びに行き、脚気(かっけ)を調べる道具を持ち出してあちこち叩きまわっては叱られていました。
以前は現在の戎公園の南側に法務局があり、司法書士の事務所もたくさん集まっていました。
川口(幸)さん
戦前は、大国交差点のところに映画館があったと聞いたことがあります。
区長
そのあたりでは月に2回夜店が開かれていて、多くの方が楽しみにされていたようですね。
区を襲った大空襲と大型台風
区長
大阪市は1945(昭和20)年3月の空襲で大きな被害を受け、浪速区では区域の約93%が焼けてしまいました。
寺田(守)さん
戦時中はどの家も防火用水を貯めていました。大空襲の夜、火を避けるために家から持ち出した布団を行く先々の防火用水に浸し、頭からかぶって必死で逃げたのを覚えています。地下鉄大国町駅まで逃げて、空襲が止むまで駅の中にいました。後で知りましたが、当時は空襲があっても駅の中に人を入れないことになっていましたが、駅員さんがみんなを気の毒に思い、特別に開放してくれたそうです。
川口(幸)さん
大国地域で焼け残ったのは大国小学校と、わずかなビルくらいではないでしょうか。
宮本さん
1回の空襲で焼けたのではないらしいですね。
寺田(守)さん
このあたりは空襲が4回ほどあって、それで焼け尽くされたのだと思います。
区長
戦争が終わってほっとしたのもつかの間、1950(昭和25)年にはジェーン台風がやってきたそうですね。
冨岡さん
あの台風は本当に風が強くて、父親が床からはがした畳を窓のガラス戸に中から立てかけて、強く押さえつけていたのを覚えています。
川口(幸)さん
当時はバラックの家が多く、風でトタン屋根がたくさん飛んでいきました。
大西さん
1961(昭和36)年の第2室戸台風の時は、家族で大国小学校に避難したのを覚えています。
宮本さん
当時、私の家は「勘助湯」という風呂屋を営んでいました。台風で停電になると、向かいにあったたばこ屋からリール線を引っ張って、裸電球をつけてもらいました。風呂場は真っ暗なので、あちこちにたくさんロウソクを立てていました。
区画整理と町名の移り変わり
区長
戦後、大阪市は市民の皆さんと土地区画整理事業にとりかかりました。
寺田(守)さん
大国地域の区画整理は、浪速区の中でも、事業の完了が早かったと思います。
宮本さん
昔この地域は準工業地域で、印刷工場や運送会社、自動車の整備工場、木工所などもたくさんありました。大国地域の道路の道幅が他の地域より広いのは、そのためではないかと思います。
区長
区画整理で大国地域にも公園ができましたね。
宮本さん
大国町南公園は以前、道路や信号機が設置された交通公園でした。年に1回、小学校の授業で訪れて交通ルールの勉強をしました。大国小学校が建替えられた頃まであったと思います。ほかの学校の児童も授業で来ていました。
なにわ児童交通公園
児童が遊びながら交通ルールを学べるように作られた、市内初の施設。1966(昭和41)年に落成式が行われました。市街地に見立てた公園内には車道や歩道が敷かれ、交差点には本物の信号機や横断歩道も設置。レールを敷いた本物そっくりの踏切もありました。
寺田(守)さん
大国小学校にはお宝があります。「知行竝進」と書かれた書画で、その為書きにあの有名な犬養毅の署名が記されています。この地域の有力者が上京した際、頼んで書いてもらったのではないかと思います。

写真提供:川口 幸信さん
区長
さきほど「勘助湯」のお話が出ましたが、かつてあった「勘助町」という町名は、浪速区ゆかりの木津勘助さんにちなんでつけられたのでしょうか。
寺田(守)さん
市電やバスの停留所にも「勘助町」という名前がついていました。今でも「勘助屋商店」という靴屋さんが残っています。
園田さん
「勘助音頭」という曲もあって、地域の地蔵盆や願泉寺の幼稚園の盆踊りでよく踊っていました。作曲があの服部 良一というのがすごいですよね。
区長
服部 良一作曲なんですか!?一度みんなで聞き直してみたいですね。
中田さん
昭和40年前後には、「勘助湯」のほかにも「大国湯」「宮津湯」など銭湯がたくさんありました。
冨岡さん
大国地域には以前、「宮津町」「貝柄(かいがら)町」(現 戎本町2丁目あたり)という町名もありました。
昔このあたりは海が近かったので、それにちなんだ名前だと思います。「今宮戎神社」も、海から戎さんが上がってきて神社になったと言われています
区長
ところで、大国地域の名所・史跡というとやはり願泉寺でしょうか。
園田さん
願泉寺は、小野妹子の八男が創建したと伝わる由緒ある寺です。戦災で失われてしまいましたが、昔は伊達政宗が寄進した書院や茶室などがありました。願泉寺はかつて幼稚園も経営していて、私もそこに通っていました。
杉本さん
私も卒業生の一人です。オルガンやピアノに合わせて歌ったり、朝礼では「仏様の歌」を歌いました。花まつりや豆まきの行事も楽しかったですね。寺にはプールもありました。
また、地域住民が誰でも参加できる運動会も行われていました。
区長
その当時は皆さん、どのような場所で買い物をされていたのですか。市場はあったのでしょうか。
寺田(日)さん
今のなにわ生野病院の場所に私設の市場があったほか、近所になんでも置いている八百屋さんがありました。
川口(和)さん
移動販売の車もよく来ていました。
かつては皮革問屋街~「大国に行けば何でも揃う」~皮革産業のメッカ
区長
話は変わりますが、大国地域は以前、皮革産業が盛んなまちだったんですね。
大西さん
革製品は手袋などの袋もの、グローブなどの運動具、靴の種類に分けられ、大国地域にはこういった革を扱う問屋が多くありました。当時はいろんな動物の革を扱っていました。
谷口さん
私は1963(昭和38)年に、この地域でライオン靴クリームの製造工場を経営する家に嫁いできました。当時は集団就職が盛んだったので、うちにも20人近くが住み込みで働いていましたね。みんな働きながら、今宮高校の夜間学校に通っていました。
寺田(守)さん
革の加工や製造、小売りだけでなく、革に関連する工場や店がこのまちにはたくさんありました。1955(昭和30)年~1985(昭和60)年頃まで皮革産業が活況だったと思います。
林さん
嫁いできた頃、地下鉄大国町の駅から外に出ると、革の強烈なにおいが漂っていたことを覚えています。
寺田(日)さん
当時は景気が良かったので、喫茶店や寿司店もたくさんありました。
区長
でも、今では「革のまち」というイメージはありませんね。
大西さん
戦前は履物といえば下駄や草履でしたが、戦後は革靴が主流になり、このまちも大いに繁栄しました。当時は靴底も革でしたが、徐々に合成ゴムやスポンジが使われるようになりましたね。
杉本さん
私の家も靴底のスポンジを扱っていました。住居の1階が作業場で、中学生のころから家の仕事を手伝っていました。大国地域の靴や皮革関連の仕事をしているところの多くは同じような造りでした。
家ではプレスに靴底の金型(ヒールやソール)をのせて、材料のハードスポンジ(ソフトスポンジの場合もある)を抜く。できた靴底原料を自転車に載せて鶴見橋などの靴材料を販売している店に配達しました。作業場には1メートル四方の原板が何百枚も積み上げられていて、注文に応じて型抜きをして配達していました。
川口(幸)さん
韓国や中国で安く作られた製品が大量に入ってきて、このまちの皮革産業は衰退してしまいました。
住民の力で違法風俗店を追放
区長
この地域は交通が便利なので、バブル期にワンルームマンションが多数建設されました。でも、バブルが崩壊し空き部屋が増えて、それを悪用した違法風俗店が乱立したのですね。
寺田(守)さん
そのことが全国に紹介され、全国から人が来るようになりました。大国地域は風俗のまちとして有名になり、ピークのときは違法風俗店は190店舗を超えていました。子どもたちの健全育成にも影響がありますし、違法駐車も大きな問題でした。
瀬川さん
よそに行くと「おばちゃん、大国町に住んでるんでしょう?大国は『風俗のまち』なの?」とよく聞かれたりしました。
区長
大変な状況だったのですね。
寺田(守)さん
そこで住民が団結し、警察と連携して、(平成)年から違法店舗の撲滅運動を本格的に開始しました。月に一度、住民パレード(大国パレード)を行ったり、店舗に抗議に行ったり、違法駐車を通報するなどの対策を徹底的に行いました。
区長
その後も新型コロナが拡大するまでは、大国パレードを続けておられたと伺っています。
寺田(守)さん
半年ほどで違法風俗店も迷惑駐車も追放したので解散を提案しましたが、当時の警察署長が「今、解散すると彼らは知恵をつけて戻ってくる。そうしたら今度は手に負えなくなる」と言われ、その一言が20年続ける結果となりました。
区長
これからも住民の皆さんで力をあわせて、「安全安心な大国地域」を創っていっていただきたいと思います。本日はありがとうございました!
大国地域の歴史
海に近かった昔の大国
大国の町は、昔から「木津」と呼ばれてきました。今も「木津中学校」や「木津卸売市場」にその名を残しています。「木津」という名が、どのようにしてついたかは定かではありませんが、この地が海に近く、材木を集積する津(港)があったことから「木津」となったと考えられます。この辺り一帯が海に近かったことは、現在では使われなくなった「宮津」「貝柄(がら)」「高岸」などの地名からも伺われます。また、風光明媚なところであったことが、万葉集をはじめ、新古今集、千歳集などに歌われています。
- 「舟なから 今宵ばかりは 旅寝せむ 敷津の浦に 夢はさむとも」
- 「名呉の浦(注)の 朝けのなごリ 今日もかも 磯の浦わに 乱れてあらん」
- 「月出てて 今こそかえれ 名古の江に タベ忘るる あまの釣り舟」
(注)名呉の浦(名古の江)日本橋の南辺りから、住吉の辺りまでの海岸の総称
大国の地名が初めて文献に登場するのは鎌倉時代の頃で、「西林寺文永注記の天平年帳」に僧行会の出自を「摂津国住吉郡大国里戸主津」と記されています。
当時の木津川は、今より川幅が広かったため、大国の地を含む木津川沿岸一帯は、戦略の要地とされていました。特に、戦乱の絶えなかった足利・織田・豊臣の3時代には、この地が、応仁の乱や石山本願寺攻め、大阪夏の陣※の時には戦場になったことが「信長公記」に記されています。
江戸時代の大国は畑作が盛ん
江戸時代の大阪の中心は、現在の中央区・北区・西区辺りでした。大坂三郷と言われ、天下の台所、日本の経済の中心地として大いに栄えていました。その三郷と道頓堀川を隔てて難波村があり、木津村はそのさらに南に位置していました。木津村の西には渡辺村、東の方には今宮村がありました。
木津村は、米作よりは専ら畑作中心で、近隣か村木津・難波・今宮・西高津・勝間(後の玉出)・中在家・今在家(後の粉浜村)・吉右衛門肝煎地(後の清堀村)を総称して、「畑場八箇村」と呼ばれていました。
木津村の名産品は何といっても干瓢(かんぴょう)で、この地は「タ顔の里」とも呼ばれていて、古い里の謡や古歌も残されています。
- 「嫁にやるまい 木津今営へ 夜さり千瓢の 皮むかす」
- 「神のなす 瓜なればこそ 白ゆふに 宿も賑はふ タ顔の里」
また、1853年の「大阪産物名物大略」によると、木津村の名産として、干瓢の他にも、木津川シジミ、木津冬瓜が記されています。
大国の農民たちを救った篠山代官
江戸時代、干瓢をはじめ、とれた作物は生産者が荷車・舟・天秤棒等を使って天満の市場へ搬入し、そこで問屋や仲買人によって市中の小売商に売りさばかれていました。すぐ近くの道頓堀川をへだてたところに大消費地があるのに、遠い天満の市場まで時間と労力をかけて運ぶのは誰の目から見ても不合理でした。直接近くで販売したほうが便利で有利なことははっきりしていました。
しかし、当時は青物類については、天満市場が独占して取り扱う特権を幕府から与えられており、生産者による直売などは厳しく禁じられていました。
しかし、農民たちは苦情のでるたびに場所を変えながら密かに売買を続け、時には代表者が、またある時は当事者が罰金刑や体罰の刑等を受けながらも、大阪の南部地区に市場の開設を許可するよう、たびたび大阪町奉行所に請願書を提出し続けました。記録に残っているだけでも実に95年間にわたり運動を続けました。 文化の初年( 1804年)、篠山十兵衛が代官として赴任してきました。彼は支配地農民の窮状を見るにしのびず、町奉行や天満市場の問屋仲間等、各方面に働きかけて斡旋努力し、遂に文化6年( 1809年) 6月に条件付きで農民の市場営業の許可を天満市場の問屋仲間に承認させ、町奉行が相方立ち会いの上で認可をしました。
農民は大変喜び、篠山代官への感謝の気持ちを表すべく、彼の没後、神として八坂神社にまつり、現在も同社の一隅で我々を見守っています。
にぎやかだった戦前の大国
大国の町は関西線今宮駅、地下鉄大国町駅、そして市電や市バス等が相次いで開業し、市内でも有数の交通至便の地となりました。また、工業都市である堺に通ずる沿道でもあり、人口はだんだんと増え、民家が所狭しと立ち並ぶようになりました。
町中は道路が極めて狭く中小の店舗が両側にぎっしりと並んでおり、中でも食料品店が多くありました。しかし、路地を一歩中に入ると昔の農家の姿が偲ばれるような門構えの大きな家もあり、表通りの近代と裏通りの昔が混在する町でした。
大国小学校の前の道は大国神社まで通じていて「宮筋」と呼ばれ、商店街を形作っており、そこには以下のような店がありました。
下駄・建具・文具・豆腐・時計・畳・菓子・薬・神具・仏壇・喫茶・魚・肉・衣料
写真館・餅・うどん・洋食・居酒屋・玩具・医院 等
人々の生活に欠かせない店ばかりで、大国の町の賑やかさが想像できます。
また、人々の楽しみとしては、大国町交差点の南東角のところに映画館 (キネマパレス)がありました。当時の花形スターである林長次郎や坂東妻三郎などが来ては実演を披露して、人々の喝采を浴びていました。
他にも夜店が2つありました。法華の夜店、6.6の夜店と呼ばれ、それぞれ10と6のつく日に開かれていました。娯楽の少ない時代だったので、人々にとって10と6のつく日は待ち遠しく、その日がくるとタ方には浴衣を着て、家族揃って出かけていきました。
焼け野原から戦後復興へ
大国の町は空襲によって全くの焦土と化しました。戦後、猛烈なインフレーションや深刻な食料不足、雨露をしのぐ家がない状態に人々は憂いの気持ちでいっぱいでした。
そのような困難な中で、浪速区ではいち早く戦災復興土地区画整理事業に着手ました。事業は5つの工区に分けて進められることなり、大国は「大国町南部工区」として昭和24年に事業計画が認可され、浪速区ではもっとも早く昭和35年に完成しました。それまでは狭い道路ばかりで緊急用の車輌も入りにくかったのですが、広い道路がつくられました。また、以前には1カ所もなかった公園が3カ所も設けられ、人々の憩いの場として、また緊急避難の場所として整備されました。
戦後、皮革間屋街として大きく栄えた大国のまち
戦災復興土地区画整理事業が進むとともに人々も住みなれた土地へと戻り、バラックを建て、もとのような生活が始まりました。大国の町は交通の便がよかったので、ささやかな商売が営み始められたり、他の地域からも多くの人が移ってきたりしました。
特に西成・西浜方面から皮革関係の人が多く新天地を求めて移転してきました、そのため、大国の町は急速に変貌をとげ、皮革産業の一大問屋街を形成するまでになりました。
中でも多かったのは原材料屋で、靴をはじめ手袋・バッグ・スポーツ用品などの皮を扱う間屋が軒を並べるようになりました。
この頃、靴は一つずつ手縫いで、客の注文に応じて作られていました。大阪市内では「たばこ屋のあるところ靴屋がある」と言われていたほど零細な店(主として注文を受けたり修理をしたりしていた)がいたるところにありました。その店の人々が皮や付属物を求めて大国にやってきました。「大国に行ったら何でも揃う」と業者の人々に重宝がられ、大国の町の存在は全国に知られるようになりました。また、月に1回、靴・手袋・バックなどの組合が競売をし、それの買いつけに多くの業者が訪れ、活況を呈していました。町中には皮革産業に関係した家が多く、人々は「大国」を「皮革産業のメッカ」と呼ぶまでになっていました。特に教宗寺前の道は大きな店が軒を連ねていたため通称「皮革通り」と呼ばれていました。町中には皮革専門のトラックが走り回り、毎日、皮や材料を積んでは主として近畿地方の各地を行き来していました。
このようにして同業者が多くなってくるのにあわせて、革の販売業者が集まって大阪革商協会を設立しました。主だった業者だけで100社くらいが加盟をしていました。そのうちの80%以上が大国の業者でした。この他、製品の問屋や加工業者をいれると、町には200社ぐらいがあったと推測されます。このように発展してくると、同業者同士で、会合をしたり製品の展示会や集会をしたりする場所が必要となってきます。同業者に出資を求めて1963(昭和38)年には念願の大阪皮革会館が建設されました。
「勘助音頭」を知っていますか?
昭和30年代には全国的に盆踊りが盛んに行われ、大国の町も同じでした。当時は娯楽が少なかったので、人々は夜のくるのを待ちわびては遅くまで踊っていました。河内音頭・江州音頭・炭坑節などの歌に合わせて踊りましたが、その中に郷土の生んだ偉人である木津勘助にちなんだ「勘助音頭」がありました。
木津勘助は町名にもその名を残す(木津勘助町、昭和35年に廃止)、町にとって大変馴染みのある人でした。その業績を称えようと1981(大正11)年 2月26日に大国神社にその銅像が建てられました。
しかし、第2次世界大戦に際して国の金属回収政策に協力し、1943(昭和18)年、銅像は供出されました。戦後、町の人々は何とか再建したいものと「木津勘助翁彰徳会」を結成しその熱意が実り、1954(昭和29)年 10月26日に、再建された銅像の除幕式が行われました。その折りにお祝いとして「勘助音頭」が制作されました。
「勧助音頭」は人々に愛され、盆踊りは言うまでもなく、大国小学校や木津幼稚園の運動会でもプログラムに取り入れられ、大いに踊りの輪が広まりました。
勘助音頭 作詞 木津勘助翁彰彰会、作曲 服部良一、振付 花柳有洸
1 見えた見えたよ 水やろ舟が(ア.サッサ) あれは勘助さんの あれは勘助さんの 慈悲の水 木津の勘助さんは よいお方 そやそやそやないか サッサ
2 忘れしやすんな 勘助島は(ア.サッサ) 木津川開いて 木津川開いて出来た島 木津の勘助さんは よいお方 そやそやそやないか サッサ
3 人の為なら お上の米も わけてやろうと わけてやろうと 蔵破り 木津の勘助さんは よいお方 そやそやそやないか サッサ
4 敷津大国 学校の栄え 基は勘助さんの 基は勘助さんの寄付の土地 木津の勘助さんは よいお方 そやそやそやないか サッサ
5 淇速名所は 大国神社 出来た勘助さんの 出来た勘助さんの 晴れ姿 木津の勘助さんは よいお方 そやそやそやないか サッサ
皮革産業のその後
皮革産業はその後益々発展を遂げ、昭和の30年から40年代にかけて最盛期をむかえました。町には大小さまざまな業種が軒を並べ、活況を呈していました。全国の皮革業のメッカとしてゆるぎない地位を誇っていました。
しかし、時を同じくして時代の流れは大きな変化をとげていきました。日本は高度経済成長期から大量生産・大量消費の時代に入っていきました。
皮革産業も同じでした。今まで靴の底は手縫いでしたが、外国よりセメント(合成コム)がもたらされ縫わずに圧着するようになり、靴を量産できるようになりました。靴の需要の高まりとともに大量生産のできる工場も現れました。また、高度経済成長とともに、人々の生活水準はどんどん上がっていきました。給与水準も高くなり、会社は人件費の負担に耐えられなくなり、生産拠点を人件費の安い外国に移すようになりました。靴は外国で大量に生産され、安く売られるようになりました。そうして、大国の皮革産業の数は減っていきました。
住民パワーで違法風俗店を撃退した「環境浄化運動」
その後大国の町は、難波から近いという好立地を生かしワンルームマンションが多く建てられました。バブル期にはどこも満室となり、活況を呈していましたが、バブルの崩壊とともに空き室が多く発生しました。そこへ進出してきたのが違法性風俗店でした。数年のうちに百数十店が営業している状態となりました。
人々はこの状態を憂え、浪速警察署と相談し、共に風俗店の一掃をめざしてたちあがりました。平成12年(2000年)、浪速署に「大国地区環境クリーン総合対策本部」が設置され一掃作戦がスタートしました。その後以下の取り組みを住民と警察とがスクラムを組んで精力的に進めていきました。
- 2000(平成12)年 9月27日 浪速署に「大国地区環境クリーン総合対策本部」設置
- 2000(平成12)年 10月18日 大国地区風俗環境浄化浪速区民総決起大会・反対パレード
- 2001(平成13)年 2月26日 大国地区安全・安心まちづくりの会発会式
- 2001(平成13)年 4月1日 大国地区少年を守る環境浄化推進協議会発足式
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、2019(令和元)年 12月24日の第190回のパレードを最後に休止し、コロナ明けの2023 (令和5)年 11月21日、最後のパレード(第191回)を実施し、環境浄化運動の幕を閉じました。
(注)「大阪市立大国小学校創立百周年記念誌」を加工、加筆し掲載しています。
年表
- 明治初年(1868年) 木津村
- 明治5年(1872年) 西成郡第1区7番組・8番組
- 明治18年(1885年) 阪堺鉄道開通(難波―大和川)関西初の私鉄電車の開業となる
- 明治22年(1889年) 大阪市が誕生。西成郡木津村となる。大阪鉄道開通(湊町―柏原間)
- 明治23年(1890年) 大阪鉄道今宮駅(現在のJR今宮駅)開業
- 明治29年(1896年) 阪堺鉄道が南海電鉄株式会社と改める。
- 明治30年(1897年) 木津村が大阪市に編入され南区となる
- 明治33年(1900年) 町名の改革が行われ、大阪市南区大国町,鴎町,勘助町,宮津町,貝柄町などと呼ばれるようになる。大国という名前が町の名前に初めて使われた。
- 明治36年(1903年) 私立成器商業学校が貝柄町に開校
- 明治37年(1904年) 「木津第2尋常高等小学校(現大国小)」開校 。今の敷津小学校より分設、児童数650名で開校する
- 明治39年(1906年) 府立今宮中学校が宮津町に開校
- 明治40年(1907年) 鉄道国有法が公布され、大阪鉄道が国鉄となる
- 大正4年(1915年) 大阪市電西道頓堀・天王寺線が通る。桜川―芦原橋―大国町―恵美須町―天王寺西門
- 大正5年(1916年) 大阪市電難波・木津線が通る。賑橋―八阪神社前―大国町
- 大正8年(1919年) 今宮区裁判所が貝柄町にできる。市立今宮共同宿泊所・簡易食堂が宮津町にできる。市立今宮職業紹介所が宮津町にできる。市立児童相談所が宮津町にできる。木津公設市場が大国町3丁目にできる。
- 大正11年(1922年) 「大国尋常高等小学校」と改称
- 大正13年(1924年) 市立今宮乳児院が宮津町にできる
- 大正14年(1925年) 第2次大阪市域拡張、第1次浪速区ができる(人口149,890人)
- 昭和2年(1927年) 大国町に市バスが通る。桜橋一堂島大橋―桜川2丁目―大国町一阿倍野橋
- 昭和3年(1928年) 勘助町一天下茶屋に市バスが通る(勝間街道を走る) 今宮駅―浪速駅(臨港線)開通(貨車専用線)
- 昭和5年(1930年) 大国町3丁目(現大国町交差点)―関西線までの区間、幅員27mの幅広い舗装道路ができる
- 昭和13年(1938年) 地下鉄難波―天王寺間開通
- 昭和13年(1938年) 南海線難波―天下茶屋間の高架工事完成
- 昭和16年(1941年) 「大阪市立大国国民学校」と改称
- 昭和17年(1942年) 地下鉄大国町一花園間開通
- 昭和18年(1943年) 大阪市15区から22区制を採用、現在の浪速区が誕生した。
- 昭和19年(1944年) 浪速保健所が宮津町に移転
- 昭和20年(1945年) B 29約90機が大阪地区を空襲する。浪速区は区域の93 %が焼失する。
終戦
- 昭和21年(1946年) 敷津校統合
- 昭和23年(1948年) 「大阪市立大国小学校」と改称
- 昭和24年(1949年) 戦災復興土地区画整理事業に着手
- 昭和28年(1953年) 敷津小学校の復旧再開に伴い、校区を変更
- 昭和38年(1963年) 大阪皮革会館が建設
- 昭和30年(1955年) 大国町5丁目(現在の1丁目)に大国市場がオープン
- 昭和56年(1981年) 大阪皮革産業会館(通称「アルフィック」)を建設
- 平成9年(1997年) 今宮駅に環状線が停車するようになった
- 平成12年(2000年) 浪速署に「大国地区環境クリーン総合対策本部」設置 、 大国地区風俗環境浄化浪速区民総決起大会・反対パレード
- 平成13年(2001年) 大国地区安全・安心まちづくりの会発会式、大国地区少年を守る環境浄化推進協議会発足式 、 大国地区環境浄化運動1周年記念集会
- 平成15年(2003年) 大国地区環境浄化運動3周年記念集会
- 令和元年(2019年) 新型コロナウィルス感染症拡大により、パレードを休止。
- 令和5年(2023年) 最後の大国パレード(第191回)を実施し、解散。
(注)この年表は「大阪市立大国小学校創立百周年記念誌」を加工・加筆したものです。
大国地域の史跡と名所
願泉寺 (大国2丁目2番)

- 開祖は、小野妹子の八男多嘉麿義持(たかまろよしもち、)で永證という。推古11年(603年)、聖徳太子から「無量寿院」と名付けられた堂舎の別当職に任ぜられた。当時の堂舎は現在地より数百メートル西北にあった。
- 堂舎は応仁の乱により焼失し、永正4年( 1507年) 3月に現在地に移り堂舎を再建した。31代住職の定龍は武勇に秀で、織田信長との戦いの功により慶長2年( 1597年)、石山本願寺の願の一字を賜り、「日下山願泉寺」と称するようになった。
- 定龍は、伊達政宗と茶道を通じて親交があった。その縁で政宗が奧州に帰る時、客殿と茶室を定龍に贈った。その後、寛永2年(1625年)正月の大火により、本堂、庫裡などを焼失したが、客殿と茶室は難を免れ、昭和12年(1937年) 7月国宝に指定され、庭園も同年に大阪府の名勝指定を受けた。
- 昭和20年( 1945年) 3月の大阪大空襲で客殿と茶室は惜しくも消失し、庭園のみ旧態を残して現在に至っている。現在の庭園は、寛永の火災の後、江戸時代の正徳の頃(1710年代)に京都の庭師であった正阿弥によって整えられたが、室町時代の絵師の相阿弥の構想に由縁があるとの伝承もある。昭和46年に大阪府名勝庭園に再指定された。
- また徳川末期より代々の住職は天王寺雅楽をたしなみ、布教伝道のかたわら雅楽・舞楽の伝承に励んでいた。特に41代経龍は、徳川末期より途絶えていた天王寺舞楽の復旧に努め、明治17年 (1884年)同志を集めて「雅亮会(がりょうかい)」を設立した。以来百数十年、今も本部を願泉寺におき、「雅亮会」はわが国雅楽界の雄として活躍している。
- 34代観龍は、縁戚であった紀伊藩士堀田家から寺に入りました。その関係から、紀伊徳川家の参勤交代の途上では必ず当寺が陣屋にあてられ、後に徳川家より「三ツ葉葵」の寺紋を許されることになりました。また慶応2年(1866)の長州征伐の際には、紀伊候は当寺から出陣されました。
- 願泉寺には、蓮如筆の墨書・草書体で記された六字名号(「紙本墨書六字名号」)が伝わっており、平成11年(1999年)度、大阪市有形文化財に指定されました。願泉寺に伝来する六字名号は、名号に加えて『教行信証』の一節と和歌、さらに蓮如の花押が記されており、蓮如筆であることが確実であり、多数存在する蓮如筆と伝えられるこの種の六字名号を考察するうえでの基準作となるもので、その学術的な価値は極めて高いと言われている。
木津勘助

江戸時代、水利や利水、新田開発・開墾などにみずからの身代や命をなげうって、窮民を救うために立ち上がった人々がいました。その行動は地域の人々に深い感銘と感謝の念を抱かせ、人々の心の奥にいつまでも残り、子々孫々語り継がれています。世にいう義民です。佐倉惣五郎が全国的に有名ですが、我が木津勘助もその一人です。その遺徳をしのび大国神社に銅像があり、また昭和55年( 1980年)まで大国には勘助町という町名がありました。
そもそも木津勘助というのは通名で、本名は中村勘助義久と言います。天正14年(1586年)相州(今の神奈川県)に生まれました。慶長15年( 1610年)頃から木津村に住み、豊臣氏に仕え「川掛役」として木津川口の人り船管理を行っていました。現在の大正区三軒家東地域に勘助島を作り、木津川口を軍港・商港として開発しました。その後も港の機能を拡大させるため、寛永7年(1630年)には木津川の流路を広げ、土砂をとって水深を深くする工事を行い航路の安全を整備しました。このことにより勘助は徳川幕府から五合舟の権利を与えられました。これは、他国の舟が入港する時に白米5合(約 750g)を徴収する権利で、勘助が木津川口の港湾関係で有力な人物であったことがうかがえます。
寛永16年( 1639年)から19年にかけて全国的に飢饉にみまわれました。人々は食べるものもなく餓死者も多数にのぼりました。勘助は私財を投じて村人に分けましたが効果なく、人々の惨状を見るに見かねて大坂城内の米蔵へ行き、貧民の先頭にたって蔵破りを行い、その罪で葦島(大正区三軒家付近)に流されました。
この件に関して、新野嘉雄著「木津勘助考」に次のように記しています。「古文書の中から寛永16年の日付けの米の配給指令書のようなものがでてきた。数通あって何町へ何俵と言った割当表のようなものまであり、莫大な数量でこれはお蔵破り当日の当局の指図書であることに意見が一致した。なるほどいかに勘助翁が強大であったとしても、当時充実した幕府の倉庫を破って莫大な軍用米を長時間にわたって5,000俵も盗み出すなどと言うことが出きるはずのものでなく、これは当時の役人が幕府の指令を待つ時日がなかったため、勘助翁の任侠を見込んで盗み出させたものであろう。しかし、勘助翁にしてみれば江戸からの指令のいかんにかかわらず、盗み出したと言う表向き責任は、絶対免れないのだから、類を及ばさないために妻子を離別勘当までして、決然敢行したもので、もとより死を賭しての一大覚悟に相違ない。」
晩年の正保4年(1696年、61歳)、勘助は田地若干を木津村に寄付しました。その件は今も願泉寺、唯専寺境内に残る「義田碑」に詳しく記してあります。それによると、「村人勘助が田地若干を木津村に寄贈した。のち、これにならう村人もあって、村有財産となっていた。村人は此所に壇を設けて、二百余年間絶えることなく勘助以下を祭ってきたが、明治 32年( 1899年)木津が大阪市に属することになったので、その田地を売って小学校の新建築費に寄付し、またその一部をもって壇跡を記念するためこの碑を建てた。」とあります。この小学校こそが、今の大国小学校と敷津小学校です。その後万治3年(1660年) 11月26日勘助は75歳で天寿を全うしました。敷津西2にある唯専寺の墓地に眠っています。
【参考資料】
- 大国小学校百周年記念誌(大阪市立大国小学校)
- 「甦えるわが街」(大阪市建設局)
- 「願泉寺史伝 木の津の遺跡」(願泉寺)
- 大阪市HP
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9683
ファックス:06-6633-8270