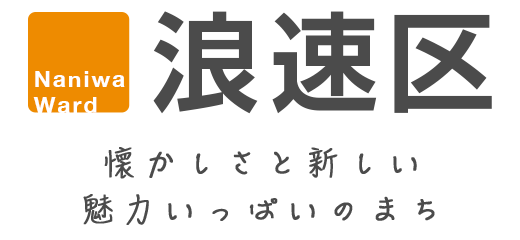浪速区制100周年プレ企画 ルックバック浪速区(第9回幸町地域)
2025年3月1日
ページ番号:642760
座談会

地域の皆さんにお話を伺いました
幸町を襲った2度の空襲
区長
大澤さんは戦前の生まれとお聞きしました。
大澤さん
私は昭和7年に幸町1丁目で生まれて、高台(たかきや)尋常小学校に入学しましたが、戦争が始まって、母の里の姫路に疎開しました。昭和20年3月、学童疎開していた児童のうち6年生と先生方は卒業式があるというので、式の2、3日前に疎開先からこの幸町に帰ってきて、明日はいよいよ卒業式と、着る服などを枕元に用意して寝た夜に、あの大空襲に襲われたと聞きました。
【深掘り】 高台(たかきや)小学校

1872(明治5)年に創立、その後、1945(昭和20)年3月の大阪大空襲で校舎の大半が焼け落ちました。1946(昭和21)年3月、日吉小学校に合併されたのを機に廃校となり、1959(昭和34)年には焼け残った校舎の一部も取り壊されました。悲惨な戦争と戦後の困難であった体験を風化させないために校舎跡地には1988(昭和63)年8月に記念碑が建立されました。
谷さん
親父はその頃、滋賀県の工場に勤務していましたが、そこからも大阪がものすごく燃えていることがわかったそうです。火映(注)のように明るく赤く染まって見えたのでしょうね。幸町は3月だけでなく6月にも空襲があって、父の家はその6月の空襲で焼けてしまいました。
(注)高温の溶岩や火山ガス等が火口内や火道上部にある場合に、火口上の雲や噴煙が明るく照らされる現象のこと。
大澤さん
私は小学校の卒業証書をもらっていません。いつだったかピース大阪で、読売新聞かどこかの主催だったと思いますが、「大阪市民で、卒業証書のない人は授与します」という会がありましてね。それに参加しましたのでピース大阪の卒業証書は持っています。6、7人でいただきました。もちろん正式な卒業証書ではありませんが、高台小学校の名前が書かれていました。
戦争のことでもう1つ記憶にあるのは、姫路の中学1年生の時に、2つ年上の先輩が3人、特攻隊に行くというので全校生徒で見送りました。自分から特攻隊に行くなんて偉い人たちだと思いました。でも飛行機がまわって来なかったらしくて、何か月かしてから戻ってきたんですが、3人ともたばこを吸っていました。特攻隊で、お酒を飲んだりたばこを吸ったりしていたんでしょうね。学校も公認でした。
千葉さん
大澤さんの先祖は昔、お医者さんだったんですよ。
大澤さん
緒方洪庵(1810~1863年、江戸時代後期の医師、蘭学者)の生きていた時代にここで医者をしていました。当時は、今の相撲の番付のように、医者の番付もありましてね。うちの先祖の名前もその番付表に載っていたようです。
また、昔は今の幸町3丁目のあたりにお茶屋さんがたくさんあったそうですが、明治の初め頃に営業が許されなくなり、松島だったかな、そちらに移転したと聞いています。。
美味しい「幸町の水」
千葉さん
私は戦後の生まれですし、長男が幼稚園に入った年に幸町に引っ越してきたので、昔のこのまちのことを直接には知りませんが、以前、酒店を営んでおられた方からよくお話をお聞きしました。その方のご先祖はここで酒樽を作っていたそうです。幸町通りに面している家の庭にはたいてい井戸があって、とてもきれいで美味しい水がとれたので、堀江にあった酒蔵はその水でお酒を作っていたそうです。堀江と幸町は昔からそういうつながりがあるんですね。
また、幸町通りにはたくさん材木問屋があって金持ちが多かったと聞きました。女の子が生まれて生理が始まると、最初の生理があった日に道頓堀川の水を汲んできて、櫛を水につけて髪を梳いてお祝いする風習があったそうですよ。
【深掘り】戦前の生活
私が物心つく時分には、もちろん、電気・ガス・水道はあったが、釣瓶井戸があって冷蔵庫がわりに使っていた。
なおトイレはくみ取り式で、近郊の農家の方がくみ取りにきて、代金がわりに大根など季節の野菜を置いていったという記憶がある。
(1927(昭和2)年から1945(昭和20年)6月の空襲まで幸町5丁目にお住まいだった廣瀬英雄さんの手記より)
区長
そんな風習があったとは。今では考えられませんが、昔は道頓堀川の水も、きれいだったんでしょうね。
なお、戦前の幸町は西区に属していましたが、昭和18年に全市的に川や道路、鉄道などによって区の境界を決めることとなり、幸町はその時に浪速区に編入されました。
大澤さん
戦時中、橋が落ちたりしたら統制が取れなくなるからという理由で、浪速区に編入されたんですね。
区長
谷さんは戦後の生まれですか。
谷さん
両親が戦後すぐに結婚して、1947(昭和22)年に僕が生まれたんですが、空襲で家が焼けてしまって住むところがありませんでした。羽曳野に道明寺という尼寺があって、昔からご縁があった関係で、僕が2歳になるくらいまで仮り住まいをさせてもらっていました。その後、幸町に戻ってきました。
区長
子どもの頃の幸町はどんな様子だったのでしょうか。
谷さん
幸町通りの道路は戦前、木レンガでできていましたが、戦争で焼けてしまったので、その後はアスファルトを使って舗装されていました。でも所々、アスファルトが剥がれているところがあって、10センチ角くらいの木レンガが見えました。
また、昔は「馬力(ばりき)」といって馬が荷車を引いていました。道頓堀に沿って北側に大きな木材せり売り市場がありましたので、そこから木材を運び出すためによく馬力が通っていました。幸橋を渡るのに馬の蹄(ひずめ)が滑って転倒してしまうこともありました。千日前通りをずっと東に行くと松屋町筋から谷町九丁目のほうに上がる坂がありますよね。昔はそこで馬力を後ろから押す人がいて、それを仕事にしている方もいました。当時の材木屋はわりと儲かっていたので、すぐにトラックに変わりましたが、馬力は僕が中学生の頃までありました。
材木のまち「幸町」
谷さん
1967~1968(昭和42~43)年ぐらいまで、幸町には材木屋さんがたくさんありました。幸町通りには製材所や材木屋、銘木(めいぼく)屋(注1)、市売り問屋(注2)など木材関係の会社が65社ほどありました。
丸太は川に浮かべておいて、それを引き上げて製材すると木材がよい具合に乾燥するので、道頓堀川には丸太の筏(いかだ)がたくさん浮かんでいました。木材関係の仲買は幸町通りに多く集積していました。材木屋が多かった関係で、木工機械屋さんも多く集積していました。

幸町材木町(浪速区史より)
(注1)色や形、材質などが特に優れていたり、独特な趣を持つ木材を取り扱う店
(注2)大きな需要に応えるために各産地から木材を仕入れる専門店
川の恵みと水害
区長
道頓堀川はどんな様子でしたか。
谷さん
僕が幼稚園の頃くらいまでは堤防がなかったので、川で泳ぐ人もいました。一部の材木屋さんはレクリエーションとしてカヌーも持っていたので、それで遊んだりもしました。
大きい台風などが来ると川から水があふれて、川沿いの会社の事務所は大きく浸水しました。その時に事務所の窓ガラスから外を見たら、まるで水族館にいるみたいだったように思います。水が引いて事務所を見に行くと、フナやドジョウ、タナゴやらなにやらいっぱいいました。1955(昭和30)年頃に第1次の防潮堤ができるまではそんな状態でした。
1953(昭和28)年の13号台風の時は浸水したと思いますが、風も大変強く感じました。当時、「家曳き」といって家を土台からジャッキで持ちあげて10メートルほど家をずらす予定でした。台風が来た時は家の2階にいたんですが、ちょうどジャッキで家を持ちあげた状態だったので、とても揺れたのを覚えています。
区長
幸町は、北は道頓堀川に面しており、西側には木津川が流れています。
谷さん
木津川には名村造船や佐野安船渠などの造船所が多くあったので、大正橋のあたりには船具屋がたくさんありました。船具屋は荷物を集めるのが上手で、船に積み込む生活用品、例えばマッチとかろうそく、料理をするためのザルや布団、毛、枕など何でも扱っていました。
うちは船具屋さんと商売をさせていただくために、棺桶も用意しました。巡視船などの公船は必要な時のために、いつも棺桶を積んでいるのです。以前は芦原橋駅の近くに棺桶屋さんがあったのでそこで買ったりしていました。棺桶は昔は木製でしたが嵩張るので、今は折り畳み式のダンボール製になっています。
区長
木津川には大正橋がかかっており、その北東詰めに安政大津波の碑がありますね。
谷さん
「大地震両川口津浪記」として地震津波の戒めのために建立され、幸町3丁目西振興町会さんを中心に今でも亡くなった方の慰霊の催しを毎夏、行っておられます。お花も手向け、石碑に書かれているように後世に役立つようとの思いをつなげていく活動や清掃活動をずっと続けて、今日に至っています。
区長
道頓堀川には橋がいくつか架かっています。昔、その橋から見える風景はどのようなものだったのでしょうか。
谷さん
昔は汐見橋や日吉橋からも木津川の向こう側(西側)がよく見えました。今のドーム球場のあたりで大阪瓦斯が石炭を乾留して都市ガスを製造していました。地方から来た人が見たら「火事かな?」と思うくらい、夕方になるとコークスの真っ赤な炎があがります。そしてそのコークスを冷やすために水面にバサッと落とすと、ものすごい水蒸気が立ちのぼります。コークスを蒸し焼きにするんですね。その様子を絵に描く人もたくさんいました。そのススがこのあたりにまで飛んできて、洗濯物に2ミリくらいのススが付いたりしていました。
その頃は幸町通りにゴザを敷いて床几(折り畳み式の床台)を出して、花火を見たり、夜空を眺めたりしていました。今、天の川を見ようと思ったら、遠いところに行くか、プラネタリウムで見るかしかありませんけど、当時はここからでもよく見えました。
これからの地域への期待
区長
そんな幸町もまた、時代とともに大きく変わってきました。
千葉さん
幸町には昔、たくさんの材木問屋がありましたが、その広い土地を賃貸マンションにしたり、処分して出て行かれました。
今はサラリーマンが住むまちになりましたが、もともとは商売人のまちでした。私が引っ越してくる前は、日吉橋を少し南下して幸町通りと交差したところの空間で、やぐらを立てて盆踊りをしていたそうです。交通量もそこそこあったはずですが、きちんと警察への手続きもして開催していたと聞きました。私だったらとてもそんなことはできません。
大店に力があったんでしょう。普段は木材を担いだり樽を運んだりする10代、20代の若者がたくさん働いていましたからね。社長がやるぞ!と言えばできるんです。ある意味「ワンマン」ですが、そういう人たちが1人欠け、2人欠けして、寂しくなりました。
区長
今、幸町の木材関係の会社はどれくらいありますか。
谷さん
幸町の地区は大阪木材仲買協同組合第6支部というのですが、今では15社くらいです。全盛期は65社くらいでしたので、その4分の1程になっています。
区長
いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に今後の幸町に期待することなど、教えてください。
谷さん
難波ほどの商業のまちではないでしょうが、かといって、住むまちというだけでもないでしょうし。でも、もう少し情緒のあるまち、誰にでも声がかけられるような下町になったらいいと思いますね。
外国人が入ってきたら治安が悪くなるという話もありますが、そんなことはないと思っています。うちの店は端材がたくさん出るので、店先でワゴンに積んで無料で差しあげています。そうしたら外国から来て近くに住んでいる方たちは、棚を作りたいからとやって来て、持って帰るのです。自分で努力して作っているのですね。そんなに頑張っている方たちに直接、端材の使い方を教えてあげたりしています。コミュニケーションを大切にし、繋がって行けば文字通りHappy Town(幸町)になっていくことでしょう。そうなってほしいです。
千葉さん
サラリーマンの多いまちですから、地域の共通する課題というのはあまりないのですが、ただ1つ共有できるのが、子どもの教育だと思うんです。今でも夏休みのラジオ体操の期間中は、体操が終わったら会館に集めて勉強できるようにしています。この地域で勉強して遊んで、近所のおじいさんやおばあさんに見守られて育ってきたんだと、子どもたちにそんな記憶が残るような地域にしていきたいです。
幸町地域の歴史
昔の幸町
1929(昭和4)年に行われた南海難波駅工事のボーリングの際、多くの貝殻や海底生物の骨等が出土した結果、石器時代のこのあたりは海の底であったと考えられています。
伝説によると、593(推古天皇元)年、四天王寺建立の際、諸国より建築用の材木が木の津に着した(のちに木津と称した)とされており、この頃には幸町のあたりも陸地化していたことが考えられます。
石山本願寺攻防の時、本願寺方は、木津(西成区出城)、川口、三津寺に砦を築き、毛利軍の援護物資を寺内に運び入れるため信長軍と戦ったとあり、幸町地域も戦場になった可能性が考えられます。
1585(天正11)年、秀吉が大坂城に入るとともに、城下町が上町台地よりも西側に広がり、東横堀川、西横堀川、阿波堀川、天満堀川、道頓堀川などの開削が盛んに行われるようになりました。
江戸時代の幸町
道頓堀川は1612 (慶長17)年、安井道頓が2人の弟(治兵衛、九兵衛)たちとともに、故郷である久宝寺村の農民を招いて開削に着手しました。1615(元和元)年11月に完成しましたが、その間に治兵衛は病死し、道頓も大坂夏の陣で西軍に加わり、同年5月の大阪城落城の日に討ち死にしてしまいます。開削した川ははじめ「南堀」と呼ばれていましたが、家康により城主となった松平忠明は道頓の志を憐んで「道頓堀」と改め、その名を永遠に記念することとしました。
元和の時代(1615~1621年)に、土佐藩が幕府に願い出て、立売堀川に材木市場を初めて開き、その周辺は材木の集散地となりました。この頃、道頓堀川南岸にあたる幸町は、土砂置場や材木置場として使われていたそうです。
1698(元禄11)年、堀江新地(現 西区)が河村瑞賢により開発されました。幸町新地も同年に開発され、大坂三郷に帰属し、堀江との間に住吉、幸、汐見、日吉の4橋がかけられました。これにより、道頓堀の南側にも材木商が進出してきました。
日吉橋の名称は、当時の太閤秀吉の幼少名にちなんでつけられたと言われています。
また汐見橋は、この場所で潮の干満が観察できたので、この名がつけられたと伝えられていますが、南側に唐金屋という掛屋(注)があり、この人が架けたとの言い伝えから、唐金橋とも呼ばれました。幸町新地は奥行を40 間とり、表と裏に大道を設けて南側に幅20間の桜川を開削しました。
幸町4、5丁目(現在の3丁目)は、道頓堀川沿いに廻船問屋が軒を並べ、全国物資の集散地として賑わいました。北国(北陸北海道)問屋が特に多く、北海問屋、松前問屋とも呼ばれて、北海道で獲れるニシンや干しイワシ、コンブなどを扱っていました。船乗りはたいてい加賀越前の人たちで、1艘に大体15人位が乗っていました。彼らは徒歩で10日もかかって大阪にやってきます。彼らの着く2月には、久宝寺の小間物屋、本町の反物屋、西横堀の瀬戸物屋、堺の木綿屋、酒屋などが廻船問屋に出張販売に来て、たいそう賑わったと言われています。3月10日頃にこれらの品物を満載し、途中で瀬戸内の塩を積み込み、北海道に着くと小樽、函館、札幌で積み荷を売りさばき、ニシン、タラ、サケ、コンブなどをまた満載して帰航するのでした。
船問屋が増えるにつれ、船具商も繁盛するようになり、薪炭問屋は幸町1丁目から3丁目に多くありました。
しかし1854(嘉永7)年11月5日、紀州沖南海トラフを震源とする安政南海地震による大津波が発生し、汐見橋など多くの橋が押し流され、大坂三郷における死者は273人を数えるなどの大きな被害が出ました。当時の様子と後の世の人への戒めを伝えるため、1855(安政2)年、「大地震両川口津波記」の碑が建立されました。その碑は現在、大正橋の東詰め(北側)にあります。
この地震よりも前、1842(天保13)年2月に、老中水野越前守が市中に遊女を抱えおくことを禁じ、新町の遊郭などの移転を命じたため、堀江一円の茶屋は幸町に移されました。このことにより全国の商人が来阪し、幸町は非常に繁盛しました。しかし、安政南海地震の被害を目の当たりにして津波を恐れた幸町の茶屋は1857(安政4)年、大阪市中御巡見のため老中脇阪中務大輔の来阪を機に、元の堀江に帰り住むことを嘆願し、その復帰を許可されたので、幸町5丁目を除く茶屋は残らず堀江の古巣に戻りました。5丁目に残った茶屋はその後も営業を続けましたが、1867(明治4)年に泊茶屋を差し止められ、翌5年には特定地外遊所が廃止され、その多くが松島花園町(西区)に移転しました。(注)江戸時代に幕府、諸藩の公金出納を扱った商人
明治時代から戦前の幸町
1869(明治2)年5月、大坂三郷は四大組に改められ、幸町1~5丁目は西大組に帰属、1875(明治8)年、四大区に改められるに伴い、幸町通1~5丁目は第3大区に属することとなりました。その後、幸町の地域は1879(明治12)年の郡区町村編成法により西区の一部となり、1889(明治22)年の市制の実現により、大阪市西区の一部となりました。
1885(明治18)年に関西初の私鉄として阪堺鉄道が難波・大和川間を、1889(明治22)年に大阪鉄道が湊町・柏原間を開業したのに続き、1900(明治33)年には高野鉄道が西道頓堀(現 汐見橋)・堺東間を開業しました。近世以来の大阪では、道頓堀川をはじめとする水路の開削が進み、舟運が発達しましたが、その後、鉄道が舟運に代わる陸上交通の主役となりました。江戸時代から明治にかけて全盛を極めた廻船問屋も時勢の推移とともに衰退に傾き、1908(明治41)年を最後に姿を消してしまいました。
市電もすでに明治時代に営業が開始されており、1915(大正4)年には西道頓堀天王寺線(桜川2丁目-芦原橋-大国町-恵美須町-天王寺西門)のほか、九条高津線(安治川2丁目渡―玉船橋―汐見橋―桜川2丁目―湊町駅前―千日前-上本町6丁目)が開通し、これに伴い、桜川は埋め立てられました。
また同年、木津川に大正橋が完成しました。舟運の阻害をできるだけ防ぐため、日本一長いアーチ橋(90.6メートル)が架けられました。
戦中、そして戦後復興へ
浪速区が誕生した1925(大正14)年には、幸町の地域は西区に属していましたが、その後、大阪市内の各区の間で人口の不均衡が生じ、人口が過大と認められる区もありました。そこでこれを分割再編するとともに、時局に伴う統制経済、防空、物資配給、軍事援護、貯蓄、生活指導、健民指導等の観点から従来の境界を見直すこととなりました。こうして区の境界の決定については、河川、運河、鉄道または軌道、地勢の高低、都市計画道路等の明確なものによることとなり、浪速区では、従来西区とは桜川を境としていた境界が道頓堀川に改められ、1943(昭和18)年4月、幸町一帯は浪速区に編入されました。
その後、戦況は厳しくなり、1945(昭和20)年3月13日、大阪市内はB29約90機による大空襲に見舞われましたが、幸町は重ねて6月7日にも空襲に遭い、大きな被害を受けました。
戦災復興土地区画整理事業は、浪速区では5つの工区において実施されることとなり、幸町地域は東側を「湊町工区」、西側を「汐見橋工区」として、それぞれ1947(昭和22)年とその翌年に事業計画が認可され、「汐見橋工区」は1967(昭和42)年に、「湊町工区」は1991(平成3)年に完了しました。
幸町地域を通っていた市電は、1968(昭和43)年までに廃止されましたが、その一方で、翌年には地下鉄千日前線の野田阪神・桜川間が、さらにその翌年(1970年)には桜川・谷町9丁目間が開通しました。
木材は戦後も川を利用して運んでいたため、1965(昭和40)年頃までは幸町一帯には多くの材木商が軒を並べていました。しかし徐々にその数は少なくなり、マンションがその跡地に次々と建てられていきました。
また平成21(2009)年には、阪神なんば線が開通し、大阪・難波を経由して神戸・三宮方面と奈良などの近鉄沿線を直接結ぶ関西の広域な鉄道アクセスルートが形成され、そのルート上に新たに桜川駅が開設されました。
難波や堀江に近く交通至便でありながら、街中に落ち着いた風情も漂う幸町地域は幅広い世代に人気があり、「住むまち」としての価値を高め続けています。
年表
- 元和 元年(1615年)11月 道頓堀川完成
- 元禄11年(1698年) 幸町新地開発
- 嘉永 7年(1854年)11月 安政南海地震による大津波が発生
- 安政 2年(1855年) 7月 「大地震両川口津波記」建立
- 明治22年(1889年)4月 大阪市が誕生
- 大正 4年(1915年) 1月 市電西道頓堀天王寺線(桜川2丁目-芦原橋-大国町-恵美須町-天王寺西門)開通
- 大正 4年(1915年) 8月 大正橋完成
- 大正 4年(1915年)11月 市電九条高津線(安治川2丁目渡―玉船橋―汐見橋―桜川2丁目―湊町駅前―千日前-上本町6丁目)開通 (これらに伴い桜川が埋め立てられる)
- 大正10年(1921年)10月 市電桜川中之島線(桜川2丁目―堂島大橋)開通
- 大正14年(1925年) 4月 第2次大阪市域拡張、第1次浪速区ができる
- 昭和 2年(1927年) 7月 桜島・堂島大橋・桜川2丁目・大国町・阿部野橋間 市バス開業
- 昭和 9年(1934年) 9月 室戸台風襲来
- 昭和18年(1943年)4月 大阪市22区制により現在の浪速区となる。幸町を西区から浪速区に編入
- 昭和20年(1945年) B29約90機が大阪地区を空襲し、区域の約93%が焼失する(3月)。空襲により幸町通を焼く(6月)。終戦
- 昭和22年(1947年)12月 戦災復興土地区画整理事業の設計認可(湊町工区)
- 昭和23年(1948年)11月 戦災復興土地区画整理事業の設計認可(汐見橋工区)
- 昭和25年(1950年) 9月 ジェーン台風襲来
- 昭和36年(1961年) 9月 第2室戸台風襲来
- 昭和38年(1963年)5月 市電九条高津線のうち、玉船橋―上本町6丁目間廃止(全線廃止)
- 昭和42年(1967年) 6月 戦災復興土地区画整理事業が完了(汐見橋工区)
- 昭和43年(1968年)10月 市電桜川中之島線(桜川2丁目―堂島大橋)廃止、市電西道頓堀天王寺線(桜川2丁目―天王寺西門)廃止
- 昭和44年(1969年)4月 地下鉄千日前線(野田阪神-桜川)開通
- 昭和45年(1970年)3月 地下鉄千日前線(桜川-谷町9丁目)開通
- 昭和49年(1974年)3月 2代目の大正橋完成
- 平成 3年(1991年) 3月 戦災復興土地区画整理事業が完了(湊町工区)
- 平成21年(2009年)3月 阪神なんば線開通、桜川駅新設
幸町地域の史跡と名所
大地震両川口津波記(安政南海地震津波の碑)(幸町3丁目9番)

大地震両川口津波記(安政南海地震津波の碑)

傍らにある解説文
幸町3丁目西の木津川に架けられた大正橋のそばに安政南海地震津波の石碑があります。
この碑は津波に襲われた翌年の1855(安政2)年7月に幸町5丁目(現在の3丁目)の渡し場に建立されました。現在、大正橋の東詰(北側)にある石碑の高さは約2メートル。石碑の西面中央には、死者の冥福を祈る南無阿弥陀仏の名号と南無妙法蓮華経の題目が大きく刻まれ、下方中央には蓮華模様が描かれています。また石碑の東面と南面には大地震両川口津波記の文章が全面にわたって刻まれており、その文章は長文で、しかも「くずし字」で書かれていますが、傍らにある解説文で内容を理解することができます。
1854(嘉永7・※安政元)年の安政南海地震の津波によって、安治川口・木津川口に碇泊していた数多くの大小船が大阪市中の堀川に押し上げられて、多数の川船を押しつぶし、多くの橋々を落橋させ、溺死者が何千人にも及んだというのです。
江戸時代、大阪は水運の便に恵まれ、背後に京都などの大消費地を控え、全国の物資の集散地となり、天下の台所と言われていました。安治川口には全国から廻船が集まり、まさしく「出船千艘、入船千艘」の「水都大坂」の賑わいを見せていました。この水の都として栄えていた大阪を2つの津波が襲いました。1707(宝永4)年の宝永地震の津波と、1854(嘉永7・※安政元)年の安政南海地震の津波です。これら2つの津波は、大阪に大きな被害を与えました。江戸時代、大阪では大火が頻繁に発生し、人々は家財道具を川船に積み込んで、堀川に逃れることを常としていました。道路が狭く、堀川が避難場所として利用されていたのです。宝永、安政の両地震の際にも、地震の激しい揺れを恐れ、多くの人々が船で堀川に避難し、その後津波が襲い、船に乗っていた人々の多くが溺死したのでした。
【安政南海地震津波による大坂での被害の概要】
- 船舶 内川へ入り込みの廻船数:1118艘(うち破船・損船の数662艘)
- 破船・流失の川船数:636艘
- 落橋の数:11橋
- 崩家の数:114箇所
- 崩土蔵:14箇所
- 溺死者の数:273人(ただし、他国からの入り込みの人々や船頭などを入れると数千人になると いう説もある)
安政南海地震の津波の被害を受けた大阪の人々は、宝永地震の津波の教訓を生かせなかったことを悔やみ、津波のあった翌年、犠牲者の霊を弔う石碑を建て、その碑文「大地震両川口津波記」で、後世の人々に津波の恐ろしさを教え、その教訓を忘れないように警告しました。
「大地震両川口津波記」は私たちが学ぶべき津波についての多くの知識を教えてくれています。まず、記述は5か月前の伊賀上野地震から始まっています。これを大地震の前兆ととらえていると考えられます。また、安政南海地震の前日に起きた安政東海地震との時間間隔が約32時間であったことを示すとともに、大地震が起こってから津波が到達するまでの時間についても推定を可能にしています。さらに、地盤の液状化が発生したことについても記述しています。
碑は最初、幸町5丁目の渡し場付近(幸町5丁目の南端の木津川のほとり)に建立されました。1915(大正4)年、市電の開通によって大正橋が架けられたことに伴い、橋の東詰めの北側に移設されましたが、今も木津川のほとりに立ち、地域の人々、道行く人々へ、津波の警告を発し続けています。
【大地震両川口津波記(口語訳)】
嘉永7年6月14日子刻(西暦1854年7月9日午前0時頃)、大きな地震があった。大坂の町の人々は皆驚いて、大通りや川端にたたずみ、余震を恐れて4、5日不安な夜を明かした。伊賀(三重県)、大和(奈良県)では、けが人が多いということだ。
同じ年、11月4日辰刻(12月23日午前8時頃)大地震が起こった。以前から恐れて、空き地に小屋がけしたり、老人や子どもの多くは小舟に乗っていた。翌5日(12月24日午後4時頃)、大地震が起こった。家が崩れ、出火もあり、恐ろしい様子であった。それらがようやく治まった日暮れ頃、雷のような響きがとどろき、海辺一帯に津波が押し寄せた。安治川はもちろん、木津川は特に激しく、山のような大波が立ち、東横堀まで泥水が4尺(約120センチ)ばかり流れ込んだ。両川筋(安治川、木津川)に碇泊していた大小の船は碇綱をうち切られて、一瞬の間に川上へ遡り、その勢いで安治川橋、亀井橋、高橋、水分、黒金日吉、汐見、幸、住吉、金屋橋などことごとく崩れ落ちてしまった。また、大道にあふれた水にあわてて逃げ迷い、橋から落ちる人もあった。
大黒橋では、大きな船が横倒しになって塞いでしまったので、川下から入ってきた船は、小舟を下敷きにして、次々に乗り上げてしまった。道頓堀川の大黒橋より西、松ヶ鼻の南北の木津川筋一帯は、少しの間に船で山のようになって、その多くが破船していた。
川岸の掛けづくりの納屋などを、大船が押し崩し、その物音や人々の叫び声が響き渡ったが、急変で助けることもできなかった。わずかの時間のうちに、夥しい水死者、けが人が出た。船場や島之内までも津波が来るという噂も流れ、上町へあわてて逃げていく人々も見られた。
今から148年前(実際には147年前)、宝永4年10月4日(1707年10月28日)、大地震の時にも小舟に乗って、津波によって溺死した人々が多かったことと聞いている。年月がたてば、そのことを伝え聞く人もほとんど無く、今また同じ場所で、多くの人が亡くなった。痛ましいこと限りない。今後もまた、このようなことが起こり得るだろう。
大地震が起こった時は、いつも津波が来ると思って、絶対に船に乗ってはならない。また、家が崩れて火災も発生するだろう。お金や証文類は蔵へ入れて保管し、火の用心が大切である。
さて、川で碇泊している船は、大きさに応じて水勢の穏やかな所を選んで繋ぎかえ、また、囲い船(北前船のように、冬期航海できず、休んで修理などされている船)は、できるだけ早く、高い場所まで引き上げて、用心すべきである。
津波というものは、沖から押し寄せるだけでなく、海岸に近い海底や川底などでも吹き湧くことがある。あるいは、海辺の新田畑で泥水が大量に吹き上がることもある。今度、大和の古市(現在の奈良市古市町)で池の水があふれ、多くの人家が流されたのも、この類である(津波による災害としているが、地震による地盤の液状化現象である。ただし、奈良の古市での災害は液状化によるものかは明確ではない)。海辺、大川、大池の近くに住む人は用心しなさい。
津波が平常の高潮と違うことを、今回被災した人々はよく知っているが、後の人々の心得のため、また溺死した人々の追善供養のため、ありのまま拙文にて記しておきます。どうか、心ある人は、文字が読みやすいように、毎年碑文に墨を入れてください。大正橋
1915(大正4)年、市電開通の時に木津川にかけられ、大正時代の幕開けを告げるものとして大正橋と命名されました。大正区の名称はこの橋名にちなんでつけられました。
舟運の阻害をできるだけ防ぐため、当時の日本では最も長いアーチ橋(90.6メートル)がかけられましたがその後、傷みが激しくなり、1971(昭和46)年3月完全に撤去されました。
1974(昭和49)年に新しい橋として完成し、幅員41.6メートルと大阪で2番目に広い橋となりました。また、高欄にべートーベン作曲の交響曲第9番「喜びの歌」の音符がデザインされています。
桜川
1698(元禄11)年、幸町新地が開発され、その南側に幅20間の桜川を開削しました。
川は難波村の用水路となり、幸町の南端から西に流れ木津川に注いでいました。大正4(1915)年の市電開通の際、東端の一部(湊町駅構内)を残して埋められました。

改正新版大阪明細全図 (大阪古地図集成 第24図)(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)「サクラ川」の表記がある
参考資料
- 創立百周年・校舎竣工記念誌「立葉」(大阪市立立葉小学校)
- 日吉六十年誌(大阪市立日吉小学校)
- 創立九十周年記念誌1964(大阪市立日吉小学校)
- 大阪市日吉小学校創立百周年記念「日吉百年」(大阪市立日吉小学校百周年記念事業委員会/編)
- 「大地震両川口津波記」記念誌第版(大阪市浪速区幸町三丁目西振興町会・大地震両川口津波記念碑保存運営委員会・浪速区役所)
- 浪速区史
- 甦えるわが街(大阪市建設局)
- 難波土地区画整理事業誌(大阪市難波土地区画整理組合)
- 浪速区まちかど歴史事業DVD など
(注)この記事は地域の語り部の方々の発言をもとに作成しております。歴史考証はしておりませんので、予めご了承ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9683
ファックス:06-6633-8270