浪速区制100周年プレ企画 ルックバック浪速区(第8回日東地域)
2025年3月1日
ページ番号:640110
座談会

地域の皆さんにお話を伺いました

【参加者】(後列左から)井上惠津子さん、黒田ふみ子さん、水口博司さん、堀内勲さん、近藤尚義さん (前列左から)吉田和史さん、井上猛さん、幡多区長、田中一彦さん
かつての日東地域
区長
日東地域は日本橋筋を中心に発展してきました。
井上(惠)さん
日本橋筋のあたりは昔、長町(ながまち)といわれていました。太閤秀吉が堺に行くためにおつくりなられたんです。その道がのちに紀州からの参勤交代の道に使われたんですね。その時、この長町のあたりに人足が求められ、交代で人足として雇われていました。宿屋が多い、旅籠(はたご)のまちでした。

「長町毘沙門堂 (写真浪花百景 上編 中編)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)
区長
旅籠は堺筋の両側にたくさん並んでいたのですか。
井上(惠)さん
はい。それから、旅籠はその奥にもありました。旅館の多いまちだったんです。
堀内さん
今の小中一貫校の東側を通っている南北の筋は、旅館がたくさんありました。今も旅館の名残が残っています。
区長
まだ、旅館をされているのですか。
堀内さん
もうやめられたと思いますけど、建物はそのまま残っています。
井上(惠)さん
堀内さん
戦前、日本橋筋の古本屋は有名でした。戦後になってから、電気屋さんが増えました。それまでは3軒くらいでしたが急激に増えて、日本橋筋の電気屋街になっていきました。
井上(惠)さん
日本橋の電気屋さんの始まりは上新電機です。名古屋相互銀行の隣に青果業を創業したのが上新電機の始まりと聞いています。
戦後、ここに真空管などを買いにきて、ラジオを家で組み立てるんです、そのための材料を買いに来るところから電気屋さんが始まっていきました。
堀内さん
昔の資料を読むと昔は髙島屋の東横から松坂屋(今の髙島屋東別館)、そして名呉橋の手前(今の阪神高速えびす町入口のあたり)までぎっしりと電気関係の商品を扱う店が占めていたそうです。
井上(惠)さん
昭和の時代って「〇〇屋さん」というのが多かったじゃないですか。日本橋筋のこの辺りにはそれが全部そろってました。眼鏡屋さん、秤(はかり)屋さん、かもじ屋さん(かつらを扱う店のこと)。本屋さん、ふとん屋さんもありました。お茶屋さん、建具屋さん、金物屋さん、骨董屋さん、お風呂屋さん、魔法瓶屋さんもありました。
いろんな「〇〇屋さん」がありましたが、めだって固まってあったのが、洋服屋さん(紳士服の店)や家具屋さんで、電気屋さんも後からめだつようになりました。
田中さん
日本橋5丁目の代表格は昭和26(1951)年にラジオパーツで開業された東亜無線電機さんです。昭和50年代になって上新電機さんがパソコン専門の店舗をつくりました。これからは絶対に会社でパソコンを使うようになると考えて、そういう人を育てて、会社にパソコンを導入してもらうことを目的に始められました。5丁目は、そういうパソコンやパーツ、電工材料を扱う店が中心です。5丁目で一般家電の店が増えたのは昭和40年代半ば以降のことで、家具屋さんや紳士服屋さんが一般家電の店に変わっていきました。
一般家電の店は、はじめは日本橋3丁目(今の髙島屋東別館あたり)から増えていき、バブルが崩壊する平成の最初の頃まではたくさんお店がありました。メーカーの方針が変わって量販店にシフトしたために3丁目や4丁目にあった一般家電の店の多くは廃業して、その後にメイド喫茶やサブカルチャーの店が入ってきて今に至っていますが、5丁目の方はまだそういう店はほとんどありませんね。
日本橋筋のまちの変化は歴史的にみると、北の方から始まって、それから南の方へ移っているんですね。
区長
日本橋筋のまちの移り変わりを詳しく教えていただき、ありがとうございます。
水口さんは何か、日本橋筋、堺筋の思い出はありますか。
水口さん
私は昭和27(1952)年に引っ越してきたので、戦後のことしかわかりませんが、小さいながらに覚えているのは堺筋に市電が走っていて、霞町だったと思いますが、ずっと南の方に市電の車庫場があって、その向かいに馬車の荷下ろし場がありました。
近藤さん
そうでしたね。私は昭和29(1954)年生まれですけど、今のダイソー新今宮店がある辺りに馬のたまり場がありました。余計な話ですけど、馬のうんこを踏んだら、走るのが速くなると言われまして、そのうんこを踏みに行きました。でも、それはロバのパン屋のうんこでした。だから走るのが遅くなったんじゃないかと思います(笑)。
区長
日東地域のお話ではありませんが、面白いので掲載させていただきます(笑)。
高津入堀川と愛染橋
近藤さん
昔、日東地域には高津新川という川が流れていました。高津入堀川とも言われています。
吉田さん
川は今の高速道路の下を流れていました。私たちはその川を東横堀川と呼んでいました。
井上(惠)さん
私たちも東横堀川と言っていました。その川は西側で鼬(いたち)川とつながっていて、それから西横堀川に続いていきました。
堀内さん
高津入堀川に架かっていた橋の1つが堀川橋で、愛染橋とも言われていて、その橋の近く、当時の下寺4丁目46の98番地が、石井記念愛染園の発祥の地です。石井十次という方がそこに保育園と夜間学校をつくりました。
石井さんのよき理解者であった、倉敷紡績の社長の大原孫三郎という方が、それらを引き継いで愛染園を設立し、昭和12(1937)年には病院も開設されました。
石井十次氏(石井記念友愛社ホームページより)
区長
それが愛染橋病院ですね。
吉田さんは生まれてからずっと日東地域にお住まいと聞きました。昔、その高津入堀川の水はきれいだったんですか
吉田さん
あまりきれいじゃなかったです。よく木津川の方から丸太を組んだイカダが流れていました。私は昭和17(1942)年生まれですが、小学校1、2年の頃までそういう風景が見られました。ある時、この川にはまって亡くなった「どざえもん」を見た記憶が今も頭から離れません。
近藤さん
昭和40年ごろまでは、川はドブ川で臭かったですけど、ギンヤンマという大きなトンボがいて、それをとった記憶があります。
井上(惠)さん
昭和40年ごろまでは材木屋さんもたくさん残っていました。
田中さん
今の阪神高速えびす町入口周辺に、たくさんありましたね。今はほとんどありませんけどね。
井上(惠)さん
みんなマンションに変わってしまいました。
軍艦アパート
田中さん
親父から聞いた話では、大正から昭和のはじめにかけて、さきほども話が出ていましたがこの辺りは宿屋がすごく多かったそうです。明治の内国勧業博覧会を機に、最先端の公営アパートが建てられて、きれいなまちになったと言っていました。
区長
「軍艦アパート」と言われた建物ですね。なぜそのような名前がついたのでしょう。

市営下寺住宅(浪速区懐かしの風景画より)
近藤さん
姿が軍艦に似ているからではないですか。
堀内さん
昭和12(1937)年に秩父宮殿下が「軍艦アパート」を視察しに来ています。完成した後に見に来ているので、昭和10(1935)年ごろにできたんじゃないかと思います。その碑が今もあります。昔は日東住宅にあったんですが、今は移されて、市営住宅の3号棟と4号棟の間に立っています。
当時は鉄筋3階建てで、各家に水洗便所がついた画期的な住宅でしたので、とても有名だったらしいです。昭和20(1945)年3月の大空襲の時にもある程度、焼け残ったようですね。

「日東市営住宅記念碑」1937(昭和12)年2月に秩父宮両陛下が視察に来られた記念に建てられた碑。現在は、市営日本橋住宅(4・5号館)にある。(参照:「浪速区懐かしの風景画」より)
区長
その軍艦アパートは今のどのあたりにあったんですか。
黒田さん
今、ライフ下寺店のある場所にありました。
吉田さん
北日東ふれあい広場の場所にもありました。
堀内さん
もと日東小学校のあったところ、今、心和中学校になっていますが、その南側にもありました。
近藤さん
軍艦アパートには戦後、香港の九龍城のセットに似ているからといって、映画を撮りに来た人がいました。その頃は、ちょっとスラムをイメージするような、香港映画のような雰囲気がありましたからね。
田中さん
軍艦アパートの近くには、普通の木造の市営住宅も結構たくさんありました。2階建てが多かったように思います。戦災に遭って、様子が変わっていきました。
井上(猛)さん
戦争の話が出ましたので、少しその話をしたいと思います。戦時中、堺筋の西側、今の日本橋4丁目、5丁目あたりですが、そこを飛行場にするというので立ち退きをさせられて、広い空き地になりました。昭和20(1945)年3月13日の大空襲の時はそこに逃げました。神棚とニワトリだけ持って逃げました。
田中さん
戦後、その空き地に市営住宅が建ったんですね。
水口さん
「新住宅」という呼び方をしていましたね。木造の住宅でした。
田中さん
市営住宅はほかに、現在、愛染橋病院の建っている附近にもありました。
区長
井上さんは、なぜニワトリを持って逃げはったんですか。
井上(猛)さん
父が、残していったら焼き鳥になってしまう、可哀そうだからと言って持ち出して、疎開先にもそのニワトリを連れて行きました。そうしたら、卵をたくさん生んでくれて、とても助かったそうです。一緒に持ち出した神棚は今でも家に祀っています。
区長
優しくて信心深いお父様だったんですね。
戦後、疎開先から戻ってこられた頃はどんな様子でしたか。
井上(猛)さん
その頃、路上で10人ほど人が集まって碁盤のようなものを広げて、賭博をしていたのを覚えています。「四五一(しごいち)賭博」といってね、3つのサイコロをころがす賭け事でした。
井上(惠)さん
義父が在郷軍人会の副会長をしていて、浪速警察署に頼まれて配給の元締めをすることになり、うちの家は浪速区の配給所になりました。戦後すぐのことです。
区長
戦後、戦災復興のための区画整理がこの地域でも行われましたが、なにかご存じの方はおられませんか。
吉田さん
私の家も区画整理のために土地を提供しました。皆、近所の家は土地を供出して、立派なまっすぐな道路ができました。
下寺 町名の由来
区長
黒田さんは下寺にお住まいですね。昔の下寺はどのようなところだったのでしょうか。
黒田さん
私は昭和51(1976)年に結婚して、下寺1丁目にあるマンションに引っ越してきました。そのマンションが建つ前はお寺だったそうで、子どもたちに習字を教えておられたと聞きました。
それから松屋町筋と堺筋を結ぶ東西の通りを昔、日銀通りと呼んでいたそうです。
井上(恵)さん
日本橋銀座のことを略して「日銀」と呼んでいたんですね。
黒田さん
そうだったんですね。
下寺の西側は川(高津入堀川)が流れていて、直線距離で行くと日東小学校(現在の心和中学校)の方が近いんですが、渡る橋がずっと北側にしかなかったので、子どもたちはその橋を渡って日本橋小学校に通っていました。地域は日東地域なんですけどね。
吉田さん
その橋は「そのつぼ橋」という名前でしたね。
区長
下寺の東側は松屋町筋で、天王寺区との境になっています。
井上(惠)さん
下寺の地名は、浪速区側は「しもでら」、天王寺区側は「したでら」と言うんですよ。
堀内さん
浪速区側は「下寺(しもでら)」ですが、天王寺区側は下に「まち」がついて「下寺町(したでらまち)」と言うんですね。
区長
そもそもなぜ「下寺」と言うんでしょうか。
田中さん
子どもの頃、今の浪速小学校の近くに住んでいましたが、1メートルほど掘ったら砂が出てくるので、よく砂を掘り出して土俵をつくって遊んでいました。つまり昔、このあたりは海岸だったんです。上町台地から下りる地形になっていました。下寺にはお寺がたくさんありましたが、四天王寺から下ってきたところにあったので、そう呼ばれたのではないでしょうか。
堀内さん
今も松屋町筋の東側はお寺が多くありますが、昔は両側にたくさんのお寺があったそうです。民家よりも寺の方が多かったと聞いています。
年末に活躍した「ちんつき屋」
区長
水口さんは、何か思い出はありますか。
水口さん
昔、日東温泉というお風呂屋さんがあって、その向かいに一文菓子屋(一文で買える菓子屋)があって、子どもの頃よく買いに行きました。
母はよく浪速市場に食材を買いに行っていました。もう今はありませんけどね。
年末になると「ちんつき」という看板が出まして、子ども心に「何のことかな?」と思っていました。
井上(猛)さん
「ちん(賃)」というのはお金のことです。正月には家で餅をつきましたが、臼(うす)がない家は「ちんつき屋」についてもらうんです。
吉田さん
家で餅をつけない場合は、その家の近くの道路上で「ちんつき」をやってもらうんです。「ちんつき」をしてもらう家は毎年決まっているので、その時期になると4、5人でそういう家を順番にまわっていました。
区長
いつ頃まであったんですか。
田中さん
大阪万博の頃までではないでしょうか。
区長
「ちんつき」という言葉は初めて聞きましたが、昔はそうやって正月を迎えていたのですね。
廣田神社と合邦辻閻魔堂
区長
日東地域の名所・旧跡のことも教えてください。
田中さん
廣田神社は今の堺筋、昔の紀州街道の中核でした。祭神は天照皇大神荒魂、撞賢木 嚴之御魂 天疎 向津媛命(つきさかき いつのみたま あまさかる むかつひめのみこと)といい、今宮村の産土神(うぶすなのかみ)でした。つまり、土地を守る神さんであり、「土地」の「ち」と「痔」の「ぢ」とで音がよく似ているということで無病息災の神さま。そして神社の神使とされてきたアカエイの「えい」を「叡智」の「えい」になぞらえて、合格必勝の神さまでもあるらしいです。由緒あるお宮さんで、社域は今の浪速小学校のあたりから住吉大社までと広かったんです。萩の名所として有名で、紅白の萩が植えられていたそうです。
神社の宮司さんは津江さんとおっしゃって、今宮戎神社の宮司さんと親戚関係にあるそうです。そんな関係もあって、十日戎とか夏祭りに一緒にイベントをされたりしています。今年も廣田神社の夏祭りの日に今宮戎神社で「こどもえびす」の催しをされていました。

廣田神社
堀内さん
合邦辻の閻魔堂もあります。聖徳太子の開基と伝えられています。浄瑠璃や芝居の主役を務める人はそこに挨拶に行ったそうです。以前は天王寺公園北口の市電の停留所の近く、今の天王殿のあたりにあったんですが、区画整理があって、明治初年の道路拡張工事の際にそこを取り壊すことになり、天王殿の筋向かいにある西方寺の境内に移されたそうです。
ちなみに昔は西方寺もそうですが下寺は皆、浪速区ではなくて天王寺区でした。今、大江神社の夏祭りの時に太鼓が出発する逢下会館も天王寺区だったんです。そして、逢下会館の場所には以前、逢坂尋常小学校がありました。
吉田さん
そのあと、その場所は中学校になりましたよね。
井上(猛)さん
私は昭和12(1937)年生まれですが、昭和25(1950)年にその「浪速東中学校」に入学しました。中学校の運動場が狭かったので、100メートル走のタイムを測るときは、天王寺動物園の西側のまっすぐな道路でタイムを測りました。また中学校の記念写真の撮影は、市立美術館の階段を使っていました。
地域に寄せる思い
区長
では最後に、日東地域への思いや期待について、お伺いできればと思います。
井上(猛)さん
これまで87、8年、浪速区と同じくらい生きてきましたが、これからこのまちがどう変わっていくのか、ものすごく興味があります。
それから私は日本橋にトラム(路面電車)を走らせようという会の顧問をしています。昔は市電が走っていました。今は地下鉄が走っていますが、もう1回、トラムを走らせたいと思っています。
区長
なぜ、トラムを走らせたいのですか。
井上(惠)さん
外国に行ってもトラムの走っているまちは多いです。富山や宇都宮などに視察に行きました。豊橋や岡山にも行きました。みんなトラムが走っているんです。今、天王寺の駅前から路面電車が走っていますが、ああいう低床型のトラムがいいんです。これからもっとお年寄りが多くなります。地下鉄は階段を下りて行かないといけないし、エレベーターに乗らないといけない、年を取るとエスカレーターを使うのが怖くなる人もいらっしゃいます。低床で、そのままスッと乗れるのがいいんです。
それから、この地域をみていると民泊がものすごく増えて、インバウンドばかりのまちになりそうで、ちょっと危惧しています。子育て支援の活動をしていますが、子どもの数が少ないために子どもにかまいすぎている状況を見ますと、これからどうなっていくのかなと思ったりします。もっと子どもが増えるといいと思います。
吉田さん
私も毎朝、子どもたちの見守りをしています。この地域では40名くらいの人が見守り活動に参加しています。これからもっと子どもたちが増えて、元気のいいまちになってほしいなと思っています。
黒田さん
私はふれあい喫茶や食事サービスの活動をしていて、これからもできる限り、地域の皆さまを見守っていきたいです。
水口さん
私は地域のお手伝いをちょこちょこさせていただいてるんですけど、お母さん方の気配りや温かさをとても感じます。本当に心温まる地域です。これからも子どもたちのために、一生懸命、温かいまちをつくってもらいたいと思います。
堀内さん
皆さんと協議をしないといけないのですが、10月くらいに、なんちゃって祭りをしたいと思っています。夏は暑いですが10月頃なら涼しくなりますので。この頃、地域の行事に参加させてもらうようになりましたが、子どもたちが参加できる行事を1つでも増やしていきたいと思っています。そうすることで、日東地域に集まろうという子どもたちが増えてくれたら、将来、もっとこの地域が発展するんじゃないかと期待しています。
近藤さん
私自身は小学校時代、天王寺区に越境してました。当時は越境する子どもが多かったんです。それで正直、地元へのなじみがなかったんです。ところが何年か前から町会の役員をすることになって感じるのは、住んでいる人が少ないということです。そうなると町会の活動の担い手も少なくなってきます。だからもっと住民が増えてほしいと思っています。
田中さん
やはり町に活気を出すためには、子どもとその親たちが一緒に参加してくれる行事を増やしていった方がよいと思います。
最近は、町会に入らない人が増えています。外国籍の方やワンルームにお住まいの方は町会になかなか入っていただけないので、そういう方たちにも行事や活動に参加しようと思ってもらえるような方法を探していかなければならないと思います。
堀内さん
私の町会には30軒ほど建売の家があるんですが、ほとんどの方が外国籍です。子どもさんのいる家には、例えば祭りの時は太鼓をたたく練習に参加してもらうとか、いろんな行事に参加してもらえるように声をかけています。つながりをつくるにはそれが1番いいんではないかと思います。
田中さん
そうですね。1人でも2人でも、地域になじんで愛着をもってもらえるようにすることは、地道ですが大事な活動ですね。
昔は自分の持ち家で商売をしていましたが、今はテナントが商売をするので、まちの様子が目まぐるしく変化します。安全安心のための取組みも、しっかりと進めていかなければならないと思っています。
数年前にNTTが建物を建て替えるときにセットバックして、浪速小学校の子どもたちの通学路になっている歩道を広げてくれました。浪速小学校は浪速区以外からも通学する小中一貫校で、教育の充実をアピールできると思います。また、日本橋5丁目に建築中のホテルはロイヤルホテルが運営すると聞いています。
伝統ある地域のイベントをどんどん行うことで、「いいところで育ったな」と子どもたちに思ってもらえる足がかりもできてきました。日東地域の見通しは明るいと思っています。
日東地域の歴史
1.宿場町から日本橋へ
堺筋沿いに形成された宿場町
江戸時代の堺筋は、大阪から堺を経て和泉・紀伊に達する紀州街道の起点部分にあたり、参勤交代で大名行列が通った道です。この堺筋を南下すると道頓堀にかかる「日本橋」(中央区)があり、公儀橋(管理・修築費用を幕府が負担した重要橋)の1つでした。この「日本橋」より南の筋を特に「日本橋筋」といい、「日本橋筋」に沿って形成された市街地は「長町」と呼ばれていました。
大阪では、東西方向の道路を「町通り」、南北方向の道路は「筋」と呼びます。豊臣秀吉以来の城下町「大坂」では、大坂城の正門=大手門から直進する方向にあたる東西道路が、港とも連絡する関係で重要でした。市内の大半の屋敷はこの東西方向の道に向かって対面し、それぞれ数十軒の屋敷群で町を構成していました。つまり東西道路はどこも、家々が間口を開いてぎっしりと並ぶメインストリートでした。一方、南北の「筋」は、家々の横壁か堀が延々と続く、通過専用の横丁というわけです。例外的に堺筋に面した屋敷群が、筋に対面していたのは、この道路が紀州街道に連なる重要交通路であったことを示しています。
南大阪方面への幹線道路であった紀州街道は、住吉大社への参道として、また紀伊藩(徳川家)や岸和田藩(岡部家)の参勤交代路として、人々の往来が盛んでした。そのため、「長町」には旅籠屋や木賃宿が多く立ち並んだのです。一般的な旅館をさす旅籠屋(はたごや)に対して、木賃宿(きちんやど)とは、本来、旅人自らが持参した米を炊くための薪代だけで宿泊することができる安宿のことをいいました。「長町」には十返舎一九の「東海道中膝栗毛」にも登場する分銅河内屋やひょうたん河内屋など高名な旅籠屋があって、「浪速の名物」と評されました。
江戸時代の日東地域は、現在の堺筋(日本橋筋)の周辺を「長町」といい、その西側は今宮村、東側は天王寺村に属していました。

「長町裏遠見難波蔵 (浪花百景)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)長町から難波御蔵を遠く望む風景が切り取られている。
下寺町の形成
日本橋筋の1本東を通る松屋町筋の南部には、江戸時代初期に大坂城内の松平忠明によって市中の一向宗(浄土真宗)以外の寺院が移転させられて寺町が形成されました。このあたりは上町台地の西の崖下に位置することから、「下寺町」と呼ばれるようになったといいます。
「下寺」は大坂夏の陣で荒れ果てた大坂の復興を進めるために邪魔になる墓と寺院をまとめてまちはずれに移し、監督しやすくするという目的で建設されたと考えられます。
この結果、寺は信者や檀家から引き離されてしまいましたが、お寺参りは散策や花見に出かける良い口実となり、下寺一帯は恰好の行楽地になりました。付近には料亭や遊郭も立ち並び大変賑わったといいます。
堀川の開削
1733(享保18)年、庶民のレクリエーション空間であった下寺と宿場町として発展していた日本橋の間に高津新地という新市街が建設されることになり、同時に延長約800メートル、幅約16メートルの高津入堀川が開削されました。その後、高津新地の南側に幕府が米蔵(天王寺御蔵)を設けると、道頓堀川とも連絡することとなり、舟運の利用も増えました。ただ入堀は水が滞留しやすく不衛生なため、1898(明治31)年に、現在の下寺と日本橋東の間に高津入堀川を延長させ、その後西に屈曲して現在の浪速警察署の北側を通り、さらに北折して、鼬川と接続させる工事が実施されました。
しかし、堀川の水路としての意義は、市電網の整備にともなって次第に失われていきました。戦後まもなく埋め立てられた高津入掘川の跡地上には現在、阪神高速道路環状線が通っています。
長町の改名
賑やかな表通りに対して、交通の便の良い日本橋や下寺の裏通りには各地からの出稼ぎ労働者や生活困窮者が集まり、日割り家賃を支払って暮らす長屋住民や無宿者となっていきました。こうした貧困街というイメージを一新するために「長町」は「日本橋」と改められたともいわれます(長町1丁目から5丁目は1792(寛政4)年、日本橋1丁目から5丁目に改称。ただし、長町6丁目から9丁目はそのまま使用された)。その「日本橋」及び「長町」は、大坂三郷が四大組に改められた1869(明治2)年に、南大組に属すことになり、その後摂津国第二大区を経て、1879(明治12)年に大阪府南区の一部となりました。
2.近代的なまちなみの形成
市電の開通
1900(明治33)年5月、第5回内国勧業博覧会を3年後の大阪で開催するという勅令がおりました。堺筋は既成の市街地から会場となる天王寺・今宮への主要な交通路にあたります。開会式当日には明治天皇の馬車も通る行幸道路でもあったため、不良住宅街は撤去されました。狭くなったところは拡張され、道にはみ出した軒の庇は屋根瓦3、4枚分の軒切りが強制されて、堺筋は幅員5メートルの道路として整備されたのです。
1903(明治36)年の内国勧業博覧会には間に合いませんでしたが、同年9月に日本初の市営市街電車が花園橋・築港間に開通し、1908(明治41)年に南北線が開通しました。梅田から四つ橋筋を南下する南北線は、難波で東に曲がった後、日本橋筋三丁目で再び南に折れて恵美須町に達します。1912(明治45)年には、第3期線として大江橋から北浜2丁目を経由して日本橋筋3丁目に至る堺筋線が、また1913(大正2)年には恵美須町と霞町を結ぶ霞町線などが開通しました。
堺筋の拡張と整備
大阪・神戸間の鉄道が開通した1874(明治7)年に梅田停車場(現在の大阪駅。レンガ仕立ての駅舎は「梅田ステンショ」と呼ばれた。)が設置されて以降、東西の「町通り」よりも交通量の増加が著しい「筋」方向の交通路の拡張・整備が必要になっていました。
道路拡張をともなう市電の敷設にあたっては、商売に差し支えるとして地元住民の猛反対にあい、堺筋線の敷設ルートも二転三転しました。将来の発展を説く声もあり、また明治末期の2度の大火災(1909(明治42)年7月の北の大火、1912(明治45)年1月の南の大火))で空き地の必要性を住民自身も痛感していたこともあって、堺筋線の敷設がようやく決定します。当時、堺筋に向かって、両側の商家の1階部分の軒は互いに半間ほど突き出しており、その軒下は荷造りや荷ほどきを行う作業空間となっていました。その軒がごっそりと削りとられた結果、堺筋は中央に市電の複線、その両側に車道が走る幅員およそ22メートルの大幹線に生まれ変わり、大阪で最初の街路樹(プラタナス)も植えられました。
近世以来の大阪では、市内を四通八達する河川を利用した水運が発達し、その反面、陸上の交通は貧弱でした。しかし、物資と人員の輸送量が激増し、馬車さらには自動車が登場する頃には、もはや従来の道路では用をなさないことは明白でした。
3.古書店街の形成
交通の便が良く、古着を中心にあらゆる古物が揃う日本橋には、懐具合の寂しい学生も多く出入りするようになりました。そこに目をつけたのが古本商です。
日本橋の古本屋の第1号とされる谷書店の創業者谷勘助はもともと左官業を営んでいました。夜間だけ店の前を古雑誌を売る露天商に場貸ししていたところ、その売れ行きがあまりにも良いので、1913(大正2)年になって自ら古本屋を開業することにしたといいます。
古書店の出店がその後も相次ぎますが、特に1923(大正12)年の関東大震災の後、はるばる東日本から古本を求めにやってくる顧客もあらわれるようになり、日本橋の古書店街の知名度は上がっていきました。
最盛期には60軒以上の古本屋が店を構えた日本橋筋界隈を歩いて目的の本を見つけることは、当時の人々の1つの楽しみでもありました。作家・織田作之助は私小説「木の都」のなかで、善書堂の書棚を漁って、国木田独歩や有島武郎などを読み耽ったために、危うく中学校へ入り損ねたと回顧しています。また古本を2、3冊持ち込んで映画代を稼ぎ、そのまま新世界へと下っていくという光景もみられたようで、古書店は小銭の融通機関としても便利だったそうです。
4.不良住宅街地区改良事業
改良事業の始まり
すでにみたように、江戸時代以来の日本橋筋や松屋町筋の繁栄の裏側には貧困街が拡がっていましたが、明治中期以降の産業・経済の急激な発展は、大都市への人口流入を促し、劣悪な環境の住宅地が形成される要因となりました。大正期にはこれら住宅地をはじめとする都市社会問題がますます深刻化し、その社会政策のひとつとして不良住宅地区改良法が1927(昭和2)年に施行され、およそ2万坪の土地が要改良地区に指定されました。
近代的な改良住宅の建設
事業は、1929(昭和4)年2月に今宮住宅が建設されて以降、264戸が居住できる改良住宅の下寺町第1住宅、北日東町住宅(126戸)、南日東町第1住宅(259戸)などが次々に誕生しました。
改良事業は、住民を一時収容施設に移して土地建物を買収した後、建物の撤去・整地を行い、道路排水設備を施して改良住宅を建設するという順序で進められました。新しい改良住宅の大部分が鉄筋コンクリート3階建ての時代の先端を行くモダニズム建築で、居室は6畳と3畳の2室を標準として、各戸に専用の炊事場・水洗便所・水道・ガスが備えられていました。屋上には物干し場が設けられ、空き地の一部は子どもの遊び場にあてられました。また、店舗向け住宅や単身者向け住宅のほか、家内工業を営む人のために2~3坪の作業場や、行商を営む人のために物置なども用意されていました。密集住宅地区に突如現れた巨大な白い鉄筋コンクリート造の集合住宅は、人々の注目を集め、屋上の煙突がかまどからの煙を噴き出す姿から「軍艦アパート」と呼ばれていました。
こうした市営住宅は当時の大阪市の誇るべき施設であり、1937(昭和12)年には秩父宮同妃両殿下が南日東町住宅へ視察に訪れています。
5.福祉活動と教育のはじまり
大阪で最初の保育所開設
1909(明治42)年7月、石井十次氏により当時の下寺町4丁目に開設された岡山孤児院附属愛染橋保育所は大阪市内における最初の保育所です。
また、附属事業として夜学校も開設されました。その当時、義務教育負担区制度に禍(わざわい)されて学校の設備が不十分であったため、不就学児童が多数いましたが、開校直後、200名の生徒が集まりました。1917(大正6)年4月、大原孫三郎氏により、石井氏の遺志と理念を受け継ぐ、財団法人石井記念愛染園が設立され、私立愛染尋常小学校が開設されました。学校は1929(昭和4)年に教育負担区制度が撤廃されるまで続けられました。
市立小学校の誕生
日東小学校の前身である天王寺第九尋常小学校が創設されたのは1924(大正13)年8月29日です。最初の校舎は下寺町2丁目に天王寺第三尋常小学校の分教場をそのまま使用し、児童673名、12学級で9月1日に開校しました。その後、校舎の新築が進められ、1927(昭和2)年10月、総コンクリート鉄筋3階建ての新校舎へと移転が行われました。学校は1939(昭和14)年4月、校名を日東尋常高等小学校に、1941(昭和16)年4月には日東国民学校と改称されました。
また、1932(昭和7)年4月には、天王寺第九尋常小学校内に幼稚園が開設されました。
6.戦時中のできごと
南区から浪速区への区域変更
1943(昭和18)年4月1日の大阪市行政区再編成により、新区の境界は原則として河川・鉄道・道路・丘陵線などにより定められることとなりました。これに伴い、日東地域の中では、現在の日本橋5丁目の堺筋沿いのエリアは南区から浪速区に、また、それよりも東側及び現在の日本橋東2丁目と3丁目、下寺1丁目から3丁目までは天王寺区から浪速区に変更されることとなりました。
学童疎開とその後
戦時中、児童の集団疎開が行われ、日東国民学校の児童も1944(昭和19)年9月、271名が滋賀県野洲郡中里村に集団疎開を行いました。疎開先でもその周辺で戦機の来襲がありましたが、幸い児童の中から犠牲者を出すことはありませんでした。
しかしその翌年、例年より早く3月14日と定められた晴れの卒業式に参加するため、3月に入ってまもなく6年生のみが帰阪しました。卒業式のまさに前夜、大阪大空襲に見舞われ、敵機の焼夷弾のために2名の女子児童が亡くなりました。
校舎は2,3の焼夷弾を受けたのみで、大きな被害を被ることなく焼け残りました。学校には避難民が続々と集まり、その数2千数百名に達したといわれています。
1946(昭和21)年4月、近くの日本橋、浪速津、逢阪の3つの国民学校が戦災のため日東国民学校に合併され、翌年4月に日東小学校と改称されました(日本橋小学校は昭和24年9月に再開校)。
その後、小学校は日本橋小学校、恵美小学校と統合することとなり、2017(平成29)年3月末に閉校。同年4月、日本橋中学校の敷地に浪速小学校を新設し、施設一体型小中一貫校「大阪市立浪速小学校・日本橋中学校(通称・愛称:日本橋小中一貫校)」へと移行しました。日東小学校の跡地には、不登校を経験した中学生の通う昼間部と、義務教育終了の年齢を超過した方々が通う夜間部の2部制を敷く「心和中学校」が2024(令和6)年4月に開校しています。
幼稚園もまた、戦争のため一時閉鎖されましたが、終戦の翌年である1946(昭和21)年5月に再開され、1949(昭和24)年9月には小学校からの独立園となりました。1978(昭和53)年に新園舎を建設・移転して現在に至っています。
7.戦後の復興
戦災復興土地区画整理事業
戦後の浪速区は、人口が戦災前のわずか4%に激減し、当時、浪速区内の閑散ぶりを俗に「浪速村」と称されたほどでした。
戦災復興土地区画整理事業は、浪速区では5つの工区において実施されることとなり、日東地域は「東部工区」として、1949(昭和24)年6月に事業計画が認可されました。
日東町付近は1962(昭和37)年に事業が完了しましたが、それ以外のエリアは、阪神高速道路大阪1号線の建設や、国鉄と南海電鉄本線の立体交差に伴う南海電鉄新今宮駅の建設など新たな動きが生まれ、事業変更がたびたび行われたことから、1991(平成3)年にようやく事業が完了しました。
この事業により、広い道路やみどり豊かな公園が配置され、整然とした街並みができあがりました。日東地域では、関谷町公園(現在は日本橋小中一貫校の敷地)や日東公園、愛染公園がこの事業により整備されました。
また、地下鉄の整備もさらに進み、1969(昭和44)年には堺筋線のうち天神橋筋6丁目・動物園前間が、1993(平成5)年には動物園前・天下茶屋間が開通しました。
壊滅した古書店街の復興
1945(昭和20)年3月の大阪大空襲で、日本橋も大きな打撃を受け、古書店街も壊滅してしまいます。しかしそののち、日本橋は戦後の物資の供給地となり、日本橋筋界隈の露店のなかには、ラジオや無線機、真空管などの中古部品を扱う店もありました。戦時中に軍事用以外の電気製品の生産が完全にストップしたうえ、終戦を迎えてもメーカーは大きな被害を受けた工場設備の修復などで生産の見通しすら立たず、電気製品は世の中にはなかなか出回りませんでした。そこで中古の部品を買い集めて完成品を組み立てる「アマチュア」と呼ばれる人たちが日本橋付近に集まって活躍したのです。
日本橋にアマチュアが多かった背景には、戦中の松坂屋(現在の髙島屋東別館)店内に無線機製作部が開設されていたこととも関係があるといえるでしょう。戦時下で一般商品の販売もままならない中で無線機の組立工場となった松坂屋では、早川電気工業(現、シャープ)で技術研修を終えた大阪店の従業員が、多くのアマチュア達の指導にあたったのです。
日本橋電器街の形成
終戦直後の電器店では、電球やソケット、電線コードに加えて、ニクロム線を渦状に巻いた電熱器や、木箱の両端に銅板を張って電流を流して焼くパン焼き器もよく売れたといいます。
とりわけ政策の徹底のために情報伝達手段の整備を優先課題としていたGHQから生産指示を受けたラジオは重要な電気製品でした。ラジオを贅沢品とする戦前の物品税率が放置されていたため、完成品のラジオは当時の金額で1万5000円もしたそうですが、日本橋ではおよそ5000円で部品を買い揃えることができました。そのためアマチュアがラジオを組み立てて販売すれば1万円の儲けとなったわけです。ラジオ部品や電球の卸売りを行う「ラジオ屋」が、アマチュアが多く集まる日本橋で繁昌し、年々増えていったのは当然の成り行きでした。
終戦から2年もたつとようやくメーカーのラジオ生産も軌道にのり、生産台数も急増します。特に朝鮮戦争(1950年~53年)による特需景気で、良質で廉価な完成品が大量に出回るようになるとラジオ生産に携わるアマチュアも次第に影を潜めるようになりました。そのため日本橋で取り扱われる商品も、ラジオ部品に比してラジオ、アイロン、ミキサーなど完成品の割合が増えていきました。それにともなって卸売りが中心であった日本橋でも、一般の客の割合が増えていったのです。
まもなく真空管式からトランジスター式の小型で高性能のラジオが登場しました。こうして技術革新が進み、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など画期的な新製品が続々と誕生すると、日本橋はあらゆる家電が揃う電器街へ成長していきました。
変貌する日本橋
日本橋筋からなんさん通りにかけて広がる電器街の愛称である「でんでんタウン」は1978(昭和53)年に一般公募の中から選ばれました。1983(昭和58)年、日本橋筋の歩道のカラー舗装が行われ商店街としてのイメージアップが図られるとともに、道路の東西にわたっていた電線を地中に埋設させてすっきりとしたまちなみになりました。
現在、AV機器、パソコン、ゲームソフトなどの専門店がめだつようになったでんでんタウンには多くの若者が訪れ、1994(平成6)年の関西国際空港の開港以降、外国人の買物客の姿もめだつようになりました。
また現在では、マンガやアニメ、ゲーム、フィギュア、トレカなどといった様々なオタクアイテムを扱う店舗が集積しています。
さらに、2005(平成17)年より日本橋筋商店街を中心に開催されている「日本橋ストリートフェスタ」は、全国から1万人以上のコスプレ参加者を集める国内最大規模のコスプレイベントとして名を馳せており、国内はもとより海外にも広く発信されています。
年表
- 明治 2年(1869年) 大坂三郷廃止。長町は南大組の一部となる
- 明治12年(1879年) 日本橋筋(旧の長町)は南区の一部となる
- 明治22年(1889年) 大阪市制発足、日本橋筋は大阪市南区の一部となる
- 明治30年(1897年) 第1次市域拡張。今宮村、天王寺村の一部を市域に編入
- 明治31年(1898年) 高津入堀川・鼬(いたち)川連絡工事完成
- 明治41年(1908年) 市電南北線(梅田―恵美須町)開通
- 明治42年(1909年) 石井十次氏が愛染橋のそばに大阪市内で初めての保育所を開設
- 明治45年(1912年) 市電堺筋線(大江橋~日本橋筋3丁目)
- 大正 2年(1913年) 市電霞町線(恵美須町~霞町)開通
- 大正 4年(1915年) 市電西道頓堀天王寺線(桜川2丁目~芦原橋~大国町~恵美須町~天王寺西門)開通
- 大正13年(1924年) 天王寺第九尋常小学校創立(のちの日東小学校)
- 大正14年(1925年) 浪速区創設
- 昭和 7年(1932年) 日東幼稚園を小学校に附設
- 昭和 9年(1934年) 室戸台風襲来
- 昭和12年(1937年) 秩父宮両殿下が改良住宅を視察、愛染橋病院開院
- 昭和13年(1938年) 松屋町筋拡幅工事完成
- 昭和18年(1943年) 大阪市22区制により現浪速区となる(区域の変更により、日東地域全域が浪速区に属することとなる)
- 昭和20年(1945年) 爆撃により区域の93.4%が消失、終戦。枕崎台風襲来
- 昭和23年(1948年) 浪速警察署設置
- 昭和24年(1949年) 日東幼稚園を小学校から独立戦災復興土地区画整理事業の設計認可(東部工区)
- 昭和25年(1950年) ジェーン台風襲来
- 昭和32年(1957年) 高津入堀川埋立開始(~昭和39年に完了)
- 昭和36年(1961年) 第2室戸台風襲来
- 昭和37年(1962年) 東部工区のうち日東町付近の戦災復興土地区画整理事業が完了
- 昭和41年(1966年) 市電南北線のうち日本橋筋3丁目~恵美須町間、市電堺筋線のうち北浜2丁目~日本橋筋3丁目間、市電霞町線(恵美須町~霞町)廃止
- 昭和43年(1968年) 市電西道頓堀天王寺線(桜川2丁目~天王寺西門)廃止
- 昭和44年(1969年) 地下鉄堺筋線(天神橋筋6丁目~動物園前)開通
- 昭和50年(1975年) 浪速区老人福祉センター開館
- 平成 3年(1991年) 戦災復興土地区画整理事業が完了
- 平成 5年(1993年) 地下鉄堺筋線(動物園前~天下茶屋)開通
- 平成17年(2005年) 第1回 日本橋ストリートフェスタ開催
- 平成29年(2017年) 日本橋小学校・恵美小学校・日東小学校を閉校し、浪速小学校開校。「日本橋小中一貫校」として小中一貫教育開始
- 令和 6年(2024年) もと日東小学校に心和中学校開校
日東地域の史跡と名所
廣田神社(日本橋西2丁目4番)
廣田神社はもともと四天王寺の鎮守で今宮村の産土神とされています。天照大神の荒魂を祭る当社の創建年代は不詳ですが、廣田神社の名前は10世紀初頭の「延喜式」「神名帳」にみることができます。この廣田神社は摂津国武庫郡(現在の兵庫県西宮市)にある官幣大社のことで、平安中期以降にはその南方に摂社「浜の南宮」がおかれ、境内には漁業神としての戎神が祭られて西宮神社となりました。当地の廣田神社の南にも今宮戎神社があることから、両社は同時に武庫郡から勧請されたものと考えられています。
江戸時代には廣田の杜といわれる鬱蒼(うっそう)とした森の中に社があったそうで、当時の広い境内の西方には紅白2種の萩が植えられていたため、付近の茶店は萩の茶屋と称していました。萩之茶屋は現在も西成区に地名として残っています。
ところで当社の神前に奉納される絵馬には、神使としてアカエイ(関西ではアカエ)が描かれています。夏の美味とされるアカエの尾には鋸歯状のトゲがあり、これに刺さると激痛を感じるために、漁師はアカエを捕らえるとすぐに尾の付け根からぶっつりと切り落としてしまったそうです。漁民の多かったこの辺りでは、尾を断ち切ることと美味のアカエを断つことをかけて、断食して祈願すれば、トゲに刺された痛みにも似た疾患が失われるという信心が生まれてきたのでしょう。このように廣田神社は無病息災・難病治癒にご利益があるとされるほか、アカエは叡知の「エイ」に通じることから合格・必勝の祈願をかなえるともいわれ、広く信仰されています。

「広田社雪景(写真浪花百景 上編 中編)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

「広田星カ池稲荷 (浪花百景)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)
合邦辻(がっぽうがつじ)閻魔堂(下寺3丁目16番)
合邦辻は合法辻ともいわれ、一説に聖徳太子が物部守屋と仏法について議論を戦わせたことに由来するといい、閻魔堂も聖徳太子の開基と伝えられます。当時の大伽藍は消失して辻堂となり、明治中頃に融通念仏宗西方寺の境内に移されました。
浄瑠璃「摂州合法辻」の舞台となる閻魔堂もこのことで、俊徳丸の難病が治るという浄瑠璃のくだりから病気平癒の祈願に訪れる人もいます。

合邦辻閻魔堂
- 合邦辻閻魔堂の閻魔信仰習俗
市域にのこる死者供養の信仰習俗で、貴重な民俗文化財として「合邦辻閻魔堂の閻魔信仰習俗」が令和4年度大阪市指定文化財に指定されている
高津入堀川
高津入堀川は、日本橋筋の隆盛に伴って、長町から東、下寺町から西の土地に高津新地として新市街が建設されることとなり、これに伴って1734(享保19)年、長さ798メートル、幅16メートルの運河が開削されました。その後、1752(宝暦2)年、新地の南天王寺領に幕府が米蔵を設けた際、川の南端に東西29メートル、南北36メートルの船入堀を穿ち、運河とつながることとなりました。しかし、道頓堀川とつながるだけでは水運の便からも、流水の上からもしばしば停水して衛生の害もあったことから、1896(明治29)年に鼬(いたち)川と連絡することとなり、2年後の1898(明治31)年に工事が完成、最終的にその長さは2730メートルに及びました。その後、難波新川とも連絡することとなりました。
戦前、高津入堀川の川沿いの一部には、川の両側に貯木業者が並んでいました。いわゆる「木場」で、そこには多くの筏(イカダ)が組まれていて、半纏(はんてん)姿の職人が立ち働く姿を見ることができました。子どもたちにとっても筏遊びのできる絶好の場所でした。川の水も澄み、昭和15、6年までは魚釣りができたし、夏の暮れなどは近所の人々が縁台を出して夕涼みをとったそうです。
戦後は戦災による焼土の捨て場となり、船出橋・南日東間が1957(昭和32)年から1958(昭和33)年にかけて、南日東・堀切橋間が1958(昭和33)年から1964(昭和39)年にかけて、堀切橋から道頓堀川合流点が1958(昭和33)年から1962(昭和37)年にかけて埋め立てられました。
石井十次氏と石井記念愛染園
富国強兵を国是として、近代国家への道を急いだ明治期は、国家興隆という華やかな面と、そこから生み落とされる社会の影ともいうべき側面をあわせ持っていました。国家体制の確立を急ぐ政府は、社会的弱者に目を注ぐ余裕もなく、都市、農村を問わず窮民が増加し、路頭に迷うものが続出しました。国家の施策として何もなかったこの時代に、幾多の篤志家が立ち上がり、これら社会的困窮者の救済を行いました。その一人が岡山孤児院院長の石井十次氏です。
石井氏は宮崎県に生まれ、17歳でキリスト教信者となり、キリスト教が盛んに行われ、かつ医学校のあった岡山に居を定めました。
岡山医学校在学中の1887(明治20)年4月、遍路の子前原定一という少年との出会いが、孤児救済事業への出発点となり、同年9月、孤児教育会を設立しました。
石井氏は個人を集めて養育するという慈善性だけで孤児救済を行ったのではなく、孤児教育会と言う名称が示すごとく教育に主眼を置きました。石井氏は孤児教育論を1893(明治26)年10月26日の日記で「第一の救は職業を知らしむるにあり。第二の救は真理を知らしむるにあり。第三の救は神を知らしむるにあり、吾等は此の三つの救を多くの孤児に与へて、其の救をふせざる可からずてふ、予が教育論を告白する」と書いており、石井氏の事業はキリスト教の信仰と職業教育及び真理を知らしめる人間の教育にその基をおいているということができます。
1898(明治31)年、大阪府警察部長の鈴木氏より、大阪市内にいる約2千人の家のない子どもたちの対策について相談を受け、大阪の悲惨さを知って以来、大阪に対する関心が高まり、キリスト教の東洋伝道の拠点としての大阪と救済事業の拠点としての大阪を考えるようになりました。
産業の中心地大阪で発生している様々な社会問題に対処することが、児童救済の根本問題解決に通じることを悟り、1902(明治35)年、岡山孤児院大阪出張所設け、孤児の救済や貧児の保護、不良少年の感化、労働者子女の保育、労働者の保護(職業紹介等)などの事業を開始しました。
石井氏はペスタロッチ、ルソー、バーナードなどに心酔し、その影響と孤児教育の経験から、児童を孤児院において養育するよりも、家庭において養育することが優れていることを知り、「子どものいない母親に孤児を養育させること(里親)」その他の児童については家庭養育の方法を考えるべきであるとし、1909(明治42)年6月、彼の理想とする児童の家庭養育と教育の実践を目的に保育所と夜学校を設けるとともに、児童を取り巻く家庭と地域社会の自立を目的として日本橋同情館を開設しました。
愛染橋保育所は、1909(明治42)年6月7日に巡査の案内によって地域を視察し、愛染橋西詰の製材所跡を保育所候補地と定め、7月12日に開設、21日より児童を受け入れました。これは大阪で初めての保育所でした。
名称については、年報に「愛染橋保育所の場所は、前に高津入堀川を控え、天王寺につづく高台に接し、此処には有名なる愛染明王がまつられていて、保育所はその橋詰に設けられている。「愛染」とは保育事業に最も趣味ある名であると感じたところから、そのまま用うることにしたのである」と記されています。
愛染夜学校は、保育所と同じ建物の中で、同年7月13日より3名の児童をもって開始しました。当時、極めて多数の不就学児童がいましたが、開校直後、200名もの生徒が集まる状況であり、地域に学校ができたと大変な人気であったことが想像されます。開校10日目には「今夕より就学児童を謝絶し、不就学児童及び生徒のみを教授する事とす」とあるように、補習塾的な利用者もあったものとみられます。夜学校はのち石井記念愛染園に引き継がれて、愛染尋常小学校が開設され、1929(昭和4)年まで運営されました。
日本橋同情館は、保育所、夜学校に続いて、同年7月22日、日本橋5丁目に開設されました。無料職業紹介や低費宿泊、医療保護、免囚保護、売笑婦救済などの事業を行い、児童を取り巻く家庭や地域社会の環境整備を行いました。
このように、保育所、夜学校、同情館の3つの事業により園の基礎が築かれ、大阪市における民間社会事業草分けの役を果たしてきました。
産業革命を達成したわが国では、この頃より極度に中小商工業者を圧迫し、庶民の生活問題や労働問題が深刻となりました。社会的困窮者が増加し、都市周辺にそれらの人々が集中し、社会事業への要請が強くなり始め、石井氏のさらなる活躍が待たれましたが、病を得て1914(大正3)年1月、その生涯を閉じました。1909(明治42)年以来、総合的隣保事業として発足した岡山孤児院大阪分院事業は、「石井の事業は石井一代」のものとする後援者たちの手により終止符が打たれました。しかし、その後石井氏の最大の理解者であった倉敷紡績社長大原孫三郎氏ら後援者の手によって、1917(大正6)年、石井氏を記念する財団法人石井記念愛染園が創立され、石井氏の事業を継承することになりました。
創立決議後、園舎の新築が完成して開園式を迎えたのは翌年1月30日、石井十字氏永眠4周年の記念日でした。託児所、幼稚園、小学校、補習学校、保母養成所、研究室及び公開図書館、小児救療、保護者や卒業生への職業紹介、代書・代読、送葬費給与、伝道及び風紀衛生講話などの事業を行いました。
小学校は教育の中心として最も力が注がれた事業ですが、1929(昭和4)年に廃校となり、その後は現在の学童保育的な放課後の補導及び保護を行う学童保育部となりました。
1928(昭和3)年から1930(昭和5)年頃は隣保事業の最盛期で、その主なるものを列挙すると、日曜学校、聖書研究会、伝道会、イエス友の会、信交会、法制講座、保育講座、成人講座、生花会、卓球クラブ、図書クラブ、音楽クラブ、運動クラブ、登山会、文芸部、弁論会などがあります。
この間に愛染園周辺は市営住宅の建設等により変化しており、その変化に対応するために新しい機能を持った建物を改築することが1933(昭和8)年2月に決定されました。
愛染園の医療活動は「貧困の原因は疾病にある」との観点に立って、創立当初から医療活動を行ってきましたが、1930(昭和5)年に訪問保健婦事業、1934(昭和9)年には愛染橋診療所が開設され、その成果を土台に1937(昭和12)年6月、愛染橋病院が開設されました。診療のほか、保健相談、妊産婦相談、乳幼児相談、訪問看護婦制度、母親学校などの事業も行われ、当時としては非常に近代的な設備を持ち、予防を中心とした事業が実施されました。
戦災により病院を除く一切が失われましたが、1952(昭和27)年9月、本館が復興し、1934(昭和9)年以来中止していた隣保事業も再開され、病院事業と隣保事業を併設した社会福祉法人石井記念愛染園が完成しました。事業内容は、医療、健康相談、周囲市営住宅その他健康管理、保育所、児童教育、児童図書館などであり、いずれも地域における生活や保健などの課題に対応するものでした。
また、1962(昭和37)年10月には愛染橋児童館を開設し他に先駆けて学童保育事業を開始したほか、病院は1969(昭和44)年11月にベッド数293床の総合病院となりました。その後、病院は2005(平成17)年、現在の場所に移転しました。
公的な社会保障制度が未整備な時代に、大阪の地に社会福祉の先達となり、すでに100年を超える歴史を有する石井記念愛染園。日東地域にある本部を拠点に、現在は医療事業、隣保事業、介護事業の3事業を運営しています。
秩父宮同妃両殿下台臨記念碑(日本橋5丁目16番)
昭和の初期に、全国で初めての鉄筋コンクリート造りの市営住宅(南日東・北日東・下寺)が建設されました。
各戸に専用水道・水洗便所・ガス・調理台等を整備し、屋上には物干場、空地の一部は児童遊戯場、さらには屋内に2~3坪の共同作業場を有する堂々たる鉄筋3階建て住宅でした。
1937(昭和12)年2月17日に、秩父宮同妃両殿下がこの地へ行啓されたのを記念して、南日東住宅地内に、地元有志により記念碑が建立されました。
同市営住宅の老朽化により建替事業が進められ、それを機に2000(平成13)年7月に同記念碑が現在地(日本橋住宅4・5号棟)に移設されました。
参考資料
- 浪速区・まちの歴史
- 日東五十年誌
- 浪速区史
- 浪速区懐かしの風景画
- 甦えるわが街
- 日東幼稚園HP、心和中学校HP、大阪市立図書館HP、浪速区HP
- 社会福祉法人石井記念愛染園HP
- 大阪府商店街魅力発見サイト「ええやん!大阪商店街」、ウィキペディア、コトバンクなど
(注)この記事は地域の語り部の方々の発言をもとに作成しております。歴史考証はしておりませんので、予めご了承ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9683
ファックス:06-6633-8270
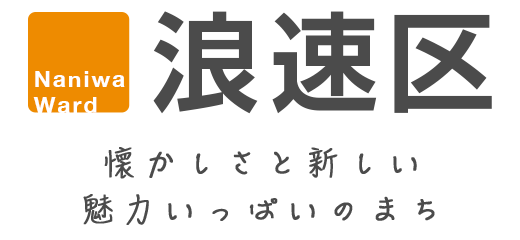





 SNSリンクは別ウィンドウで開きます
SNSリンクは別ウィンドウで開きます


