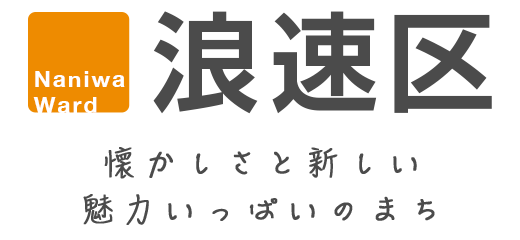浪速区制100周年プレ企画 ルックバック浪速区(第11回恵美地域)
2025年3月1日
ページ番号:648018
座談会
地域の皆さんにお話を伺いました

【参加者】
(後列左から)大原克美さん、田河和美さん、新井泰男さん、菅野喜久男さん、槇喬さん
(前列左から)鍋島加津子さん、朝野敏之さん、幡多区長、大南勇吉さん、髙橋慎太郎さん
俳人 小西来山
区長
では、遠い昔の恵美地域について教えてください。
新井さん
昔は海岸線に近かったんですね。恵美小学校の閉校記念誌を読むと、このあたりには「入船」「馬淵」「水崎」といった水に関係する地名が多く残っていた、と書かれています。確かにこの地域は、ボーリングするとわかりますが、砂地です。天王寺のお寺が並んでいるところが昔は海岸だったらしいですよ。
区長
そして、このあたりは江戸時代、「今宮村」と呼ばれていたそうですね。
菅野さん
恵美地域のほかに、西成の地域も今宮村に含まれていたと思います。
新井さん
廣田神社の氏子区域が、ちょうど今宮村だったのかもしれませんね。
区長
その今宮村に居を構えた、恵美地域ゆかりの人物が小西来山ですね。
大南さん
1654年(承応3年)に今の中央区の薬種問屋に生まれた、元禄時代の代表的な俳人です。晩年にこの地に居を構えて「十萬堂」と名付けて閑静な余生を送りました。住居は戦災で焼けてしまいましたが、その石碑が恵美須西2丁目に建っています。
大阪の真ん中に住みながら、「お奉行の 名さへ覚えず 年の暮」という句を詠み、それが奉行の耳に入って立腹され、この地に移ってきたそうです。「時雨るるや しぐれぬ中の 一心寺」という句は、十萬堂から一心寺までの当時草原だった情景を眺めて詠んだと言われていて、一心寺に句碑があります。墓は一心寺と、今宮戎神社の隣にある海泉寺にあります。
まち工場が多かった、かつての恵美地域
区長
村はその後大阪市に帰属し、地名や町名も時代とともに変わりました。先ほど、「入船」「馬淵」「水崎」といった地名が出ましたが、どのあたりだったのでしょう。また、どんなまちだったのでしょうか。
菅野さん
今、「YOLO BASE」があるあたりが「馬淵町」でした。馬淵町には昔、「ケンコーチョコレート」という工場がありました。
槇さん
「アライ鉱泉」というラムネ屋さんもあったんじゃないかな。
鍋島さん
私が1968(昭和43)年にお嫁に来た時の住所が「馬淵町」でした。馬淵町にはまち工場が多かったんですよ。金属工場のほかに、化粧品の工場もありました。
大南さん
はい。今の星野リゾートのある場所には昔、「中山太陽堂」のクラブ化粧品の工場がありました。
槇さん
あのあたりを通ったら、化粧品のよい匂いがしたのを覚えています。
朝野さん
友だちがそこに働いていて、その化粧品をよくいただきました。
新井さん
馬淵生活館が建つ前は鉛筆工場がありました。工場がなくなった後に、その裏手の野山のようになっているところを掘ったら、鉛筆の芯がいっぱい出てきました。
区長
戦争で焼け野原になった後、この地域にはいろんな工場が建ったんですね。大原さんは戦前のお生まれですが、戦争の記憶はありますか。
大原さん
私は大阪大空襲の経験をしました。6歳の時でした。このまちの中を逃げまどったのを覚えています。もう、凄かったですよ。焼夷弾のせいで、広い道路も何もかも燃えていました。母に手をつながれて天王寺駅まで逃げました。道中、焼死体がたくさんありました。昔は馬が交通手段だったので、かわいそうに馬の死骸もたくさんありました。天王寺駅に着いたら、驚いたことに国鉄は動いていました。空襲であっても動いていたんです。その国鉄に乗って奈良に疎開しました。
槇さん
今宮戎神社も戦争で焼けてしまいました。私が大阪に来たのは1954(昭和29)年頃でしたが、その頃、神社の再建のために道端で大工さんが材木を削ったりしていたことを覚えています。
区長
恵美地域といえば、今宮戎神社と十日戎も有名です。
新井さん
神社の創建は、西暦600年と伝えられています。
菅野さん
私は1947(昭和22)年生まれですが、小学生の頃の十日戎の露店は、神社のまわりと廣田神社まで、神社の東門から堺筋までの間しかなくて、今ほど広くはありませんでした。今の阪神高速道路の下は、昔は川だったんですが、それが埋め立てられてから、露店が広がったんだと思います。
今はなき、川、橋、そして市電
菅野さん
ちなみに川には橋が架かっていて、今宮戎神社の北側にあったのが廣田橋。紀州街道に架かっていたのが夕日橋です。

昭和23年頃の恵美地域周辺の地図。現在の阪神高速道路があるエリアには、川(高津入堀川)が流れ、「広田橋」「夕日橋」が架かっていたのがわかる。
大原さん
昔、「十津川屋」といううどん屋さんがあって、橋がなくて皆、困っていたので、そのうどん屋さんが私財で、そんなに立派ではない細い橋でしたけど、川に木の橋をかけたんですよ。その後に、夕日橋ができました。
区長
その川は高津入堀川のことですね。恵美地域の中を流れていたんですか。
朝野さん
恵美地域と日東地域のちょうど境界のところを流れていました。
区長
どんな川でしたか。
槇さん
材木がいっぱい浮かんでいました。川べりには材木屋が多かったです。川から材木を引き上げて作業場で製材をしていました。作業場の上階に人が住んでいました。表の道路から見ると地下が作業場で、1階部分が住む家になっていました。
菅野さん
材木は木津川の方から流していました。台風で高潮が来そうな時には、地下の作業場の資材や家財を高いところに上げるんです。昔、その手伝いをした記憶があります。川べりには材木屋のほかに、瓦屋さんや砂利屋さんもありました。
川はいわばドブ川で、メタンガスがボコボコ湧いていました。トンボをとったり、魚をすくったりしましたが、僕が小学生の頃は、汚くて泳げるような状態ではありませんでした。
大原さん
当時は、糞尿を載せた船も通っていましたので、きれいではなかったですね。
区長
堺筋も恵美地域の方々にとっては身近で、昔から生活に欠かせない道だったと思います。何か思い出はありますか。
大南さん
阪神高速道路のえびす町入口の東側の、今、ローソンがあるところに以前は三和銀行が、西側のセブンイレブンがあるところには協和銀行がありました。
槇さん
三和銀行は石造りのしっかりした良い建物でした。真鍮(しんちゅう)の扉が正面にありました。
大南さん
堺筋には市電が走っていました。以前、フェスティバルゲートのあった所は、「霞町」という名前だったんですが、そこから市電に乗って旭区の大阪工業大学の高校に通っていました。堺筋を越えて、北浜、天神橋筋6丁目、そして太子橋の手前まで乗っていきました。私が高校2年の時ですから、1966(昭和41)年だったかな。市電が廃止になって、その後は市バスに乗って天六で乗り換えて、そこから大宮町まで市バスに乗って通学しました。
堺筋の地下鉄工事はオープン工法といって、トンネルではなくて、地表面から下に掘り進めて、鉄くいを打ち込んで、その上に鉄板を敷いて、路面の交通に支障がないようにした後に、さらに掘り進めていく方法ですが、その工事の最中に、天六でガス爆発が起きて鉄板が全部、上に飛んでしまいました。ガス管がぶら下がった状態になっているところに、何かで引火して爆発したんでしょう。当時、ちょっとした大事件だったんですよ。
菅野さん
市電といえば、私は花電車を思い出します。電車に電飾をして、パレードというのかな。走らせていたのを覚えてます。

花電車(写真提供:Osaka Metro)
大原さん
私は、花電車に乗ったことがあります。天六まで乗ったんですが、沿道の人が皆、見ているので、自分が偉くなったような気がしました。うれしかったですね。
区長
その市電は、どういうルートだったんでしょうか。
大南さん
霞町が始発駅になっていまして、そこから、日本橋5丁目、4丁目、3丁目、2丁目、1丁目、長堀、八幡筋、そして天六まで。天六からは都島線が出ていました。シートが堅かったので長く乗るとお尻が痺れました。
朝野さん
私が市電に初めて乗ったのは、1958(昭和33)年のことでした。田舎で学校を卒業して、翌日に大阪に来ました。迎えに来てくれたおじさんたちと一緒に大阪駅から市電に乗って、霞町まで来ました。15歳でした。
槇さん
今宮戎神社の前にも市電の駅がありましたよ。
恵美小学校の思い出
区長
恵美小学校のことを伺いたいと思います。何か思い出があれば、教えてください。
大原さん
先ほど、戦災のことをお話ししましたが、恵美小学校だけは、かろうじて燃え残ったんです。私は小学4年生の時にこちらに戻ってきたんですが、校舎もそのまま残っていました。でも、火が入っていたので、コンクリートの階段は、端っこに乗ったら角がボロボロと欠けていました。修理なんか、すぐにはできないですからね。
その頃の学校の給食はとても粗末なものでした。
区長
戦後まもなくでも給食はあったんですね。
大原さん
大きなパンは全然、味がしませんでした。それと牛乳かスープかよくわからない飲み物が給食でした。おいしくなかったです。
大南さん
コッペパンと脱脂粉乳だけだったんですね。
大原さん
パンだけは大きかったです。
菅野さん
私も恵美小学校の卒業生ですが、昔の暖房器具は石炭ストーブでした。冬は、当番の児童が、石炭小屋まで一輪車で石炭を取りに行っていました。
新井さん
昔の小学校の運動会はすごかったですよ。親御さんらが、運動会の前の晩から席を取りに来て、当日は自分の子どもを一生懸命、応援していました。
田河さん
私は1961(昭和36)年生まれで、恵美小学校の卒業生です。今の運動会は半日開催になっているようですね。昔は家族がお弁当を持ってきてくれて、昼休みに一緒に食べました。昨年の運動会では、見守り活動を通じて知り合った児童に「運動会、応援に行くよ」と約束をしていたのですが、気軽に声をかけられる雰囲気ではなく、自分の頃の運動会と比べて寂しいなあと感じました。
新井さん
昔は運動会で1等をとったら、鉛筆やノートをもらえた時代もあったようですよ。
田河さん
私が小学生の頃は児童の数も多くて、1学年5クラスくらいありました。そのためクラス替えのたびに、友だちとはバラバラになりますが、また新しい友だちができる楽しみがありました。
今、子どもたちの登校の見守り活動をしていて、少し気になっていることがあります。信号のある横断歩道を渡る時、赤に変わりそうなのに慌てることなく、信号を気にせずに渡ろうとすることです。危ないので注意を促すのですが、なかなかわかってくれない子どももいます。常に声かけはしていこうと思っています。
区長
恵美小学校には、株式会社クボタの創業者である久保田権四郎氏から寄贈された銅像があったと聞きましたが。
大南さん
二宮金次郎の銅像ですね。
髙橋さん
学校の池の横にありましたね。それから正門のところに「残念石(注)」がありました。閉校する時にどちらも残したかったんですが、保管場所がないと言われました。かろうじて学校のプレートだけは残しています。
恵美小学校は、ICT教育も盛んでした。全生徒にタブレットが配られたのは、たぶん恵美小が1番早かったと思います。
ロボットも、日本橋のメーカーさんや電子部品屋さんがたくさん持ってきて、指導もしてくれました。全国大会にも出ていたんじゃないですかね。そういえば、算数の全国大会で、タイトルをとった子もいました。
(注)残念石:大阪城の石垣に選ばれながら石垣になれなかった小豆島の石のこと
懐かしの夜鳴きそば
区長
戦後、恵美地域でも区画整理が行われました。何か、エピソードはありますか。
新井さん
区画整理で、うちはだいぶお金をもらいましたけど、その代わりに土地はもとの3分の1ほど提供しました。
昔はずらっとバラック建ての家が並んでいて、大勢の人が住んでいました。当時、バラックに住んでる子がいて、学校帰りにその子の家に付いて行ったことがありましたが、来た道がわからなくなって、1人では出られなくなるような場所でした。共同トイレがあったんですが、トイレの周りに注射器がいっぱい捨ててありました。後で、それがヒロポン(注)だったとわかりました。
(注)ヒロポン
メタンフェタミン塩酸塩の商品名。覚せい剤。覚せい剤取締法公布以降は「限定的な医療、研究用途での使用」にのみ厳しく制限されている。
鍋島さん
あの頃は、あそこには絶対に近づかないようにと言われていました。
新井さん
何回もそこで火事が起きて、そのたびに10軒か15軒ほどの家が燃えてなくなりました。住むところがなくなった人たちをどうにかしないといけないということで馬淵生活館が建てられて、そこに入られたんですが、それは市営住宅ではなかったそうで、最後の立ち退きの時、揉めている話を聞きました。
区長
恵美公園も区画整理でできたんでしょうか。元からあったんですか。
朝野さん
もとは広場だったところにバラックが増えていったんですが、そのバラックを整理して、今の公園になったのだと思います。
夜鳴きそばの屋台のリヤカーもずらっと並んでいました。今のように24時間営業のファミリーレストランなんかありませんでしたので、僕らのように夜間に工事をするときは、夜鳴きそばが1番助かりました。夜鳴きそばの屋台が音を鳴らしてやって来るとそれを止めて、よく食べていました。結構おいしかったですよ。その屋台の溜まり場があって、夜になるとそこから皆、リヤカーを引いて出ていくんです。40から50台ほどあったと思います。
大南さん
昼頃から皆さん、一生懸命、そこで仕込みをしていました。
住みやすいまちをめざして
区長
では最後に皆さんに、この恵美地域への思いやこれからの期待についてお話いただきたいと思います。
菅野さん
コロナ禍以前からインバウンドの影響で、ホテルやマンション、民泊が増えて、環境がすごく変わりました。歴史や伝統を大切にしながら、今、髙橋さんがやってるような、新しい活動やイベントを続けてもらって、我々もそれに協力して、恵美に住みたいと思う人に集まってもらえるように努めていきたいと思います。
新井さん
恵美地域は大阪市内でも特に「忘れられたまち」だと感じています。最近やっと、南海がこの地域に注目して、新今宮の駅をきれいにし、YOLO BASEができました。星野リゾートも来ました。では、もっと商業地として発展させていくのか、それとも住宅地として残していくのか。このままだと大きな企業さんに飲み込まれて、住みにくいまちになっていくのではないか。
私は、これまで何十年も、新今宮の駅をどこにも負けないきれいな駅にしてほしいと言ってきました。星野リゾートができましたが、新今宮は西成区側よりも浪速区側の方が遅れてると感じています。新今宮は良いまちだと言われるように、でも住む人が住みにくいまちにならないように、地域で考えていかなければならないと思います。
朝野さん
新今宮をきれいなまちにするのに、星野リゾートのホテルが建ったのは失敗だったと思います。役所の建物を建てるべきでした。あれが建ったために、新今宮の開発に対して、地域は何もできなくなっているんじゃないか。インバウンドの客は入っていますが、それがダメになった時にどうなるのか。これから商業地として、大きな企業を中心に開発が進んでいくと、一般の人たちがまちでイベントをすることができなくなるのではないか。
実際に、ホテルやマンションが建ち、民泊ができて、一般の人たちが住めない状況になりつつあります。商業にもっと力を入れて開発をした方が、人が集まるんじゃないか。でもそうなると、一般の人たちは外に追いやられるかもしれません。
どちらをとるかは難しいですが、私は急務は駅前再開発と商業施設、美しいまち並みにしないと人は集まりません。更地はダメです。緑があるまちは発展します。今更、遅いかもしれませんが、まだ望みはあると思っています。
大南さん
恵美地域は今まで住宅地だったのが、だんだん商業化してきています。南海さんにしても「EKIKAN」を延ばしてくるだろうし、恵美小学校の跡地に商業施設を建てたい意向もあるんじゃないかと思います。新今宮と難波が発展すれば、この地域にも人の流れが出てくるでしょう。私は、この地域は商業的に発展すると良いと思っています。
なにわ筋線が入ってきたら、またイメージが変わるのではないかと思います。南海やJRのホームを広げたり、エレベーターやエスカレーターをつけるのに、今は敷地がありませんが、なにわ筋線を整備する時には新しいホームができるはずです。その時にしかJRは動かないでしょう。
星野リゾートができる前は、毎年何をするのかを計画で決めて実行していましたが、その後の計画のことや、なにわ筋線ができあがった時に南海のホームがどうなるかについて、まだ何も聞いていません。今は、線路が来るとしか聞いていないので、詳しい情報を地元に伝えてほしいです。
恵美小学校の跡地の活用も延び延びになっています。公園にした時のイメージの話は聞いていますが、何年に完成させます、といった話はまだありません。
槙さん
私は長屋に住んでいるんですが、空いたところは民泊になってしまうんです。昔は皆でお金を積み立てて、年に1回くらいは浜寺公園や京都に行ったりしていました。そういう付き合いがだんだんなくなって、今では近所の方が亡くなっても、知らなかったということが多いです。
町会の役員をしてくれる人を見つけるのも大変です。昔のような人と人とのつながりが強いまちになってほしいですね。
区長
ファミリー向けのマンションが建つような話があれば、町会に入っていただけるよう、区役所も一緒に働きかけをしますので、教えてくださいね。
鍋島さん
私が嫁に来た時から比べたら、今はものすごく住みよいまちになりました。昔は下着1枚で歩いてる人や、お酒飲みの人が多かったです。遊びに来た友だちに「このまち、臭いね」とよく言われました。今は、もっと公園がきれいになればよいと思います。若いお母さん方は「子どもを遊ばせるところがない」と困っておられます。それで他所に行ってしまうんです。きれいなまち、住みよいまちにしてもらいたいです。
大原さん
私はこの恵美地域が好きです。子どもは2人とも遠くに住んでいて、引っ越しておいでと言われるんですが、頑張って1人で暮らしています。昔は槙さんの家の近くにお地蔵さんがあって地蔵盆もあったし、近所の人がバイオリンを弾いたし、歌を歌ったり、そんな楽しいまちでした。今は全然違って、うちの家の通りは民泊通りと言われるほどになっていますが、それでもやっぱり、ここが好きなんですね。
田河さん
親しみやすい、住みやすいまちであったらいいなと思います。担い手の方が本当に少ないので、私たちの世代や、まだ働いている人も含めて、何らかの形で声をかけるなりして、担い手を増やしていきたいです。
最近、気になっていることは、災害が起きた時の避難所のことです。私たちの地域の避難所は民間施設になっています。先日、訓練がありまして、女性専用待機場所のフロアを決めていただいていましたが、訓練の準備をしている時にそこに住んでいる方とすれ違ったりして戸惑いました。公共施設なら、本当に必要な訓練ができたのではないかと感じて、非常に残念に思いました。
大南さん
小学校であれば、ぼくらが訓練をしたいと思えばできますが、今の施設は「他の予定があるので日を変えてほしい」などと言われます。民間の施設を避難所にするのは無理があると思いますね。今回の訓練の時も「今日は上の階は使えません」と言われました。住民の皆さんに一緒に上がって見てもらいたかったんですが、それができませんでした。
区長
そういう不自由な側面もあるかもしれませんが、一方で、若い人たちが住んでおられるのは強みで、いざという時には頼りになると思います。
使い勝手の悪いところがあれば、一緒に改善していきましょう。
恵美地域の歴史
1.古代から中世
今宮戎神社の創建は西暦600年と伝えられ、四天王寺建立にまでさかのぼります。四天王寺の西を守る存在として建立されましたが、当時、このあたりは海岸線に近く、付近には「入船」「馬渕」「水崎」といった水に関係する地名が多く残されています。特に海を連想させる文字が使われた地名が多いことから、かつてはこのあたりが海岸線にあったことがわかります。今宮の人々は、魚を朝廷に献上する習わしがあり、毎日平安京まで帝が食べる魚を献上していたという記録が残されています。戦乱により、中断されていた時期もあるようですが、江戸時代の記録によると、今宮村の庄屋が年始に鯛2匹を朝廷に献上し、その後京都所司代等を挨拶回りするのが習わしであったと記録されています。
室町時代と思われる地図には、四天王寺から西に延びる道と南北に延びる街道の交わる点に「今村」と記された集落があり、近くに鳥居が描かれています。これが現在の恵美須町付近にあたります。今宮戎については、今村につくられた神社であることから、今宮と呼ぶようになったという説も残されています。
室町時代から安土桃山時代にかけて、大阪は幾度も戦乱に巻き込まれました。しかし江戸時代には船場を中心に大阪のまちが作られ、商都大阪の礎となるまちがかたち作られました。当時の大阪のまちは現在の大阪市よりはるかに狭く、今宮の村は神社周辺を除けば畑が広がる長閑な地であり、大阪のまちに野菜を供給する「畑場八カ村」の1つでした。
また地図では現在の堺筋、国道25号線といった幹線になる道路が既に形作られており、当時の今宮が人々の行き交う地であったことがわかります。
江戸時代には、十日戎はすでに現在のような賑わいであったと伝えられています。当時の様子を描いた住吉名勝図会には、大勢の参拝客で今宮戎神社の境内が埋め尽くされている様子が描かれています。笹を持って歩く人も描かれており、現代の十日戎と同じような様子であったことがわかります。
2.明治時代から昭和初期
明治初期には、このあたりは今宮村と呼ばれており、大阪市には含まれていませんでした。今宮村は、北端が現在の浪速区役所周辺、南端が西成区役所周辺、東西はほぼ現在の恵美・新世界にあたる南北に細長い村でした。当時の今宮村は、神社を中心に南北(紀州街道) ・東西(後の国道25号線)に延びる道を中心に集落が広がっているものの、まだまだ民家はまばらで畑が広がる地でした。神社周辺には樹木が茂り、うっそうとした森の中に神社は佇んでいました。
今宮村の子どもたちが通うため、1873(明治6)年3月、第6大区1小区第1番小学校(通称 今宮小学校)が開校しました。後の恵美小学校です。開校当時の児童数は100名あまりでしたが、大阪の南にある小学校としてどんどん発展を遂げていきました。
1889(明治22)年、大阪市が誕生。当時の大阪市は今より狭く、今宮村は大阪市には含まれていませんでした。同年、大阪鉄道(後のJR関西本線)が今宮村を横切るように開通しました。1897(明治30)年、大阪市の第1次市域拡張に伴い、線路の北側だけが大阪市に編入されて南区の一部となりました。
恵美地域には以前、運河が流れていました。18世紀中頃に開削された、道頓堀川から延びる高津入堀川を鼬(いたち)川、難波新川と連絡することとなりました。現在の下寺と日本橋東の間に高津入堀川を延長させ、その後西に屈曲して現在の浪速警察署の北側を通り、さらに北折して鼬川と接続させる工事が実施され、1898(明治31)年に完成しました。
運河には広田橋、夕日橋などが架けられ、水運にも利用され、川べりには材木商が多くありましたが、堀川の水路としての意義は、市電網の整備にともなって次第に失われていきました。戦後まもなく埋め立てられた高津入掘川の跡地上には現在、阪神高速道路環状線が通っています。
1900(明治33)年に町名改称が行われ、それまでの字名から恵美須町、水崎町などの新しい町名が生まれました。しかし、市部に編入されたとはいえ、まだ畑地の多い地域でした。
この地が大きな転機を迎えたのは、1903(明治36)年に現在の新世界から天王寺公園にかけての一帯が第5回内国勧業博覧会の会場として整備されたことです。内国勧業博覧会は、明治時代に政府主導で開催された博覧会で、この地で開催された第5回博覧会は、規模も入場者数も第4回までを大幅に上回る大盛況となり、その後の博覧会へも大きな影響を与えました。
博覧会終了後は会場の西半分が新世界、東半分が公園として整備されることとなり、同時にこの時期、陸上交通網も格段に発達しました。
1907(明治40)年、南海鉄道(後の南海電鉄)が恵美須町駅を開設(1915(大正4)年、今宮戎駅に改称)したのに続き、1911(明治44)年には阪堺電気軌道が恵美須町-堺市大小路間を開通させました。
市電は1908(明治41)年に南北線(梅田-恵美須町)が開業し、この後も1913(大正2)年に霞町線(恵美須町-霞町)、1915(大正4)年に西道頓堀天王寺線(桜川2丁目-芦原橋-大国町-恵美須町-天王寺西門)が開通しました。
明治末年には自動車交通も確立し、第5回内国勧業博覧会では自動車の試運転が行われましたが、これが機縁となって中川辰之助ら有志がアメリカから2台の蒸気自動車を購入し、恵美須町から梅田に至る乗合自動車の営業を始めました。この蒸気自動車の営業運転は 市電南北線等の開通にともなって廃止されましたが、1924(大正13)年から大阪乗合自動車株式会社が市内中心部の主要道路に青く塗装したバスを走らせました。市営バスも1927(昭和2)年に開始され、先発の青バスに対し、銀色の市バスは銀バスの愛称で呼ばれたそうです。
1912(明治45)年、新世界が誕生しました。当時、海外旅行に誰もが行ける時代ではありませんでしたが、ここに来れば世界各国の雰囲気を体験できることから「新世界」と命名され、初代通天閣を中心に多くの施設が並びました。
初代通天閣はエッフェル塔と凱旋門をモチーフにしており、アーチ状の門の部分には見事な壁画が描かれていました。通天閣南側にはルナパークができ、料亭など飲食店が軒を連ねて大変に賑わいました。
恵美須町では市電や阪堺線など交通網も充実しており、南海鉄道の今宮戎駅も近く、恵美須町周辺は大阪南のターミナルとしても繁華街としても大きく発展しました。
小学校の児童数も増加し、明治末期には児童数が500名を超える大規模校となりました。それへの対応として、1904(明治37)年と1919(大正8)年に、それぞれ小学校が分離独立しています。
3.戦後の復興
1945(昭和20)3月の第1次大阪大空襲により、浪速区は区域面積の約93%を焼失し、一面焼野原となりました。これ以降も空襲はやむことなく、終戦前日までの市内への空襲は28回に及びました。
戦後の浪速区は、人口が戦災前のわずか4%に激減し、当時、浪速区内の閑散ぶりを、俗に「浪速村」と称されたほどでした。
戦災復興土地区画整理事業は、浪速区では5つの工区において実施されることとなり、恵美地域は「東部工区」として、1949(昭和24)年に事業計画が認可されました。
土地区画整理事業は施行対象の区域が広範かつ事業内容が多様で、施行期間が長期に及ぶため、区域内外の道路や交通事情、社会情勢の変化が生じます。浪速区も例外ではなく、「東部工区」では阪神高速道路大阪1号線の建設、国鉄と南海電鉄本線の立体交差に伴う南海電鉄新今宮駅の建設など、新たな動きも出てきました。これらの動きや変化に対応するため、東部工区では7回に及ぶ事業変更が行われ、1991(平成3)年にようやく事業が完了しました。
この事業により、広い道路や公園が配置され、整然としたまち並みができあがりました。恵美公園もこの事業により整備されました。
戦後、馬淵町でアパートが増加し、恵美須町3丁目には人家が密集していましたが、数度の火災で焼失し、現在は恵美コミュニティプラザとなっています。
戦後、まち並みの整備は進みましたが、子どもの数が減少し、恵美小学校の児童数は年々減少していきました。近隣の小学校も同様の傾向を辿っていたため、3つの小学校を統合することが決定され、2017(平成29)年4月から浪速(なみはや)小学校(通称 日本橋小中一貫校)として新たなスタートを切ることになりました。交通の利便性は、戦後さらに充実が図られました。戦前よりあった大阪環状線の構想が戦災復興事業によりついに実現し、1961(昭和36)年に開通、1964(昭和39)年に環状運転が開始されました。同年、国鉄(後のJR)新今宮駅が新設され大阪環状線の列車が停車するようになり、2年後には南海電鉄の新今宮駅が開業して乗換駅になりました。さらに1972(昭和47)年には、国鉄関西本線の列車も停車するようになり、大阪市外からの交通条件も格段に良くなりました。
市民の足として長年親しまれた市電は、地下鉄にその地位を譲り、1969 (昭和44)年には完全に姿を消しましたが、同年に地下鉄堺筋線(天神橋筋6丁目-動物園前)が営業を開始。天神橋筋6丁目駅で阪急電鉄と接続することにより、翌年の日本万博博覧会の期間中は会場輸送線としての役割を担いました。
1994(平成6)年に関西国際空港が開港しました。新今宮駅は空港とも直結し、国際都市大阪の「南の玄関口」としての活躍がスタートしました。
4 新今宮駅北側のまちづくり
新今宮駅と動物園前駅は、南海本線、南海高野線、JR関西本線(大和路線)、JR大阪環状線、大阪メトロ御堂筋線、大阪メトロ堺筋線、阪堺線の計7路線が乗り入れる、大阪市内でも有数の交通結節点となりました。大阪・梅田やなんば、天王寺・阿倍野に加え、広域交通の拠点である新大阪や関西空港にも直結し、奈良や大阪南部・和歌山方面へのアクセスにも優れています。2031年に開業予定のなにわ筋線が乗り入れることにより交通結節性のさらなる強化も期待されています。
また、新今宮駅北側では近年のインバウンドを始めとした来街者の増加に伴い、宿泊施設等の建設・開業が進んでいます。2022(令和4)年4月には、以前、化粧品会社や金属会社の工場で、大阪市が取得したものの長い間、使用されずにあった土地に「OMO7(おもせぶん)大阪 by 星野リゾート」が開業しました。
かつて生活困窮者等のための宿泊施設であった「馬淵生活館」の跡地には、2019(令和元年)年9月に日本初の外国人向け就労トレーニング施設として「YOLO BASE」が開業し、外国人の就労支援や暮らしのサポートをワンストップで提供しています。2024年(令和6)年には「YOLO BASE」に隣接して、文理融合型のIT技術活用人財を育成するエール学園ICT校が開校し、海外からの留学生の受け入れを積極的に行っています。
浪速区では、2020(令和2)年9月、まちの変化が進む新今宮駅北側エリアにおける、観光やにぎわいづくりの視点を踏まえた、概ね5年から10年のまちづくりのビジョンを策定しました。
このまちの特性や課題、地域の方々の思いを踏まえ、『新たな大阪の玄関口となる「訪れてよし・住んでよし」のまちに』をめざして、快適な歩行者空間の創出や玄関口にふさわしいおもてなし環境づくり、賑わい・憩い空間の創出、乗り換え導線の強化等に向けた駅改修の方向性の決定、駅周辺における適正な放置自転車対策などに官民連携で取り組んでいます。
年表
- 明治 6年(1873年) 今宮村戸長役場にのちの恵美小学校開校
- 明治 8年(1875年) 市郡を通じ大小区制定。南大組を第二大区、西大組を第三大区、東成郡を第五大区、西成郡を第六大区とする※現在の日本橋、日東、難波元町、塩草の一部は第二大区、浪速の一部、幸町は第三大区、日本橋、日東の一部、下寺は第五大区、浪速、難波元町、塩草、日本橋、日東の一部、立葉、敷津、大国、恵美、新世界は第六大区となる
- 明治12年(1879年) 郡区町村編成法により四区役所及び郡役所を開設、第二大区は南区、第三大区は西区、第五大区は東成郡、第六大区は西成郡となる
- 明治22年(1889年) 大阪市制発足(東・西・南・北区)
- 明治30年(1897年) 大阪市第一次市域拡張
- 明治31年(1898年) 高津入堀川・鼬(いたち)川連絡工事完成
- 明治40年(1907年) 南海鉄道(現 南海電鉄)恵美須町駅(現 今宮戎駅)開設
- 明治41年(1908年) 市電南北線の梅田―恵美須町間が開通し三日間、花電車運転
- 明治44年(1911年) 阪堺電気軌道が恵美須町-堺市大小路間を開通
- 大正 2年(1913年) 市電霞町線(恵美須町-霞町)開通
- 大正 4年(1915年) 市電西道頓堀天王寺線(桜川2丁目-芦原橋-大国町-恵美須町-天王寺西門)開通
- 大正 7年(1918年) 市電霞町玉造線の霞町-阿倍野橋間が開通
- 大正13年(1924年) 高津入堀川に名呉橋を架橋
- 大正14年(1925年) 大阪市第二次市域拡張に伴い大阪市13区制になる。旧南区から分かれ、浪速区創設。
- 昭和 9年(1934年) 室戸台風襲来
- 昭和13年(1938年) 南海鉄道(現 南海電鉄)が難波-天下茶屋間の高架工事完成
- 昭和16年(1941年) 太平洋戦争起こる
- 昭和20年(1945年) 爆撃により区域の約93%が消失。※空襲前12万7千人の人口がわずか4,749人に減少。終戦。枕崎台風襲来。
- 昭和21年(1946年) 桜川、芦原は立葉に、難波、塩草、稲荷は元町に、浪速津、戎は恵美に、南栄、東栄は栄に、敷津は大国に、日本橋、浪速津、逢阪は日東に、それぞれ国民学校を統合
- 昭和24年(1949年) 戦災復興土地区画整理事業の設計認可(東部工区)
- 昭和25年(1950年) ジェーン台風襲来
- 昭和32年(1957年) 高津入堀川埋立開始(~昭和39年に完了)
- 昭和36年(1961年) 第2室戸台風襲来
- 昭和39年(1964年) 国鉄(現 JR)大阪環状線の完全環状運転開始、新今宮駅開設
- 昭和41年(1966年) 市電南北線のうち日本橋筋3丁目-恵美須町間、市電霞町玉造線(霞町―阿倍野橋)、市電霞町線(恵美須町-霞町)廃止。南海電鉄が新今宮駅開設。
- 昭和43年(1968年) 市電西道頓堀天王寺線(桜川2丁目-天王寺西門)廃止
- 昭和44年(1969年) 地下鉄堺筋線(天神橋筋6丁目-動物園前)開通、恵美須町駅開設
- 昭和45年(1970年) 市内主要道路(御堂筋・松屋町筋・四つ橋筋・堺筋)一方通行実施。阪神高速道路14号松原線(日本橋東付近(現在のえびすJCT)-阿倍野間)、15号堺線(湊町-堺)開通。
- 昭和47年(1972年) 国鉄(現 JR)新今宮駅に関西本線の列車の停車開始
- 昭和53年(1978年) 恵美公園開園。恵美コミュニティプラザオープン。
- 昭和60年(1985年) 住居表示完了
- 平成 3年(1991年) 戦災復興土地区画整理事業(湊町工区と、東部工区の残り部分)が完了
- 平成29年(2017年) 日本橋小学校・恵美小学校・日東小学校を閉校し、浪速小学校開校。「日本橋小中一貫校」として小中一貫教育開始。
- 令和 元年(2019年) 南海新今宮駅前に「YOLO BASE」開業
- 令和 2年(2020年) 阪堺線恵美須町駅が移転。「新今宮駅北側まちづくりビジョン」策定。
- 令和 3年(2021年) なにわ筋線工事着手
- 令和 4年(2022年) JR新今宮駅北側にOMO7大阪by星野リゾートがオープン
恵美地域の史跡と名所
今宮戎神社(恵美須西1丁目6番)
今宮戎神社は浪速区恵美須西1丁目に鎮座し、本殿に天照皇大神(あまてらすおおみかみ)・事代主命(ことしろぬしのみこと)・素盞嗚命(すさのおのみこと)・月読命(つきよみのみこと)・稚日女命を奉斎(わかひるめのみこと)、大国社に大国主命(おおくにぬしのみこと)・五男三女八柱神を奉斎、稲荷社に宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)を奉斎し、その創建は皇紀1260年(西暦600年)推古天皇の御代に聖徳太子が四天王寺建立にあたり、同地西方の守護神として鎮齋せられ、市場鎮護の神として尊崇せられたと伝えられています。
戎様は、左脇に鯛を右手に釣竿をもっておられる姿がよく描かれています。その姿は、漁業の守り神であり海からの幸をもたらす神を象徴しています。当社の鎮座地もかつては海岸沿いにあり、平安中期より朝役として一時中断があるものの宮中に鮮魚を献進していました。
また、このような海辺で物資の集まりやすい土地では、海の種々の産物と里の産物、野の産物とが物物交換される、いわゆる「市」が開かれますが、当社でも四天王寺の西門に「浜の市」が平安後期には開かれるようになり、その市の守り神としても当社の戎さまが祀られるようになりました。
時代を経て、市場・商業の発展に伴い、いつしか福徳を授ける神、商業の繁栄を祈念する神としても厚く信仰されるようになりました。
室町時代以降、庶民の信仰はより厚くなり、大阪の町も発達し大阪町人の活躍が始まり、今宮戎神社も大阪の商業を護る神様として更に篤く崇敬されるようになりました。江戸元禄時代には、十日戎の神事も今日と同じような祭礼となり、当時の記録地誌等にも盛大な様子が伝えられています。
神社の後ろの羽目板をたたきながら大声で「やってきました」と訴えるのは、戎神の耳は不自由だと昔からいわれてきたからです。社頭では、米花袋、小判・米俵など縁起物が売られており、これらを笹の枝に結いつけて持ち帰り、家の内に飾って富貴繋昌の先表としました。
大阪大空襲の前にご神体を移し、戦災の被害を免れましたが、戦後すぐの十日戎の参拝客は1万人ほどだったそうです。1956(昭和31)年に今のご本殿が竣工しました。1月9日は宵戎、1月11日は残り福といわれ、現在もこの3日間で100万人以上が参詣に訪れます。
七福神とは、福徳の神として信仰される大黒天、恵比須、弁財天、毘沙門天、福禄寿、寿老人、布袋の七神を指します。七福神信仰は室町時代に生まれ、江戸時代の大阪でも七福神めぐりが盛んに行われたといいます。
浪速区には商売繁盛の神として有名な今宮戎神社のほか、大黒天(福徳開運)を祭る大国主神社、毘沙門天(融通招福)を祭る大乗坊があります。なお、弁財天(知恵財宝)は法案寺(中国)、福禄寿 (招徳人望)は長久寺(中央区)、寿老人(富貴長寿)は三光神社(天王寺)、布袋(笑門来福)は四天王寺布袋堂(天王寺区)にそれぞれ祭られています。
今宮戎神社十日戎の様子(1)

今宮戎神社 十日戎の様子(2)
小西来山と十萬堂跡顕彰碑(恵美須町西2丁目1番)
小西来山は元禄時代の代表的な俳人です。1654(承応3)年、北船場平野町の薬種商の生まれで、西山宗因の門下となり、18歳で俳諧点者(宗匠)となりました。大阪のど真ん中に住みながら詠んだ「お奉行の名さへ覚えず年の暮」の句は有名です。
60歳の時、今宮村に居を移し、十萬堂と称して閑静な暮らしを楽しみました。十萬堂には10畳ほどの座敷があり、小間の茶室などが付属していました。1716(享保元)年10月3日に63歳で死去しました。
「時雨るるやしぐれぬ中の一心寺」の句は、今宮の地から当時草原だった新世界、動物園を隔て眺められた実景と言われ、一心寺(天王寺区)に句碑が立てられています。一心寺と海泉寺に墓があり、海泉寺の墓地には夫婦墓が祀られています。
十萬堂の建物は1945(昭和20)年の戦災で焼失しましたが、その後に建立された記念碑が近くに残されています。
.jpg)
十萬堂跡顕彰碑
.jpg)
顕彰碑横にある解説文
高津入堀川
日本橋筋の隆盛に伴って長町から東、下寺町から西の土地に高津新地が建設され、その翌年の1734(享保19)年、長さ798メートル、幅16メートルの運河が開削されました。それが高津入堀川です。その後、1752(宝暦2)年、新地の南天王寺領に幕府が米蔵を設けた際、川の南端に東西29メートル、南北36メートルの船入堀を穿ち、運河とつながることとなりました。しかし、道頓堀川とつながるだけでは水運の便からも、流水の上からもしばしば停水して衛生の害もあったことから、1896(明治29)年に鼬(いたち)川と連絡することとなり、2年後の1898(明治31)年に工事が完成、最終的にその長さは2730メートルに及びました。その後、難波新川とも連絡することとなりました。
戦前、高津入堀川の川沿いの一部には、川の両側に貯木業者が並んでいました。いわゆる「木場」で、そこには多くの筏(いかだ)が組まれていて、半纏(はんてん)姿の職人が立ち働く姿を見ることができました。子どもたちにとっても筏遊びのできる絶好の場所でした。川の水も澄み、1940(昭和15)年頃までは魚釣りができ、夏の暮れなどは近所の人々が縁台を出して夕涼みをとったそうです。
戦後は戦災による焼土の捨て場となり、船出橋・南日東間が1957(昭和32)年から1958(昭和33)年にかけて、南日東・堀切橋間が1958(昭和33)年から1964(昭和39)年にかけて、堀切橋から道頓堀川合流点が1958(昭和33)年から1962(昭和37)年にかけて埋め立てられました。
阪堺線 恵美須町駅(恵美須西2丁目1番)
1910(明治43)年3月に設立された旧阪堺電気軌道株式会社が阪堺線のおこりです。同社は片岡直輝氏らが発起人となって、大阪市~浜寺村間および堺市宿院~大浜間の2路線に電気鉄道を建設する目的で設立されました。翌年12月に恵美須町~大小路間、その翌年の3月に大小路~少林寺橋(現・御陵前)間、4月に少林寺橋~浜寺駅前間が開通、阪堺線の路線が完成しました。
競合する南海鉄道と激しい旅客誘致競争が起こりましたが、1915(大正4)年に両社は合併し、南海鉄道の阪堺線となりました。その後さらに変遷を経て、1980(昭和55)年、阪堺電気軌道として再スタートを切りました。
路面電車は交通手段の多様化などによる乗客の減少により、各地で廃止が相次ぎましたが、近年は環境にやさしい便利な交通機関として再び注目されています。
2020(令和2)年、駅のホームを100メートル南に移設し、副駅名を「通天閣前」と名付けました。
.jpg)
移設後の恵美須町駅(2025年2月24日撮影)

副名は「通天閣前」
参考資料
- 大阪市立恵美小学校閉校記念誌2016「恵美」
- 創立30周年記念誌「日本橋」(大阪市立日本橋中学校)
- 浪速区・まちの歴史
- 浪速区史
- 甦えるわが街
- 新今宮駅北側まちづくりビジョン
- 今宮戎神社ホームページ、阪堺電車ホームページ、ウィキペディア など
(注)この記事は地域の語り部の方々の発言をもとに作成しております。歴史考証はしておりませんので、予めご了承ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9683
ファックス:06-6633-8270