第10回 生野区持続可能なまちづくり活動支援事業報告会を開催しました!
2025年5月19日
ページ番号:647973
生野区持続可能なまちづくり活動支援事業にかかる事業報告会において、10組の認定事業者様より、令和6年度の事業活動をご報告いただきました。
開催概要
【日時】
令和7年2月4日(火曜日) 午後2時00分~午後4時30分
【場所】
生野区役所 5階 502・503会議室
【講評】
(敬称略・五十音順)
田中 晃代( 近畿大学 総合社会学部 環境まちづくり系専攻 教授 )
田中 逸郎(特定非営利活動法人 NPO政策研究所 理事・研究員)
藤原 明 ( りそな総合研究所 リーナルビジネス部長 )
報告概要
生野長屋大学ぽんぽこキャンパス
生野長屋大学ぽんぽこキャンパス
「多世代交流」×「共育」(共に育つ)を軸に子どもから大人までが本気で遊び、学び、やりたいことを表現できる居場所作りの取組み
(講評)
- 「まねること」から「学ぶこと」を始めるという考え方に感銘を受けた。今後も子どもたちに学ぶきっかけを与えてあげてほしい。
- 様々な地域に活動の拠点を設ける中で、生野区においては長屋に着眼点を置いている。地域の問題解決になりうる活動でもあるので、今後も続けてほしい。
- 大人が楽しんでいる姿を子どもに見せることができているので、いい影響があると思う。
輪母ネットワークのピアコミュニティ運営事業「わははの輪」
特定非営利活動法人輪母ネットワーク
障がい児者とその家族及び障がい児者の支援を行う団体及び支援者のピアコミュニティの運営
(講評)
- 「わはは」ネーミングセンスや親子を表現するロゴに意味が込められていて、寄付型事業として魅力的に映っている。
- 事業活動は困難な課題も生じうるが、参加者が人のためだけでなく、自分のためにも参加する動機を持つことができるので、参加を継続しやすい環境を作っている。
- 実際の活動の中から困っていることが出てきてそれを解決したいという思いがあり、この策を実践しようとしているところが事業の進展につながっている。また、「寄付型NPO法人」として遂行することに一貫性を持っていることもその一助になっていると思う。今後もつながりを作ってほしい。
さまざまな人が住みやすい地域共生社会を築くために ~ 当事者目線で取り組む福祉対象者への人権を考える ~
特定非営利活動法人コミュニティーサポート研究所
地域で暮らす社会福祉サービス対象者の権利・人権を考え、活動拠点である生野区の地域課題のひとつである外国籍の方への支援の取組み
(講評)
- 多文化共生について法制度的な課題と文化・生活習慣的な課題は行政の中でもよく議論される。人間として共通するものもあれば文化や慣習によって違うものもある。このような「みんな同じでみんな違うもの」を同時にしていくことを、福祉の現場で勉強会やフォーラムを開催したりすることはとても有意義である。多文化共生においてはマイナスの価値を埋めていくことと同時にプラスの価値を生み出すことが大事になっていく。福祉の専門職の方がこのような研究をされていることは貴重である。
- 生野区は外国人にとって住みやすいという当事者の意見もある。この活動も同じ目的を持っているので、このような感覚を持つ方が増えていくような方策を今後も続けてほしい。
- 対人援助職が事例を持ち寄って集合知として活動することができているのが強みであると思う。今後も多文化共生について現実的な解決策を模索し、地域活性化の一助になってほしい。
障がい児・者を対象にしたチャレンジイベント企画&様々な教室体験、発達障がいの理解の為の啓発事業
特定非営利活動法人サンフェイス
「すべての子どもたちに夢は必要だ」を合言葉に、障がい児・者の「可能性」を信じ、「夢」を広げていく取組み
(講評)
- 長年続いていて、かつスタッフが増えているのは大きな進歩である。ボランティアにおいても登録者が増加している点で持続可能なまちづくりに貢献している。
- 通っていた児童が卒業してからボランティアとして参加してもらえており、事業として循環している。今後もこのような方が増えていくといい。
- 地域でのネットワークを活かしてさらに発展を遂げられる。
- 事業を遂行していく中で本来の目的を再確認する機会があるので、児童もスタッフも満足していると考えられる。今後も脱マンネリ化を意識しつつ事業を遂行してほしい。
- イベントの開発や運営力が強みとして活かせている。
- 学校教育とリンクすることと地域に根を張ること両面を押さえると事業も持続可能性が増すと思う。
生野理科実験ショー
ラボラトリー・ワーク・グループ大阪
「わくわく!ドキドキ!生野でも身近に体験できる理科の楽しさを!」をテーマに、理科教育活動および理科実験を通して、子どもたちに理科リテラシーの育成に取組む
(講評)
- まちづくりや地域活動においては、NPOや行政などが行う福祉分野が中心になりがちになるところに、理科という専門性とスキルを活かして社会貢献ができている。子どもたちに理科への関心を持たせ、将来の選択肢を増やしていく取り組みは非常に素晴らしい。
- 子どもたちが主体(客体でなく観せる側)となる「理科実験ショー」を実施することができている。子どもたちの主体性を引き出すことに成功していると考えられる。
- 事業を実施しているうちに運営側にもノウハウなどの点で気づきがあったとうかがえる。この気づきを強みに今後も活動を継続してほしい。
- 若い担い手が活躍してくれる場面もあった。後継者の育成といった面からも事業の担い手を増やしてほしい。
つながりの場smile~すまいる~(子ども食堂)
特定非営利活動法人smile~ちあふる~
地域に住む親子が、困難や悩みを一人で抱えるなどして孤立する事がないよう地域での交流・居場所をつくり「孤立減少」をめざす
(講評)
- 活動の担い手の人手不足は死活問題である。この中で、応援してもらえる方を増やすことが大事であると思う。今後は手伝ってくれるボランティアたちに主体性のある活動をしてもらうことで、継続することができるかもしれない。
- 40名のボランティアを募ることができたのは大きな成果であり、それだけの魅力があると思う。
- ジュニアスタッフの方が入れ代わり立ち代わり活動してもらえることで事業の持続可能性が上がるとともに、横のつながりも増えている。
- コミュニケーション力はこの活動の大きな強みであるから、ジュニアボランティアの方もかなり学びになる。法人化されて間もなく、今後も課題が出てくるかもしれないが、居場所づくりなどについて柔軟に活動していただけると地域により大きな功績をもたらすと思う。
陶芸Tocoton
合同会社Tocoton
スペイン人陶芸家と大阪人Ft Mデザイナーが生野区の100年目古民家で教える陶芸を通じて、国内外の人を問わず、異文化・ジェンダーレス交流を図る。
(講評)
- 異文化・多文化・ジェンダーレスを文化を通して伝えられている。
- 文化を持続的に伝えつつビジネスも行っているので、持続的に活動を続けられるシステムができている。カタルーニャと日本、ひいては生野のつながりの交点としての意味も持っている。貴重な事業である。
- 万博に際してたくさんの外国人が来日する中、このような活動を見習って同じ活動するかもしれない。こういった場合に横のつながりを持っているのは大いに期待できる。循環型のまちづくりやつながりづくりは防災に関連する活動にも生かせるので、これらの要素を取り入れてこれからもぜひ続けてほしい。
地域活性化・多文化交流事業
大阪市生野ふれあい児童遊園サクラの樹を守る会
地域の活性化を図るための、地域に在住する外国人の方々との文化交流の取り組み
(講評)
- 生野区は共生課題の先進地区である。近所の中での外国人との共生をサポートする活動が共助や公助につながるので、有意義な活動であると思う。
- 様々な方とつながりを作ることができるので、この強みを活かして今後も活動してほしい。
- 海外在住経験を活かした声かけは多文化共生の基礎的なステップを担っている。今後はこのような活動を区民に幅広く普及し、つながりをひろめてほしい。
FPファーム
(一社)FPファーム生野支部
理念の「FP技能でもっと幸せに」を掲げ、家計の向上、相続・空き家等の問題解決に、相談者の選択肢を増やすアドバイス及び子ども向け「金融教育」の取り組み。
(講評)
- お金の専門家が地域で活躍してもらえることは地域にとっても心強い。子どもたちには生きるためのお金とはどういうものなのか、これからもわかりやすく伝えてほしい。
- 生野はものづくりのまちでもあるので、お金にかかわる知識は重要である。今後の生活において大きなヒントとなる。
- 来場した子どもたちやその保護者の理解度が分かると事業効果が高まると思う。また、来場者をフォローアップしていくことで今後の活動が飛躍すると思う。
きたつランド
KISA2子ども応援部隊
地域の子どもたちにとって、安心して過ごせる居場所づくりを行うとともに、子どもたちの教育格差の是正を図る学習支援の取り組み
(講評)
- 来てくれた子どもたちにとって、自分たちに居場所があることを感じられると同時に子どもたち自身が置かれている環境について話すことができる場所であると思う。
- 子どもの支援ニーズを把握することができる有意義な取り組みである。
- 地域において子どもやその家庭を個別に支援することができることが画期的である。
- つながりをつくりづらい子どもへのアウトリーチを行うことでより細やかなニーズの把握ができると同時に、今まで把握されてこなかった子どもたちにも支援の手が届くと感じられる。
- イベントを多く実施しているところが強みであると感じる。この点を活かして、今後もかかわる人が増え続ければより広く支援することができ、問題解決に大きな進展を生み出す頃ができる。
総括
第10回持続可能なまちづくり活動支援事業評定委員総括
すべての事業において、各団体が持つ強みを活かすことができていた。また、地域において各事業の存在感が増しているような印象があった。これは各団体の強みが増していることはもちろん、課題を解決する区内の団体どうしのつながりが広まっていることが理由であると思う。各事業は個々の団体だけでなく、複合型のコミュニティとして地域課題を解決することができている。事業報告会に参加していただいた事業もどこかでつながっている。この重層的なつながりをさらに広げて重ねて事業の効果を発揮してほしい。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
生野区役所 地域まちづくり課
電話: 06-6715-9010 ファックス: 06-6717-1163
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)
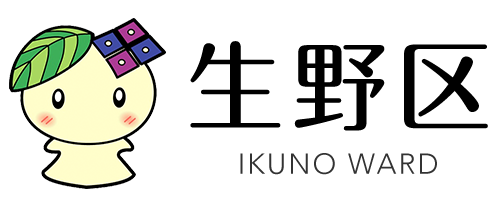







 SNSリンクは別ウィンドウで開きます
SNSリンクは別ウィンドウで開きます

